宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
今回は、現在のマンション市場の熱狂を象徴する存在でありながら、一部の専門家からは将来の「バブル崩壊のきっかけ」になるのではと危惧されている「晴海フラッグ」を題材に、不動産価値の本質について深く掘り下げていきます。なぜ、この物件はこれほどの人気と、同時に厳しい視線を向けられているのでしょうか。その理由を理解することは、皆さんが不動産のプロとして物件の価値を見抜く目を養う上で、極めて重要です。
不動産価値の原理原則「すべては立地で決まる」
まず、不動産、特にマンションの資産価値を決定づける最も重要な要素は何か。それは、ほぼ100%「立地」である、と記事の筆者は断言しています。どの沿線の、どの駅から、徒歩何分に位置するのか。これが価値の根幹をなします。山手線のような主要路線や、銀座線・丸ノ内線のような歴史ある地下鉄路線の駅近物件は価値が安定しやすい一方、比較的新しい路線や駅から距離のある物件は、評価が低くなるのが市場の原理原則です。
なぜ晴海フラッグは「原理原則」から外れるのか
この原理原則に照らすと、晴海フラッグは極めて異例な存在です。最寄り駅は都営大江戸線の「勝どき」駅ですが、物件までは徒歩で20分程度かかります。これは、日々の通勤・通学にはかなり厳しい距離です。にもかかわらず、分譲時には最高で数百倍もの抽選倍率がつくほどの人気となり、中古市場では新築分譲時の1.5倍から3倍もの価格で取引されています。この「立地の不便さ」と「市場の熱狂」との大きなギャップが、専門家から「狂っている」と指摘される所以なのです。
低い入居率と投資目的購入という実態
では、なぜこれほど人気化したのでしょうか。その要因は「選手村跡地」というブランドイメージや、異次元の金融緩和が続く「局地バブル」の影響が大きいと見られています。しかし、その人気を裏付ける「実需」、つまり実際にそこで生活する人の数は、想定を大きく下回っている可能性が指摘されています。
記事の筆者が現地を訪れた際も人影はまばらで、賃貸の募集戸数などから推測すると、実際の入居率は5割に満たないのではないかとされています。また、購入者には投資目的の法人なども多く含まれており、純粋な居住目的の購入が少ないことが、この街の現状を物語っています。
将来の地下鉄計画は救いとなるか
もちろん、このエリアには将来的に地下鉄の新路線を敷設する計画が存在します。これが実現すれば、交通の便は飛躍的に向上するでしょう。しかし、その実現には20年、30年という長い年月がかかる可能性が高いと見られています。その頃には、現在の建物は築年数が経過し、大規模修繕などの課題も出てきます。未来の計画を過度に期待することには、大きなリスクが伴うのです。
宅建士として「熱狂」と「本質」を見極める
今回の晴海フラッグの事例から、私たち宅建士を目指す者が学ぶべき最も重要な教訓。それは、市場の「熱狂」に惑わされず、不動産価値の「本質」を見極める目を持つことです。ブランドイメージや一時的な話題性で価格が実力以上に高騰している物件は、将来、市場が冷静さを取り戻した際に、厳しい価格調整を迎えるリスクをはらんでいます。
なぜこの物件はこの価格なのか、その価値を支えているものは何か。交通の便、生活利便施設、管理状態といった普遍的な価値基準に立ち返り、冷静に分析すること。そして、その分析結果を基に、顧客が長期的に見て後悔しない選択をするための的確なアドバイスを行うこと。それこそが、AIには真似のできない、不動産のプロフェッショナルとしての真価なのです。

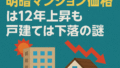

コメント