宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
今回は、住宅金融支援機構から発表された、2024年度の「フラット35利用者調査」の結果について解説します。この調査は、全期間固定金利の代表的な住宅ローンであるフラット35の利用者の動向をまとめたもので、現在の住宅購入者のリアルな姿を映し出す貴重なデータです。今回の調査からは、「購入物件」と「購入者層」に関する、いくつかの非常に重要なトレンドが見えてきました。
新築から中古へ 住宅取得の大きな潮流変化
2024年度の調査で最も顕著だった変化は、購入される住宅の種類です。フラット35の利用において、「中古住宅(戸建て・マンション)」の割合が前年度から7.4ポイントも大幅に増加しました。その一方で、「注文住宅」の割合は9.3ポイントも減少しています。
このデータは、高騰し続ける建築コストや新築物件の価格を背景に、住宅購入を検討する多くの人々が、より価格帯の広い「中古住宅」へと選択肢を広げているという、市場の大きな潮流を明確に示しています。
進む購入者の「高齢化」 平均年齢は44.5歳に
次に、購入者の年齢層の変化です。利用者の平均年齢は上昇傾向が続いており、ついに44.5歳となりました。特に、50歳代や60歳以上の利用者の割合が増加しているのが特徴です。これは、住宅価格の高騰により、十分な頭金を準備したり、年収が安定したりするまでに時間がかかり、結果として住宅の初回取得年齢が上がっていることを示唆しています。もはや、住宅購入は若い世代だけのものではなく、ミドル・シニア層にとっても重要なライフイベントとなっているのです。
上昇続く住宅価格と世帯年収
住宅の取得に必要な資金(所要資金)も、ほとんどの種類で前年度から上昇が続いています。特に新築マンションは5,592万円、建売住宅は3,826万円と、それぞれ価格が大きく上がりました。これに伴い、購入者の平均世帯年収も669万円と増加傾向にありますが、住宅価格の上昇ペースに追いつくのが厳しい状況がうかがえます。
「年収倍率」の横ばいが示す”限界”
ここで、最も注目すべきデータが「年収倍率」です。年収倍率とは、住宅の購入価格が世帯年収の何倍にあたるかを示す指標で、住宅の買いやすさ(アフォーダビリティ)を表します。
今回の調査では、この年収倍率が、多くの住宅タイプで横ばい、もしくはわずかに低下しました。これは非常に重要なシグナルです。つまり、住宅価格が上昇しすぎた結果、これ以上は年収に見合わない、という価格の「限界点」に達しつつあることを示唆しています。購入者のローン返済能力の上限に、市場価格がぶつかり始めているのです。
宅建士がデータから読み解くべき顧客像の変化
この調査結果は、私たち宅建士を目指す者にとって、顧客像が大きく変化していることを教えてくれます。
【1】新築だけでなく、中古住宅+リフォーム・リノベーションという提案の重要性が増していること。
【2】顧客の年齢層が上がり、ライフプランや老後の資金計画までを考慮した、より長期的な視点でのアドバイスが求められていること。
【3】年収倍率が限界に近づいているため、顧客の資金計画の妥当性をシビアに判断し、無理のない購入をサポートする役割が不可欠であること。
フラット35のデータは、単なる統計数字ではありません。それは、私たちが向き合うべき「お客様の今の姿」を映し出す、極めて重要なビジネス情報なのです。
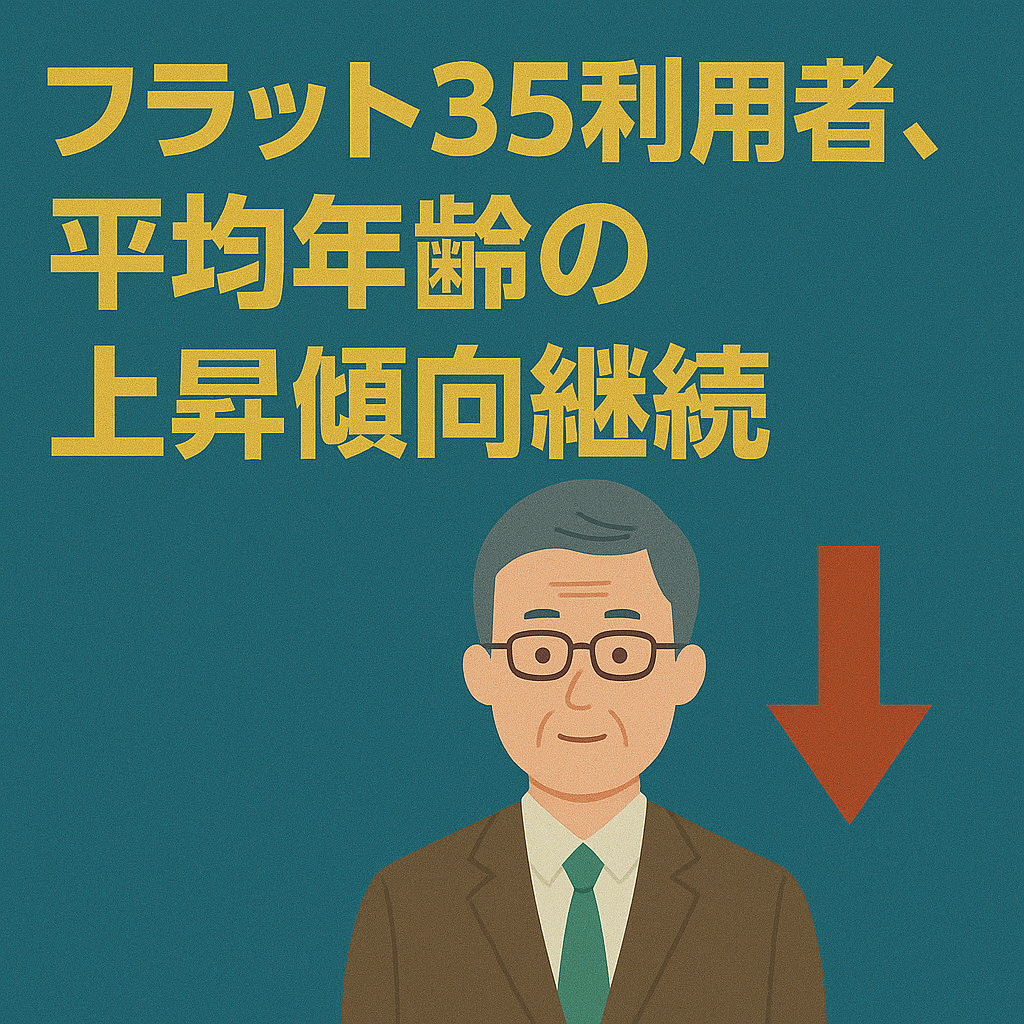
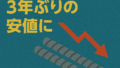

コメント