宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
昨日7月31日、不動産小口化商品の大手「みんなで大家さん」が、主力商品である「シリーズ成田」の分配金の支払いを遅延するという、極めて重大な事態が発生しました。累計2000億円超の資金を集めたとされる著名な商品なだけに、多くの投資家に衝撃が走っています。この事件は、皆さんが試験で学ぶ「不動産特定共同事業法(不特法)」で規定される商品の、リスクと現実を浮き彫りにしています。プロの不動産取引の専門家を目指す者として、この事件から学ぶべきことは非常に多いです。
何が起きたのか?支払い日当日の「配当遅延」通知
まず、事態の概要です。「みんなで大家さん」の運営会社は、7月31日の分配金支払い日当日に、出資者に対して支払いが遅れる旨を通知しました。その理由として、「テナントからの賃料入金が4月以降行われていないため」と説明しています。予定されていた分配金が、支払い当日に突然払われないという異常事態です。投資家からは「電話もつながらない」「いつ支払われるのか」と不安の声が上がっており、1年前から解約を申し出ていたにもかかわらず、いまだに返金されていないという証言も出ています。
最大の危険信号「行政処分」の重み
今回の配当遅延は、決して青天の霹靂ではありませんでした。運営会社である都市綜研インベストファンドと、そのグループ会社は、昨年6月に不動産特定共同事業法に基づき、行政処分(一部業務停止命令)を受けています。理由は、事業計画に大幅な遅れが出ているにもかかわらず、出資者への説明が不十分だった、というものでした。
宅建受験者の皆さんにとって、「行政処分」がどれほど重い意味を持つかは言うまでもありません。これは、監督官庁がその事業者の運営に重大な問題があると認定したことを示す、最大の危険信号(レッドフラッグ)です。この時点で、事業の健全性に大きな疑問符がついていたのです。
不動産特定共同事業法(不特法)と投資家保護
ここで、試験知識の確認です。「みんなで大家さん」のような商品は、「不動産特定共同事業法(不特法)」という法律に基づいて組成・販売されています。この法律は、小口の資金で不動産投資を可能にするためのルールを定めており、投資家を保護するための様々な規定が設けられています。しかし、法律はあくまで事業の枠組みを定めるものであり、投資の元本を保証するものではありません。
運営会社は「不動産という資産は確かに存在する」と説明していますが、運営会社自体の資金繰りが悪化し、事業が立ち行かなくなれば、その資産を売却して投資家にお金が戻ってくるまでの道のりは、極めて険しいものになります。
「テナント=関連会社」というスキームの危うさ
今回の事件で、もう一つ注目すべきは、賃料を支払っていないテナントが、運営会社の「グループ会社」であるという点です。これは、独立した第三者から賃料を得ているわけではなく、グループ内で資金を循環させているに過ぎない可能性があります。
このスキームの危うさは、グループ全体の経営が傾いた時に、賃料の支払いが簡単に止まってしまうことにあります。投資家への分配金の原資が、外部からの安定した収益ではなく、内部の資金繰りに依存している場合、そのリスクは非常に高くなります。
理解すべき「商品説明」と「リスク開示」
今回の事例から、最も重要な教訓。それは、不動産投資商品を扱う際の「リスク開示」の重要性です。「想定利回り7%」という魅力的な数字の裏には、以下のような、様々なリスクが存在します。投資商品を宅建士として扱うことはないですが、不動産関連の商品として理解しておくべき事柄です。
- 元本割れのリスク
- 分配金や償還が遅延・停止するリスク
- 運営事業者自身の倒産リスク
- 行政処分を受けていないかといった信用のリスク
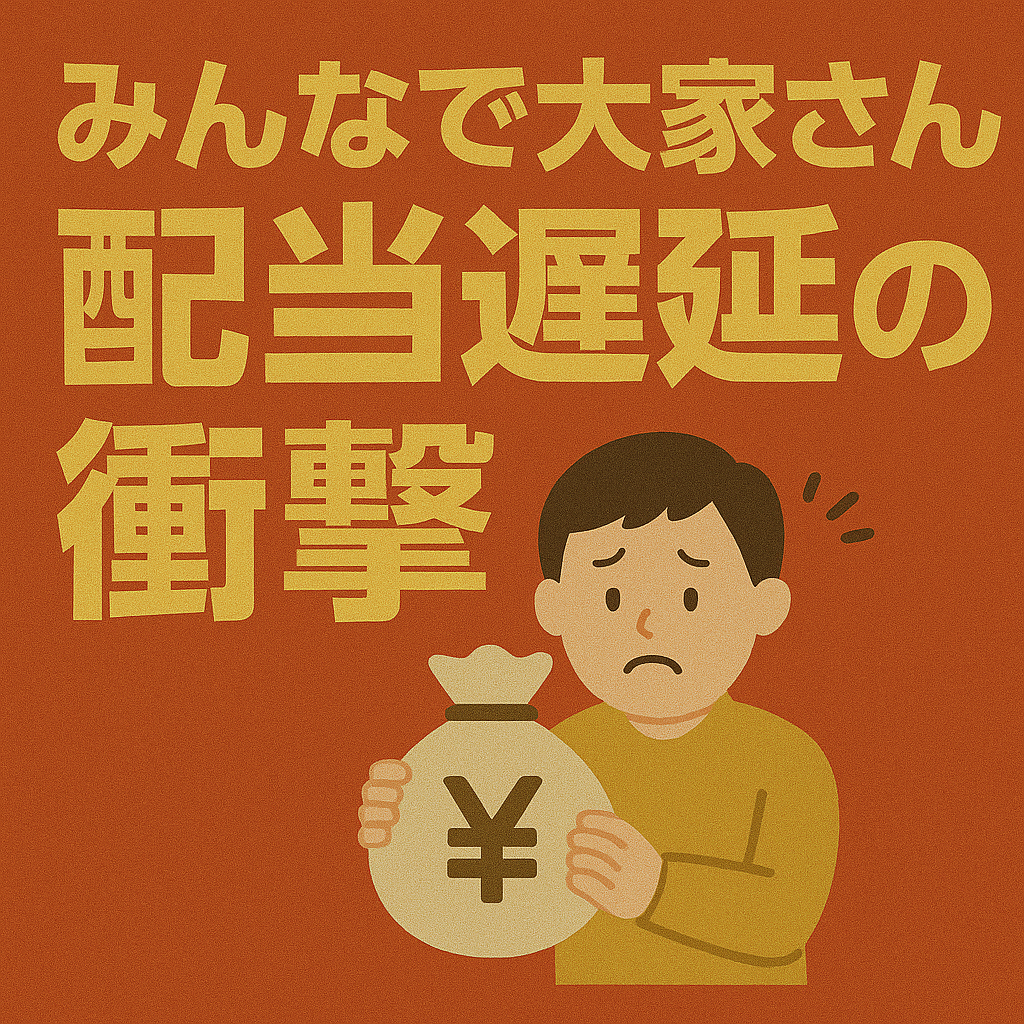
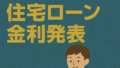

コメント