はじめに
賃貸住宅管理業法と並んで、宅建業法の「重要事項説明」は試験でも実務でも重要なテーマです。特に賃貸借契約においては、借主が契約内容や物件状況を正しく理解し、不利益を被らないようにするために不可欠な制度となっています。
賃貸不動産経営管理士試験では、宅建業法そのものが直接問われるのではなく、「宅建業法の規定と賃貸住宅管理業法の関係」や「説明義務の範囲」などを整理して理解しておく必要があります。本記事では、重要事項説明の概要から、説明すべき具体的項目、IT重説の活用、告知義務に至るまで詳細に解説します。
宅建業法における重要事項説明の位置付け
宅建業法35条は、不動産取引における透明性と安全性を確保するために、宅地建物取引業者に「重要事項説明」を義務付けています。
賃貸借契約においても例外ではなく、賃貸人と借主の間で契約が成立する前に、契約条件や物件の状況などについて、宅地建物取引士が借主に説明する必要があります。
ここで重要なのは、「契約締結前」である点です。契約成立後に説明しても意味がなく、法令違反となります。また、説明の実施主体は「宅建業者」ですが、実際の説明を行うのは「取引士」であり、取引士証を提示する義務があります。
説明の方法と手続き
書面交付の義務
- 「重要事項説明書」(いわゆる35条書面)を作成し、借主に交付します。
- 書面は紙媒体が原則ですが、当事者の承諾があれば電磁的方法(メール、クラウドシステムなど)による交付も可能です。
取引士の関与
- 重要事項説明は、必ず宅地建物取引士本人が行わなければなりません。
- 取引士は説明の際に「取引士証」を提示することが義務付けられています。
説明の相手方
- 借主本人が対象です。
- 借主が宅建業者である場合には、書面交付のみで足り、口頭説明は不要です。
ITを活用した重要事項説明(IT重説)
IT重説は、テレビ会議システムなどを利用して非対面で重要事項を説明する制度です。
新型コロナウイルス流行を契機に広く認められるようになり、現在は賃貸取引において一般化しています。
IT重説の条件
- 双方向で映像・音声が明確に確認できる環境であること
- 事前に重要事項説明書を交付しておくこと
- 借主が説明書面を手元で確認できること
- 宅地建物取引士証を画面上で提示すること
- 通信が途切れた場合には中断し、復旧後に再開すること
👉 ここを覚えると試験での正誤判断に強くなります。
建物賃貸借における説明事項
宅建業法35条と施行規則では、説明事項が細かく規定されています。試験では「どこまで説明義務があるか」を問われることが多いため、以下の整理が有効です。
物件に関する事項
- 登記簿上の権利関係(所有者・抵当権の有無など)
- 都市計画法・建築基準法による制限
- 水道・電気・ガスなどインフラの整備状況
- 建物の設備(台所・浴室・トイレ等)
- 管理会社や管理人の体制
- 耐震診断・石綿使用調査の結果
- ハザードマップに基づく水害リスクや土砂災害警戒区域
取引条件に関する事項
- 賃料、敷金、礼金、共益費、その他金銭の額や支払方法
- 契約期間と更新の有無(定期借家契約であればその旨)
- 敷金精算の方法
- 損害賠償予定額や違約金の定め
- 終身借家契約である場合、その特約内容
👉 特に「水害ハザードマップ」「耐震診断」「石綿使用の有無」は近年追加された重要ポイントです。
人の死に関する告知義務
宅建業法自体は「人の死」に関する説明義務を直接規定していませんが、実務では心理的瑕疵として扱われます。
国土交通省のガイドライン(令和3年10月)によれば、以下の整理となります。
- 自然死や日常生活での不慮の死:告知不要
- 自殺・事件・事故死:原則3年経過で告知不要
- 社会的影響の大きい事案や借主から質問があった場合:経過期間にかかわらず告知必要
この告知義務は「借主の契約判断に影響を与える事項」であるため、重要事項説明の対象と考えられています。
宅建業法と賃貸住宅管理業法の比較
賃貸住宅管理業法でも「管理受託契約に関する重要事項説明」が定められていますが、宅建業法の重要事項説明とは別物です。
- 宅建業法 → 借主に対して、契約の成立前に行う説明
- 賃貸住宅管理業法 → 賃貸人(オーナー)に対して、管理受託契約を締結する前に行う説明
👉 試験では「どちらに対する説明か」を混同しないことが大切です。
例題で理解を深める
問題1
宅建業法に基づく重要事項説明について正しいものはどれか。
- 契約締結後に説明をしてもよい。
- 借主が宅建業者の場合は、書面交付のみで足りる。
- IT重説では、取引士証を画面で提示する必要はない。
- 自然死があった場合は必ず告知しなければならない。
解答:2
問題2
宅建業法35条に基づき、建物賃貸借契約で説明義務があるものはどれか。
- 契約期間と更新の有無
- 建物の所有者の家族構成
- 入居者の近隣住民との関係性
- 借主の職業
解答:1
→ 契約期間と更新の有無は必須説明事項。その他は説明義務に含まれません。
まとめ
- 重要事項説明は契約成立「前」に、取引士が借主に対して行う。
- 書面交付は必須で、借主が宅建業者なら説明は省略可。
- IT重説は近年普及しており、試験でも頻出分野。
- 建物賃貸借契約における説明事項は「物件情報」と「契約条件」の二本柱。
- 人の死に関する告知義務はガイドラインに基づき、3年を目安に考える。
- 賃貸住宅管理業法の重要事項説明との違いを明確に理解することが得点のカギ。
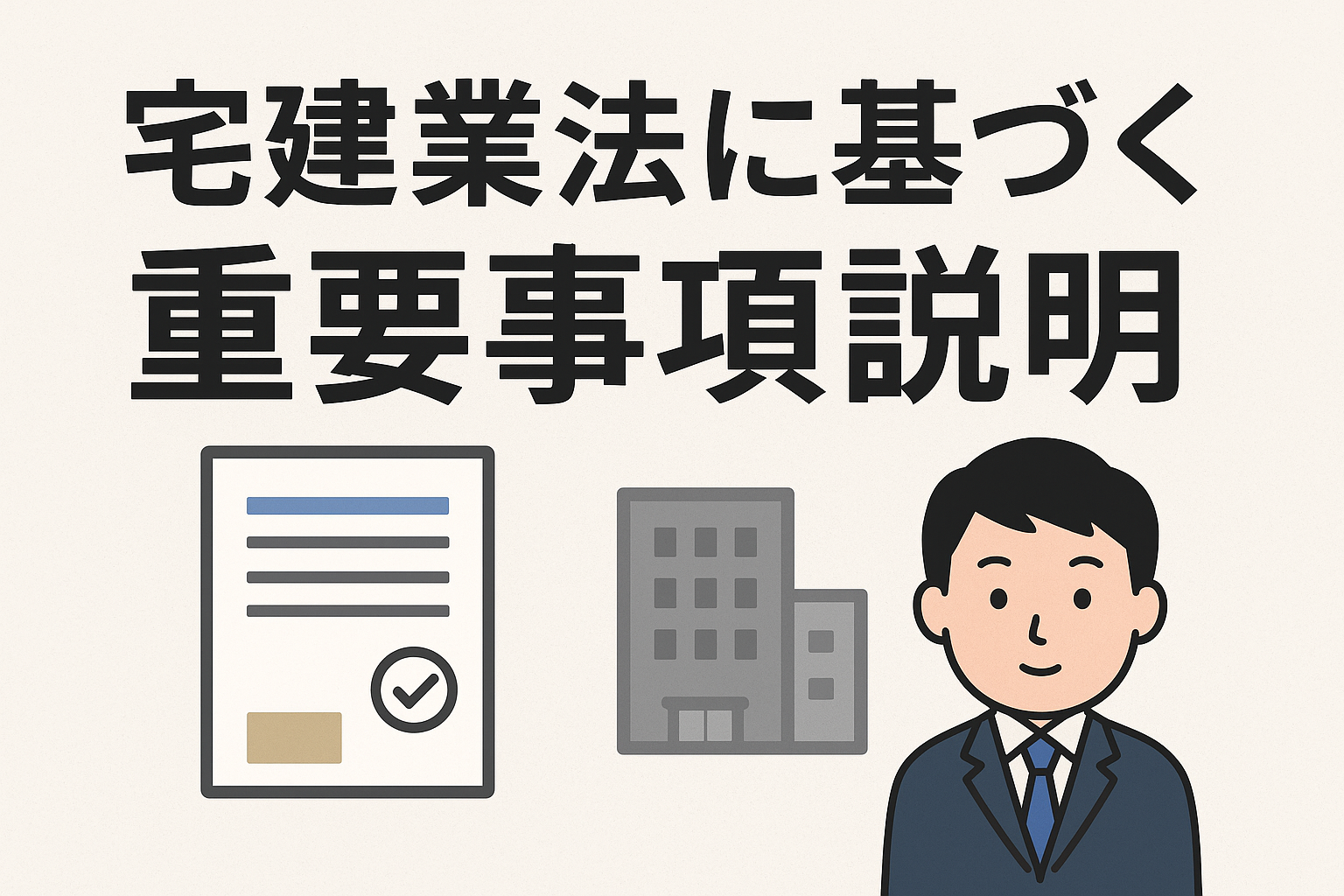
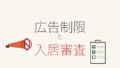
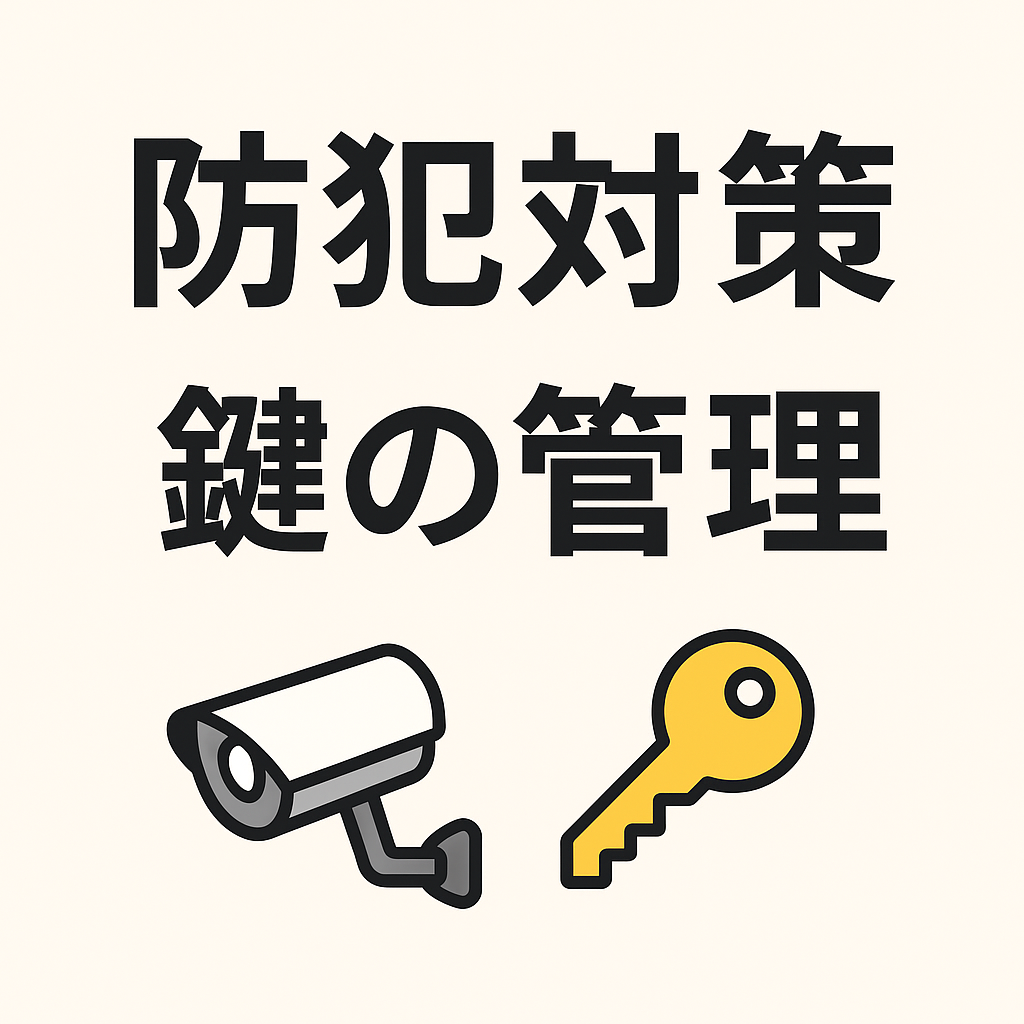
コメント