賃貸不動産経営管理士試験では、「保証」「敷金」「少額訴訟」「支払督促」など、契約終了や賃料回収に関わる分野から毎年のように出題があります。
これらは実務でも重要なテーマであり、正確な条文知識と判例の理解が求められます。
この記事では、頻出論点を体系的に整理し、試験対策に役立つよう例題付きで解説します。
少額訴訟とは?60万円以下の金銭請求を簡易に解決する手続
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする訴えに利用できる簡易裁判所の手続です(民事訴訟法368条〜381条)。
原則として1回の期日で審理を終える「一期日審理の原則」があり、迅速に判決を得られる点が特徴です。
主なルールは次のとおりです。
- 年間10回を超えて利用できない(368条1項但書)
- 原告が訴え提起時に申述し、被告は第1回期日前までに通常訴訟への移行を申し出可能
- 反訴はできない(369条)
- 判決後の控訴は禁止され、「異議申立て」によって通常訴訟へ移行する(377条〜379条)
また、裁判所は判決に際して、被告の事情を考慮し、最長3年の支払猶予や分割払いの定めを行うことができます(375条)。
支払督促制度とは?賃料回収のための迅速な法的手続
通常の訴訟では判決確定までに時間がかかりますが、「支払督促制度」(民事訴訟法382条以下)は、裁判所書記官が債務者を審尋せずに発する命令で、迅速に債務名義を得られる制度です。
申立てから確定までの流れは以下の通りです。
- 債権者が簡易裁判所書記官に申立て(383条)
- 裁判所書記官が督促発付(386条)
- 債務者が2週間以内に異議申立てをしなければ確定(395条・396条)
確定した支払督促は確定判決と同一の効力を持ち、強制執行が可能です。
ただし、公示送達による送達ができない場合には、支払督促は利用できませんので注意しましょう。
保証契約の基礎と保証人の責任
保証契約とは、主たる債務者が履行しない場合に代わって履行をする契約です(446条)。
書面または電磁的記録によらなければ効力を生じません(要式行為)。
賃貸借契約書に保証人の署名押印があれば、新たな契約書を作らなくても有効です。
保証債務は主たる債務に「付従」するため、主たる債務が無効や消滅となれば保証債務も消滅します。
また、債権が譲渡されても、保証債務は自動的に新債権者に移転します(随伴性)。
連帯保証と普通保証の違い
普通保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」があり、まず主債務者に請求するよう求めることができます(452条・453条)。
一方、連帯保証人にはこれらの権利が認められず、債権者は主債務者と連帯して直ちに請求できます(454条)。
したがって、連帯保証人の責任は極めて重く、主債務者と同等の義務を負う点に注意が必要です。
連帯保証契約も書面(または電磁的記録)で行うことが求められます。
個人根保証契約と極度額の定め
賃貸借では「個人根保証契約」(465条の2)が問題となります。
これは、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約であり、極度額の定めがなければ無効です。
また、保証人が死亡、破産、または債権者による強制執行の申立てがあった場合には、元本が自動的に確定します(465条の4)。
極度額の上限内でのみ保証責任を負う点が重要です。
敷金の意義と返還ルール
敷金とは、賃借人の債務を担保するために預ける金銭です(622条の2)。
未払賃料や原状回復費用などに充当され、残額が返還されます。
返還時期は次の通りです。
- 賃貸借が終了し、かつ明渡しが完了した時
- 賃借人が適法に賃借権を譲渡した時
また、敷金返還請求権と明渡債務は同時履行関係にありません(最判昭49・9・2)。
賃借人は敷金の返還がないことを理由に、明渡しを拒むことはできません。
敷金の承継と敷引特約の有効性
賃貸人が交替した場合、敷金の返還債務は新賃貸人に承継されます(605条の2)。
旧賃貸人が敷金を新賃貸人に引き渡していなくても、返還義務を負います(最判昭44・7・17)。
また、「敷引特約」については、敷引金額が社会通念上高額でなければ有効とされています(最判平23・3・24、同7・12)。
礼金・更新料・保証金の法的取扱い
礼金は、返還されない一時金として認められています。慣習的な支払いであり、消費者契約法に反しない限り有効です(京都地判平20・9・30)。
更新料も同様に有効であり、その性質は賃料の補充や契約継続の対価などと解されています(最判平23・7・15)。
保証金は敷金と同じ性質を持つ場合と、建設協力金のように貸付金的性格を持つ場合があります。後者は「金銭消費貸借契約」と判断されることもあります(最判昭51・3・4)。
【例題】保証・敷金に関する過去問対策
例題1:連帯保証人の抗弁権
賃貸借契約において、連帯保証人は、債権者からの請求に対して「まず主たる債務者に請求してほしい」と主張できる。
(正誤を判断せよ)
解答:誤り
連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権はいずれも認められません(民法454条)。
例題2:敷金返還のタイミング
賃貸借が終了したが、借主がまだ物件を明け渡していない。この場合、敷金の返還請求はできるか。
解答:できない
敷金返還請求権は、賃貸借終了後に明渡しが完了した時点で初めて発生します(622条の2)。
例題3:更新料特約の有効性
賃貸借契約において、賃料の2年分に相当する更新料特約がある。これは有効か。
解答:場合により無効
更新料の額が賃料の額や契約期間に比して高額に過ぎる場合、消費者契約法10条違反として無効と判断される可能性があります。
まとめ
保証や敷金のルールは、民法改正後の出題が増えている重要テーマです。
特に「個人根保証」「極度額の定め」「敷金返還と明渡しの関係」は、判例と条文を組み合わせて理解することがポイントです。
本記事を活用して、理論と実務を結びつけながら確実に得点源にしていきましょう。
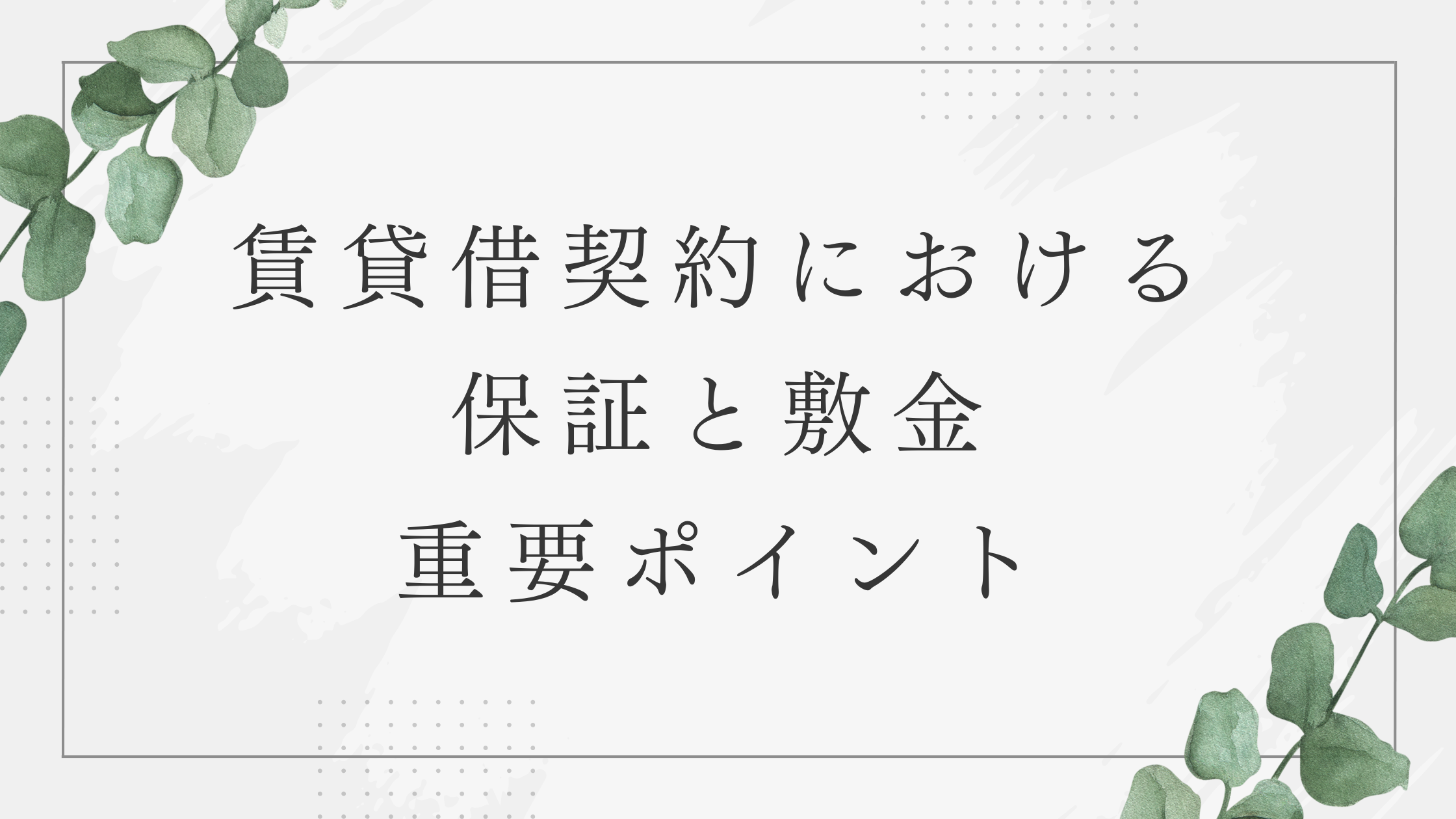
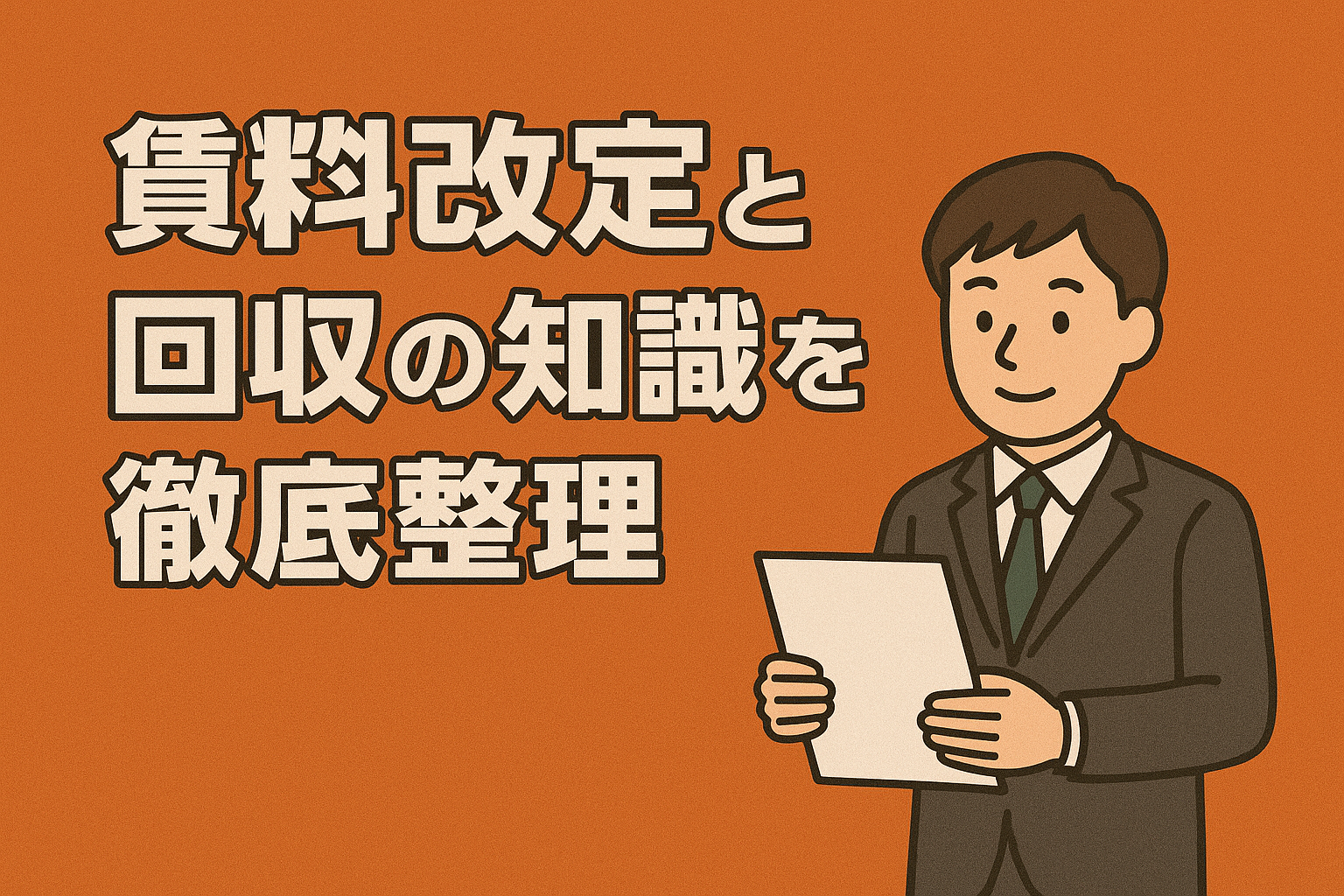
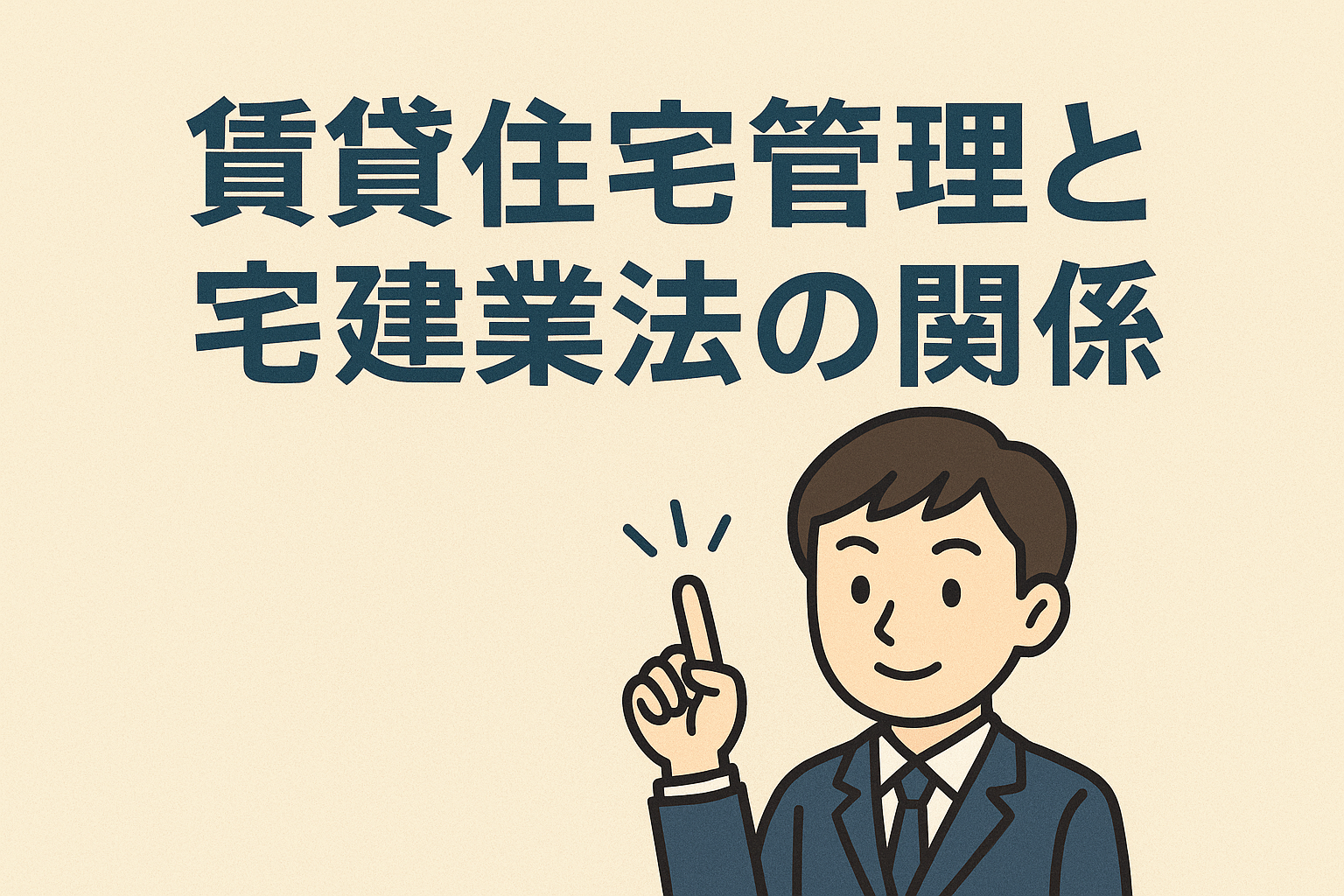
コメント