賃貸不動産経営管理士試験では、民法の「相続」分野からも毎年出題があります。
特に、相続人の範囲や順位、代襲相続、法定相続分、限定承認・放棄の手続など、基本理解が問われるテーマです。
今回は、賃貸不動産管理にも関連する「相続の基礎知識」を、条文ベースで丁寧に整理します。
相続の意味と開始
相続とは、死亡した人(被相続人)の財産上の一切の権利義務を相続人が承継することをいいます(民法896条本文)。
財産にはプラスの財産(預金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。
ただし、「被相続人の一身専属権」(=個人の人格や身分と密接な関係を持つ権利)は相続されません。
たとえば、身元保証契約上の債務や扶養を受ける権利などは、相続の対象外です。
💡補足:相続は被相続人の住所地で開始します(民法883条)。
相続人の範囲と順位
相続人になれるのは、次の人たちです。
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(及び代襲相続人) | 常に配偶者とともに相続 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母など) | 子がいない場合 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子・直系尊属がいない場合 |
| 常時相続人 | 配偶者 | 常に他の相続人とともに相続 |
たとえば、被相続人Aに「配偶者と子」がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
補足
胎児も「相続についてはすでに生まれたもの」とみなされ、出生を停止条件に相続権が認められます(民法886条)。
代襲相続と再代襲
子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた場合などは、その子が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
子の代襲(民法887条)
- 被相続人の子が死亡・欠格・廃除された場合
→ その孫が代襲相続人になる。 - 孫も死亡していた場合 → ひ孫が再代襲相続。
兄弟姉妹の代襲(民法889条)
- 被相続人の兄弟姉妹が死亡・欠格となった場合
→ その子(=おい・めい)が代襲相続人になる。 - 再代襲はなし。
💡補足:被相続人と子が「同時死亡」と推定されるときも代襲相続が発生します(民法32条の2)。
相続人の欠格と廃除
欠格事由(民法891条)
次のいずれかに該当すると、当然に相続権を失います。
- 被相続人や他の相続人を故意に殺害・殺害未遂
- 殺害を知っても告発・告訴しなかった
- 被相続人の遺言を詐欺・強迫で妨害した
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した など
廃除(民法892条)
被相続人の意思によって、家庭裁判所の審判または遺言によって推定相続人の相続権を奪うことができます。
対象は、被相続人を虐待・侮辱・著しい非行をした「遺留分を有する推定相続人」(配偶者・子・直系尊属)です。
法定相続分の基本(民法900条)
相続人が複数いる場合、それぞれの法定相続分は以下のとおりです。
| 相続人 | 順位 | 配偶者との関係 | 相続分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 常に相続 | 子とともに相続 | 1/2 |
| 子 | 第1順位 | 配偶者とともに相続 | 1/2(複数なら等分) |
| 直系尊属 | 第2順位 | 配偶者とともに相続 | 1/3 |
| 兄弟姉妹 | 第3順位 | 配偶者とともに相続 | 1/4(半血兄弟は1/2) |
例題①:法定相続分の計算
問題
被相続人Aには、配偶者Bと2人の子C・Dがいます。法定相続分はどのようになりますか?
解答
B:1/2、C:1/4、D:1/4。
→ 子が複数いる場合は、子の持分(1/2)を等分します。
特別受益と寄与分
特別受益(民法903条)
生前贈与などにより、他の相続人より多くの利益を受けた者は、その分を相続分から控除します。
例:
- Aの遺産:1,000万円
- 子Bは生前に200万円の贈与を受けた
→ 計算:1,000+200=1,200万円
→ 法定相続分(1/2ずつ)=各600万円
→ Bは受益分200万円を控除 → 実際はB400万円、C600万円。
💡特例:婚姻20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与・遺贈は特別受益に算入しない(民法903条4項)。
寄与分(民法904条の2)
被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人には、その分を上乗せして相続分を計算します。
例:
- 遺産:1,000万円
- Bの寄与分200万円
→ 1,000-200=800万円を法定分配
→ B400万円+寄与200万円=600万円
→ C400万円。
例題②:特別受益・寄与分
問題
Aの遺産1,200万円。子B・Cが相続。Bは生前に200万円の贈与、Cは介護で寄与200万円。
それぞれの具体的相続分は?
解答
みなし財産=1,400万円(1,200+200)
→ 法定分配=各700万円
→ Bは200万円控除 → 500万円
→ Cは200万円加算 → 900万円。
相続財産に含まれないもの
一身専属的な権利義務は相続されません。
賃貸管理業にも関係する点としては次のようなものがあります。
- 使用貸借契約上の借主の権利(民法597条3項)
- 終身建物賃貸借の賃借権(高齢者居住法52条)
- 公営住宅の使用権(最判平成2年10月18日)
- 個人根保証契約の保証人地位(民法465条の4)
→ 特に賃貸借関係では、「借主死亡=終了」となる契約と、「相続される契約」を区別することが重要です。
遺産分割の仕組み
相続人が複数いる場合、遺産分割によって誰が何を相続するかを決めます(民法906条)。
協議で法定相続分と異なる分け方も可能です。
例:
- 相続財産:土地1,000万円+預金1,000万円
- 相続人:BとC
→ 遺産分割協議により「土地はB」「預金はC」と決定可能。
💡補足
遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼるが、第三者の権利を害することはできません(民法909条)。
相続の承認と放棄
単純承認(民法920条)
被相続人の財産・債務すべてを無制限に承継します。
特別な手続は不要です。
法定単純承認(921条)
次の行為をした場合は自動的に承認したとみなされます。
- 財産の全部または一部を処分したとき
- 3か月以内に限定承認・放棄をしなかったとき
- 相続財産を隠匿・消費したとき
限定承認(民法922条)
被相続人の財産の範囲内で債務を弁済する制度。
共同相続人全員の同意が必要で、3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
相続放棄(民法938条・939条)
権利義務のすべてを放棄し、初めから相続人でなかったことになる。
3か月以内に家庭裁判所で申述します。放棄者には代襲相続は生じません。
💡補足
相続放棄は各相続人が独立して行うことができます。
放棄した者が財産を占有している場合は、清算人に引き渡すまで善良な管理義務を負います(民法940条)。
例題③:相続の承認・放棄
問題
Aが死亡し、相続人BがAの車を売却した。この場合の扱いは?
解答
Bは相続財産を処分したことになり、法定単純承認とみなされます(民法921条1号)。
→ 限定承認や放棄はできません。
まとめ:相続の出題ポイント整理
| 論点 | 試験頻出ポイント | 条文 |
|---|---|---|
| 一身専属権 | 相続されない権利の区別 | 896条但書 |
| 相続人の順位 | 配偶者+第1~3順位 | 887~889条 |
| 代襲相続 | 子→孫→ひ孫(再代襲可) | 887条2・3項 |
| 欠格・廃除 | 欠格=当然消滅/廃除=家庭裁判所の決定 | 891~893条 |
| 特別受益・寄与分 | 計算式を正確に | 903・904の2条 |
| 承認・放棄 | 3か月以内・単純承認の推定 | 920~924条・938条 |
✅試験直前ワンポイント
賃貸不動産経営管理士試験では、民法の「賃貸借」「相続」「保証」「代理」が有機的に出題されます。
特に「使用貸借の終了=借主死亡」や、「終身建物賃貸借は相続されない」といった賃貸実務と民法の接点は得点源です。
相続は数字・条文の整理が中心なので、条文番号とともに「誰が・どれだけ・いつまでに」を明確に覚えておきましょう。

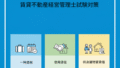

コメント