令和3年の法改正により、「障害者差別解消法」における合理的配慮の提供がすべての事業者に義務づけられました。
これは、障害者が社会生活や経済活動に参加する際に直面する「社会的障壁」を取り除くため、事業者が必要な範囲で配慮を行うことを求める制度です。
賃貸不動産経営管理士試験でも、近年の法改正を踏まえた出題が増えており、「合理的配慮の提供義務」は重要テーマの一つです。
この記事では、その概要と不動産業務における対応方法を整理して解説します。
合理的配慮の提供義務とは
合理的配慮とは、障害者が他の人と平等に社会生活を営むために必要な配慮を、過重な負担にならない範囲で提供することをいいます。
具体的には、障害者本人から「こうした配慮をお願いしたい」と意思の表明があったとき、事業者はその要望に応じて柔軟に対応する必要があります。
たとえば、不動産業者であれば、
- 段差の移動を手伝う
- 契約内容を音読して説明する
- 筆談やメールでのやり取りに応じる
などの行為が「合理的配慮」に該当します。
過重な負担の考え方
合理的配慮は義務ですが、事業者に過重な負担を強いるものではありません。
「過重な負担」にあたるかどうかは、以下の要素を総合的に判断します。
- 事業の規模や財務状況
- 事業の目的や機能への影響
- 実施の難易度(物理的・技術的制約)
- 費用や人員面での負担
ただし、配慮を拒否する場合でも、「なぜできないのか」「代替手段はないか」を丁寧に説明することが求められます。
不動産業務で求められる合理的配慮の具体例
■ 適切な配慮の例
- 車椅子利用者のために携帯スロープを用意する
- 聴覚障害者とのやり取りを筆談やメールで行う
- 視覚障害者に契約書内容を読み上げる、またはデータで提供する
- 専門用語を避けて、わかりやすい言葉で説明する
■ 不適切な対応例
- 「障害者対応はできません」と一方的に断る
- 手話通訳や筆談の申し出を拒否する
- 「時間がかかるから」と説明を省略する
このような対応は、差別的取扱いとして法違反に問われる可能性があります。
環境の整備との違い
合理的配慮は、個々の障害者への個別対応です。
これに対して「環境の整備」とは、不特定多数の人が利用しやすいように事前に改善しておく取組みを指します。
■ 環境整備の例
- 店舗の段差をスロープ化
- 大きな文字の書類や音声案内の導入
- 社員研修による障害理解の推進
環境の整備を進めておくことで、合理的配慮の実施もスムーズになります。
不動産業者に求められる実務対応
合理的配慮の提供義務に対応するため、不動産業者は次のような取組みが求められます。
- 相談窓口の設置と周知
- スタッフへの障害対応研修
- 障害者や支援団体との継続的な対話
- 過去の対応事例を記録・共有
これらは「法的義務」であると同時に、企業の信頼性向上にもつながる取組みです。
「合理的配慮」は、特別扱いではなく、全ての人に等しい機会を与えるための合理的な対応なのです。
試験対策ポイントまとめ
| 論点 | 内容 | 出題頻度 |
|---|---|---|
| 合理的配慮の定義 | 障害者に対し必要かつ合理的な対応を行う義務 | 高 |
| 提供の条件 | 本人の意思表明+過重な負担でない範囲 | 高 |
| 不動産実務での例 | 段差補助、筆談対応、書類読み上げ | 中 |
| 環境の整備との違い | 個別対応と事前整備の違いを区別 | 中 |
| 過重な負担の判断要素 | 財政状況・業務目的・実現可能性 | 中 |
まとめ
合理的配慮の提供義務は、令和6年4月から完全義務化されました。
今後の不動産業務では、障害のある方への対応が「努力義務」ではなく「当然の責務」となります。
賃貸不動産経営管理士試験では、
- 合理的配慮の定義
- 義務化の背景
- 不動産業務における具体例
の3点が出題されやすいため、しっかりと整理しておきましょう。
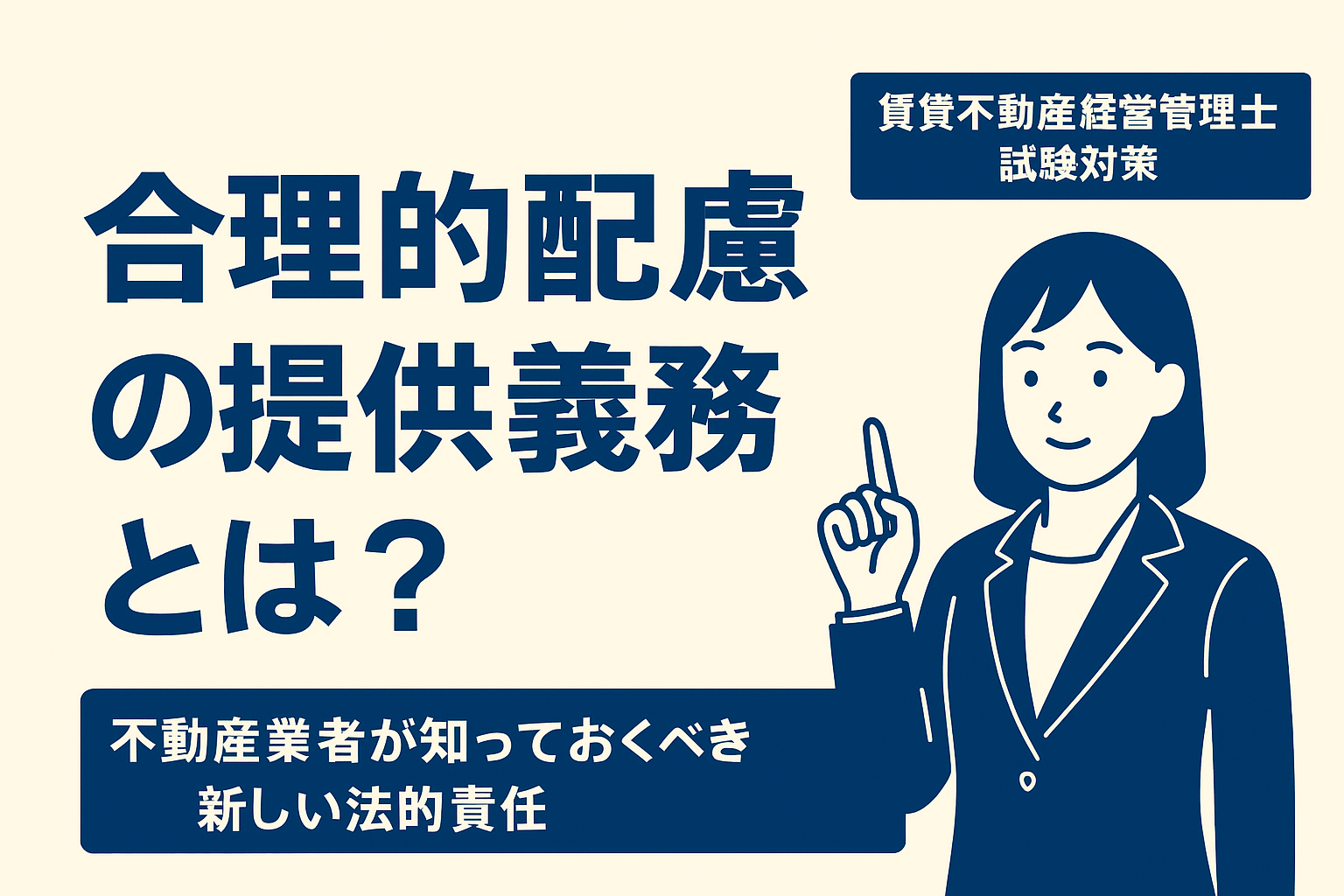

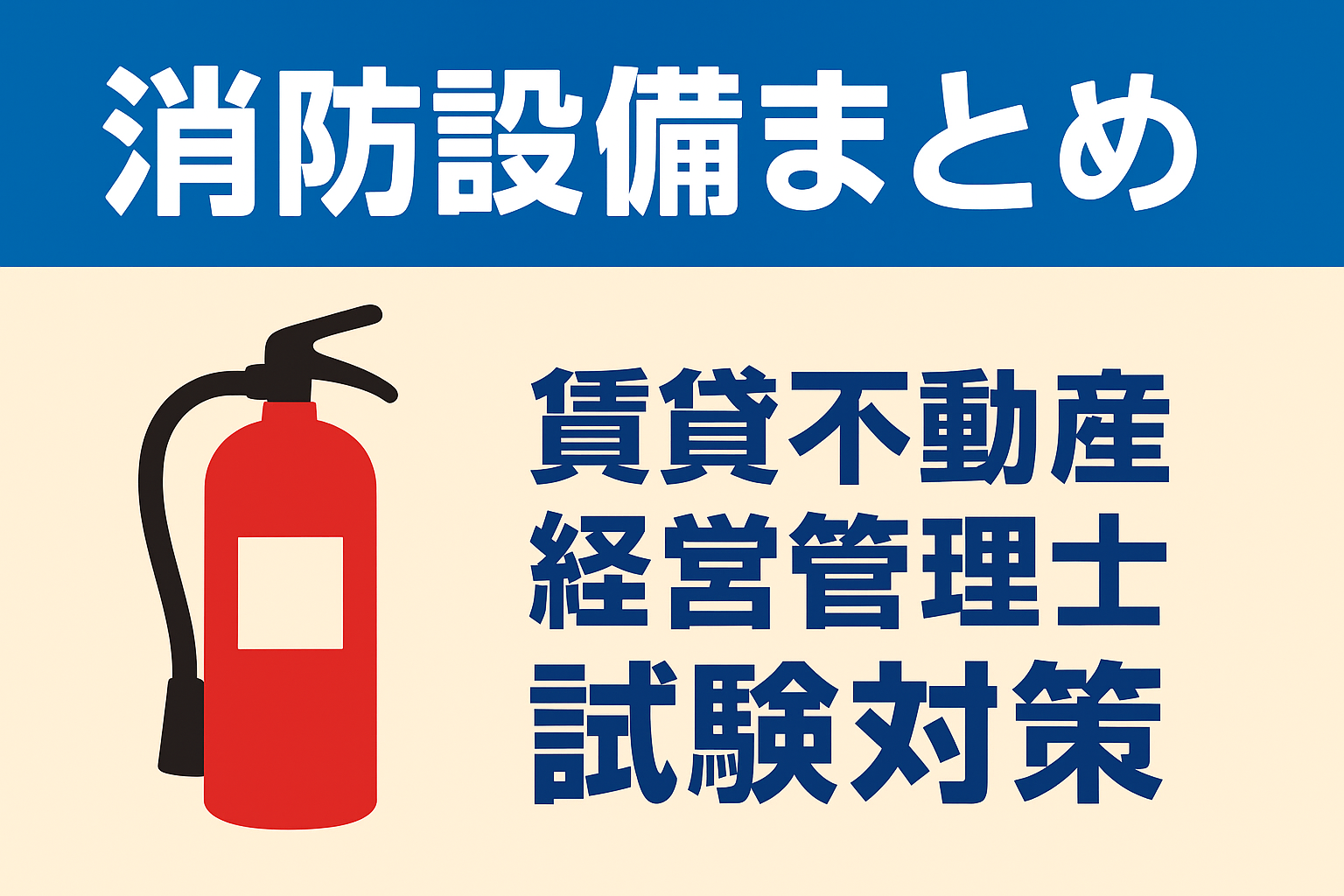
コメント