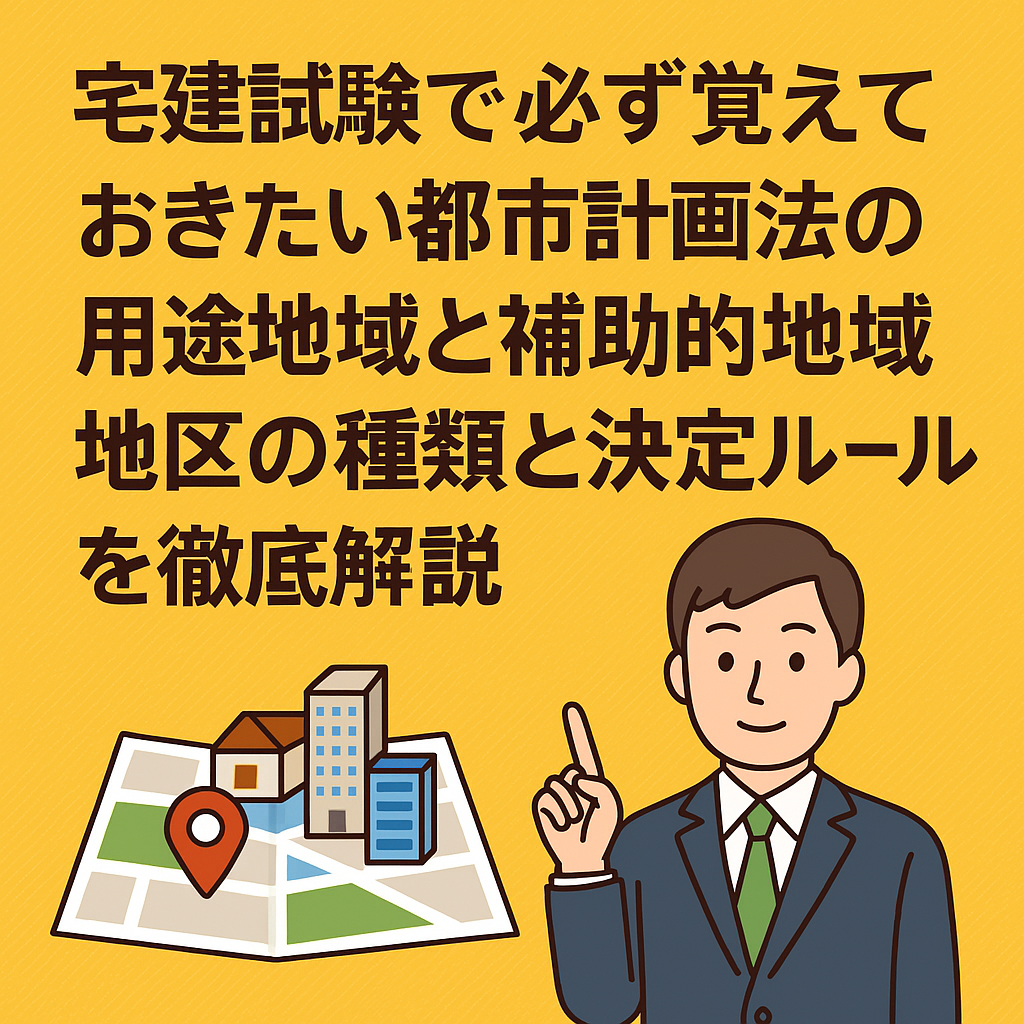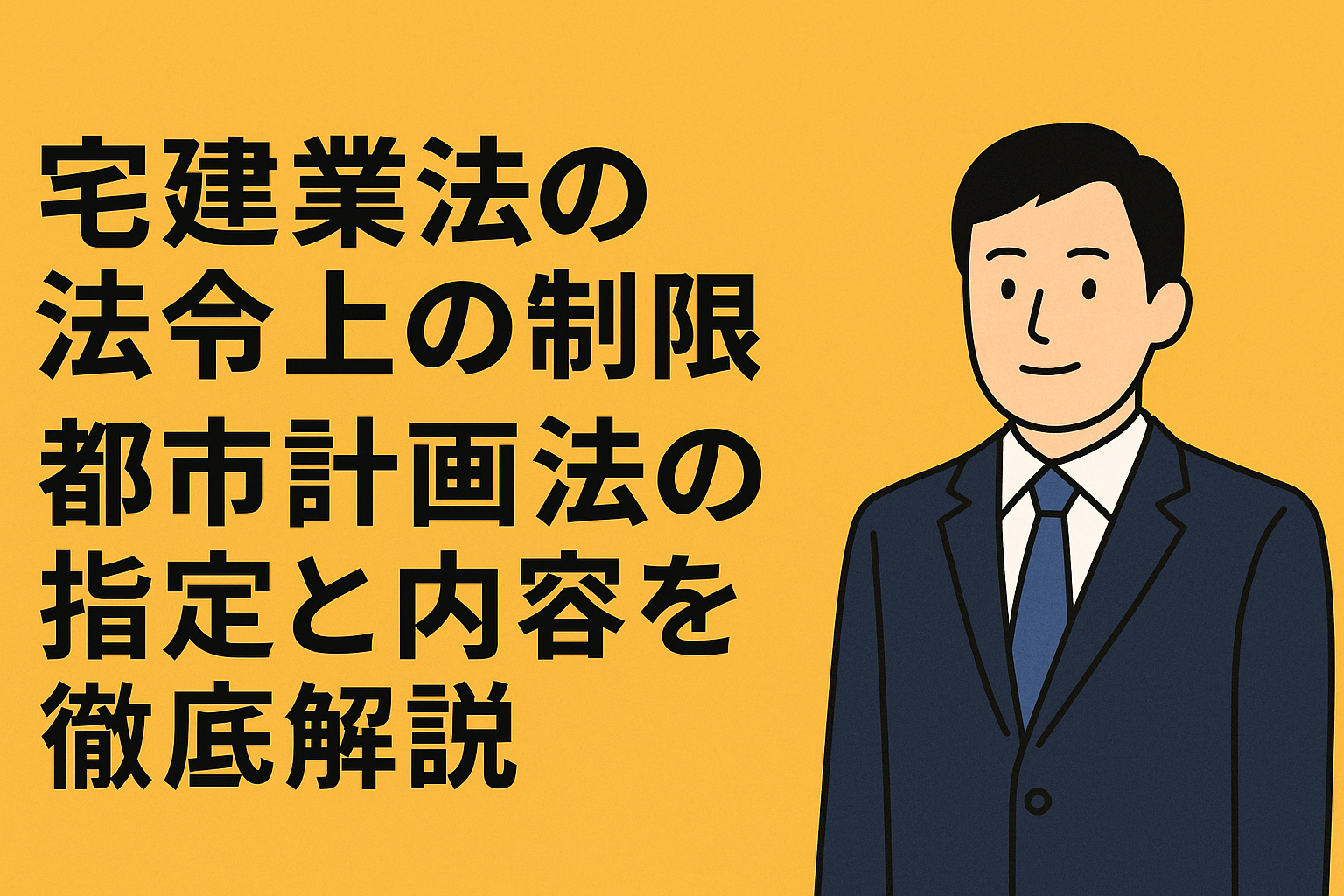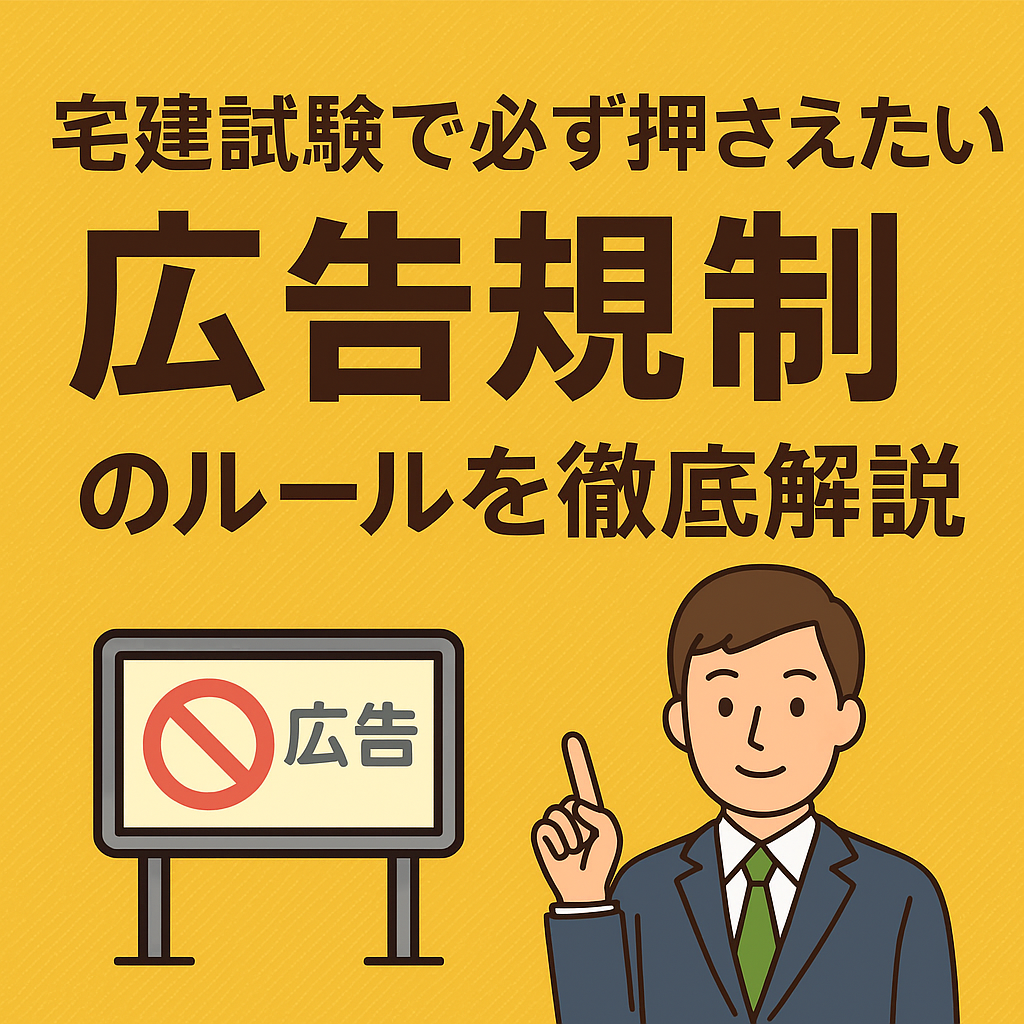宅建試験受験者の皆さん、こんにちは。
今回は「都市計画法」の中でも特に出題頻度の高い用途地域と補助的地域地区、そして都市計画の決定手続きについて、詳しく解説していきます。
用途地域は快適な街づくりのために必要不可欠なルールで、試験でも毎年のように出題される超重要テーマ。例題も交えながら、確実に得点源にできる内容にまとめました。ぜひ最後まで読んでしっかり理解しましょう。
⸻
用途地域とは
用途地域は、都市計画区域内の土地利用を住宅・商業・工業などの目的ごとに分ける地域のことです。
全体で住居系・商業系・工業系の3つの区分と13種類の用途地域に分かれていて、それぞれに建てられる建物の種類や規模、容積率・建蔽率が決められています。
住居系用途地域(8種類)
1. 第一種低層住居専用地域
2. 第二種低層住居専用地域
3. 第一種中高層住居専用地域
4. 第二種中高層住居専用地域
5. 第一種住居地域
6. 第二種住居地域
7. 準住居地域
8. 田園住居地域(平成30年新設)
例題1
第一種低層住居専用地域に建てられないものはどれか。
A. 小中学校
B. 小規模な飲食店
C. 大規模なパチンコ店
D. 店舗兼住宅
正解 → C
第一種低層住居専用地域は静かな住宅街を守るための地域で、大規模な遊戯施設は建てられません。
⸻
商業系用途地域(2種類)
1. 近隣商業地域
2. 商業地域
駅前や商店街などに指定され、利便性の高い地域をつくるための用途地域です。住居も可能ですが、商業施設や業務用建物が中心になります。
⸻
工業系用途地域(3種類)
1. 準工業地域
2. 工業地域
3. 工業専用地域
工場が立ち並ぶ地域で、特に工業専用地域のみ住宅の建築が禁止されています。ここも試験の頻出ポイントです。
例題2
住宅の建築ができないのはどの地域か。
A. 準工業地域
B. 工業地域
C. 工業専用地域
D. 商業地域
正解 → C
工業専用地域は住宅の建築が禁止されています。
⸻
補助的地域地区とは
用途地域だけでは街のルールが不十分な場合、補助的に設けられる地区が補助的地域地区です。
【主なもの】
- 用途地域内のみ定められるもの
- 特別用途地区
- 高度地区
- 高度利用地区
- 高層住居誘導地区
- 特例容積率適用地区
- 用途地域外でも定められるもの
- 特定街区
- 防火・準防火地域
- 景観地区
- 風致地区
- 用途地域外のみ定められるもの
- 特定用途制限地域
例題3
小学校周辺でパチンコ店を規制するために定められる地区はどれか。
A. 特別用途地区
B. 特定街区
C. 高度地区
D. 高層住居誘導地区
正解 → A
特別用途地区は、用途地域に追加で制限を加える地区です。
⸻
都市施設・市街地開発事業・地区計画
都市計画の中で、さらに以下の施設や計画も重要です。
- 都市施設
道路・公園・下水道・学校など
市街化区域では道路・公園・下水道を必ず定め、住居系用途地域では義務教育施設も必須。
- 市街地開発事業
新しい街づくりや再開発を行う事業。
※市街化区域と区域区分のない区域のみ可能、市街化調整区域には定められない。
- 地区計画
町丁単位でのきめ細かい計画。
すべて市町村が定め、市街化調整区域には原則定められない。
⸻
都市計画の決定手続き
都市計画は、都道府県または市町村が決定します。
決定の流れは
1. 公聴会や説明会の開催
2. 都市計画案の公告と2週間の縦覧
3. 住民からの意見募集
4. 審議会の議を経て正式決定
複数の都市計画が重なる場合は都道府県の計画が優先される点も重要です。
⸻
試験対策まとめとポイント
都市計画法でよく出題されるのは以下のポイント。
- 用途地域は13種類、住居系・商業系・工業系に分類
- 住宅が建てられないのは工業専用地域のみ
- 補助的地域地区の種類と役割
- 市街化区域と市街化調整区域の違い
- 市街化区域には用途地域を必ず定める
- 都市計画の決定権者と決定手続きの流れ
これらを表にまとめたり、過去問を繰り返し解いて身につけましょう。例題形式で問題を解きながら学習するのが最も効果的です。