宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
参院選の争点ともなった「外国人による不動産取得」の問題について、その実態を具体的に示すニュースが報じられました。瀬戸内海に浮かぶ山口県の離島・笠佐島(かささじま)で、中国資本による土地の取得が進んでいるというのです。このニュースは、過疎地の不動産が海外から注目されている現状と、それに対する法的な規制の議論を、私たちにリアルに突きつけています。未来の不動産のプロとして、この問題の論点を深く理解しておくことは不可欠です。
なぜ離島の不動産が買われるのか?その背景
まず、なぜ人口わずか7人の小さな島の土地が、海外から注目されるのでしょうか。別荘目的での取得が主であり、瀬戸内海の景観などが人気を博しているようです。しかし、問題はそれだけではありません。瀬戸内海は、多くの船舶が行き交う海上交通の要衝であり、自衛隊や在日米軍の基地も存在する、安全保障上きわめて重要なエリアです。こうした場所に外国資本が流入することに対し、懸念の声が上がるのは当然と言えるでしょう。
専門家が提言する「外為法」による事前審査制度
このような事態に対し、専門家はどのような対策を提言しているのでしょうか。一つ目の重要なポイントが「外国為替及び外国貿易法(外為法)」の見直しです。
宅建試験の範囲ではないですが、現在の外為法では、外国人投資家が不動産を取得した場合、原則として「事後報告」が義務付けられています。しかし、専門家はこれだけでは不十分であり、オーストラリアの事例などを参考に、取引前の「事前審査」のような制度を設けるべきではないか、と指摘しています。つまり、「買った後で報告する」のではなく、「買う前に国のチェックを受ける」という、より厳しい規制への転換です。
豪州の事例に学ぶ「国益」を重視した規制
記事で紹介されているオーストラリアの事例は、今後の日本の法整備を考える上で参考になります。オーストラリアでは、外国人による住宅投資が国の利益(国益)にかなっているかをチェックする制度が設けられています。これは、無秩序な海外からの投資が、自国の不動産価格を不当に高騰させ、国民の生活を圧迫することを防ぐための措置です。安全保障だけでなく、国民生活を守るという観点からも、規制が議論されているのです。
もう一つの選択肢「条例」による地域独自の縛り
国の法律である外為法の改正には時間がかかります。そこで、もう一つの対策として専門家が指摘するのが、自治体による「条例」での対応です。具体的には、以下のようなものが挙げられています。
- 景観条例:地域の景観を守るため、建物のデザインや高さなどを規制する。
- 別荘等所有税:別荘の所有者に対して独自の税金を課す。
このように、国レベルの大きな法改正を待つだけでなく、地域の実情に合わせて、自治体が独自のルールで一定の縛りをかけることも可能である、という視点です。
宅建士に求められる「社会正義」と「合意形成」の視点
今回のニュースで、専門家は「地域住民のウェルビーイング(幸福)」や「ソーシャルジャスティス(社会正義)」という言葉を使っています。これは、私たち宅建士が心に刻むべき非常に重要な概念です。
宅建士の仕事は、単に法律に則って契約を成立させるだけではありません。その不動産取引が、地域社会にどのような影響を与えるのか。住民との「合意形成」は必要ないか。こうした、より広い視野を持つことが、これからの不動産のプロフェッショナルには求められます。特に、過疎地や離島、安全保障上重要なエリアでの取引に関わる際には、法令遵守はもちろんのこと、社会的な文脈を理解し、配慮する姿勢が不可欠となるでしょう。


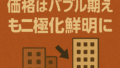
コメント