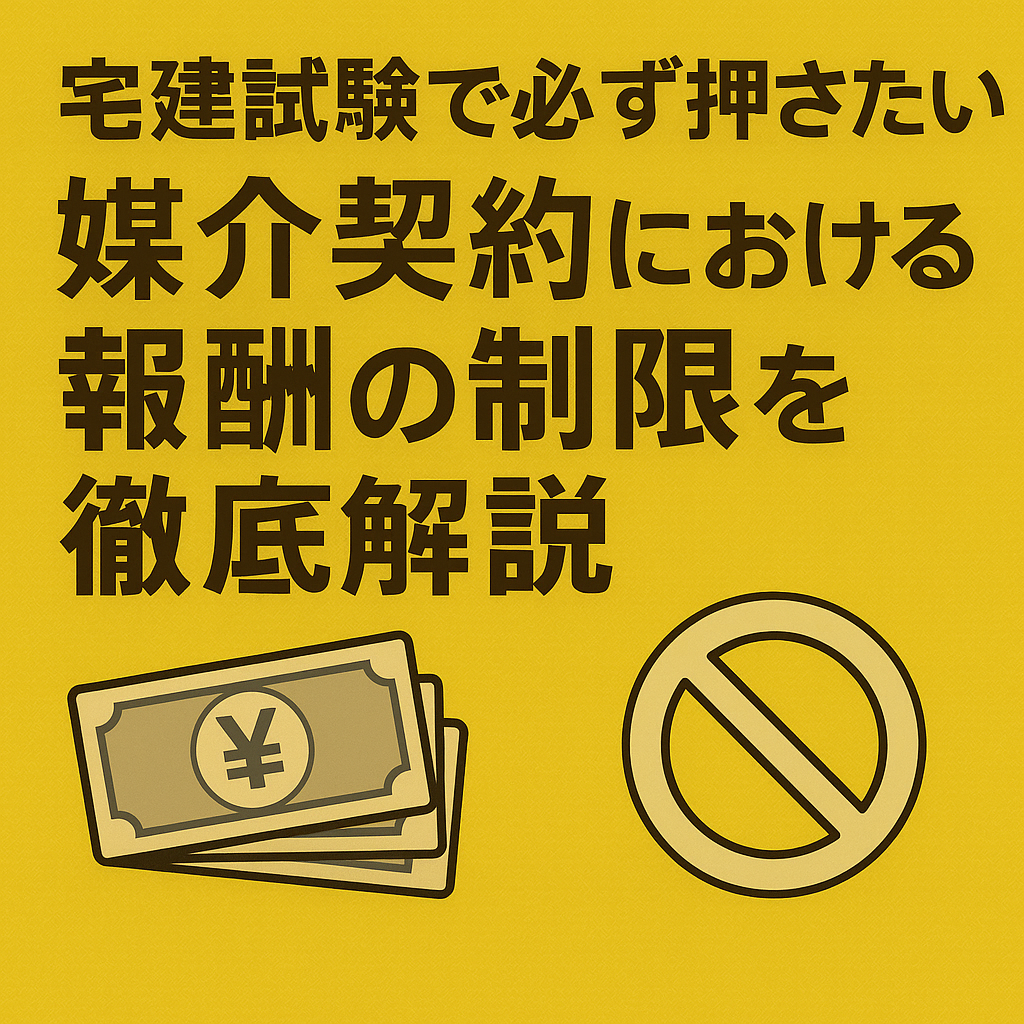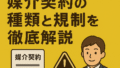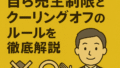宅建試験受験者の皆さん、こんにちは。
今回は媒介契約の第二弾として、宅建業法で定められている報酬の制限について詳しく解説します。
売買・交換・貸借それぞれで異なる報酬額の計算ルールや、消費税の扱い、特例ケースについても例題を交えながら整理しました。
得点源に直結する分野ですので、しっかりマスターしていきましょう。
⸻
報酬の制限とは?
宅建業者が媒介や代理を行い、取引を成立させたときに受け取ることができる報酬には、国土交通大臣が定めた上限額が設定されています。
依頼者との自由な交渉で無制限に高額な報酬を受け取ることを防ぐための制度です。
【ポイント】
- 上限額を超えて受領することは禁止
- 自ら売主の場合は報酬受領禁止(売買益で利益を得るため)
⸻
売買・交換の報酬額(消費税考慮なし)
売買・交換における報酬額の基本計算式は以下の通りです。
【報酬基準額の速算式】
- 200万円以下部分 → 5%
- 200万円超400万円以下部分 → 4%
- 400万円超部分 → 3%+6万円
例:売買代金1,000万円の場合
1,000万円×3%+6万円=36万円
【媒介・代理別の上限】
- 媒介:報酬基準額そのまま(両方から受領可)
- 代理:報酬基準額の2倍(片方からのみ受領)
例題1
売買の媒介で受領できる報酬の計算式として正しいものはどれか?
A. 代金×5%
B. 代金×3%+6万円
C. 代金×4%
D. 代金×2%
正解 → B
⸻
消費税を考慮した報酬額の計算
試験では消費税を含めた計算が必要になります。ポイントは次の2点です。
1. 売買価格から建物分の消費税を除外して報酬基準額を計算
2. 計算後の報酬限度額に消費税を上乗せ
【上乗せ率】
- 課税事業者 → 10%加算
- 免税事業者 → 4%加算
※土地は非課税なので消費税除外不要です。
⸻
貸借の報酬額(消費税考慮なし)
貸借契約では次の2つの制限が設けられています。
【制限1】
- 依頼者双方から受け取れる上限 → 賃料の1ヶ月分
【制限2(居住用建物のみ)】
- 片方から受け取れる上限 → 賃料の0.5ヶ月分(※承諾あれば1ヶ月分までOK)
※事業用建物・代理契約の場合、片方から1ヶ月分までOK(承諾不要)。
例題2
居住用建物の貸借媒介で、借主の承諾がない場合、借主から受領できる報酬の上限は?
A. 賃料1ヶ月分
B. 賃料0.5ヶ月分
C. 賃料2ヶ月分
D. 賃料の制限なし
正解 → B
⸻
貸借の消費税考慮
貸借取引では以下に注意しましょう。
- 居住用建物・土地 → 非課税(消費税除外不要)
- 事務所用建物(課税対象)→ 賃料から消費税を除外して基準額を計算
報酬限度額には、課税事業者なら10%、免税事業者なら4%の消費税を加算します。
⸻
権利金がある場合の特別計算
貸借契約において、権利金が発生する場合には特別ルールが適用されます。
- 権利金を売買代金とみなして、通常の売買同様に報酬額を計算しても良い
- 通常の貸借報酬額と比較して、有利な方を採用可能
⸻
低廉な空き家等の売買・交換の報酬特例
本体価格800万円以下の空き家等については、現地調査などの実費相当額(最大33万円(30万円+消費税10%))を通常の報酬に加算できる特例が認められています。33万円の限度額は通常の報酬と合わせての額で、上乗せできるわけではない点には注意が必要です。
【適用条件】
- 依頼者への事前説明と合意が必要
- 合計33万円が限度
⸻
報酬とは別に請求できる費用の制限
原則、宅建業者は報酬とは別に費用請求できません。
ただし、依頼者の特別な依頼による費用(特別広告・遠方調査など)は別途請求可能です。
「特別な依頼」がない限り、通常業務の経費(広告・事務費など)を請求することはできません。
⸻
試験対策まとめとポイント
この分野のまとめポイントは次の通りです。
- 売買交換の速算式と媒介・代理の違い(媒介は基準額そのまま、代理は2倍)
- 貸借は1ヶ月制限+居住用なら片方0.5ヶ月(承諾あれば1ヶ月)
- 消費税の除外・加算ルールを正確に押さえる
- 権利金・空き家特例の計算方法も確認
- 報酬以外の費用請求には「特別な依頼」が必要
これらをしっかり整理し、例題で繰り返しアウトプットすることが得点アップへの近道です!