賃貸借契約の中でも、「一時使用のための建物賃貸借」「取壊し予定の建物の賃貸借」「終身建物賃貸借」「使用貸借契約」は、試験で混同しやすい分野です。
この記事では、それぞれの違いと押さえるべき判例、また試験で狙われやすい論点を、例題とともに整理していきます。
一時使用のための建物賃貸借とは?
借地借家法40条により、「一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合」は、借地借家法の適用がありません。
この場合、民法の賃貸借に関する一般規定が適用されます。
典型例としては、
- 催事などのために短期間のみ貸す場合
- 建物の改築中に仮店舗として貸す場合
などが挙げられます。
判例での判断基準
単に「期間が短い」だけではなく、次の点を総合的に判断します。
- 目的・動機
→ 賃貸借の目的・動機・契約時の事情から「短期間内に限る趣旨」が客観的に明らかであること(最判昭36・10・10)。 - 期間
→ 「1年未満でなければならない」わけではない(最判昭36・10・10)。 - 書面性
→ 契約書に「一時使用」と書かれていても、実態が伴わなければ一時使用とは認められない(東京高判昭29・12・25)。
つまり、形式よりも実質で判断される点がポイントです。
取壊し予定の建物の賃貸借
借地借家法39条に基づき、次の要件を満たす場合は「更新なし」で契約終了します。
- 法令または契約により一定期間後に建物を取り壊すことが明らかであること
- 書面(または電磁的記録)で特約を結んでいること
- 確定期限を設ける必要はなく、「おおよその時期」が示されていれば足りる
この点は定期建物賃貸借(借地借家法38条)と混同しやすいため注意が必要です。
定期建物賃貸借は「確定した期間の満了」で終了しますが、取壊し予定建物賃貸借は「取り壊す時期が到来した時点」で終了します。
法令による取壊しの例
- 都市計画事業による移転(都市計画法67条)
- 土地区画整理法による除却(77条)
- 土地収用法に基づく収用(102条)
- 都市再開発法による権利変換(87条)
契約による場合の例
- 一般定期借地権(借地借家法22条)
- 事業用定期借地権(借地借家法23条)
例題①:一時使用と定期建物賃貸借の違い
問題:
以下のうち、借地借家法が適用されないのはどれですか?
- 1年の期間を定めて居住のために貸した場合
- 改築のため3か月だけ仮店舗として貸した場合
- 定期建物賃貸借として10年の期間を定めた場合
正解:2
→「一時使用のための賃貸借」は借地借家法の適用が除外されます。期間の短さだけでなく、使用目的が一時的であることが重要です。
終身建物賃貸借(高齢者居住法)
高齢者居住法の目的
正式名称は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」であり、高齢者が安心して生活できる住宅環境を確保することを目的としています。
この法律に基づき、次の制度が設けられています。
- サービス付き高齢者向け住宅の登録制度
- 終身建物賃貸借の認可制度
終身建物賃貸借の内容
都道府県知事の認可を受けた事業者が行う「高齢者本人一代限りの賃貸借契約」です。
借主(原則60歳以上)が死亡した時点で契約が終了します(高齢者居住法52条・54条)。
契約は必ず公正証書等の書面(または電磁的記録)で締結する必要があります。
建物要件
- 国交省令で定める規模・設備基準を満たすこと
- 段差のない床、手すり、車椅子対応などの「加齢対応構造」であること
賃料の増減額
終身建物賃貸借では、賃料増額・減額請求権の排除が可能です(高齢者居住法63条)。
例題②:終身建物賃貸借の特徴
問題:
次のうち、終身建物賃貸借に関する説明として誤っているものはどれですか?
- 賃借人が死亡すると契約は終了する
- 契約書は口頭でも有効である
- 賃料の増減額請求を排除できる
正解:2
→ 終身建物賃貸借は公正証書等の書面で結ぶ必要があります。
使用貸借契約との違い
| 区分 | 賃貸借契約 | 使用貸借契約 |
|---|---|---|
| 対価 | 有償 | 無償 |
| 契約の性質 | 双務契約 | 片務契約 |
| 適用法 | 借地借家法あり | 借地借家法なし |
| 契約終了 | 原則、期間満了・更新可 | 借主死亡で終了 |
| 原状回復義務 | あり(621条) | あり(599条3項) |
特に試験では、**「借主が死亡したときに終了するのはどちらか?」**という設問が頻出です。
→ 答えは「使用貸借契約」(民法597条3項)です。
工作物責任(民法717条)
建物の設置・保存の瑕疵によって第三者に損害が生じた場合、まず「占有者(管理業者など)」が過失責任を負います。
占有者が相当の注意をしていた場合には、「所有者」が無過失責任を負う点がポイントです。
試験対策のまとめ
- 占有者:過失責任
- 所有者:無過失責任
- 建物管理を行う管理業者=占有者とみなされる場合がある
破産と賃貸借
破産が絡むと「賃料債権」や「敷金返還請求権」の取扱いが変わります。
区分
| 種類 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 破産債権 | 破産手続前に発生した債権(未払賃料など) | 破産法100条 |
| 財団債権 | 手続後に発生した債権(将来の賃料) | 破産法2条7項 |
敷金の扱い
貸主が破産した場合、借主は敷金返還請求権を「破産債権」として主張できますが、破産法70条により、敷金分を「寄託」として保護する制度があります。
これにより、借主は敷金の返還を後に精算で受け取ることが可能です。
例題③:破産と敷金の関係
問題:
貸主が破産した場合、借主の敷金返還請求権はどのように扱われますか?
- 財団債権として全額弁済される
- 破産債権となるが、敷金保護のため寄託が認められる
- 自動的に消滅する
正解:2
→ 敷金返還請求権は「破産債権」ですが、破産法70条により寄託による保護が認められています。
まとめ:混同しやすいポイント整理
| 論点 | 終了時期 | 特徴 | 試験の落とし穴 |
|---|---|---|---|
| 一時使用 | 明らかに短期間 | 借地借家法の適用なし | 期間の短さだけで判断しない |
| 取壊し予定 | 取壊し時に終了 | 確定期限不要 | 定期借家契約と混同注意 |
| 終身賃貸借 | 借主死亡時終了 | 高齢者居住法に基づく | 書面要件あり |
| 使用貸借 | 借主死亡時終了 | 無償・片務契約 | 借地借家法の適用なし |
| 破産時 | 管財人が権利義務を承継 | 敷金保護あり | 敷金は破産債権になる |
✅学習アドバイス
賃貸不動産経営管理士試験では、「民法 × 借地借家法 × 高齢者居住法 × 破産法」が絡む複合論点として出題されることがあります。
一見細かい条文も、「どの法律の規定か」を意識して整理することが合格の鍵です。
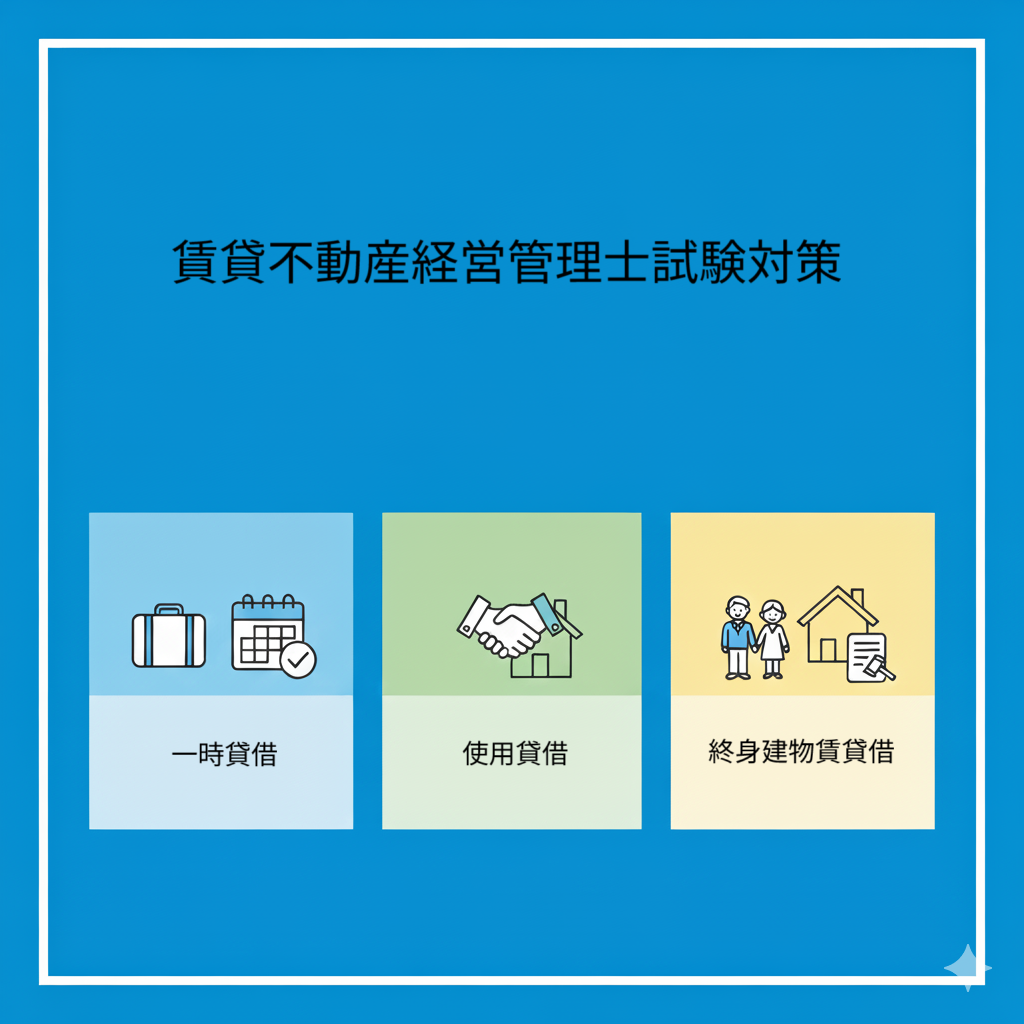


コメント