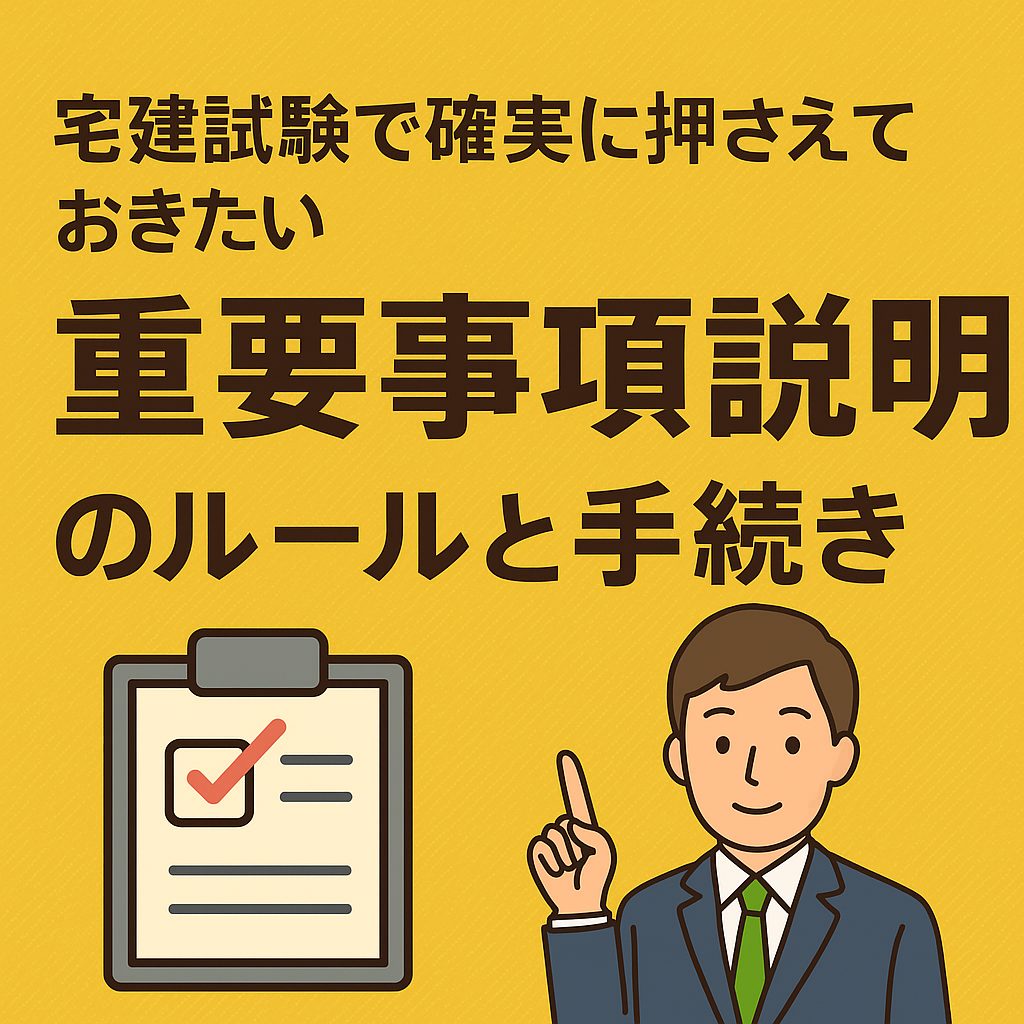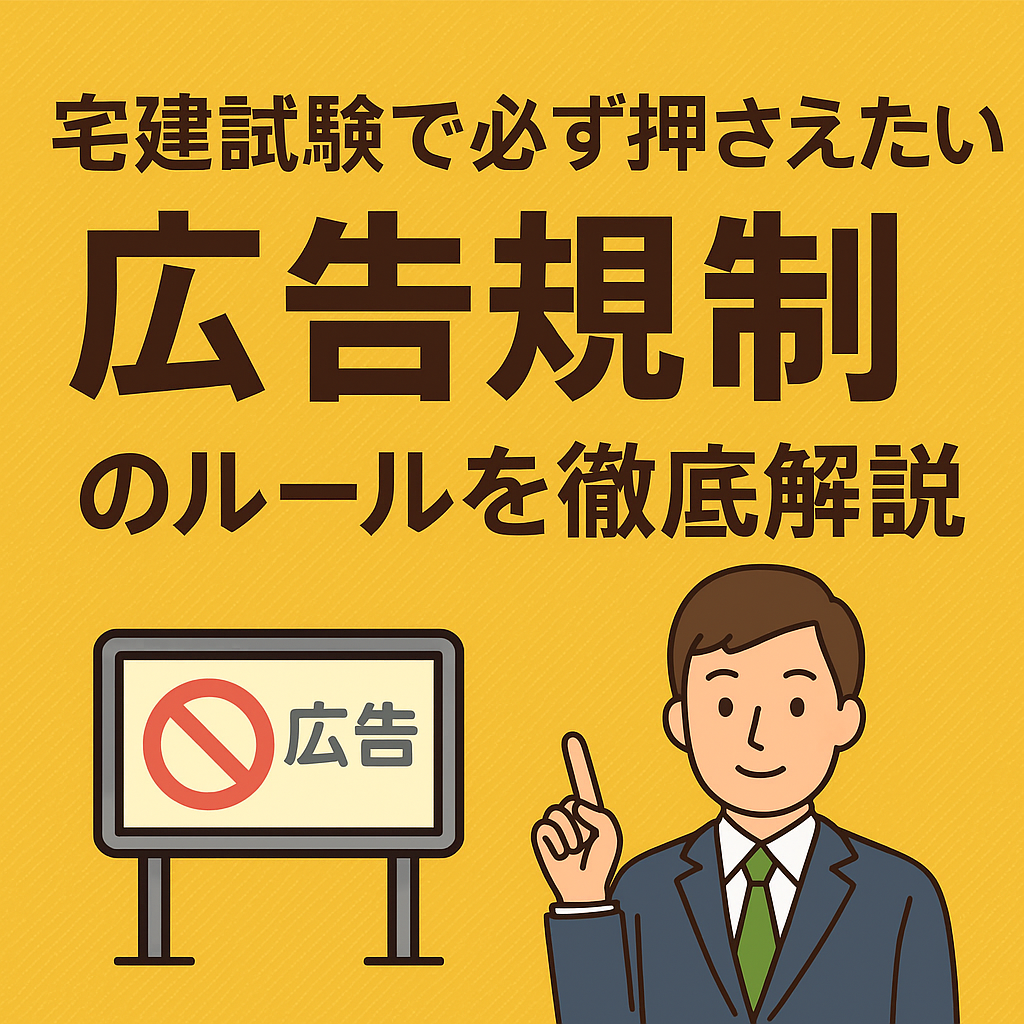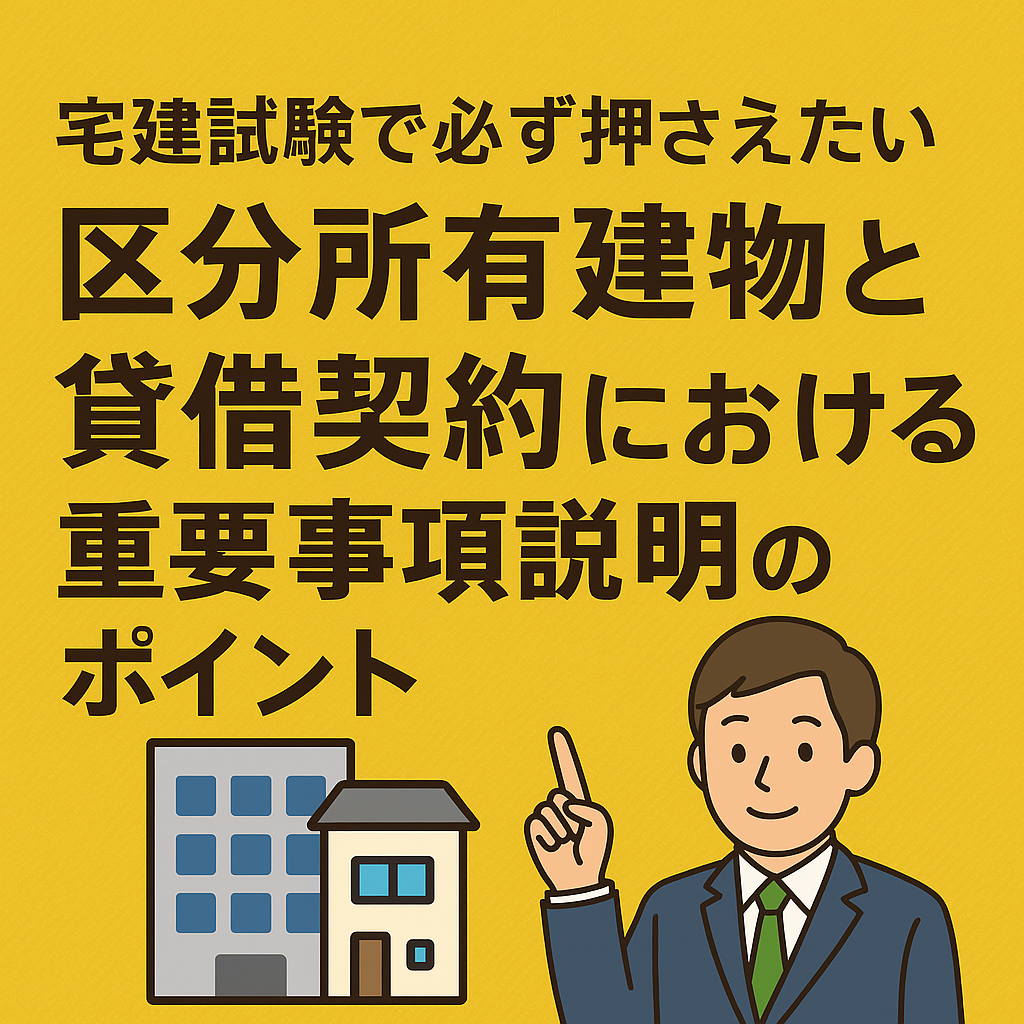宅建試験受験者の皆さん、こんにちは。
今回は宅建業法の中でも毎年出題される「重要事項説明」について詳しく解説します。
35条書面と呼ばれるこの説明は、不動産取引の前に必ず行わなければならない重要な手続きです。
この記事では、誰が・いつ・どこで・どのように行うのか、そして内容の分類と注意点を例題付きで整理しました。
しっかりマスターして試験の得点源にしましょう。
⸻
重要事項説明の基本ルール
宅建業者は、契約を締結する前に物件に関する重要事項を説明する義務があります。
このとき、取引士が記名押印した書面(35条書面)を交付し、取引士証を提示しながら説明する必要があります。
説明義務を負うのは誰か
- 宅建業者(実施者は取引士)
- 取引士は「専任の取引士」でなくても可
説明の相手
- 売買→買主になろうとする者
- 交換→取得しようとする者
- 貸借→借主になろうとする者
※宅建業者相手には書面交付のみで説明は不要
説明のタイミング
契約成立までの間に実施すること。
説明の場所
制限なし。自宅、事務所、カフェ、オンライン(IT重説)でもOK。
⸻
IT重説について
近年はオンラインの「IT重説」も可能になっています。
以下の条件を満たせば、対面と同様の扱いになります。
- 双方向の映像・音声通信で説明と質疑応答が可能
- 事前に重要事項説明書の交付(または電磁的方法での提供)
- 取引士証の提示と画面上での確認
- 通信不具合時は説明を中断し、復旧後再開
⸻
重要事項説明の内容と分類
重要事項説明は大きく3つに分類できます。
① 基本的な情報
- 登記内容・所有者氏名
- 法令上の制限(用途地域、建蔽率など)
- 私道負担
- インフラ整備状況
- 未完成物件の完成時概要
② 取引条件の情報
- 手付金や権利金の額と目的
- 契約解除の方法
- 損害賠償や違約金
- 手付金等の保全措置
- ローンあっせんの有無と不成立時の措置
- 保証保険契約の有無と概要
③ その他 相手方保護のための重要事項
- 土砂災害・津波災害警戒区域内の有無
- 水害ハザードマップ上の所在地
- アスベスト使用の有無
- 耐震診断の有無
- 住宅性能評価の有無(新築のみ)
⸻
例題で確認!
例題1
重要事項説明は誰が行う必要があるか?
A. 宅建業者の従業員
B. 取引士
C. 専任取引士
D. 誰でも可
正解 → B
説明は必ず取引士が行います。専任である必要はありません。
例題2
建築確認未了の物件について「確認後契約可」と注記して広告した。違反か?
A. 違反しない
B. 違反する
正解 → B
建築確認が下りるまで広告不可。注記しても違反です。
例題3
水害ハザードマップの内容として説明義務がないものは?
A. 建物の所在地
B. 洪水の危険度
C. 最寄り避難所の位置
D. 津波災害警戒区域
正解 → C
避難所の位置は説明義務なし。ただし案内するのは望ましい。
⸻
試験攻略まとめとポイント
重要事項説明で必ず押さえるべき点は次のとおり。
- 説明者は取引士、専任でなくてもよい
- 必ず取引士証を提示し、35条書面を交付する
- 売主・買主が宅建業者の場合は書面のみでOK
- IT重説は映像と音声の双方向で可能
- 水害ハザードマップ、土砂・津波災害区域の説明は義務
- 建物貸借のみ説明不要の項目に注意
暗記の際は、35条書面と37条書面(契約書)の記載事項の違いにも注意しましょう。
過去問でよく問われるのは、どちらに記載すべきかの区別です。
「代金」「借賃」「支払方法」「登記・引渡しの時期」などは37条書面の記載事項です。