住生活基本計画の最終章では、これまで掲げた目標や方針をどのように実現するかという実施体制がまとめられています。
ここでは、「国・地方公共団体・民間事業者・国民」の役割分担が明確に示されており、賃貸不動産経営管理士試験でも問われる可能性のある部分です。
第4章の目的
この章の目的は、
「住生活基本法」に基づく基本理念を具体化し、国民一人ひとりの住生活の向上を図るための施策を、総合的かつ計画的に進めること
です。
つまり、「国の計画(全国計画)」が実効性をもって運用されるための仕組みづくりがポイントです。
主な推進の仕組み
「施策の総合的かつ計画的な推進」は、次の4つの柱で構成されています。
- 国、地方公共団体、民間事業者、国民の役割分担
- 住宅政策関連制度の連携・統合
- データに基づく政策運営(EBPM)の推進
- 計画の進行管理と見直し
それぞれの内容を順に見ていきましょう。
① 各主体の役割分担
■ 国(国土交通省など)
- 住生活基本法に基づく全国計画の策定・実施・評価を行う。
- 住宅政策全体の総合調整役として、関係省庁・自治体との連携を主導。
- 公営住宅、住宅金融支援、住宅性能評価などの全国的制度を整備。
- 住宅関連データの収集・分析・公開を通じ、政策立案を支援。
■ 都道府県・市町村
- 地域の実情に応じた地方計画(都道府県計画・市町村計画)を策定。
- 国の方針と整合を図りながら、住宅確保要配慮者支援、空き家対策、耐震化促進などを地域単位で実施。
- 都市計画、福祉政策、防災政策などとの連携を強化。
■ 民間事業者
- 新築・リフォーム・賃貸管理・流通などを通じて住宅市場を担う中心的存在。
- 省エネ住宅やZEH、リノベーション、管理の高度化などで良質な住宅ストック形成に貢献。
- 登録住宅制度や居住支援事業への参画も期待される。
■ 国民(居住者・消費者)
- 安全・安心で持続可能な住まいづくりに積極的に関与。
- 空き家の適正管理、災害時の自助努力、住宅の長寿命化への意識向上が求められる。
② 住宅政策の連携と統合
「住宅だけ」に焦点を当てず、他の分野と連携した政策推進が特徴です。
主な連携分野
| 分野 | 具体的な連携内容 |
|---|---|
| 都市計画 | 立地適正化計画・都市再生特別措置法との整合を図る。 |
| 福祉政策 | 高齢者・障害者・低所得者への居住支援を福祉部局と連携して実施。 |
| 防災・減災 | 災害リスクの高い地域での住宅立地抑制、被災者の住まい確保支援。 |
| 環境政策 | ZEH、LCCM住宅、省エネ改修の普及で脱炭素社会を推進。 |
| 地域振興 | 空き家活用・二地域居住・テレワーク推進などによる地方創生。 |
このように、住宅政策は他の行政分野と一体化して進められる点が重要です。
③ データに基づく政策運営(EBPM)
EBPMとは、
Evidence-Based Policy Making(証拠に基づく政策立案)
の略です。
計画では、以下のような施策が示されています。
- 住宅・土地統計調査や登記データ、建築確認データなどの活用。
- 空き家、耐震性、省エネ性能などの情報を「住宅ストックデータベース」として整備。
- 政策効果を定量的に評価し、必要に応じて見直しを実施。
→ このEBPMの導入は、今後の賃貸経営にも影響するトレンドであり、本年の試験でも出てくる可能性のある新しいキーワードです。
④ 計画の進行管理と見直し
住生活基本計画は、一度作って終わりではありません。
概ね5年ごとに見直しが行われ、社会状況の変化に応じて改定されます。
- 国土交通省が施策の進行状況を定期的に公表。
- 有識者による「住生活基本計画フォローアップ会議」などで進捗を検証。
- 必要に応じて新しい目標値や施策を設定。
→ 現行の令和3年計画も、令和8年頃に中間見直しが想定されています。
試験で問われるポイントまとめ
| 出題テーマ | 押さえるポイント |
|---|---|
| 各主体の役割 | 国=全国計画/都道府県・市町村=地方計画の策定 |
| 民間の役割 | 良質な住宅ストック形成、居住支援事業への参画 |
| 国民の役割 | 自助努力・空き家管理・防災意識 |
| 連携分野 | 都市計画・福祉・防災・環境・地域振興との統合 |
| EBPM | データに基づく政策立案・住宅ストックDB |
| 見直し | 概ね5年ごと、進行状況は国交省が公表 |
【例題】
問題:
住生活基本計画の「施策の総合的かつ計画的な推進」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A. 住生活基本計画は、一度策定されれば原則として改定されない。
B. 都道府県や市町村は、全国計画に基づく地方計画を策定することができない。
C. EBPMとは、経験や勘に基づいた政策立案を指す。
D. 民間事業者は、良質な住宅ストック形成の担い手として期待されている。
正解:D
→ 民間事業者は、賃貸住宅の供給・管理を含む住宅市場全体の担い手として重要な役割を果たします。
まとめ
第4章「施策の総合的かつ計画的な推進」は、
住生活基本計画の実現のための仕組み部分です。
国・地方・民間・国民それぞれの役割を整理し、EBPMや見直しのサイクルを理解しておくことが、試験対策のポイントになります。
特に「EBPM」「住宅ストックデータベース」「概ね5年ごとの見直し」は要チェックです!

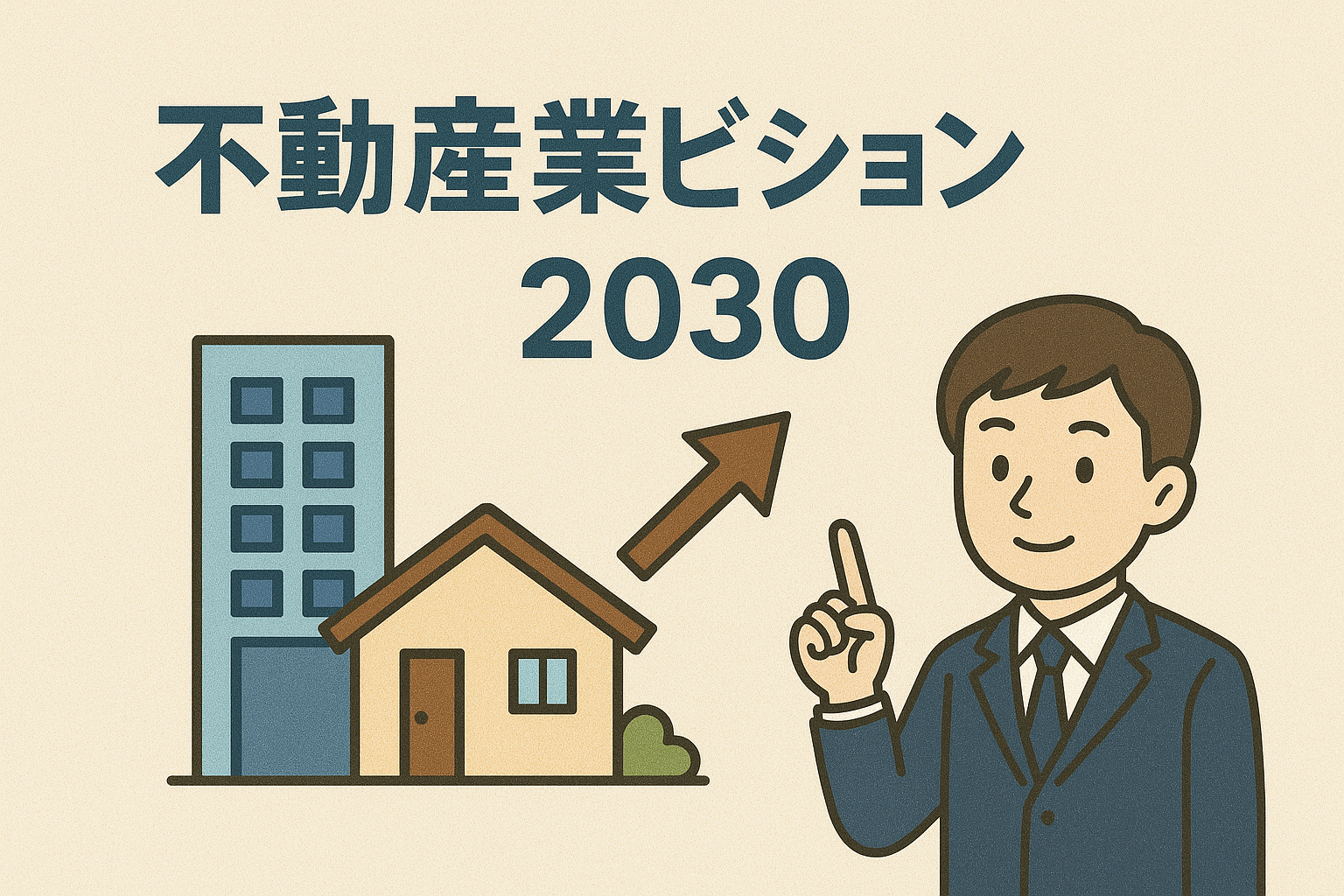
コメント