宅建試験においては、不当表示や広告に関するルールを定めた景品表示法の理解が問われます。本記事では、景品表示法の目的から、具体的な広告規制、不動産業界における表現ルールまで、例題を交えて徹底解説します。合格に直結する知識をしっかりインプットしていきましょう。
景品表示法と不動産広告の関係
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。この法律の目的は、一般消費者が不当な景品や虚偽の表示によって誤って取引をしないよう保護することにあります。不動産取引においても、チラシ・パンフレット・看板・ウェブサイトなど、すべての広告に適用されます。
加えて、不動産業界では「不動産の表示に関する公正競争規約」や「景品類の提供の制限に関する公正競争規約」など、独自のルールが設けられています。
不当表示と措置命令の仕組み
事業者が、商品や役務(サービス)について、実際よりも優良または有利だと誤認させる表示をした場合、不当表示となり禁止されています。
内閣総理大臣(実際は消費者庁長官)や都道府県知事は、このような違反に対し「措置命令」を出すことができます。措置命令には行為の差し止めや再発防止策の命令などが含まれます。
例題:
Q. 不当表示があった場合、被害者が出ていなくても違反となる。○か×か?
→ 正解:○
表示自体が不当であれば違反になります。
優良誤認・有利誤認の具体例
景品表示法では、次のような表示は原則として禁止されています。
- 不当な二重価格表示
- おとり広告
- 実際よりも優良な物件であるように見せる表示
- 実際よりも有利なローン利率を表示
- 根拠のない比較広告
たとえば「通常価格5,000万円のところ、今なら4,000万円!」といった表示が、実際には5,000万円で販売されていなかった場合は違反になります。
例題:
Q. アドオン利率だけを表示し、実質年率を明示しないのは違法である。○か×か?
→ 正解:○
実際よりも低利に見せかけるため、誤認を招く表示に該当します。
建築前の物件広告に関するルール
建築中や完成前の物件を広告する際には、以下の条件を満たす場合に限り、過去に施工した建物の写真などを使うことが認められます。
- 外観・仕様・構造などが類似している
- 写真が他の建物である旨を明示する
- 内装も同様に条件を満たすものに限る
誤認を防ぐため、写真の近くに明示表示が必要となります。
特殊な物件に関する表示義務
特定の特徴を持つ物件については、広告でその内容を正確に明記しなければなりません。たとえば以下のような場合です。
- 高圧電線の下にある土地 → 面積と制限の有無を明記
- 傾斜地が30%以上 → 割合または面積を表示
- 路地状の土地 → 路地部分の割合表示
例題:
Q. 傾斜地が30%未満でも、有効利用に支障がある場合は表示義務がある。○か×か?
→ 正解:○
傾斜地による支障があれば、割合表示が必要です。
景品の提供に関する制限
不動産業界では、懸賞やプレゼントによる景品提供も厳しく制限されています。
- 懸賞による場合 → 取引価格の20倍または10万円まで、かつ総額は取引総額の2%以内
- 全員提供する場合 → 取引価格の10分の1または100万円まで
例題:
Q. 懸賞によらない景品提供でも、100万円を超えてはならない。○か×か?
→ 正解:○
10分の1または100万円のいずれか低い方が上限です。
交通機関や施設の表示ルール
徒歩時間は毎分80mで換算し、1分未満は繰り上げます。電車やバスの所要時間についても、種別やラッシュ時の時間、乗り換え時間まで明記する必要があります。
施設についても、現に利用できる施設名や距離を明示する必要があります。将来的に設置される施設については、公式な発表がない限り記載できません。
NGワードの具体例と規制
以下のような表現は、使用に際して制限があります。
- 「完全」「絶対」→ 資料があればOK
- 「最安」「日本一」→ 根拠資料が必要
- 「新築」→ 建築完了1年未満かつ未入居
- 「新発売」→ 初回販売時や販売期が明確な場合
例題:
Q. 建築から8か月経過し入居済の物件に「新築」の表示は可能である。○か×か?
→ 正解:×
未入居が条件なのでNGです。
まとめ
景品表示法は、消費者を守るための重要な法律であり、宅建業者が広告や販売促進を行う際には必ず守るべきルールが詰まっています。試験でも出題率の高いテーマのため、事例や数値基準を含めて確実に押さえておきましょう。
試験本番で自信を持って解答できるよう、繰り返し問題演習をして理解を深めてください。
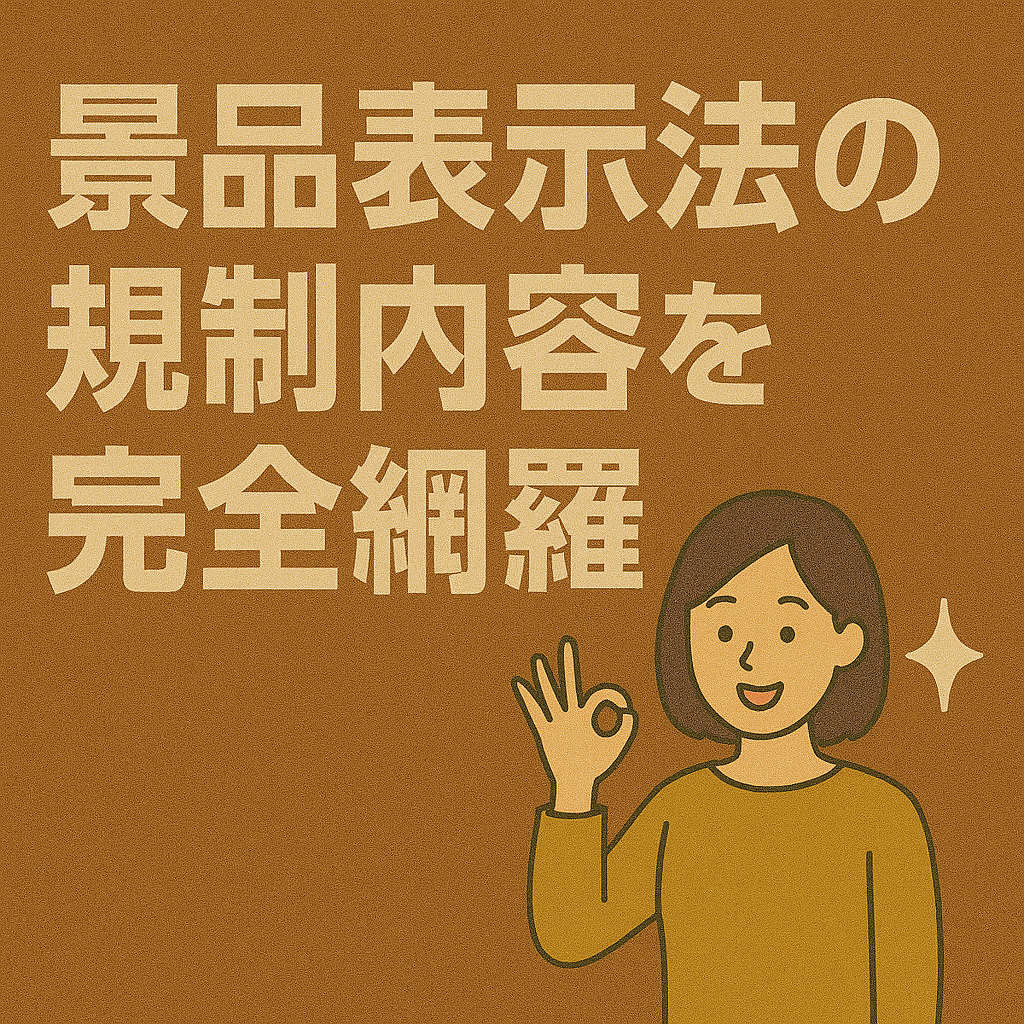

コメント