宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
今回は、最新の調査から見えてきた「新築戸建て購入者」のリアルな姿について解説します。リクルートの調査によると、2024年に首都圏で新築戸建てを購入した世帯の7割以上が「共働き世帯」であることが明らかになりました。これは調査開始以来、最高の比率です。なぜ今、共働き世帯の比率がこれほど高まっているのか。その背景を理解することは、現代の不動産市場の構造と、顧客の姿を捉える上で非常に重要です。
購入者の新常識「世帯年収875万円・共働き率7割」
まず、現代の住宅購入者の平均像をデータで確認しましょう。2024年の新築戸建て購入者の平均世帯年収は875万円、そして共働き比率は72%に達しました。物件の平均購入価格も4844万円と過去最高を更新しており、特に東京23区では7202万円と、7000万円の大台を突破しています。この「高価格な住宅」と「共働きの増加」は、切っても切れない関係にあるのです。
高価格化を支える「ペアローン」という選択
高騰する住宅価格を、どうやって現在の所得で購入しているのでしょうか。その鍵を握るのが「ペアローン」です。ペアローンとは、一つの物件に対し、夫婦がそれぞれ住宅ローンを契約し、お互いが連帯保証人になる仕組みです。これにより、単独でローンを組む場合に比べて、借入可能額を大幅に増やすことができます(ある調査では1.3倍になるとも言われています)。共働き世帯の増加は、このペアローンという金融商品を活用して、高額な住宅を購入するための必然的な流れとも言えるのです。宅建士としては、このペアローンの仕組みやメリット・デメリットを顧客に正確に説明できる知識が不可欠です。
土地は狭く、建物は広く「3階建て」の増加
物件の物理的な特徴にも、市場の変化は表れています。今回の調査では、平均の土地面積は2年連続で縮小した一方で、建物面積は2年連続で拡大したという、一見矛盾した結果が出ています。これは、土地価格の高騰が著しい首都圏において、限られた土地を最大限に活用するために「3階建て」住宅の供給が増えていることを示唆しています。狭い土地でも、上に階を重ねることで、広い居住スペースを確保するという工夫です。こうしたトレンドは、物件を案内する際の重要なポイントとなります。
変化する購入動機「資産性」への注目
なぜ人々は、ローンを工夫し、3階建てを選んでまで家を買うのでしょうか。「子供や家族のため」「もっと広い家に住みたい」といった従来からの動機が依然として多い一方で、近年は「資産を持ちたい、資産として有利だと思ったから」という、資産価値を重視する声が増加しています。インフレが進み、将来への不安が高まる中で、不動産を単なる「住む場所」としてだけでなく、自身の財産を守り、増やすための「資産」として捉える価値観が広がっているのです。
宅建士が向き合う「新しい顧客像」と提案力
今回の調査結果は、私たち宅建士が向き合う「顧客像」が大きく変化していることを教えてくれます。もはや、夫の単独収入で家を買うというモデルは少数派となり、ペアローンを組む共働き世帯がスタンダードです。彼らは、家族の快適な暮らしを求めると同時に、その家の「資産性」にも敏感です。
これからの宅建士には、法律や物件の知識はもちろんのこと、ペアローンのような複雑な金融商品の知識、3階建て住宅のメリット・デメリットに関する建築的な知識、そして顧客の資産形成にまで踏み込んだ提案力が求められます。試験で学ぶ一つひとつの知識が、この新しい時代の顧客の多様なニーズに応えるための武器となるのです。

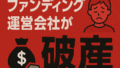
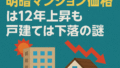
コメント