宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
2021年7月3日に静岡県熱海市で発生した大規模土石流災害から、4年の歳月が経ちました。今なお、法廷では原因究明と責任の所在をめぐる議論が続き、遺族の方々はもどかしい思いを抱えています。この「人災」とも言われる悲劇は、私たち不動産業界に関わる者にとって、決して他人事ではありません。そして、この災害を直接的なきっかけとして、ある重要な法律が大幅に改正されました。それが「盛土規制法」です。
なぜ悲劇は防げなかったのか
ニュースでも報じられている通り、熱海の土石流は不適切な「盛り土」が崩落したことが原因とされています。しかし、誰にその責任があるのか、法的な判断は未だ確定していません。行政と事業者が互いに責任をなすり付け合う状況は、改正前の法制度に隙間があったことの裏返しとも言えます。従来の「宅地造成等規制法」では規制の対象が宅地造成などに限定されており、森林や農地での盛り土など、規制が及ばない危険なケースが存在していました。
熱海を教訓に改正された「盛土規制法」
このような悲劇を二度と繰り返さないために、国が動きました。そして、従来の「宅地造成等規制法」を大幅に改正し、2023年5月に全面施行されたのが「宅地造成及び特定盛土等規制法」、通称「盛土規制法」です。この法改正の最大の目的は、これまで規制が及ばなかった危険な盛り土を、土地の用途にかかわらず全国一律の基準で、隙間なく規制することにあります。
宅建士として押さえるべき法改正のポイント
盛土規制法を学ぶ上で、宅建受験者が必ず押さえるべきポイントがいくつかあります。まず、都道府県知事が「宅地造成等工事規制区域」や「特定盛土等規制区域」を指定することです。これらの区域内で一定の工事を行う場合、知事の許可が必要になります。つまり、不動産取引の際には、対象地がこの区域に含まれているかどうかの調査が、宅建士の重要な責務の一つとなったのです。
重要事項説明における責任の重み
区域の指定の有無は、買主の土地利用計画や安全性に直結する極めて重要な情報です。したがって、宅建士は重要事項説明(重説)において、この点を正確に説明する義務を負います。万が一、説明を怠ったり誤った説明をしたりすれば、損害賠償責任を問われる可能性も十分にあります。この法律は、宅建士の調査義務と説明責任の範囲をより広げ、その専門性を一層高めるものなのです。
法律の背景を知り、未来の責任を担う
熱海で起きた悲劇は、一つの盛り土が多くの人々の命や生活を奪い、今なお遺族を苦しめているという事実を私たちに突きつけています。盛土規制法を単なる試験知識として覚えるだけでなく、「なぜこの法律が改正されなければならなかったのか」という背景を理解することが大切です。法律の条文一つひとつの向こうには、守るべき人の命と暮らしがあります。その重みを理解してこそ、信頼される不動産のプロフェッショナルになれるはずです。


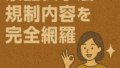
コメント