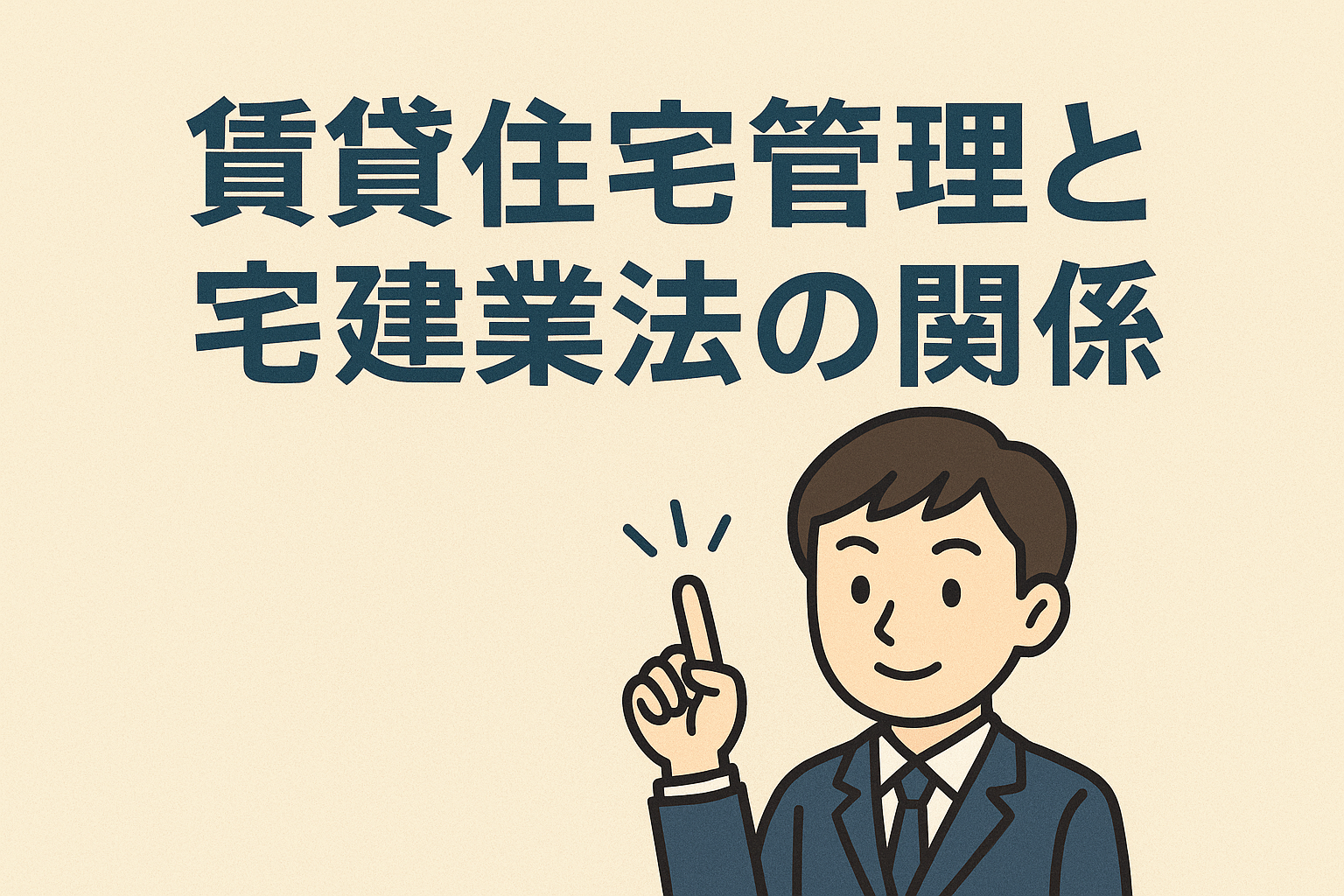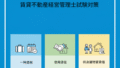宅建試験、賃貸不動産経営管理士試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
試験直前期、最後の追い込み本当にお疲れ様です。今回は、本日10月16日に発表されたばかりの、不動産市場の潮目の変化を示すかもしれない非常に重要なデータについて解説します。東京カンテイの調査によると、2025年9月の首都圏分譲マンションの平均募集賃料が、10ヶ月ぶりに下落に転じたのです。これまで上昇一辺倒に見えた市場に、何が起きているのでしょうか。この背景を読み解くことは、皆さんの試験知識と実務能力を直結させる絶好の機会です。
何が起きた?首都圏(1都3県)がそろって下落
まず、今回のニュースの核心部分です。9月の首都圏の平均賃料は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県すべてで前月比マイナスとなりました。これまで力強く市場を牽引してきた東京都でさえ1.2%低下するなど、広範囲で賃料の弱含みが見られます。
一方、近畿圏も4ヶ月連続で下落傾向が続く中、大阪府では上昇。中部圏・愛知県では過去1年の最高値を更新するなど、地域によって全く異なる動きを見せており、市場の複雑さがうかがえます。
なぜ首都圏の賃料は下落に転じたのか?3つの考察
これまで上昇を続けてきた首都圏の賃料が、なぜここにきて下落したのでしょうか。複数の要因が考えられます。
- 高騰しすぎた賃料への抵抗感(アフォーダビリティの限界)
これまで賃料は上昇を続けてきましたが、借り手の所得の上昇がそれに追いつかず、ついに「高すぎる」という抵抗感(価格抵抗)が強まってきた可能性があります。特にファミリー層などは、予算の上限から少しでも賃料の安い物件やエリアを探す動きを強め、結果として平均賃料を押し下げたのかもしれません。 - 新築・築浅物件の供給サイクルの影響
近畿圏のレポートで「築浅事例の減少」が言及されているように、賃料相場は、その月に募集が出された物件の築年数に大きく影響されます。首都圏でも、たまたま9月は高額な賃料を設定できる新築・築浅物件の募集が少なく、相対的に賃料の安い築年数の古い物件の募集が多かったため、全体の平均値が下がったという一時的な要因も考えられます。 - 金利上昇観測による「貸す」から「売る」へのシフト
少し専門的になりますが、将来の金利上昇を見越した投資家(オーナー)の一部が、「賃料収入(インカムゲイン)」よりも「売却益(キャピタルゲイン)」を優先し、賃貸に出していた物件を売却市場に回す動きが出始めた可能性も否定できません。賃貸市場の供給が少し緩んだことも、賃料の頭打ちにつながったのかもしれません。
【試験知識とのリンク】このニュースから何を学ぶか
このニュースは、皆さんがまさに試験で学んでいる知識と密接に結びついています。
- (賃貸不動産経営管理士)市場調査と賃料査定
賃貸不動産経営管理士にとって、適正な賃料を査定する能力は最も重要なスキルの一つです。今回のデータは、賃料が「需要と供給のバランス」「地域の経済状況」「金利動向」そして「新規供給物件の質と量」といった様々な要因で常に変動していることを示しています。管理業務を行う上で、こうしたマクロな市場動向を常に把握し、オーナーに的確な賃料設定をアドバイスすることがいかに重要であるかを物語っています。 - (宅建)不動産市場の経済変動
宅建試験の「税・その他」の分野では、地価公示や不動産市場の動向が問われることがあります。今回のニュースは、不動産価格(今回は賃料)が、一本調子で上がり続けるわけではなく、必ず調整局面や転換点が訪れることを示す好例です。市場を分析する際には、平均値だけでなく、その内訳(エリア別、築年数別など)を細かく見ていく必要があること。そして、その背景にある経済的な要因を考察する視点が不可欠です。
「なぜ?」を考えることがプロへの第一歩
試験まで残りわずか。多くの知識をインプットすることで頭がいっぱいになっているかもしれません。しかし、そんな時こそ、こうしたリアルな市場のニュースに触れ、「なぜ賃料が下がったのだろう?」と考えてみてください。その「なぜ?」を考えるプロセスこそが、暗記した知識を「使える知恵」に変え、合格の先にある実務で活躍するための、プロとしての第一歩となるのです。
最後の最後まで、体調に気をつけて頑張り抜いてください。応援しています!