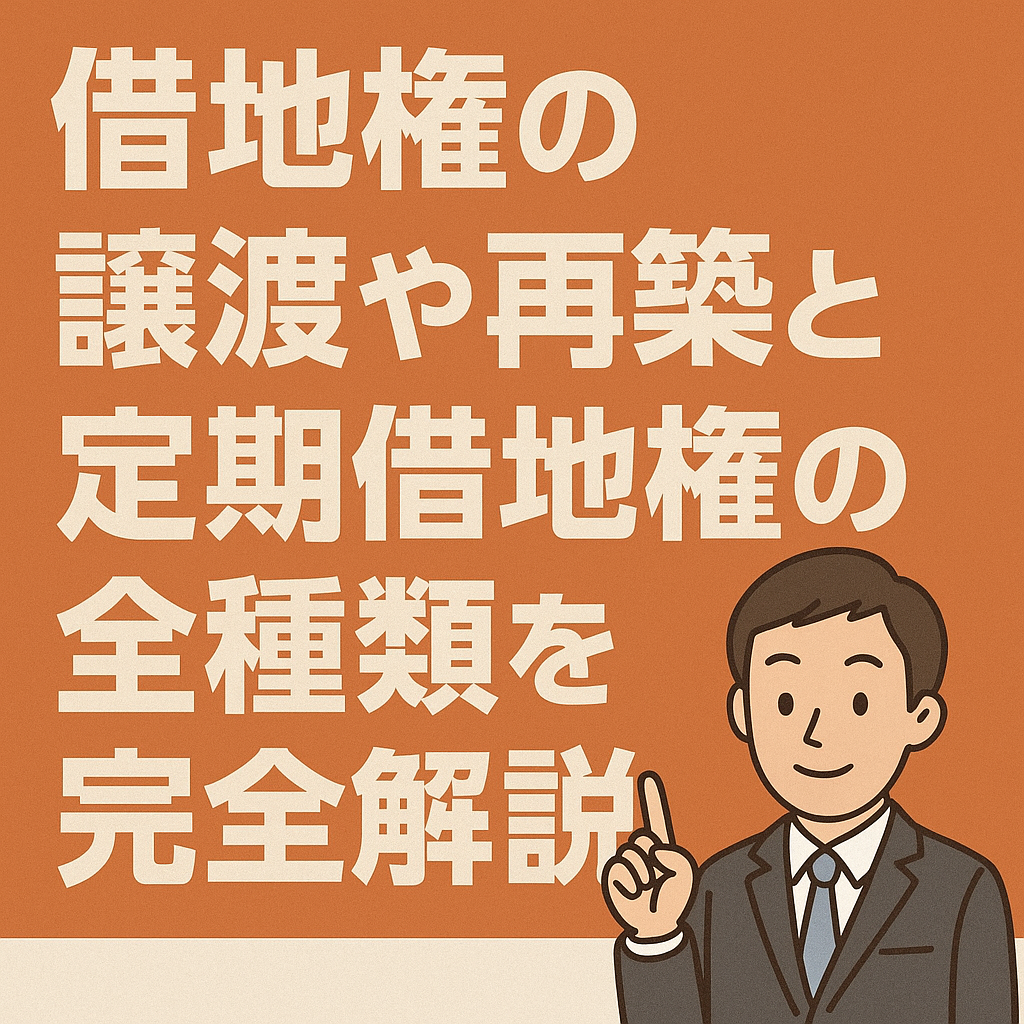借地権に関する知識は宅建試験の中でも出題頻度が高く、法的な手続きや特例の理解が問われます。特に借地権の譲渡や再築に関する裁判所の許可制度や、定期借地権の種類と要件、建物の滅失時の対応などは正確な知識が必要です。
この記事では、実務と試験に役立つ知識をしっかり整理しながら解説していきます。
⸻
裁判所の許可が必要になる場面とその仕組み
借地権の譲渡と裁判所の許可
借地上の建物が譲渡される場合、通常は借地権も一体として譲渡されたものと推定されます。しかし、地主が譲渡に承諾しない場合でも、借地権者が裁判所に申立てることで、承諾に代わる許可を得ることが可能です。
- 裁判所に申立てるのは借地権者
- 建物の買主(第三者)は建物買取請求権を行使可能
- 裁判所の許可や地主の承諾があると、賃借人の地位は新所有者に移転します
借地上の建物の競売と許可
借地上の建物を競売で取得した場合でも、借地権の譲渡には地主の承諾が必要です。承諾が得られないとき、競落人(買受人)は裁判所に申立てて許可を得られます。
- 申立期間は、代金支払後2か月以内
- この場合も買受人は建物買取請求権を行使可能
⸻
借地条件の変更・増改築の許可
借地条件の変更
土地利用に関する法令や地域状況の変化により、既存の借地条件(例:建物の構造制限等)が不相当になった場合、当事者間で協議が調わなければ、裁判所に申立てて条件変更の許可を得ることができます。
増改築の制限と許可
借地契約で増改築が制限されている場合でも、土地の通常の利用上、相当と認められる増改築については、借地権者が裁判所に申立て、地主の承諾に代わる許可を得ることができます。
⸻
借地上の建物が滅失した場合の取扱い
当初契約期間中の滅失
借地権者が契約期間中に建物を滅失し、再築を行う場合:
- 地主の承諾があれば、新たに20年間の借地期間が始まる
- 承諾がなければ、期間延長なし。ただし更新は可能
みなし承諾制度
再築の通知をして地主が2か月以内に異議を述べなければ、「承諾があった」とみなされ、期間延長の効果が発生します。
⸻
更新後の滅失
更新後に建物が滅失した場合:
- 地主の承諾があれば同様に20年の期間延長が可能
- ただし、みなし承諾の制度は適用されない
地主が承諾しない場合でも、借地権者にやむを得ない事情があれば、裁判所が許可を与えることも可能です。
⸻
定期借地権とは?3種類の内容と要件
定期借地権は、通常の借地権と異なり、「更新なし」「再築による延長なし」「建物買取請求権なし」の3点が共通する特徴です。以下の3種類があります。
① 一般定期借地権
- 50年以上の存続期間
- 更新・再築による延長なし
- 建物買取請求権なし
- 書面(公正証書でなくても可)が必要(電磁的記録も可)
- 目的建物は自由(居住用・事業用どちらも可)
② 事業用定期借地権
- 10年以上50年未満の存続期間
- 目的は事業用建物の所有に限定(居住用は不可)
- 必ず公正証書による契約が必要
- 更新・再築延長・買取請求は一切なし
【補足】
- 10年以上30年未満:上記3項目は無条件で適用外
- 30年以上50年未満:特約により適用外とすることができる(特約なしなら通常の借地権に準ずる)
③ 建物譲渡特約付借地権
- 設定から30年以上経過した時点で建物を地主に譲渡
- 書面不要
- 居住用でも事業用でもOK
- 借地権消滅後も使用を継続していれば、借地権の賃貸借契約が成立したものとみなされる
⸻
実力確認!例題で知識を定着
例題1:次のうち、裁判所の許可を申立てできるのは誰か?
ア.借地権を譲り受けた者
イ.建物を競売で落札した者
ウ.借地権者本人
エ.地主本人
正解:ウ(借地権者本人)
⸻
例題2:当初契約期間中に建物が滅失した場合に関する記述で正しいものはどれか?
ア.再築しても借地期間は延長されない
イ.地主の承諾があれば20年延長される
ウ.更新後の場合でもみなし承諾制度がある
エ.みなし承諾制度があるのは更新後である
正解:イ
⸻
例題3:次の定期借地権に関する記述で正しいものはどれか?
ア.事業用定期借地権は必ず書面で締結すればよい
イ.一般定期借地権の契約は居住用目的では設定できない
ウ.建物譲渡特約付借地権は30年以上で譲渡すればよい
エ.事業用定期借地権は再築によって延長が可能である
正解:ウ
⸻
まとめ
今回の借地権(2)では、以下の点を押さえておくことが宅建試験対策として非常に重要です。
- 借地権の譲渡や競売後でも、裁判所の許可により譲渡が可能
- 借地条件や増改築の制限も、裁判所の許可で変更可能
- 建物滅失時の再築では、当初契約期間中はみなし承諾制度あり、更新後はなし
- 定期借地権は3種類あり、それぞれ要件や効力が異なる
⸻