宅建試験では、土地と建物に関する基本的な知識も頻出分野のひとつです。とくに宅地に適した地形や、建物構造の種類・特徴に関する問題は、毎年安定して出題されます。本記事では、土地・建物の出題ポイントを例題とともに丁寧に解説します。
宅建試験における土地問題とは
土地に関する問題では、「この土地は宅地に適しているか否か」が主な論点となります。災害リスクや地形の特徴を正確に把握することで、出題パターンに強くなれます。
特に次のような土地は、宅地に不適とされる傾向があります。
- 盛土・地すべり地・崖錐
- 谷底平野・旧河道・干拓地
- 埋立地(液状化の恐れがある)
例題:
Q. 地すべり地では、一般に宅地造成に適している。○か×か?
→ 正解:×
よく出る地形の特徴と宅地適性
以下に、代表的な地形と宅地への適性をまとめます。
- 丘陵・段丘・台地:水はけが良く地盤も安定。宅地に適している。
- 扇状地:水はけが良く、宅地向き。ただし土石流に注意。
- 後背低地・旧河道:水はけが悪く、軟弱地盤。宅地には不適。
また、等高線の読み取りも重要です。傾斜が急なら線が密になり、ゆるやかなら疎になります。地図上で谷や尾根を見極められるかも問われることがあります。
例題:
Q. 等高線の間隔が大きく乱れている場合、過去に崩壊した可能性がある。○か×か?
→ 正解:○
盛土と切土の違いと宅地リスク
- 盛土:軟らかく、沈下や滑りのリスクあり。とくに樹木を残した盛土は崩壊リスクが増す。
- 切土:もとの地盤を削るため、沈下リスクが低い。ただし盛土と切土が混在する場合は不同沈下に注意。
造成によってできた傾斜面(のり面)は、原則として擁壁で覆い、排水処理が必要です。
例題:
Q. 盛土において、元の地盤に残された樹木は崩壊の危険を高める。○か×か?
→ 正解:○
建物構造の基礎知識
宅建試験では、建物の構造や使用材料ごとの長所・短所が出題されます。
木造の特徴
- 長所:軽く、加工しやすい、熱伝導率が低い
- 短所:燃えやすい、湿気に弱い、シロアリに注意
乾燥状態(気乾状態)では強度が高くなり、湿潤状態では強度が落ちます。
例題:
Q. 木材は湿潤状態より気乾状態の方が強度が高い。○か×か?
→ 正解:○
構造別の建築方式と出題ポイント
以下の建築工法は試験において頻出です。
木質工法
- 軸組工法(在来工法):日本古来の木造建築。筋交いの欠き込み禁止など、細かい規定あり。
- 枠組壁工法(ツーバイフォー):壁で支える工法。筋交いの規定なし。
鉄骨造(S造)
- 強度大、粘り強い、自由設計が可能
- 高温で強度低下 → 耐火被覆が必要
鉄筋コンクリート造(RC造)
- 耐火・耐久・耐震性に優れる
- 自重が大きいため、基礎の設計に注意
例題:
Q. 鉄骨造は高温になると強度が下がるため、耐火被覆が必要である。○か×か?
→ 正解:○
基礎と耐震構造の理解
基礎の種類
- 直接基礎:フーチング基礎、ベタ基礎
- 杭基礎:深い地盤に杭を打ち込む
耐震・制震・免震の違い
- 耐震構造:柱や梁の強度で揺れに耐える
- 制震構造:ダンパーで揺れを吸収(高層ビル向き)
- 免震構造:地盤との間に装置を入れて揺れを伝えない(建物全体を守る)
例題:
Q. 免震構造は建物の下に装置を入れて揺れを吸収する構造である。○か×か?
→ 正解:○
まとめ
宅建試験では、土地と建物に関する基本知識が複数回出題されるため、油断せずに対策をしましょう。特に「宅地に適しているか」「構造の特徴」などは出題されやすく、例題とセットで覚えると効果的です。
土地の安全性、建物構造、耐震性の違いなどをしっかり把握することで、試験本番でも迷わずに解答できるようになります。

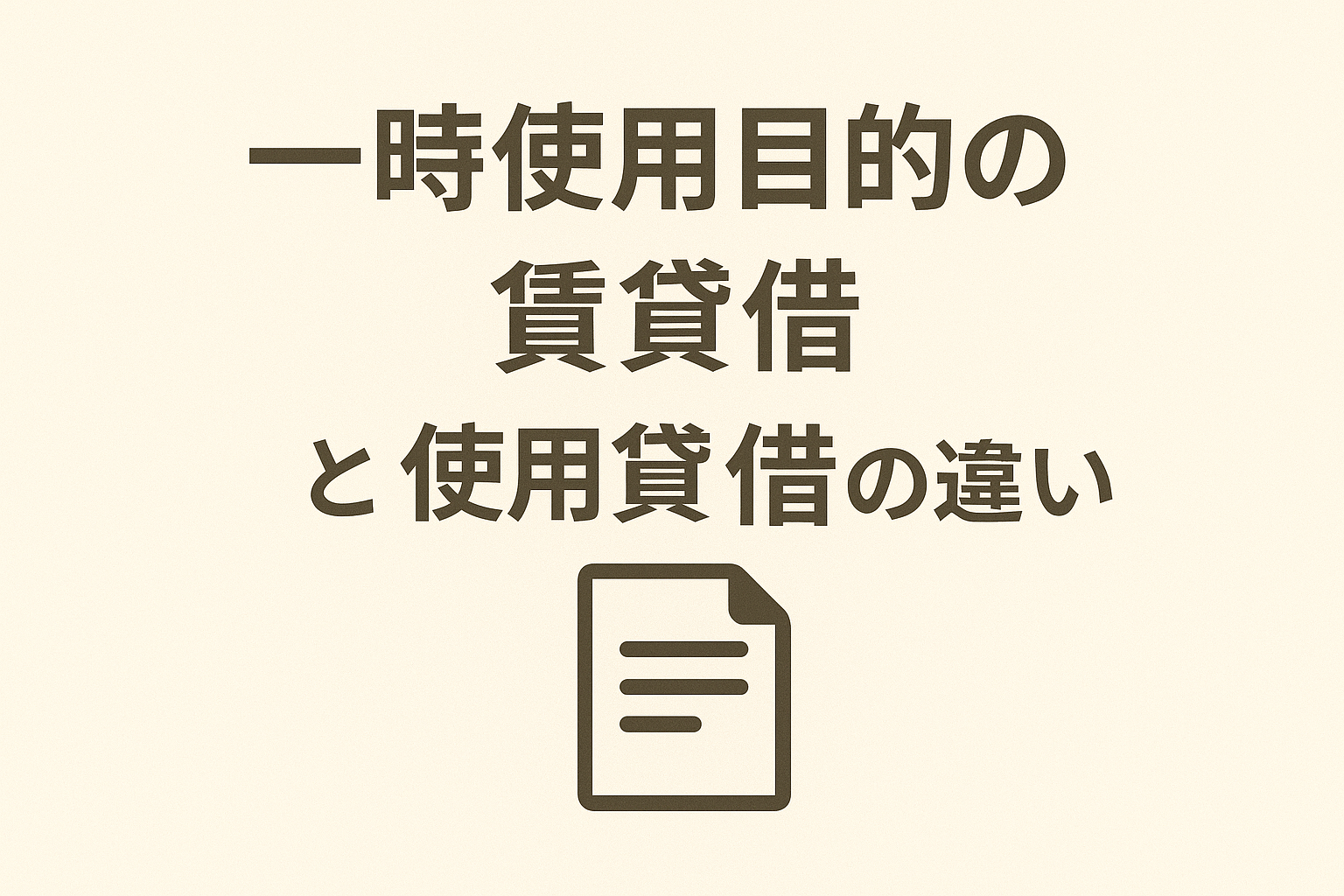
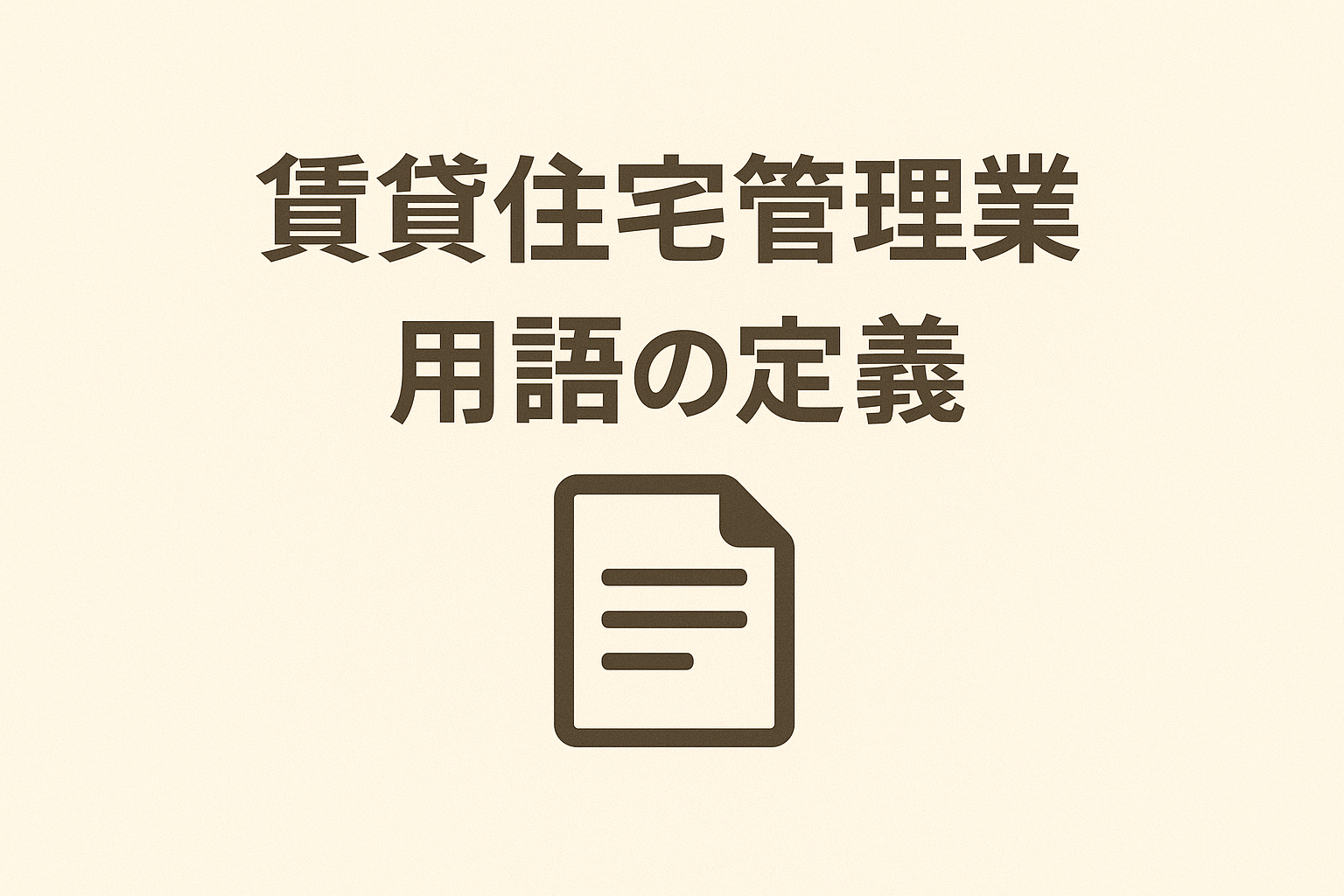
コメント