宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
今回は、建設経済の専門機関が発表した、2025年度・26年度の建設投資の見通しについて解説します。このような未来予測のニュースは、不動産市場の大きな流れを掴む上で非常に重要です。特に、新設住宅着工戸数と投資額の動きには、現在の市場を読み解く鍵が隠されています。将来、不動産のプロとして活躍するために不可欠な、マクロな視点を養っていきましょう。
25年度「駆け込み需要の反動」で着工戸数は減少
まず、2025年度(25年4月~26年3月)の見通しから見ていきます。予測によると、新設住宅の着工戸数は78万戸と、前年度に比べて4.4%減少する見込みです。この減少の最大の理由は、2025年4月から全面施行された「改正建築物省エネ法」による省エネ基準適合の義務化です。法改正前の駆け込み需要が大きかった分、その反動で着工戸数が一時的に落ち込むと分析されています。
なぜ着工減でも投資額は横ばいなのか
ここが今回のニュースで最も重要なポイントです。着工戸数が4.4%も減少するにもかかわらず、民間住宅への投資額は16兆8,500億円と、前年度比で0.1%の微減、つまり「ほぼ横ばい」をキープすると予測されています。
「建てる家の数は減るのに、使われるお金の総額は変わらない」とは、どういうことでしょうか。これは、住宅一戸あたりの価格が上昇していることを意味します。資材価格や人件費の高騰に加え、省エネ基準適合のための高性能な建材や設備の導入など、建築コストが上昇していることが、この数字から明確に読み取れるのです。
26年度は回復へ 緩やかな増加を見込む
次に、2026年度の見通しです。25年度の反動減から回復し、着工戸数は79万1,000戸(前年度比1.4%増)と、再び増加に転じると見込まれています。住宅投資額も17兆2,600億円(同2.6%増)とプラス成長が予測されており、市場が再び緩やかな成長軌道に戻ることが期待されています。25年度の落ち込みはあくまで一時的な調整であり、住宅への投資意欲自体は底堅いことがうかがえます。
法改正が不動産市場に与える影響の実例
この一連の予測は、宅建試験で学ぶ「法令上の制限」などの知識が、現実の経済にどれほど大きな影響を与えるかを示す絶好のケーススタディです。「省エネ基準適合の義務化」という一つの法改正が、駆け込み需要とその反動による着工戸数の増減、さらには住宅の単価上昇といった、目に見える形で市場を動かしています。法律の知識が、机上の学習だけでなく、実社会の経済活動と密接に結びついていることを実感できる好例と言えるでしょう。
未来予測から宅建士が読み取るべきこと
私たち宅建士を目指す者は、こうした未来予測から何を読み取るべきでしょうか。それは、「住宅の数は減っても、一戸あたりの価値・価格は高まる傾向にある」という大きなトレンドです。これからの住宅市場では、より高性能で、高付加価値な住宅が主流になっていく可能性があります。顧客に適切なアドバイスをするためには、こうしたマクロな市場動向を常に把握し、個別の物件だけでなく、市場全体の流れを見通す力が不可欠です。専門機関のレポートは、そのための重要な情報源となるのです。
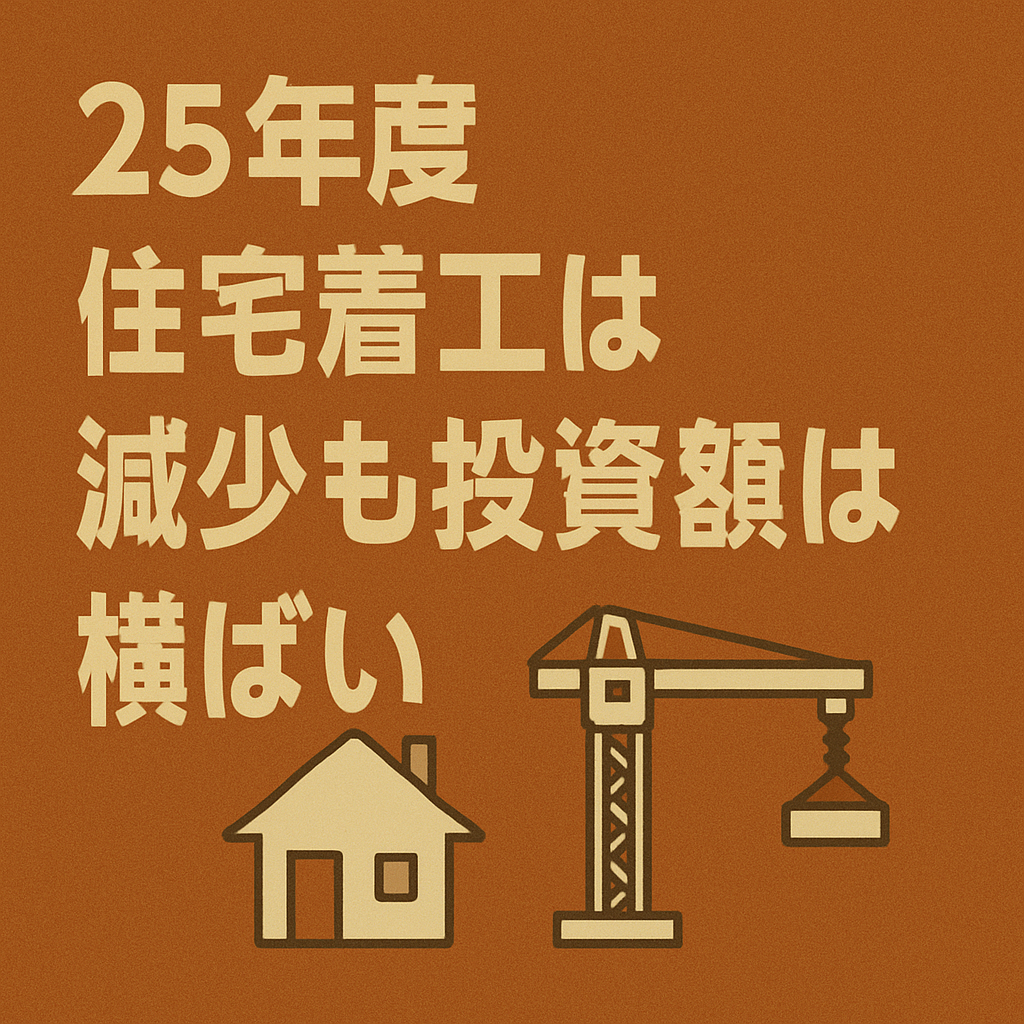
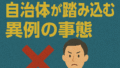
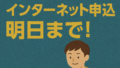
コメント