宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
今回は、老朽化したマンションの再生において、歴史的な一歩となるニュースが報じられましたので解説します。旭化成不動産レジデンスなどが手掛けた、東京都世田谷区の団地建て替え事業において、「マンション建替え円滑化法」に基づく容積率の緩和措置が、団地としては全国で初めて適用されました。このニュースは、皆さんが試験で学ぶ法律が、いかに社会課題の解決に貢献しているかを示す、またとない実例です。
「マンション建替え円滑化法」とは何か
まず、このニュースの核となる法律についておさらいしましょう。「マンション建替え円滑化法」とは、その名の通り、老朽化したり耐震性に問題があったりするマンションの建て替えを、スムーズに進めるために制定された法律です。多数の権利者が存在するマンションの建て替えは合意形成が非常に難しいため、この法律では決議要件の緩和など、様々な支援措置が定められています。
初適用された「容積率の緩和」その仕組みと効果
今回の事業で最も画期的だったのが、「容積率の緩和」が適用された点です。
ご存知の通り、容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合を定めたもので、建物の規模を決定づける重要な規制です。今回の事例では、敷地内に歩道や広場といったオープンスペース(公開空地)を設けることで、この容積率の割増しが認められました。
その効果は絶大です。容積率は建て替え前と比べて約4割もアップ。これにより、総戸数を171戸から248戸へと45%も増やすことができたのです。
戸数増がもたらす「事業費の捻出」というメリット
では、なぜ戸数を増やすことが重要なのでしょうか。それは、建て替えに要する莫大な事業費を捻出するためです。
増やした住戸(これを「余剰床」と言います)を、新しく一般の購入者に販売します。その売却で得た利益を、解体費用や建設費用に充当することができるのです。これにより、元の団地の住民(権利者)たちの金銭的な負担が大幅に軽減されます。負担が少なくなれば、建て替えへの合意も得やすくなります。この「容積率緩和→戸数増→事業費捻出→合意形成の円滑化」という好循環こそ、この制度の最大の狙いなのです。
建て替えの背景にある耐震基準に満たない建物という課題
そもそも、この団地がなぜ建て替えられることになったのか。そのきっかけは、2011年の東日本大震災で建物に被害が出たことでした。その後の調査で、1971年に完成したこの団地が、現在の耐震基準を満たしていない建物であることが判明したのです。
日本には、このような耐震性に不安を抱える老朽化したマンションや団地が数多く存在します。これらは、住民の安全を脅かすだけでなく、放置すればスラム化しかねない大きな社会問題です。今回の事例は、こうした社会課題を解決する一つのモデルケースとなります。
宅建士として知るべき「団地再生」の未来
今回の成功事例は、全国に数多く存在する他の老朽化団地の再生事業に、大きな弾みをつけることになるでしょう。
宅建士として、これからの時代は、こうした大規模な建て替え・再開発事業に関する知識がますます重要になります。「マンション建替え円滑化法」や「区分所有法」、そして「容積率」といった建築基準法の知識をしっかりと身につけておくこと。それは、老朽化したマンションに住む顧客に適切なアドバイスをしたり、新たに生まれ変わったマンションの価値を正しく評価し、販売したりする上で、不可欠な専門知識となるのです。

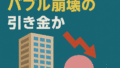
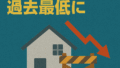
コメント