はじめに
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理業者の業務管理者として、管理受託契約の適正な実施や入居者の居住安定を確保するために重要な役割を担います。
近年では、高齢者や住宅弱者への対応、空き家問題、住宅宿泊事業(民泊)への関与など、活躍の場が大きく広がっています。
本記事では、試験で頻出の
✅ 賃貸不動産経営管理士の業務内容
✅ 倫理憲章の7原則
✅ 現代社会で期待される新たな役割
を整理し、理解を深めるための例題も交えて解説します。
賃貸不動産経営管理士の業務内容
賃貸住宅管理業者は、営業所ごとに「業務管理者」を1名以上選任しなければなりません(賃貸住宅管理業法12条1項)。
この業務管理者こそが、賃貸不動産経営管理士です。(独占業務ではないことには注意が必要です。)
■業務管理者の主な役割(規則13条)
業務管理者は、次のような管理・監督に関する事務を行います。
- 管理受託契約前の「重要事項説明書」の交付・説明
- 契約締結時の「締結時書面」の交付
- 賃貸住宅の維持保全・金銭管理(家賃・敷金・共益費など)
- 帳簿の備付けおよび保存
- 委託者(オーナー)への定期報告
- 秘密保持に関する事項
- 入居者からの苦情処理
- 国交大臣が定めるその他必要事項
これらの業務を通じて、入居者の居住の安定と賃貸経営の円滑化を図ることが求められています。
サブリース業者と賃貸不動産経営管理士の関係
特定転貸事業者(サブリース業者)は「業務管理者」を設置する義務はありません。
しかし、国土交通省の「サブリースガイドライン」では、オーナーへの重要事項説明を行う際には、
賃貸不動産経営管理士などの専門知識を持つ者による説明が望ましい
とされています。
つまり、サブリース契約においても、正確な情報提供と説明責任を果たすために、賃貸不動産経営管理士の知識と倫理が活かされるのです。
賃貸不動産経営管理士試験とは
賃貸不動産経営管理士試験は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が実施する国家資格試験です。
この試験は「業務管理者として必要な知識・能力を有する者」であることを証明する登録証明事業に位置づけられています。
民法や借地借家法、建築基準法などの法令だけでなく、賃貸経営・建物管理・リスクマネジメントなど、広範な分野が問われるのが特徴です。
倫理憲章(7原則)
賃貸不動産経営管理士には、専門職としての高い倫理観が求められます。
そこで協議会は「倫理憲章」を制定し、7つの原則を定めています。
試験でも頻出の内容なので、しっかり整理しておきましょう。
(1) 公共的使命
公共の福祉に貢献するという社会的使命を自覚し、公正な業務を通して地域社会に寄与します。
例として、防犯・防災活動への協力提案などが挙げられます。
💡試験例:令和2年問47肢4
地域の防犯活動への参加提案は「公共的使命」に該当する。
(2) 法令の遵守と信用保持
法令や社会的ルールを遵守し、業界全体の信用を損なう行為を慎みます。
自社の方針に問題がある場合でも、法令に基づいて是正する立場が求められます。
💡試験例:平成27年問3肢1
所属会社の不適切な方針にも、賃貸不動産経営管理士として適正対応を求めなければならない。
(3) 信義誠実の義務
依頼者や関係者に対して誠実に職務を行い、虚偽の説明や重要事項の不告知をしてはなりません。
直接の依頼者だけでなく、入居者・取引関係者にも誠実な対応が必要です。
(4) 公正と中立性の保持
管理士は常に公正・中立の立場を保ち、依頼者や関係者の利益を公平に扱う必要があります。
「依頼者寄り」でも「会社寄り」でもなく、バランスの取れた判断が求められます。
💡試験例:令和元年問38肢1
管理士は依頼者に偏らず、公正中立の立場で対応すべき。
(5) 専門的サービスの提供と自己研鑽
常に最新の法令や実務知識を学び、専門性の向上に努める必要があります。
資格取得後も継続学習が義務と言えるほど重要です。
💡試験例:令和2年問47肢3
試験問題を毎年チェックして知識を更新していることは「自己研鑽」に該当。
(6) 能力を超える業務の引受け禁止
自らの知識や能力で対応できない業務を安易に引き受けてはなりません。
依頼者の承諾があっても、専門家としての責任回避はできない点に注意。
💡試験例:平成27年問3肢2
能力を超える業務は、依頼者が了承しても引き受けてはならない。
(7) 秘密を守る義務
職務上知り得た情報を、正当な理由なく漏らしてはなりません。
退職後も秘密保持義務は継続します。
ただし、法令上の提供義務がある場合は例外です。
💡試験例:令和元年問38肢4
退職後も秘密保持義務は継続する。
賃貸不動産経営管理士に期待される新たな役割
(1) 社会的課題への対応
近年の少子高齢化や住宅不足などの社会的課題に対し、管理士は制度設計や実務運用の面で積極的に関与することが期待されています。
具体的な役割例:
- 高齢者・障害者・低所得者への住宅供給支援
- 民泊・シェアハウスなど新しい賃貸形態への対応
- 空き家の賃貸活用の促進
(2) 住宅セーフティネット法における役割
「住宅確保要配慮者」に対する入居支援制度の円滑運用に関与します。
具体的には、家賃の代理納付制度や入居者死亡時の残置物処理についてオーナーへ助言します。
社会的弱者が安心して暮らせる環境づくりに貢献するのが管理士の使命です。
(3) 民泊(住宅宿泊事業)への関与
住宅宿泊事業では、利用者の安全や近隣トラブル防止など高度な管理が必要です。
賃貸借契約・建物管理の知識をもつ管理士は、民泊運営の適正化にも寄与します。
(4) 空き家の賃貸化支援
放置された空き家を賃貸物件化する際、オーナーに法的リスクや管理体制の提案を行うことができます。
管理士は、空き家問題の「実務的な解決者」としての役割を担います。
(5) 賃貸経営の支援業務
管理士は、オーナーの経営パートナーとして、次のような書類を作成・助言します。
- 予算計画書・収支報告書
- 物件状況報告書
- 長期修繕計画書
これらの文書は、賃貸経営の収益改善や修繕計画の立案に不可欠です。
作成時には記名・説明を行い、専門家としての責任を明確にします。
💡補足:長期修繕計画書とは?
10〜30年先を見据え、いつ・何を・どの程度の費用で修繕するかをまとめた書面です。
管理士はこの計画をもとに、賃貸人に長期的な経営戦略を提案します。
💡試験対策例題で理解を深めよう!
例題1
賃貸不動産経営管理士は、所属会社の方針で法令違反の可能性がある管理方法を取るよう指示された。この場合、どのように対応すべきか?
→法令遵守の立場から適正な対応を求める。
例題2
依頼者の承諾を得て、自分の専門外の建物診断を引き受けた。
→倫理憲章の「能力を超える業務の引受け禁止」に違反。
例題3
退職後に以前の顧客情報をSNSに投稿した。
→秘密保持義務違反(退職後も義務は継続)。
例題4
住宅確保要配慮者への住宅提供に関し、家賃代理納付制度をオーナーに説明した。
→社会的役割(住宅セーフティネット法対応)として適正。
まとめ:管理士は「現場と社会をつなぐ専門家」
✅ 賃貸不動産経営管理士は「業務管理者」として法令遵守・契約管理の中心を担う
✅ 倫理憲章の7原則を理解し、専門職としての自覚を持つ
✅ 社会課題(住宅弱者支援・空き家問題・民泊など)にも積極的に関与
おわりに
賃貸不動産経営管理士は、単なる管理業務の従事者ではなく、**オーナーと社会をつなぐ“信頼の専門家”**です。
試験では、倫理憲章や新しい社会的役割の理解を問う問題が増えています。
「管理士としてのあり方」を意識しながら、学習を進めていきましょう。

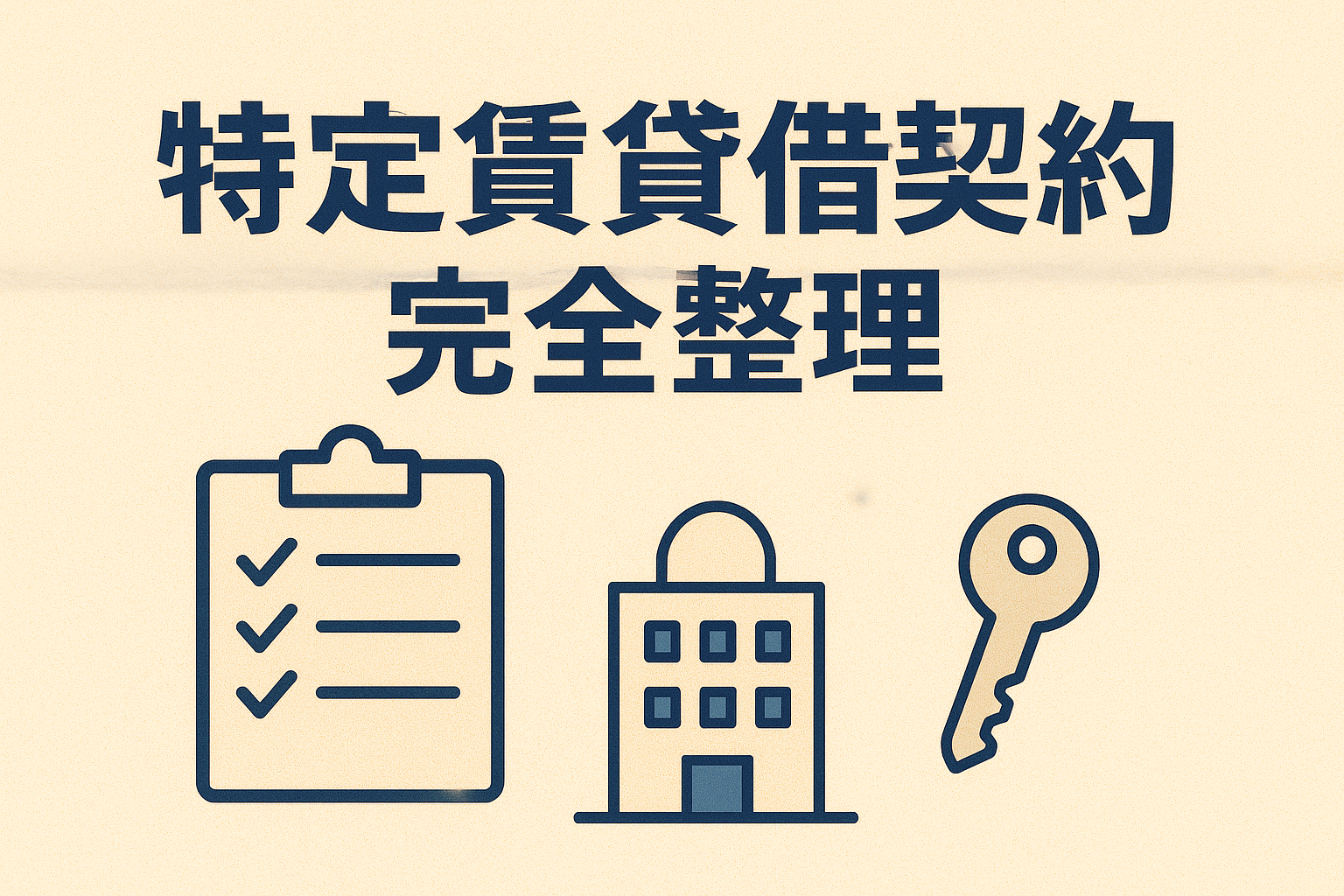
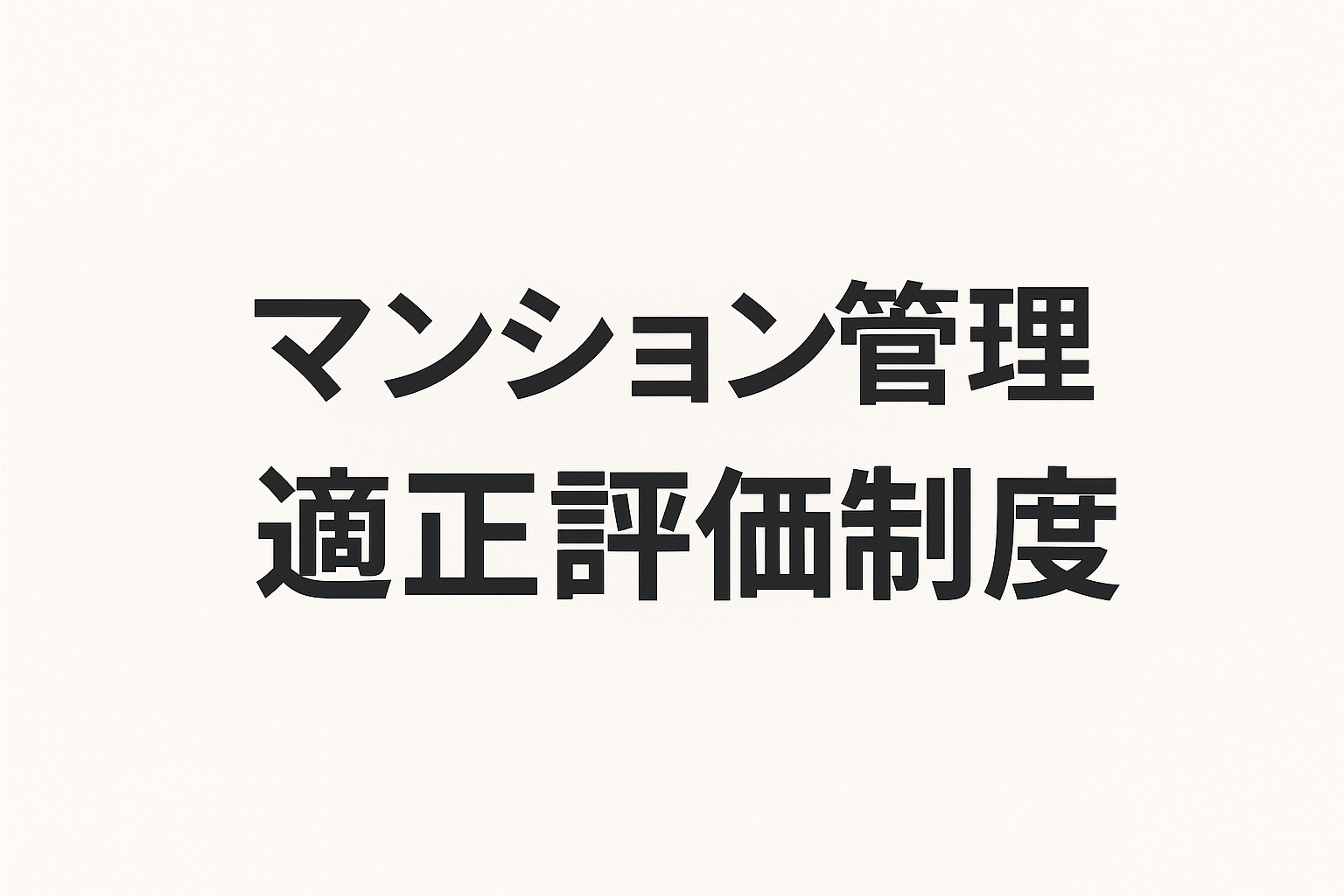
コメント