不動産取引において、物件内で「人の死」があった場合に、どこまで調査・告知すべきかが明確でないため、取引の円滑化が阻害されるとの指摘がありました。 (国土交通省)
このため国土交通省は、取引業者(宅地建物取引業者)が負う義務の解釈を整理したこのガイドラインを、令和3年10月8日に策定しました。 (国土交通省)
試験では「心理的瑕疵」「告知義務」「調査義務」などのキーワードで出題されますので、重要な内容をしっかり把握しましょう。
リンク
背景・意義
- 不動産取引の際、対象不動産に過去に「人の死」が生じたかどうかについて、業者がどう調査し告知するか明確な基準がありませんでした。 (国土交通省)
- 業者による対応のぶれや、買主・借主の心理的な不安が、流通を妨げる要因ともなっていました。
- 検討会を通じて、実務・裁判例を踏まえながら「一般的に妥当と考えられる判断基準」を整理したのが本ガイドラインです。 (国土交通省)
主な内容とポイント
1. 調査義務(情報収集義務)
- 媒介を行う宅建業者は、売主・貸主に対して「過去に人の死があったかどうか」について、告知書等への記載を求めることで、「通常の情報収集義務」を果たしたとみなされるとしています。 (国土交通省)
- ただし、周辺住民への聞き込みやインターネット調査など、業者が主体的に行う調査を義務づけるものではありません。
2. 告知義務の判断基準
- 原則として「自然死」または日常生活中の不慮の死(例:転倒事故・誤嚥など)で、かつ物件に特別な改修・特殊清掃が行われていない場合、告知義務はありません。 (国土交通省)
- 集合住宅において、その「日常的に通常使用する共用部分」で発生した同様の死も、原則として告知対象外とされます。 (国土交通省)
- 他方で、他殺・自殺・長期間放置・特殊清掃等があった死亡など、社会的影響や契約者の心理的影響が大きい事案では告知が必要となります。 (国土交通省)
- また、賃貸借取引の場合、事案発生からおおよそ3年が経過していれば告知不要とする取り扱いも示されています。 (国土交通省)
3. 問われた場合の告知義務
- 死亡事案の有無を買主・借主から問われた場合、あるいは買主・借主にとって把握すべき「特段の事情」があると業者が認識した場合には、経過年数・死因に関係なく、告知しなければなりません。 (国土交通省)
試験対策チェックポイント
| 項目 | 押さえるポイント |
|---|---|
| 調査義務 | 売主・貸主に告知書記載を求めることで通常の調査義務を果たすとみなされる。 |
| 告知不要のケース | 自然死/日常事故死/通常使用しない共用部分/概ね3年経過 など。 |
| 告知が必要なケース | 自殺・他殺・特殊清掃・社会的影響が大きい事案など。 |
| 問われた場合 | 買主・借主から質問された場合には告知必須。 |
| キーワード | 「心理的瑕疵」「特殊清掃」「通常使用部分」「概ね3年経過」など。 |
実務上の留意点
- 業者としては、物件引渡し前に売主・貸主へ「死亡事案の有無」について必ず確認し、告知書・物件状況説明書等への記載を依頼することが望ましい。
- 自社の判断だけで「この程度の死なら問題ない」と判断せず、ガイドラインの基準をもとに社内で判断基準を整備しておくと安心です。
- 告知不要と判断しても、買主・借主に問われた場合には説明責任が生じます。契約書・重要事項説明書に備えをしておくことが実務上有効です。
- 死亡事案の内容によっては、「事故物件」となるケースもあり、心理的瑕疵の観点から別途注意が必要です。
まとめ
「人の死の告知」に関するガイドラインは、取引の透明性・安心・信頼性を確保するための重要な枠組みです。試験対策としては、下記の点をしっかり押さえておきましょう。
- 調査義務の範囲
- 告知不要/告知必要の判断基準
- 質問された場合の対応
- 実務的な確認・説明体制
これらを整理しておくことで、資格試験のみならず、実務現場でも適切な対応が取れるようになります。
リンク
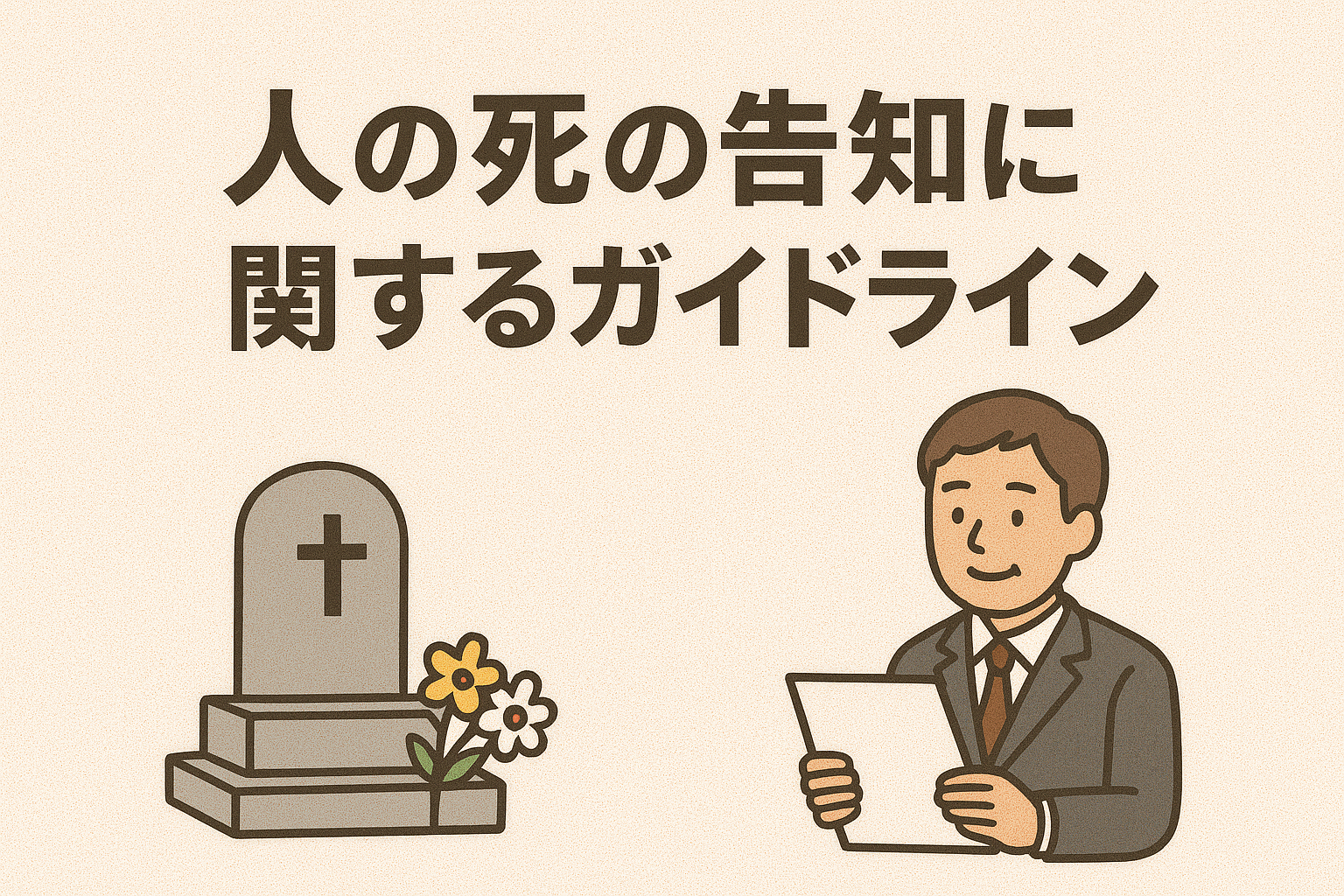

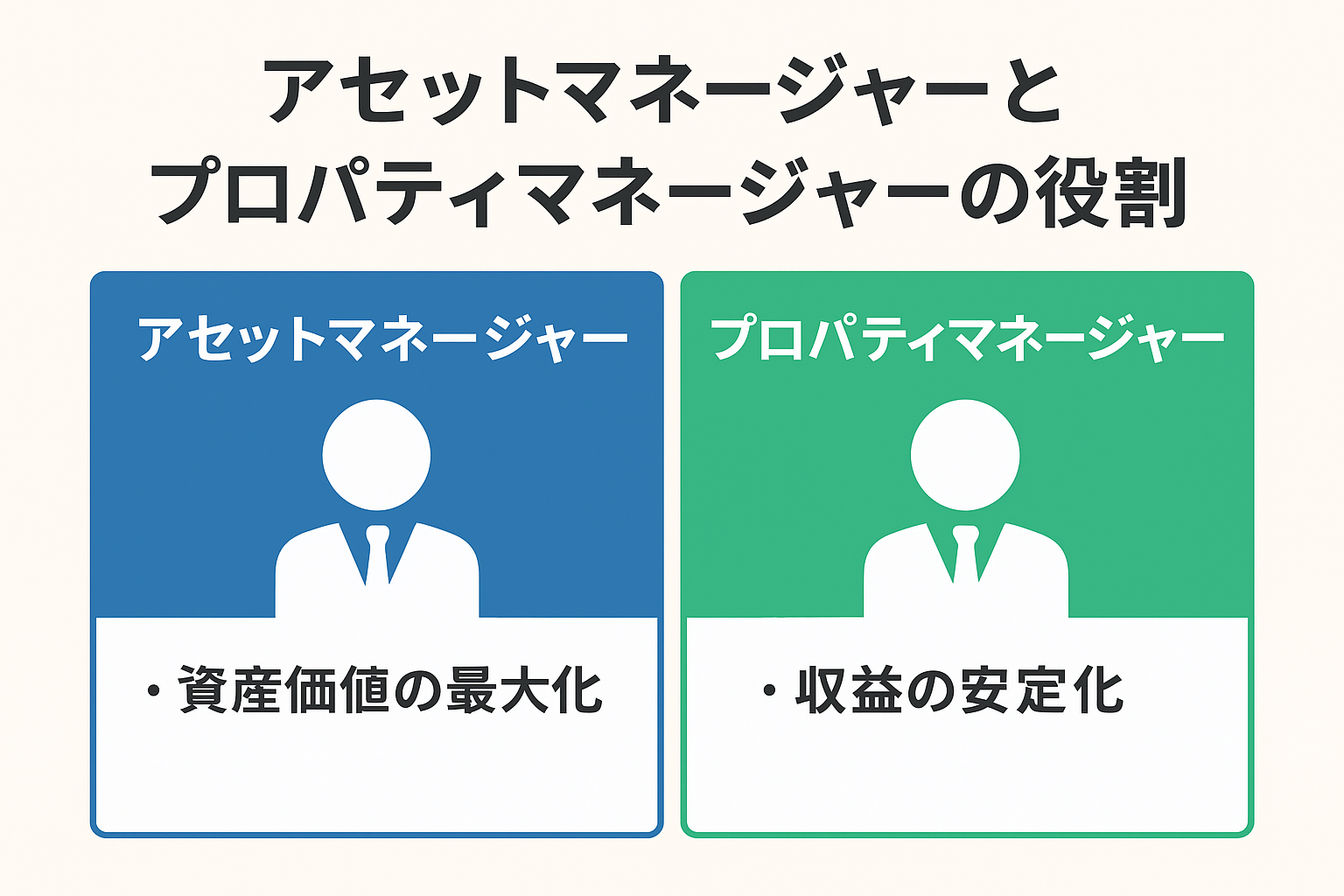
コメント