今回は「賃貸借契約における賃料の改定・回収」について、賃貸不動産経営管理士試験対策として詳しく解説します。
民法・借地借家法・弁護士法など複数の法律が関係するこの分野は、条文知識だけでなく「どの立場で何ができるか」を正確に整理しておくことが重要です。
弁済とは何か?債務を果たす行為の本質
「弁済」とは、債務者が債務の内容である給付を本旨に従って実現することをいいます(民法473条)。
たとえば、賃借人が賃料を支払う行為や、売主が建物を引き渡す行為などが該当します。
弁済によって債権は消滅し、契約上の義務が果たされたことになります。
弁済の充当とは?複数債務がある場合のルール
債務者が複数の債務を負っている場合、支払った金額がすべての債務を消すのに足りないとき、どの債務から充てるかを決める必要があります。これを「弁済の充当」といいます。
- ①合意による充当:当事者間で合意があればその順序に従う(民法490条)
- ②指定充当:合意がないときは、弁済者(賃借人)が指定でき、しない場合は受領者(賃貸人)が指定できる
- ③法定充当その1:弁済期や利益の大小など一定の法定順序に従う
- ④法定充当その2:費用・利息・元本がある場合は「費用→利息→元本」の順に充当(民法489条)
供託とは?弁済できないときの救済制度
賃料の支払いは、原則として賃貸人が受け取ることによって完了します。
しかし、賃貸人が受け取りを拒否したり、不在であった場合などに、賃借人が支払いを完了できないことがあります。
このような場合、民法は「弁済供託」という制度を認めています。
供託できるのは次の3つの場合に限られます(民法494条)。
- 賃貸人が受領を拒否したとき(受領拒否)
- 賃貸人が受領不能のとき(所在不明など)
- 賃貸人が誰かわからないとき(相続や譲渡により債権者不明)
供託を行った賃借人は、遅滞なく賃貸人に通知し、供託金は貸主が後日いつでも受け取ることができます。
これにより賃借人は債務不履行責任を免れます。
賃料の改定に関する法律知識
賃貸借契約期間中に経済事情が変動した場合、賃料が相当でなくなることがあります。
この場合に関係するのが「賃料自動改定特約」と「賃料増減請求権」です。
賃料自動改定特約(スライド条項)
物価指数や一定期間経過などを基準に自動的に賃料を改定する特約をいいます。
合理的な内容であれば有効とされ(最判平15・6・12)、社会経済状況が変化して不相当となった場合は拘束されません。
賃料の増減請求権(借地借家法32条)
借地借家法32条では、賃料が不相当になった場合、賃貸人・賃借人いずれも「将来に向かって」賃料の増減を請求できます。
- 増額請求の場合:裁判確定まで相当額を支払えばよいが、不足分には年1割の利息をつけて支払う
- 減額請求の場合:裁判確定まで相当額を受け取れるが、超過分は年1割の利息をつけて返還する
また、「増額しない」特約は有効ですが、「減額しない」特約は無効です。
定期建物賃貸借における借賃改定特約
定期建物賃貸借で借賃改定特約がある場合、借地借家法32条は適用されず、特約が優先します(借地借家法38条9項)。
賃料回収と自力救済の禁止
賃借人が賃料を滞納しても、貸主が裁判手続を経ずに実力行使すること(自力救済)は禁止されています。
社会秩序を乱すため、公序良俗違反として無効になります。
以下のような行為は自力救済に該当します。
- ドアの鍵にカバーを掛ける
- 鍵を交換する
- 承諾なしに残置物を処分する
このような行為を行った貸主には、不法行為責任や損害賠償義務が発生します。
賃料回収と弁護士法の関係
弁護士でない者が報酬を得て法律事務を行うことは、弁護士法72条で禁止されています。
そのため、管理受託契約の場合、管理業者は貸主名義で内容証明郵便を送る必要があります。
一方、サブリース方式(転貸)で自ら貸主となる場合は、管理業者名義で通知しても問題ありません。
内容証明郵便自体に強制執行力はありませんが、公正証書に「直ちに強制執行に服する旨」が記載されていれば、金銭請求に限って強制執行が可能となります。
公正証書とは
公正証書は、公証人が作成する強い証明力をもつ公文書です。
原本は原則20年間、公証人役場で保管されます。
契約書を公正証書化しておくことで、万一のトラブル時に迅速な債権回収が可能になります。
例題で理解を深めよう
例題1
賃借人Aは、賃貸人Bに家賃を支払おうとしたが、Bが所在不明となった。Aはどうすればよいか?
→ 民法494条に基づき、Aは賃料を供託することで債務不履行責任を免れることができます。
例題2
「5年間は賃料を減額しない」という特約を結んだ。この特約は有効か?
→ 借地借家法32条ただし書により「減額しない特約」は無効です。ただし、定期建物賃貸借で借賃改定特約がある場合は有効です。
例題3
貸主Cが、家賃滞納を理由に借主Dの部屋の鍵を無断で交換した。この行為の法的評価は?
→ 自力救済に当たり、公序良俗違反で無効。不法行為として損害賠償責任を負います。
まとめ
賃料の改定・回収は、民法・借地借家法・弁護士法など複数の法律が関係する複雑な分野です。
特に試験では「弁済」「供託」「賃料増減請求権」「自力救済禁止」「弁護士法との関係」が頻出ポイントです。
条文の趣旨を理解し、貸主・借主どちらの立場でも適法に対応できるよう整理しておきましょう。
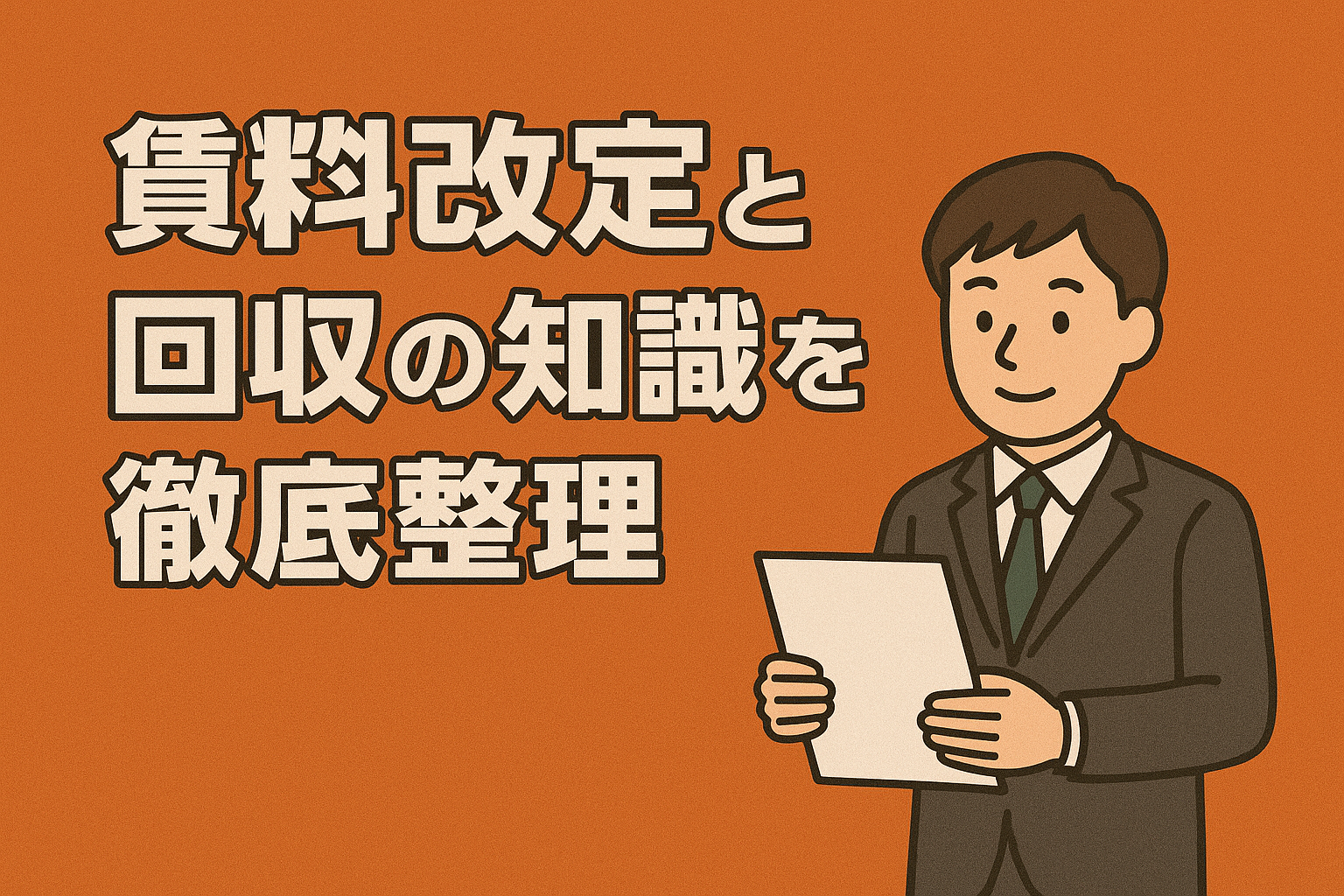
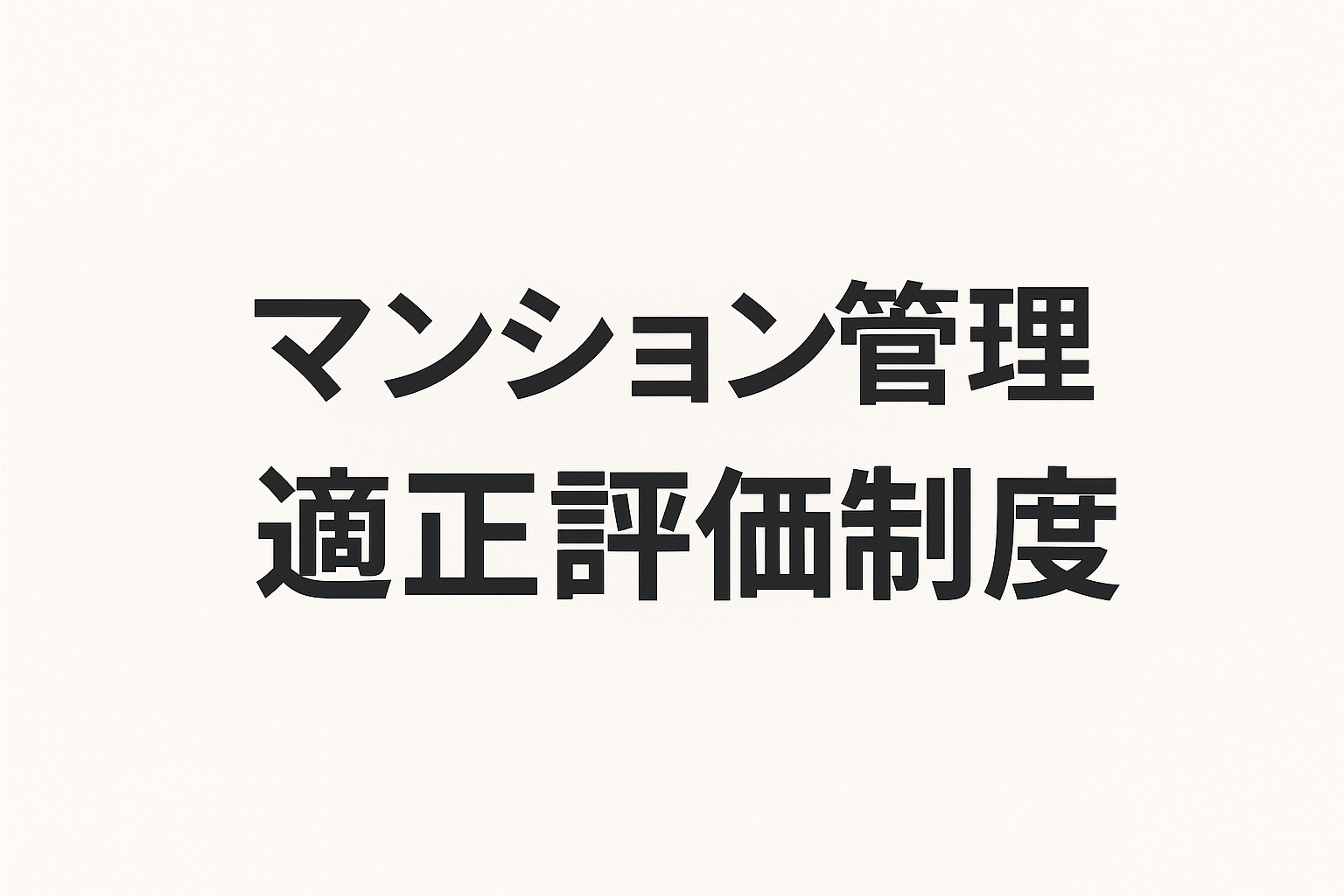
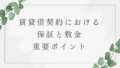
コメント