賃貸借契約は、当事者の信頼関係を基盤とする継続的な契約です。しかし、賃料の不払いなどが発生すれば契約を解消せざるを得ない場面もあります。本記事では、解約と解除の違い、それぞれの具体的な要件や効果を整理し、賃貸不動産経営管理士試験に役立つ知識を解説します。最後に例題も掲載していますので、理解度チェックにご活用ください。
解約と解除の基本的な違い
- 解約 … 契約を将来に向かって終了させる制度。
- 解除 … 債務不履行などを理由に契約を終了させる制度で、原則は契約締結時に遡って効力が生じるが、賃貸借契約では将来に向かってのみ効力が生じる(620条)。
つまり、「解約」=将来消滅、「解除」=原則遡及だが賃貸借は例外、と覚えておきましょう。
期間の定めがない賃貸借と解約
民法では、期間の定めがない賃貸借の場合、各当事者はいつでも解約の申入れが可能です。
- 建物賃貸借の場合:解約の申入れから3か月後に終了(民法617条)。
- 借地借家法の場合:
- 賃貸人 → 正当事由が必要。申入れから6か月後に終了。
- 賃借人 → 正当事由不要。申入れから3か月後に終了。
なお、賃貸人が申入れをしても、借主が使い続けている場合には、正当事由に基づいて異議を述べなければ契約は存続します(借地借家法27条2項)。
期間の定めがある賃貸借と解約
原則として、期間の定めがある賃貸借は中途解約できません。
ただし、「期間内解約条項(解約権留保特約)」がある場合には例外的に解約可能です。
- 賃借人 → 解約の申入れから3か月後に終了(正当事由不要)。
- 賃貸人 → 解約の申入れから6か月後に終了(正当事由必要)。
契約の解除と信頼関係破壊の法理
解除原因となる主なケースは以下の通りです。
- 賃料の不払い
- 無断譲渡・転貸
- 用法遵守義務違反
- 善管注意義務違反
ただし、判例は「信頼関係が破壊されない限り解除はできない」という立場を取っています。特に賃料不払いについては、長期にわたる滞納があれば信頼関係を破壊するとされ、解除が認められます。
履行遅滞と解除の手続き
賃料不払いは「履行遅滞」にあたります。解除には以下の流れが必要です。
- 相当の期間を定めた催告を行う(内容証明郵便が望ましい)。
- 期間内に履行がなければ解除可能。
ただし、次のような場合は無催告解除が認められます(民法542条)。
- 債務の履行が不能であるとき
- 債務者が履行を拒絶したとき
- 長期の賃料不払い(判例)
合意解除と複数貸主の場合
- 合意解除 … 当事者の合意で契約を終了させるもの。将来効にとどまる。
- 貸主が複数いる場合 … 賃貸借契約の解除は「共有物の管理行為」とされ、持分価格の過半数で決定可能。
賃貸人・賃借人の死亡と契約
- 賃貸人が死亡した場合 → 相続人が賃貸人の地位を承継。
- 賃借人が死亡した場合 → 相続人が賃借権を承継。
- 相続人がいない場合 → 借地借家法36条により、同居の内縁配偶者や事実上の養親子が承継可能。
 |
Bioré ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 100g 日焼け止め SPF50 【Amazon.co.jp限定】 新品価格 |
【例題】
問1
AはBに対して建物を賃貸していたが、Bが2か月分の賃料を滞納した。Aは直ちに賃貸借契約を解除することができるか。
解答・解説
原則として、解除には「相当の期間を定めた催告」が必要であり(民法541条)、2か月程度の滞納だけでは直ちに解除はできません。ただし、長期の滞納や信頼関係破壊と評価される事情がある場合には「無催告解除」が認められます(最判昭42.3.30)。
まとめ
- 解約は将来に向かって契約を終了させる制度。
- 解除は債務不履行を理由とする制度だが、賃貸借では将来効のみ。
- 賃料不払いについては、催告→解除が原則だが、信頼関係破壊の場合は無催告解除も可能。
- 死亡によって契約は終了しない。相続人や同居者が承継する。
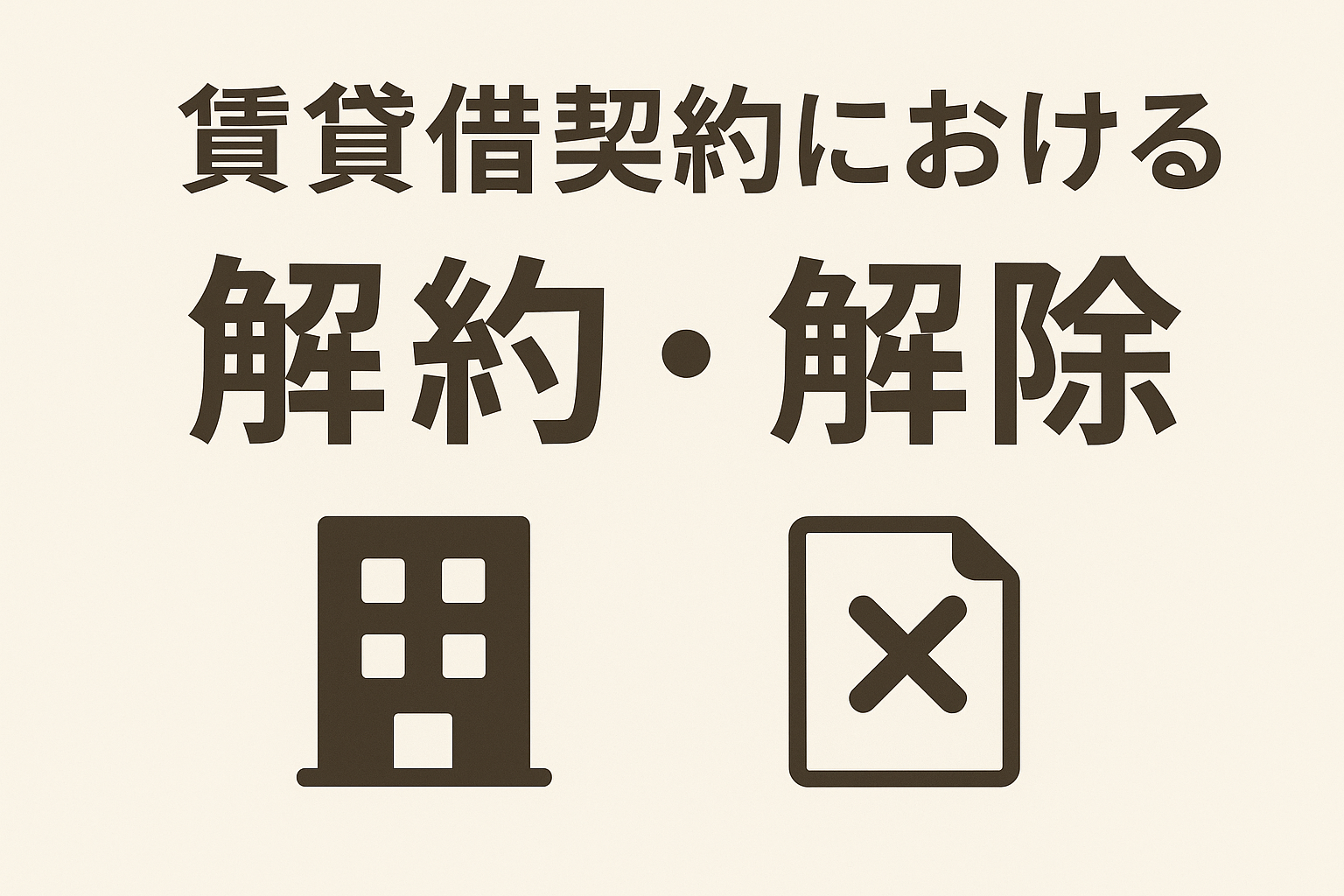
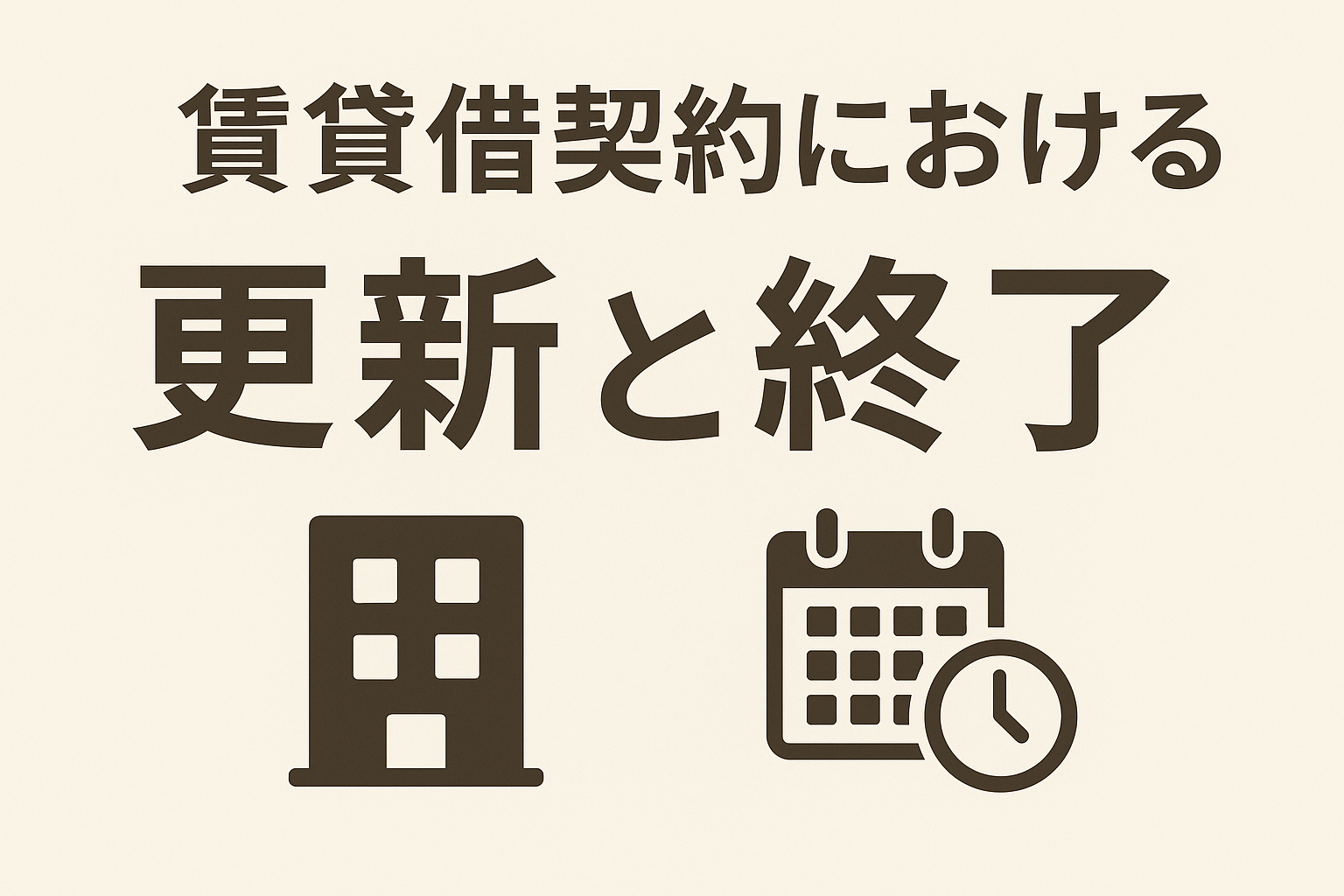
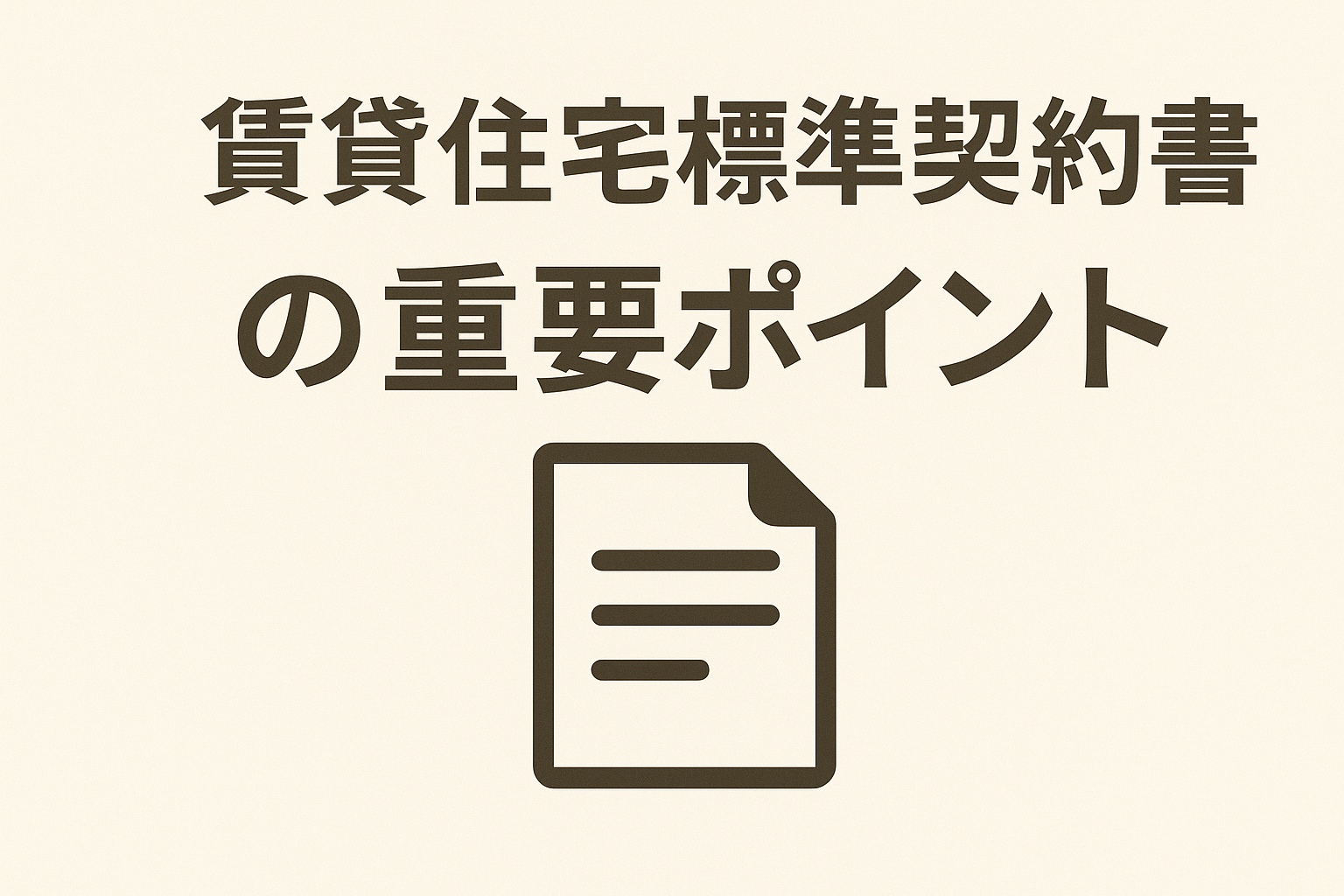
コメント