宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
今回は、世界の主要都市の物価や生活の質を比較した、ドイツ銀行の2025年版レポートから見えてくる、日本の不動産市場の大きな課題について解説します。このレポートで東京の「生活の質」は世界26位とされましたが、より深刻なのは、その背景にある日本の「購買力平価」の長期的な下落です。このマクロな視点は、皆さんが不動産のプロとして市場を読み解く上で、極めて重要な知識となります。
東京の生活の質を押し下げる不動産の問題
まず、なぜ東京の「生活の質」の順位が伸び悩んでいるのでしょうか。レポートでは、その要因として「高い家賃」「長い通勤時間」「大気汚染」などが挙げられています。特に「高い家賃」と「長い通勤時間」は、不動産と密接に関わる問題です。都心部の住宅価格や家賃が高騰しすぎた結果、多くの人が郊外に住まざるを得ず、それが長い通勤時間に繋がっています。これは、宅建士として日々向き合うことになる、都市の構造的な課題そのものです。
より深刻な問題 日本の「買う力」の歴史的な低下
しかし、今回のレポートで最も注目すべきは、日本の「購買力平価(PPP)」の驚くべき変化です。購買力平価とは、為替レートだけでは測れない、その国のお金が持つ「実質的な購買力」を示す指標です。レポートによれば、2000年当時、日本の購買力平価は世界第1位でしたが、その後25年間で26位に順位を落としています。これは、バブル経済の崩壊後、日本経済が長期にわたって停滞し、諸外国の成長から取り残されてきた結果であり、「失われた数十年」の代償を払っている姿とも言えます。
購買力平価の低下が不動産市場に与える影響
この「買う力」の低下は、不動産市場に二つの異なる影響を与えています。
一つは、国内の購入者にとっての「割高感」です。平均賃金が伸び悩む中、不動産価格だけが高騰を続けているため、国内の消費者にとってマイホームはますます「高嶺の花」になっています。
もう一つは、海外の投資家にとっての「割安感」です。相対的に日本の「円」の価値が下がっているため、海外の投資家から見れば、日本の不動産は非常に魅力的な投資対象に見えます。都心部の高額物件が海外の富裕層やファンドに買われる一方、国内の一般層は手が出せない、という市場の二極化は、この購買力平価の低下が大きな要因なのです。
世界の金融ハブとの比較から見えること
レポートでは、ニューヨークやロンドンといった他の国際金融都市も、東京と同様に家賃の高さなどから生活の質のランキングでは下位(50位)に位置しています。都市部の住宅問題は世界共通の課題です。しかし、米国などの都市は物価や所得も世界トップクラスで上昇しているのに対し、日本は「買う力」そのものが長期的に低下しているという点で、問題の根深さが異なります。
これからの宅建士に求められるマクロ経済の視点
今回のレポートが示す現実は、宅建士が単に物件情報や法律知識に詳しければ良いという時代ではないことを教えてくれます。なぜ日本の不動産は国内の給与所得者にとってこれほど高いのか。なぜ海外からの投資が続くのか。その背景にある「購買力平価」のようなマクロ経済の大きな流れを理解して初めて、顧客に対して本質的なアドバイスができます。試験で学ぶ知識を基礎としながら、こうしたグローバルな視点を持つことが、これからの不動産のプロフェッショナルには不可欠です。
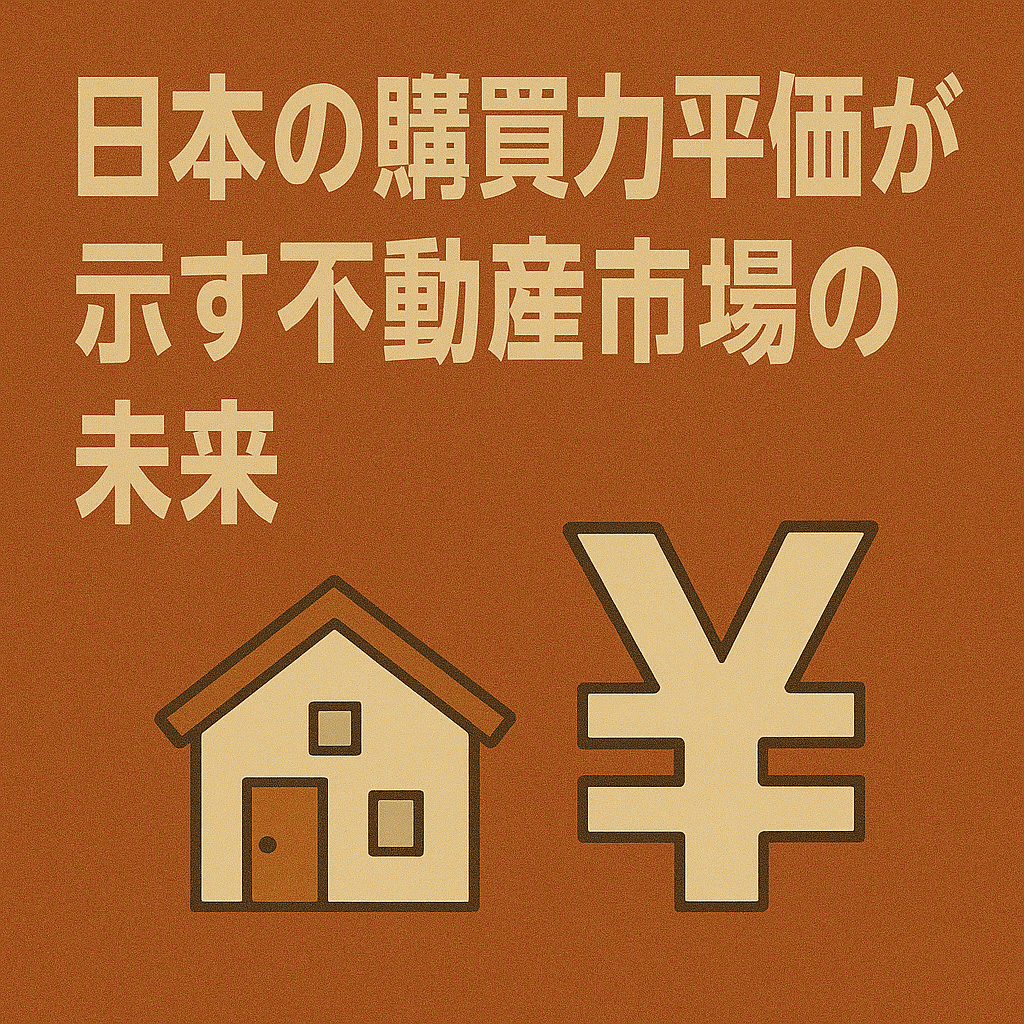
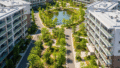
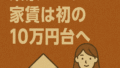
コメント