宅建試験の合格を目指し、日々学習に励んでいる皆さん、こんにちは。
今回は、不動産市場の大きな流れを掴む上で非常に興味深いニュースをご紹介します。ある調査によると、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)の約7割が「マイホームは今が買い時」と考えているというのです。住宅価格は高騰を続けており、一見すると買い控えム-ドになりそうですが、なぜ専門家は「今」を推奨するのでしょうか。その理由を深掘りすることは、将来不動産のプロとして活躍する皆さんにとって、必ず役立つ視点を与えてくれます。
最大の理由「本格的な金利上昇」への警戒感
専門家たちが「今が買い時」と判断する最大の理由は、今後の「金利上昇」を見据えているからです。ご存知の通り、日本銀行は長年のマイナス金利政策を解除し、金融市場は正常化へと舵を切り始めました。現在はまだ歴史的な低金利が続いていますが、この状況が永遠に続く保証はどこにもありません。住宅ローンの金利が本格的に上昇する前に、現在の比較的有利な条件で借り入れを確定させたい、という考えが「買い時」論の根底には強くあります。
止まらない建築コストの上昇
もう一つの大きな要因は、建築費用の高騰です。ウッドショックに始まり、ウクライナ情勢や円安などを背景に、建築資材の価格は上がり続けています。さらに、建設業界の人手不足による人件費の上昇も重なり、新築住宅の価格を押し上げています。この流れは今後も続くと見られており、「今日が一番安い日」という考え方が現実味を帯びています。待てば待つほど、同じ家でもより高額な資金が必要になる可能性が指摘されています。
インフレ時代における「不動産」という資産価値
現在の経済は、様々なモノやサービスの値段が上がるインフレの局面に入っています。このような状況では、現金や預金の価値は相対的に目減りしていきます。一方で、土地や建物といった「実物資産」である不動産は、インフレに強い資産とされています。物価の上昇に伴って不動産価格や家賃も上昇する傾向があるため、資産防衛の観点から不動産を所有するメリットが大きいと判断する専門家も多いのです。
専門家の意見をどう読み解くべきか
ここで重要なのは、専門家の意見を鵜呑みにするのではなく、その背景を理解し、多角的に見ることです。7割が「買い時」ということは、残りの3割は慎重な見方をしているということです。今後の景気後退や、一部の過熱したエリアでの価格調整リスクを懸念する声も当然あります。また、個人の収入やライフプランによって最適な購入タイミングは全く異なります。
未来の宅建士として顧客に伝えるべきこと
私たち宅建士を目指す者にとって、こうした市場の動向を理解することは必須です。将来、お客様から「今は買い時ですか?」と質問された時、私たちは単に「専門家がこう言っています」と伝えるだけでは不十分です。金利、建築費、インフレといったマクロな視点からの情報を提供しつつ、お客様一人ひとりの状況に合わせたミクロな視点でのアドバイスができてこそ、真のプロフェッショナルと言えます。今回のニュースは、そのための思考訓練として絶好の教材となるでしょう。



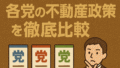
コメント