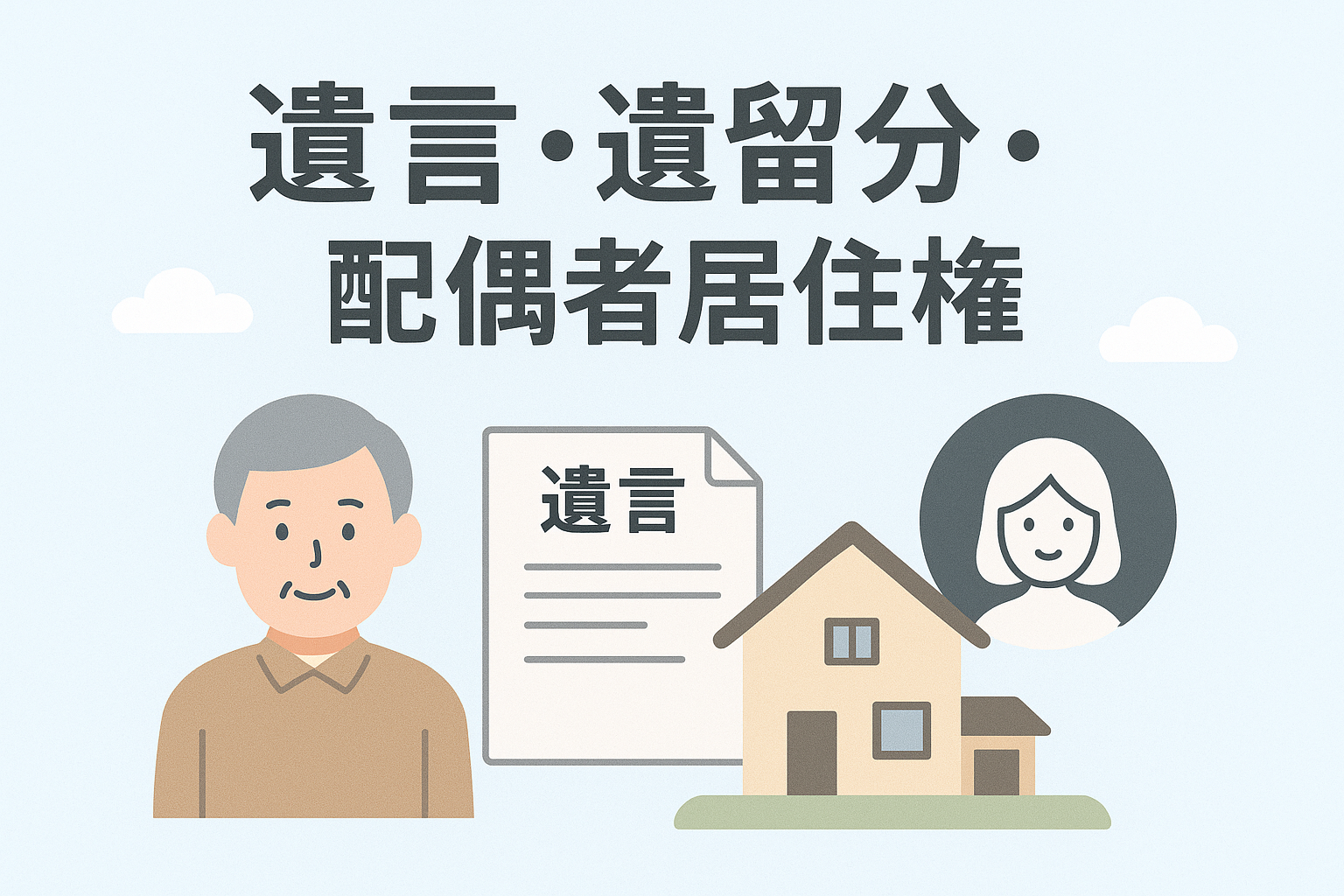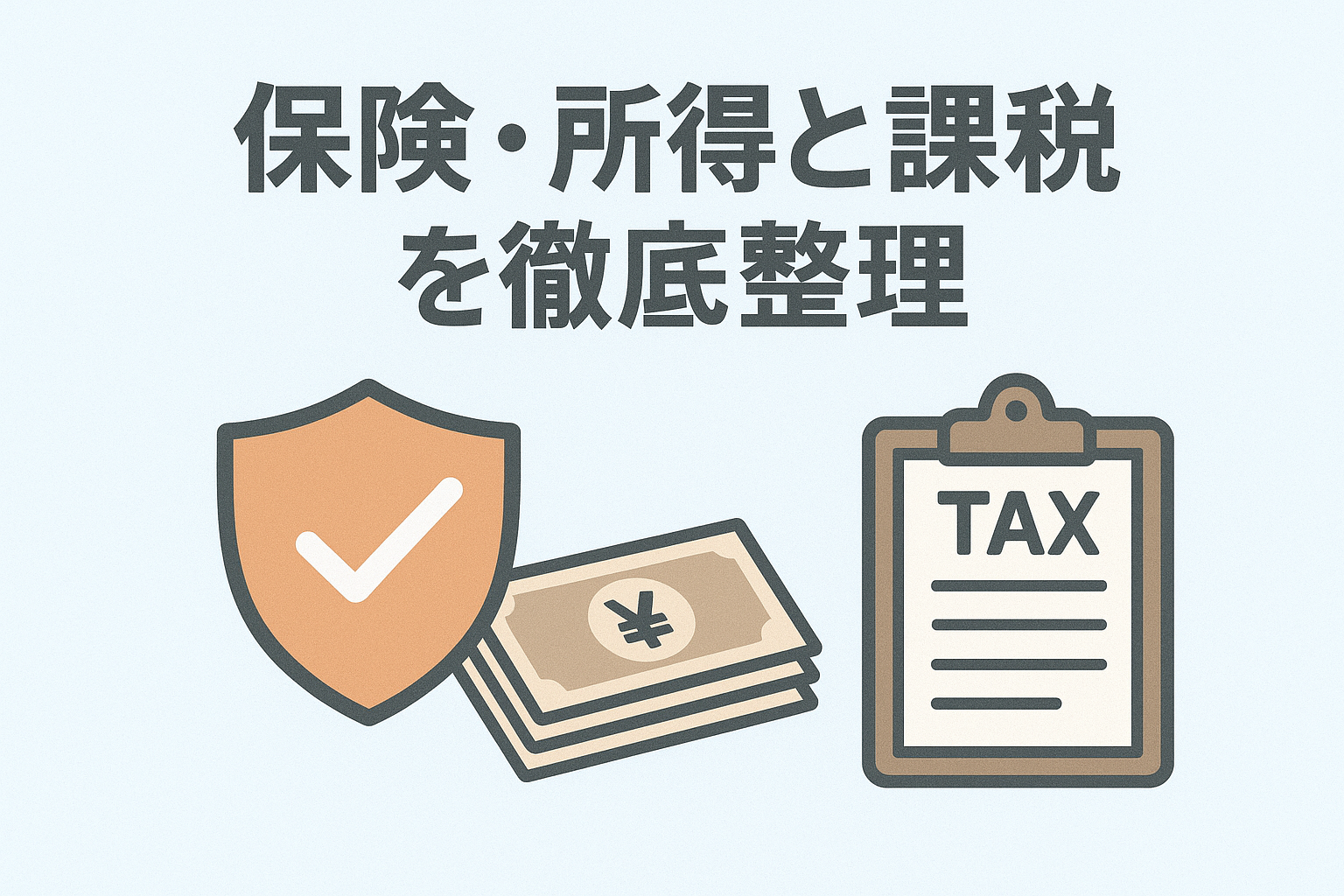宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
試験まで1ヶ月を切り、最後の追い込みに励んでいることと思います。今回は、10月1日から実施される、賃貸実務に大きな影響を与える法改正関連のニュースについて解説します。住宅金融支援機構が、「家賃債務保証保険」制度を拡充すると発表しました。この改正は、高齢者や低額所得者などが抱える「部屋が借りにくい」という社会課題の解決を目指すものであり、未来の不動産のプロである皆さんが知っておくべき、非常に重要な制度変更です。
なぜ制度が拡充されるのか?「住宅確保要配慮者」という社会課題
まず、今回の制度拡充の背景にあるのが、「住宅確保要配慮者」の存在です。これは、高齢者、障害者、低額所得者、ひとり親世帯など、様々な理由から民間賃貸住宅への入居が困難な方々を指します。
大家さん(貸主)側には、「家賃を滞納されたらどうしよう」「もし部屋で亡くなられたら…」といった経済的・心理的な不安があり、その結果として、これらの人々が入居を断られてしまうケースが後を絶ちません。この社会的なミスマッチを解消するため、「住宅セーフティネット法」が改正され、それを受けて今回の保険制度の拡充が行われるのです。
拡充のポイント① 保険対象の拡大と「孤独死」対応
今回の制度拡充で、最も画期的なポイントの一つが、保険の対象範囲の拡大です。具体的には、従来の家賃滞納などに加え、新たに以下の費用が保険でカバーされることになりました。
- 残置物撤去費用
- 特殊清掃費用を含む原状回復費用
これは、特に高齢の単身者が入居する際に、大家さんが最も懸念する「孤独死」が発生した場合の費用負担に、真正面から対応するものです。これまで、こうした費用は家賃債務保証の対象外となることが多く、大家さんにとって大きなリスクでした。このリスクが保険でカバーされることで、高齢者などへの入居のハードルが大きく下がることが期待されます。
拡充のポイント② 「居住サポート住宅」の保険割合を9割へ
二つ目の重要なポイントは、特定の住宅に対する保険割合の引き上げです。
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、大家さんが都道府県などに登録する制度を「居住サポート住宅(認定住宅)」と言います。今回の改正で、この「居住サポート住宅」に要配慮者が入居する場合、家賃債務保証保険の保険割合が、従来の7割から9割へと大幅に引き上げられます。
これは、国が大家さんに対して、「住宅セーフティネットに協力してくれるなら、リスクの9割を国が支援する保険でカバーしますよ」という、非常に強力なメッセージを送っていることを意味します。大家さんにとって、安心して要配慮者を受け入れるための、大きなインセンティブ(動機付け)となるでしょう。
宅建士が知るべき「家賃債務保証」の役割
宅建試験の学習、特に「賃貸住宅管理業法」の分野において、「家賃債務保証業者」は重要なプレーヤーとして登場します。彼らは、入居者の家賃支払いを保証することで、賃貸借契約を円滑にする役割を担っています。
今回のニュースが示しているのは、民間事業者である家賃債務保証会社のリスクを、さらに公的な機関である住宅金融支援機構が「保険」という形でバックアップする、という重層的なセーフティネットの仕組みです。
「貸主の不安」を解消し、円滑な入居を支援する専門家として
私たち宅建士を目指す者にとって、この新しい制度は、実務における強力な武器となります。
高齢者などの入居希望者に対し、入居をためらう大家さんに対して、宅建士はこう説明できるのです。
「ご心配されている孤独死の際の特殊清掃費用なども、10月からの新しい保険でカバーされるようになりました。さらに、お持ちの物件を『居住サポート住宅』として登録すれば、リスクの9割がカバーされます。安心して貸し出してはいかがでしょうか。」
このように、最新の法制度の知識を駆使して、貸主の不安を解消し、借主の入居を円滑にサポートすること。それこそが、単なる物件案内に留まらない、社会的な意義を持った不動産のプロフェッショナルとしての仕事なのです。