賃貸借契約の実務では「転貸借」「賃貸人・賃借人の交代」「抵当権と賃借権の関係」「契約期間」の知識が欠かせません。賃貸不動産経営管理士試験でも頻出のテーマです。本記事では、それぞれの論点を整理し、学習のポイントを具体例とともに解説します。
転貸借の基本と賃借権の譲渡
まず「賃借権の譲渡」と「転貸借」を区別して理解することが重要です。
- 賃借権の譲渡
賃借人が自らの「賃借権」という法律上の地位を第三者に移転するものです。この場合、承諾を得れば旧賃借人は契約関係から外れ、新賃借人が直接オーナーと契約関係に入ります。 - 転貸借(サブリース)
賃借人が借りた物件をさらに第三者に貸すものです。ここでもオーナーの承諾が必要であり、承諾があれば「二重の賃貸借」が成立します。
試験で問われやすいのは「承諾を得て転貸した場合、オーナーは転借人に直接請求できる金額はどちらか」という論点です。答えは「原賃貸借と転貸借の賃料のうち少ない方」です。
無断譲渡・転貸の効果
オーナーの承諾なく賃借権を譲渡したり、転貸をした場合はどうなるでしょうか。
- 民法612条により、オーナーは契約解除が可能です。
- ただし、判例では「背信的行為とならない特段の事情」がある場合には解除できないとしています。
つまり「無断転貸=自動的に解除」と覚えるのではなく、「背信性があるかどうか」で判断される点が試験対策として重要です。
賃貸借と転貸借の関係
転貸借は元の賃貸借契約を前提とするため、原契約が終了すれば転貸借も終了するのが原則です。ただし、借地借家法は転借人を保護する規定を設けています。
- 原契約終了の通知が転借人にされなければ対抗できない(借地借家法34条)
- 通知を受けた場合は6か月後に終了する
さらに、実務で見られる「三者合意による承継特約」によって、転貸借の地位や敷金返還義務を調整することも可能です。
賃貸人・賃借人の交代と敷金
建物が売却される、いわゆる「オーナーチェンジ」の場合も試験で狙われやすい論点です。
- 賃借権に対抗力(登記や引渡し)があれば、新オーナーに自動的に賃貸人の地位が移転します。
- 賃借権に対抗力がなくても、合意により新オーナーへ地位移転が可能です。
- この場合、敷金に関する権利義務も承継される点に注意。
一方で賃借人の交代では、敷金は新しい賃借人に自動承継されません。判例(最判昭53.12.22)により、特別の合意がない限り旧賃借人に対する敷金返還義務は残ります。
抵当権と賃借権の関係
建物に抵当権がついている場合、抵当権設定の前後で大きく結果が異なります。
- 抵当権設定後に賃借 → 競売買受人に対抗できない。原則すぐに明渡し。ただし民法395条により「6か月の明渡猶予」が認められる。
- 抵当権設定前に賃借 → 対抗要件(登記や引渡し)があれば、競売買受人に対しても対抗でき、明渡不要。
この区別は過去問で繰り返し出題されており、正確な理解が必要です。
契約期間の制限
最後に契約期間について整理します。
- 民法のルール:賃貸借期間は最長50年。更新は可能だが、更新後も最長50年。
- 借地借家法のルール:建物賃貸借には期間制限なし。ただし、1年未満の契約は「期間の定めのない契約」とみなされる。
この「民法と借地借家法の違い」も試験で頻出です。
まとめと試験対策ポイント
賃貸不動産経営管理士試験では、単なる条文知識だけでなく「どちらに請求できるか」「どちらに承継されるか」といった当事者間の関係整理が問われます。
学習の要点は以下の通りです。
- 転貸借の賃料請求は小さい方
- 無断転貸は解除事由だが、背信性がなければ例外あり
- オーナーチェンジでは賃貸人の地位・敷金が承継される
- 抵当権設定前後で借主の保護が異なる
- 民法と借地借家法の契約期間の違いを区別する
これらを整理しておくと、実務知識としても試験対策としても非常に役立ちます。
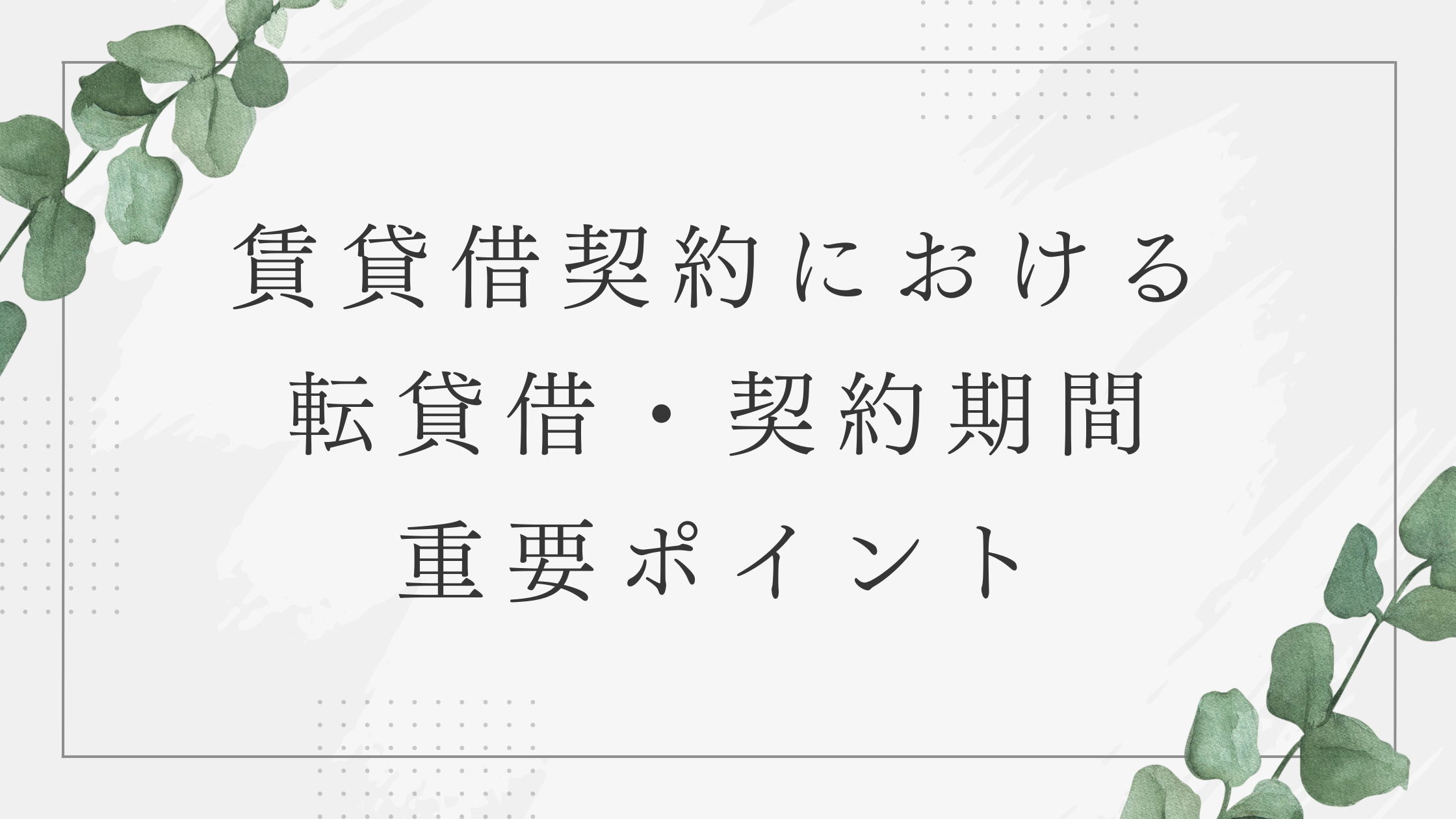
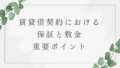
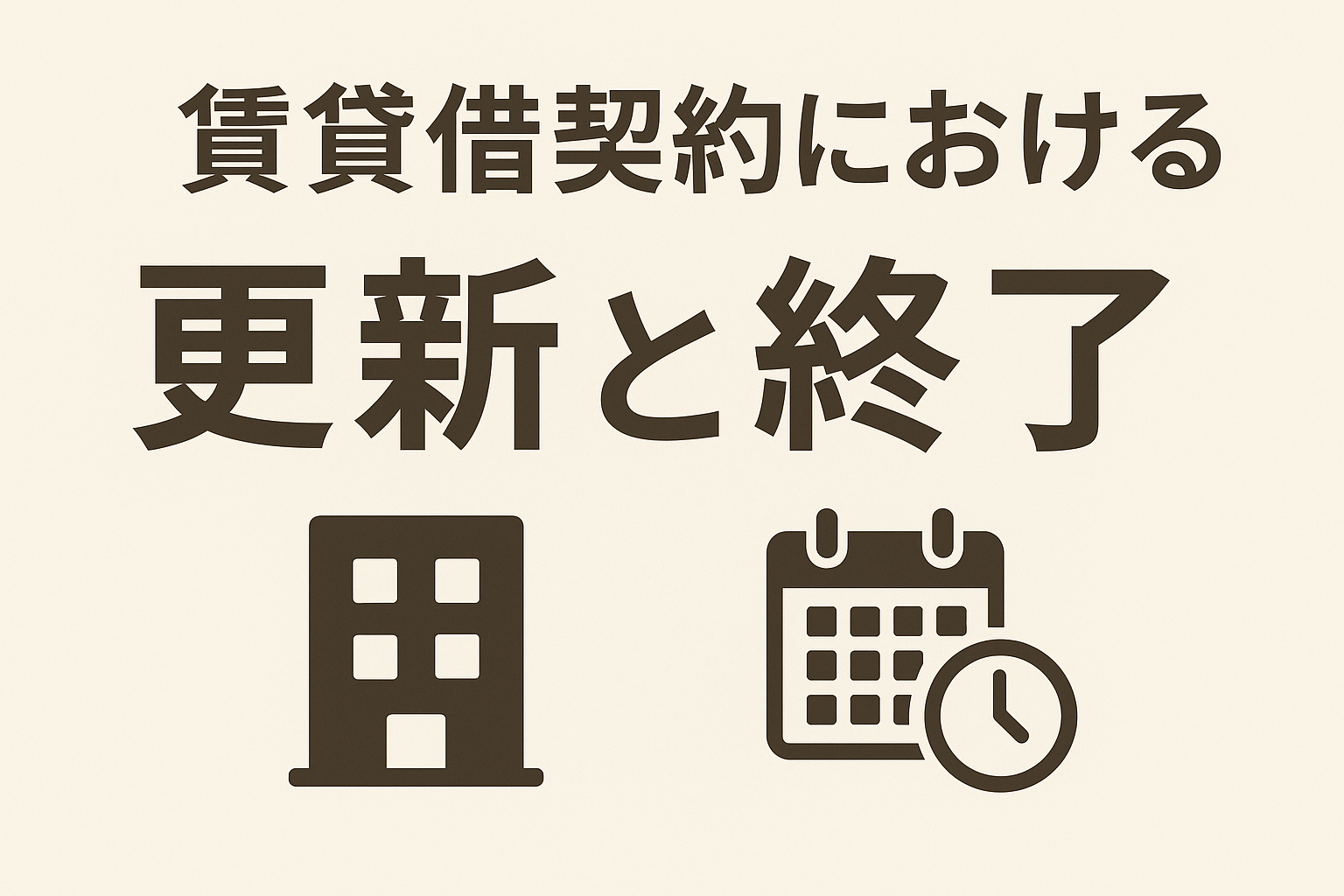
コメント