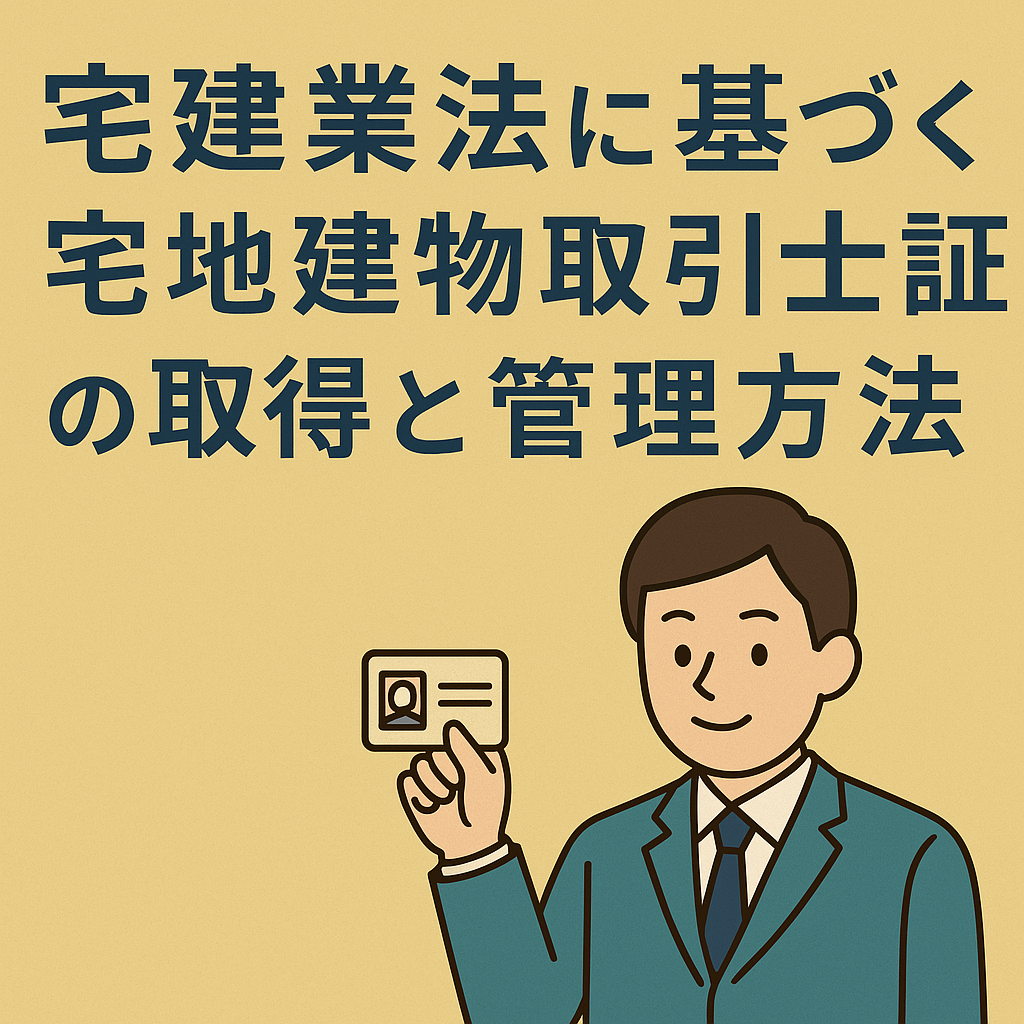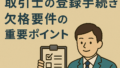宅建試験の受験者の皆さん、合格後に必要な「取引士証」の制度について理解はできていますか? 宅建業法に基づき、宅建士の業務を行うには必ず「取引士証」が必要です。本記事では、取引士証の取得から更新、書換え、返納までの手続きをわかりやすく解説していきます。
取引士証の基本情報と記載内容
取引士証には、氏名、生年月日、住所、登録番号、登録年月日、有効期間の満了日、都道府県知事名、交付年月日、発行番号といった情報が記載されています。この証明書は、宅建業の現場で必ず提示する場面がある非常に重要なものです。なお、有効期間は5年間です。更新には法定講習の受講が必要であり、申請前6か月以内に講習を受けなければなりません。
取引士証の交付申請と講習制度
取引士証の交付申請は、登録を行った都道府県知事に対して行います。原則、交付前6か月以内に実施される法定講習を受講しなければ交付を受けられません。ただし、宅建試験合格後1年以内に交付申請する場合や、登録の移転による新規交付の場合は、法定講習が免除されます。この免除条件も試験によく出題されるので、しっかり確認しておきましょう。
書換え交付と変更手続きの違い
氏名や住所を変更した場合、取引士証の書換え交付申請を行う必要があります。結婚による氏名変更や引越しによる住所変更などが典型です。住所のみの場合は、取引士証の裏面に記載する方法も認められています。ただし、本籍や勤務先の変更では、書換え交付は不要です。変更の登録のみで完了しますので、間違えないよう整理して覚えましょう。
取引士証に課せられる3つの義務
取引士証には、「提示の義務」「提出の義務」「返納の義務」があります。特に重要なのは、取引関係者から請求があれば提示し、重要事項説明時には必ず提示しなければならない点です。事務禁止処分を受けた場合は速やかに都道府県知事へ提出し、登録が消除された場合や効力を失った際、また亡失後に発見されたときは、返納義務が発生します。
提出と返納の違いとその扱い
提出は、事務禁止期間中に一時的に預ける行為で、期間終了後には返還請求が可能です。一方、返納は取引士証を無効化する手続きであり、返還されることはありません。この違いも試験で狙われるポイントですので、混同しないように理解を深めましょう。実際の業務でも適切に対応できるよう、今のうちに整理しておくことが大切です。