宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
先日、大手の不動産クラウドファンディング事業者で配当遅延が発生したニュースは、多くの投資家に衝撃を与えました。この事態を受け、国土交通省は8月1日、まさにタイムリーと言うべき「不動産特定共同事業のあり方についての中間整理」を公表しました。これは、相次ぐ投資トラブルを踏まえ、「不動産特定共同事業法(不特法)」の制度をどう見直していくか、その方向性を示したものです。今後の法改正に直結する内容であり、未来の不動産のプロである皆さんは、必ず押さえておくべき重要動向です。
なぜ今、制度見直しが急がれるのか
まず、国が制度見直しを急ぐ背景には、不動産クラウドファンディング市場の急拡大があります。特にインターネットを通じた個人の投資家が急増しており、2023年には約30万人にも達しました。市場が拡大し、参加者が多様化する一方で、事業者の情報開示が不十分であったり、運営体制に問題があったりするケースも散見されるようになりました。投資家が安心して投資できる市場を整備するため、投資家保護の強化が喫緊の課題となっているのです。
投資家保護の4本柱①「情報開示」の徹底
中間整理では、投資家保護を充実させるための4つの方向性が示されました。その第一の柱が「情報開示の拡充」です。これは、投資家が契約前に、その商品のリスクや妥当性を正しく判断できるようにするためのものです。具体的には、以下のような情報の開示を充実させるべき、とされています。
- 想定利回りの具体的な根拠
- 対象不動産の価格の妥当性(不動産鑑定評価をとらない場合はその理由)
- 運営会社の関連会社などとの取引(利害関係人取引)における価格の妥当性
- 集めた資金(出資金)の具体的な使い道
これらは、まさに投資の核心部分であり、この情報が透明化されることは極めて重要です。
投資家保護の4本柱②「公正な売却価格」の確保
第二の柱は、「対象不動産の売却価格等における公正性の確保」です。不特法の商品では、運用期間が終了した際、対象不動産を売却して投資家に元本を償還します。この時、運営会社の関連会社などに不当に安い価格で売却されてしまうと、投資家は損失を被ってしまいます。
これを防ぐため、利害関係者に物件を売却する場合は、原則として不動産鑑定評価額に基づいた価格での売却を求める、という方向性が示されました。これは、恣意的な価格操作を防ぎ、投資家の財産を守るための重要なルールです。
投資家保護の4本柱③④「行政監督」と「業界連携」
第三、第四の柱は、「行政による監督の充実」と「業界団体との連携」です。国や都道府県が事業者への立入検査を積極的に行うなど、監督体制を強化すること。そして、事業者団体自身が自主的なルールを設けて、業界全体の健全性を高めていくこと。この両輪で、市場の信頼性を高めていくとしています。
宅建士が学ぶべき「不特法」の未来と専門家の責任
今回の国交省の動きは、近年の投資トラブルに対する明確な回答です。「不特法」は、近い将来、この中間整理で示された方向性に沿って、より投資家保護を重視した形に改正される可能性が非常に高いと言えます。
不特法の案件を宅建士として扱うことはありませんが、不動産業界のニュースとして知っておいて損はありません。
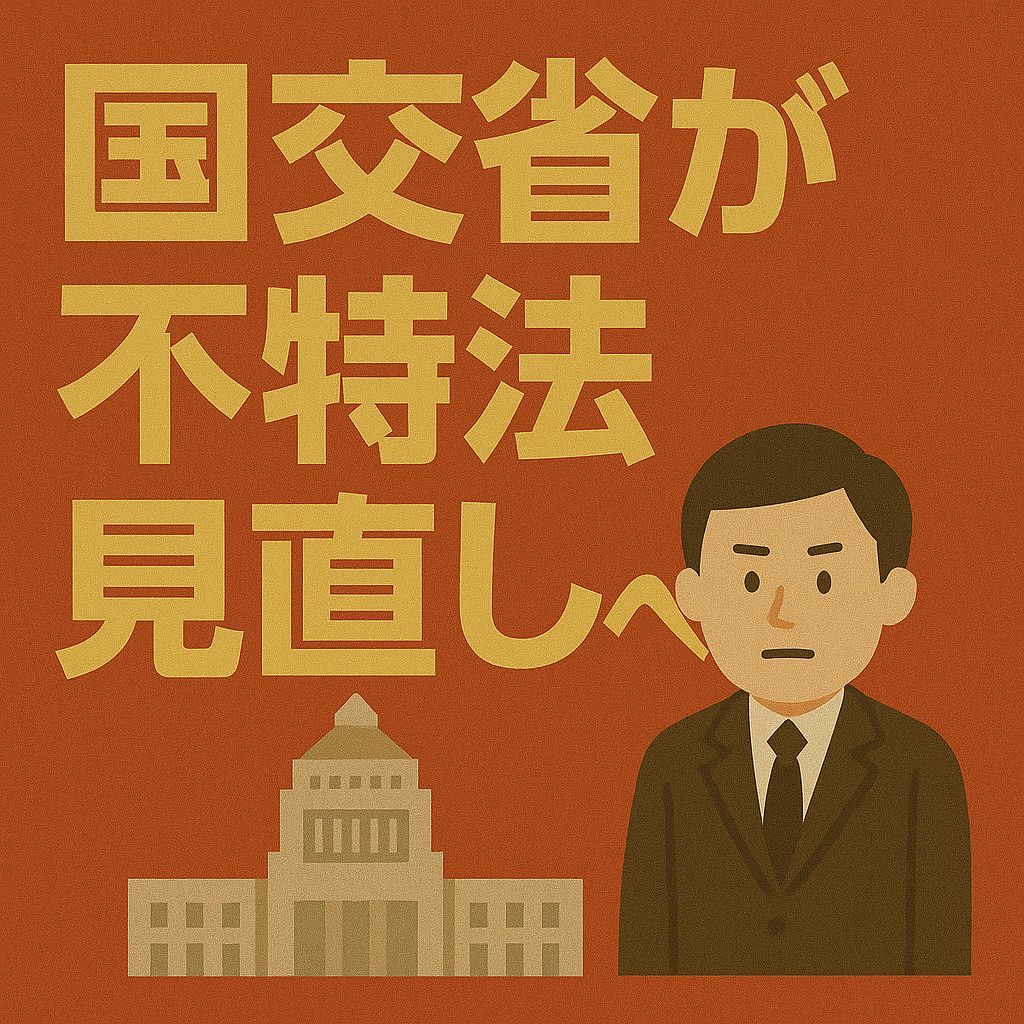

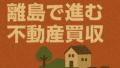
コメント