賃貸住宅管理業法では、管理受託契約を結ぶ前後に「書面の交付と説明」を行うことが義務づけられています。
これは、オーナー(賃貸人)が契約内容を十分に理解し、安心して管理を委託できるようにするための重要なルールです。
本記事では、試験で頻出の「重要事項説明」「契約締結時書面」そして「再委託の禁止」までを体系的に整理します。
管理受託契約の重要事項説明とは
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結する前に、賃貸人へ「管理受託契約重要事項説明書」を交付して内容を説明しなければなりません(13条1項)。
この制度は、宅建業法における「重要事項説明」に似ていますが、対象や説明者の要件に違いがあるため、混同しないよう注意が必要です。
重要事項説明の内容(11項目)
管理受託契約重要事項説明書には、次の11項目を記載し説明します(施行規則31条)。
- 管理業者の商号・登録番号など
- 管理業務の対象物件(所在地・構造・設備等)
- 管理業務の内容・実施方法(頻度や範囲も明示)
- 報酬額と支払方法
- 報酬に含まれない費用(光熱費・空室管理費など)
- 管理業務の一部再委託に関する事項
- 責任および免責に関する事項
- 委託者への報告内容と頻度
- 契約期間(始期・終期)
- 入居者への周知方法
- 契約の更新・解除に関する事項
💡 試験のポイント:
「報酬に含まれない費用」「再委託」「入居者への周知方法」は出題頻度が高く、正確に覚える必要があります。
書面交付が不要なケース
次の者が賃貸人である場合、書面交付・説明は不要です(13条1項かっこ書、規則30条)。
- 賃貸住宅管理業者
- 特定転貸事業者
- 宅地建物取引業者
- 特定目的会社(SPC)
- 不動産特定共同事業法上の組合
- 信託の受託者(委託者が上記のいずれか)
- 都市再生機構
- 地方住宅供給公社
つまり、専門知識を有する法人・公的機関には説明を省略できるという趣旨です。
説明の実施者とタイミング
重要事項説明は「賃貸住宅管理業者の従業員」が行う必要があります(FAQ 3(2)7)。
ただし、業務管理者である必要はなく、管理者の監督下で行えば可です。
また、説明と契約締結の間は、オーナーが内容を十分に理解できるよう、1週間程度の期間を空けることが望ましいとされています(解釈13条関係1)。
管理受託契約の変更時にも説明が必要
新規契約だけでなく、契約内容の変更(管理受託契約変更契約)を行う際にも、変更内容についての説明と書面交付が必要です。
ただし、「契約期間の延長」や「名称変更」のように形式的な変更のみであれば、再説明は不要です。
💡 試験での注意点:
法施行前に結ばれた契約で、まだ説明をしていない場合、変更契約時にすべての説明事項(①~⑪)を再度説明しなければなりません。
賃貸人が変わった場合の対応
管理物件が売却されて賃貸人が変わると、管理受託契約も引き継がれます。
この場合、賃貸住宅管理業者は、新オーナーに契約内容を説明し、必要に応じて締結時書面を交付する必要があります(解釈13条関係3)。
ITを活用した説明(電子契約の活用)
2022年以降、IT重説が賃貸住宅管理業にも導入されました。
書面の交付・説明は、賃貸人の承諾を得れば電磁的方法(メール・クラウド・Web閲覧)で行うことができます(13条2項、規則32条)。
主な要件
- 賃貸人の承諾を記録に残すこと(メールやWeb承諾等)
- 書面が出力可能で改変できない形式であること
- 双方向で音声・映像のやり取りが可能であること
💡 試験ポイント:
電話による説明は原則不可。ただし「契約変更契約」に限り、特定の条件を満たせば電話説明が認められます。
管理受託契約締結時の書面(14条)
契約を締結した後は、管理受託契約締結時書面を遅滞なく交付する義務があります(14条1項)。
内容は重要事項説明書とほぼ同様ですが、実際に締結した契約の内容を記録するものです。
主な記載事項(規則35条)
- 管理業務の対象となる賃貸住宅
- 管理業務の実施方法
- 契約期間
- 報酬の額と支払時期・方法
- 更新・解除に関する定め
- 管理業者の商号・登録番号
- 管理業務の内容
- 再委託に関する事項
- 責任・免責に関する事項
- 委託者への報告に関する事項
- 入居者への周知に関する事項
💡 補足:報酬の額や支払方法は必ず記載(規則35条1項)。
管理業務の再委託の禁止(15条)
管理業務の全部を他者に再委託することは禁止されています(15条)。
ただし、一部を再委託することは可能であり、その際は自らが再委託先を指導・監督する責任を負います。
再委託先は賃貸住宅管理業者でなくても構いませんが、信頼性のある事業者に委託することが望まれます。
契約を交わさずに他社へ業務を任せると、「名義貸し」とみなされるおそれがあります。
💬例題で確認!
例題1(基本)
管理受託契約の締結前に交付・説明すべき「管理受託契約重要事項説明書」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)説明は賃貸住宅管理業者の従業員が行う必要がある。
(2)説明の相手方が宅地建物取引業者の場合も、必ず説明を行う必要がある。
(3)説明事項には報酬額や支払方法が含まれる。
(4)説明から契約締結まで、1週間程度の期間をおくことが望ましい。
👉 正解:(2)
宅建業者など専門知識を有する者には、書面交付・説明を省略できる(規則30条)。
例題2(応用)
賃貸住宅管理業者A社は、オーナーBに対し、管理受託契約の変更契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)契約期間のみを延長する場合でも、重要事項説明をやり直す必要がある。
(2)契約変更時には、変更事項のみを説明すればよい。
(3)契約変更契約では電話による説明は一切認められない。
(4)再委託先の選定に関しては、責任は再委託先に移る。
👉 正解:(2)
変更契約では、変更部分のみの説明で足りる(解釈13条関係1)。
例題3(発展)
次のうち、管理受託契約締結時書面に記載すべき事項として正しいものはどれか。
(1)賃貸住宅の構造計算書の写し
(2)契約の更新・解除に関する定め
(3)管理業務に関する社内規程の写し
(4)賃貸人の家賃収入の履歴
👉 正解:(2)
契約更新・解除の定めは締結時書面の記載事項である(規則35条1項)。
まとめ:管理契約の「事前説明」と「事後交付」はセットで覚える!
- 契約前:重要事項説明書を交付・説明(13条)
- 契約後:締結時書面を交付(14条)
- 全部の再委託は禁止(15条)
- IT重説は承諾と記録が必須
これらの条文は「出題率が極めて高い」部分です。
特に、書面の内容の違い・省略可能な相手方・IT説明の要件は混同しやすいので、過去問で繰り返し確認しましょう。
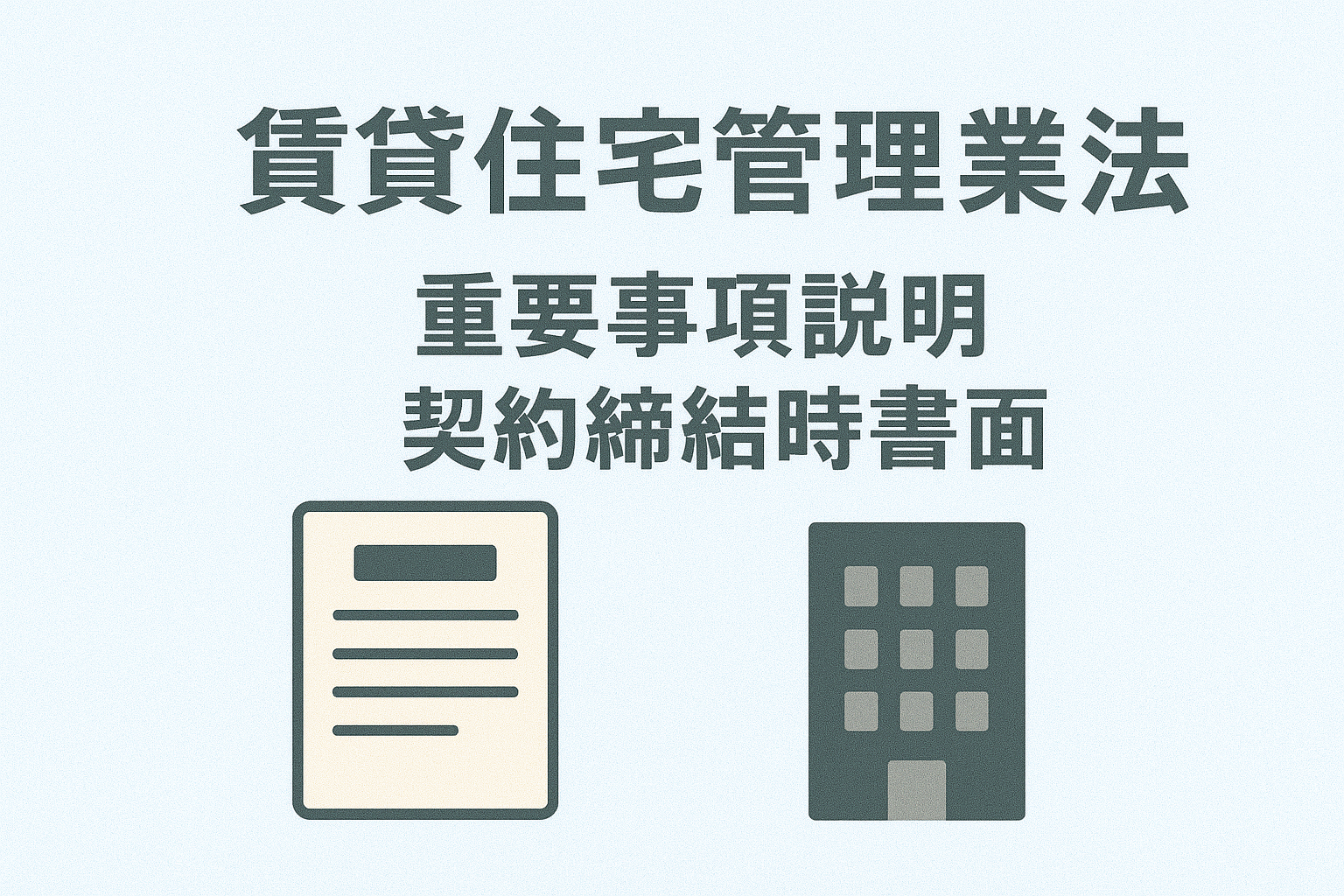

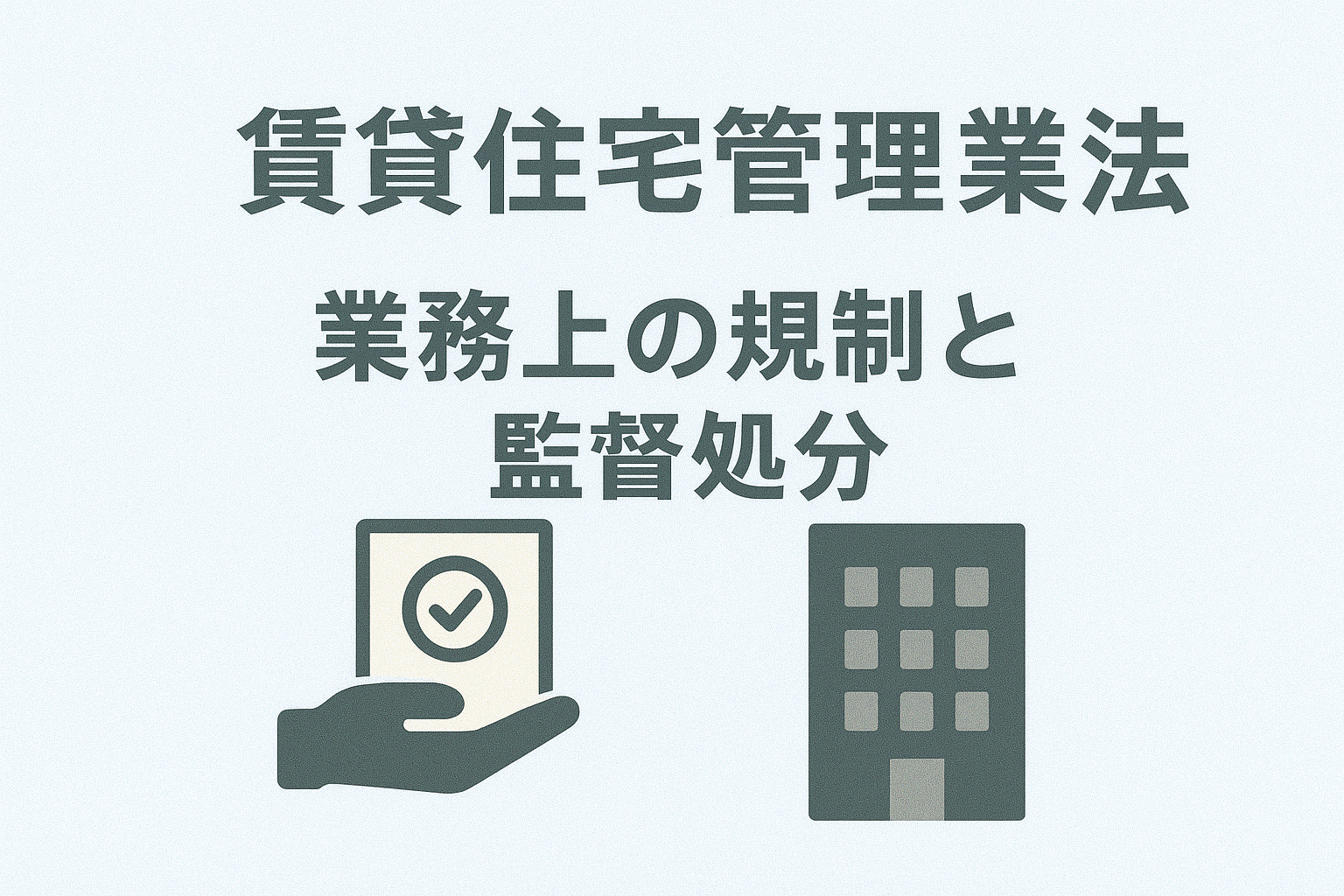
コメント