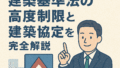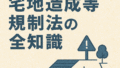農地法は、農地の適正な利用と保全を目的とした法律であり、農地の売買や転用を制限する重要なルールを定めています。宅建試験では「3条・4条・5条許可」の違いや、許可が不要となる例外、罰則、協議制度、さらには「農地所有適格法人」など、細かく問われることが多いため、正確な理解が欠かせません。
この記事では、農地法の基本から例題を交えて丁寧に解説していきます。
⸻
農地法の目的とは?
農地法の目的は、「耕作者の地位の安定」と「国内の農業生産の増大」を図り、最終的には「国民への食料安定供給を確保すること」にあります。
この目的を達成するため、農地法は以下のような制限を課しています。
- 農地や採草放牧地の売買・賃貸などの権利の移動
- 宅地などへの転用
- 転用目的での権利移動
これらは、それぞれ「3条・4条・5条」許可に分類されます。
⸻
農地・採草放牧地とは?
- 農地:耕作の目的に供される土地(実際に田・畑として使用中かどうかではなく、使用可能な状態であれば農地とみなされます)
- 採草放牧地:主に家畜の放牧や飼料草の採取に使われる土地
登記簿上で農地でなくても、実態として農地であれば、農地法の制限が適用されます。
⸻
農地法に基づく3つの許可制度
第3条許可:農地のままで権利移動をする場合
対象:
農地や採草放牧地を、そのまま農地等として利用する目的で所有権などを移転する場合。
申請者:
契約当事者双方(売主・買主、貸主・借主)が農業委員会に申請
例外:
国・都道府県への移転、相続、農事調停など。
ただし、相続は届け出が必要です。
罰則:
無許可での移転は契約無効。3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
⸻
第4条許可:自分の農地を転用する場合
対象:
自己所有の農地を宅地や駐車場など、農地以外に利用する場合。
申請先:
原則、都道府県知事または指定市町村の長
例外:
- 市街化区域内の農地:農業委員会への事前届け出で足りる
- 国・都道府県等が公益施設を整備する場合
- 耕作者が農業用施設に転用(200㎡未満)
罰則:
無許可転用は、原状回復命令+3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)
⸻
第5条許可:転用を目的とする権利の移動
対象:
農地や採草放牧地を転用目的で売買・賃貸する場合
申請先:
都道府県知事または指定市町村の長(4ha超なら事前に農水大臣と協議)
例外:
- 市街化区域
- 国・都道府県等による公益事業用
- 土地収用法等に基づく取得
罰則:
無許可での契約は無効。転用行為も原状回復命令+罰則あり(法人は最大1億円罰金)
⸻
法定協議制度とは?
国・都道府県等が学校や病院など公共施設を建てるために農地を取得・転用する場合、許可を得る代わりに都道府県知事との協議が成立すれば許可があったものとみなされる制度です。
ただし、許可が「不要になる」のではなく、「協議により許可がみなされる」ことに注意しましょう。
⸻
宅建で問われるその他の重要点
- 売買予約には5条許可不要だが、本契約時には必要
- 4条許可取得後でも、その農地を転用前に譲渡するなら5条許可が必要
- 農地賃借権は登記がなくても引渡しで第三者に対抗可能
- 使用貸借は引渡しでも対抗力なし
- 農地の賃貸借の存続期間は最長50年
- 賃貸借の終了には都道府県知事の許可が必要(原則)
⸻
農地所有適格法人とは?
農地法では、農地の取得は原則として個人の農業従事者に限られています。しかし、例外的に農地を取得できる法人が農地所有適格法人です。
条件:
- 主たる業務が農業であること
- 役員の過半数が農業に常時従事していること
適格法人以外の法人は、農地の所有権は取得できません。ただし、条件を満たせば使用貸借や賃借は可能です。
⸻
例題で理解を確認しよう!
問題:
Aは所有する農地を駐車場に転用しようとしている。転用の工事に着手する前に、当該農地をBに売却しようとしている。この場合、必要な許可はどれか?
ア.3条許可
イ.4条許可
ウ.5条許可
エ.許可不要
正解:ウ(5条許可)
→ 転用+権利移動=5条許可が必要。たとえ4条許可を取得していても、譲渡の際には改めて5条許可が必要です。
⸻
まとめ:農地法の学習ポイント
宅建試験では、「農地法の3条・4条・5条の違い」と「例外規定」「誰が申請するか」「罰則の内容」などが繰り返し問われます。特に間違えやすいポイントを押さえておきましょう。
- 権利移動 → 3条/転用 → 4条/転用目的の権利移動 → 5条
- 市街化区域の例外は事前届け出制
- 許可を受けずに行った契約は無効。罰則は重い
- 農地所有適格法人の制度は要確認
繰り返し問題を解きながら、確実に知識を定着させてください!