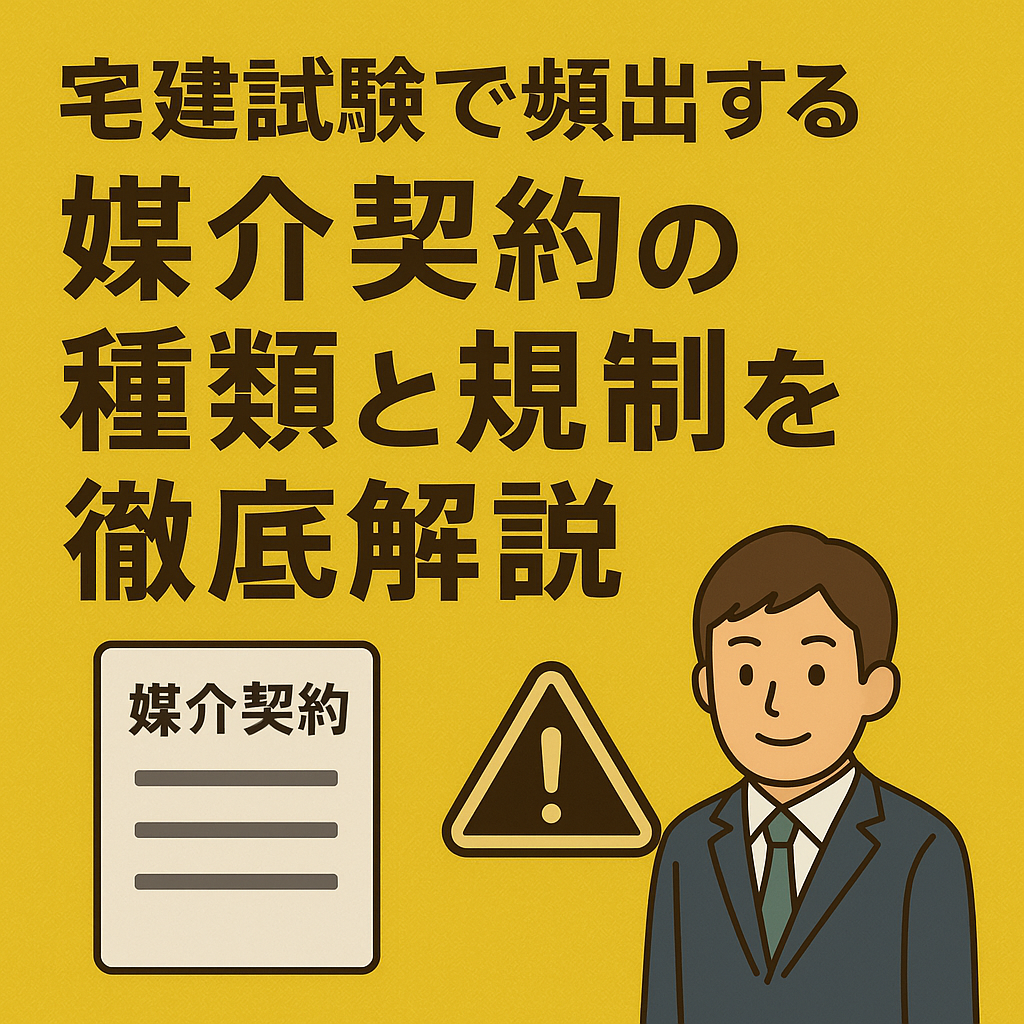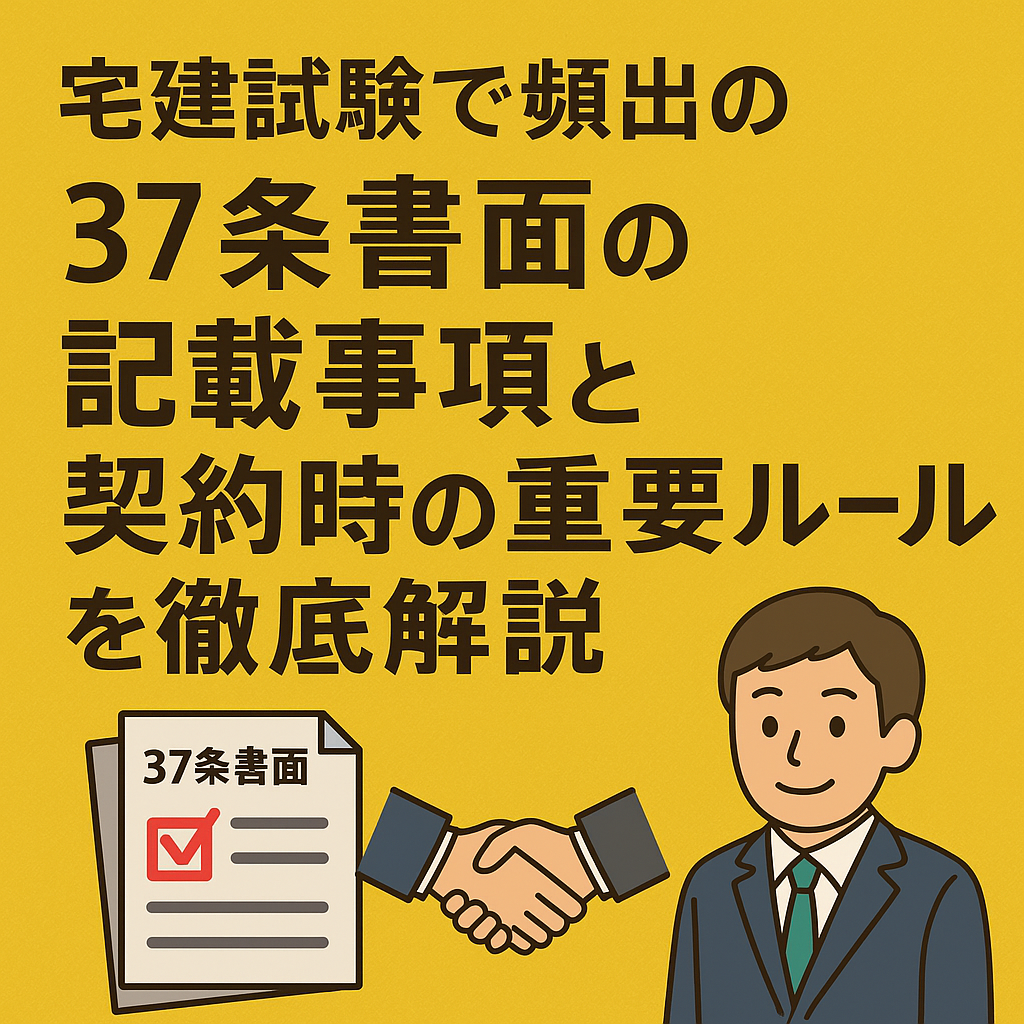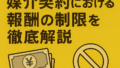宅建試験受験者の皆さん、こんにちは。
今回は宅建業法の中でも重要テーマである「媒介契約」について、分かりやすく解説していきます。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」という3つの種類があり、それぞれに異なるルールと規制が定められています。
また、報告義務や指定流通機構への登録など、細かい規制も多く、試験での出題率も非常に高い分野です。
例題を交えながら、理解しやすくまとめましたので、しっかり押さえておきましょう。
媒介と代理の違いとは?
まず、媒介と代理の違いを押さえておきましょう。
- 媒介:契約を成立させるために、売主・買主、貸主・借主の間を取り持つ行為
- 代理:依頼者の代理人として、宅建業者が直接契約を締結する行為
宅建業者が媒介や代理の依頼を受けた場合、必ず媒介契約または代理契約を締結します。
※代理契約も、媒介契約と同様の規制が適用されます(報酬を除く)
媒介契約の3種類と特徴
媒介契約は以下の3種類に分類されます。
一般媒介契約
- 他の宅建業者にも重ねて依頼OK
- 自分で買主を見つけて契約もOK
- 明示型(他業者を知らせる)と非明示型がある
専任媒介契約
- 他の宅建業者に重ねて依頼はNG
- 自分で買主を見つけて契約はOK
専属専任媒介契約
- 他の宅建業者にも重ねて依頼NG
- 自分で見つけた買主との契約もNG
例題1
次のうち、依頼者が自分で買主を見つけて契約できない媒介契約はどれか。
A. 一般媒介契約
B. 専任媒介契約
C. 専属専任媒介契約
D. 明示型一般媒介契約
正解 → C
専任媒介・専属専任媒介契約に課される規制
これらの契約では宅建業者に以下の義務が課されます。
1. 有効期間の制限
- 3ヶ月以内(超える特約は無効)
- 自動更新はNG(依頼者の申し出があれば更新可能)
2. 業務処理状況の報告
- 専任媒介:2週間に1回以上
- 専属専任媒介:1週間に1回以上
※報告は口頭でも可
3. 申込みの報告義務(※すべての媒介契約が対象)
- 申込みがあったら遅滞なく依頼者に報告
- 一般媒介契約も含まれる点に注意!
指定流通機構(レインズ)への登録義務
依頼を受けた物件の情報を国土交通大臣が指定する「指定流通機構(レインズ)」に登録する義務があります。
- 専任媒介:契約締結日から7日以内
- 専属専任媒介:契約締結日から5日以内
- 一般媒介:登録義務なし(任意)
【登録内容】
1. 物件の所在地・規模・形質
2. 売買価格
3. 主な法令制限
4. 専属専任媒介契約かどうか
登録後、宅建業者は「登録済証」を依頼者に遅滞なく交付(電磁的方法可)し、取引が成立した場合は内容を通知する義務があります。
例題2
専属専任媒介契約を締結した宅建業者が指定流通機構に物件情報を登録するのは、契約締結日から何日以内か?
A. 2日以内
B. 5日以内
C. 7日以内
D. 任意で登録すればよい
正解 → B
媒介契約書(34条の2書面)の作成・交付義務
宅建業者は、売買・交換の媒介契約を締結したとき、次の内容を記載した媒介契約書を作成・記名押印し、依頼者に交付しなければなりません。
※取引士ではなく宅建業者の義務です。
※貸借契約では作成義務なし。
【記載事項】
1. 物件の表示(所在地・地番など)
2. 売買価格または交換評価額
3. 媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)
4. 有効期間
5. 報酬に関する事項(額・税・支払時期)
6. 解除・契約違反に関する事項
7. 建物状況調査のあっせん有無(平成30年追加)
8. 指定流通機構への登録に関する事項
9. 標準媒介契約約款に基づくかどうか
例題3
媒介契約書の作成義務者として正しいのは誰か?
A. 取引士
B. 宅建業者
C. 買主
D. レインズの職員
正解 → B
試験対策まとめとポイント
この分野で特に問われるポイントは以下の通りです。
- 一般・専任・専属専任の違い(依頼・自己発見の可否)
- 専任・専属専任のみ課される報告・登録義務
- 媒介契約の有効期間は3ヶ月以内、更新は申出が必要
- 媒介契約書は売買・交換のみ作成義務あり(貸借は不要)
- 記名押印義務は宅建業者、取引士ではない点に注意
特に、一般媒介でも申込み報告が必要であることや、媒介契約書の記名押印義務の主体を問う問題がよく出ます。
覚えるべきことが多い分野ですが、表にして整理すると効果的です。