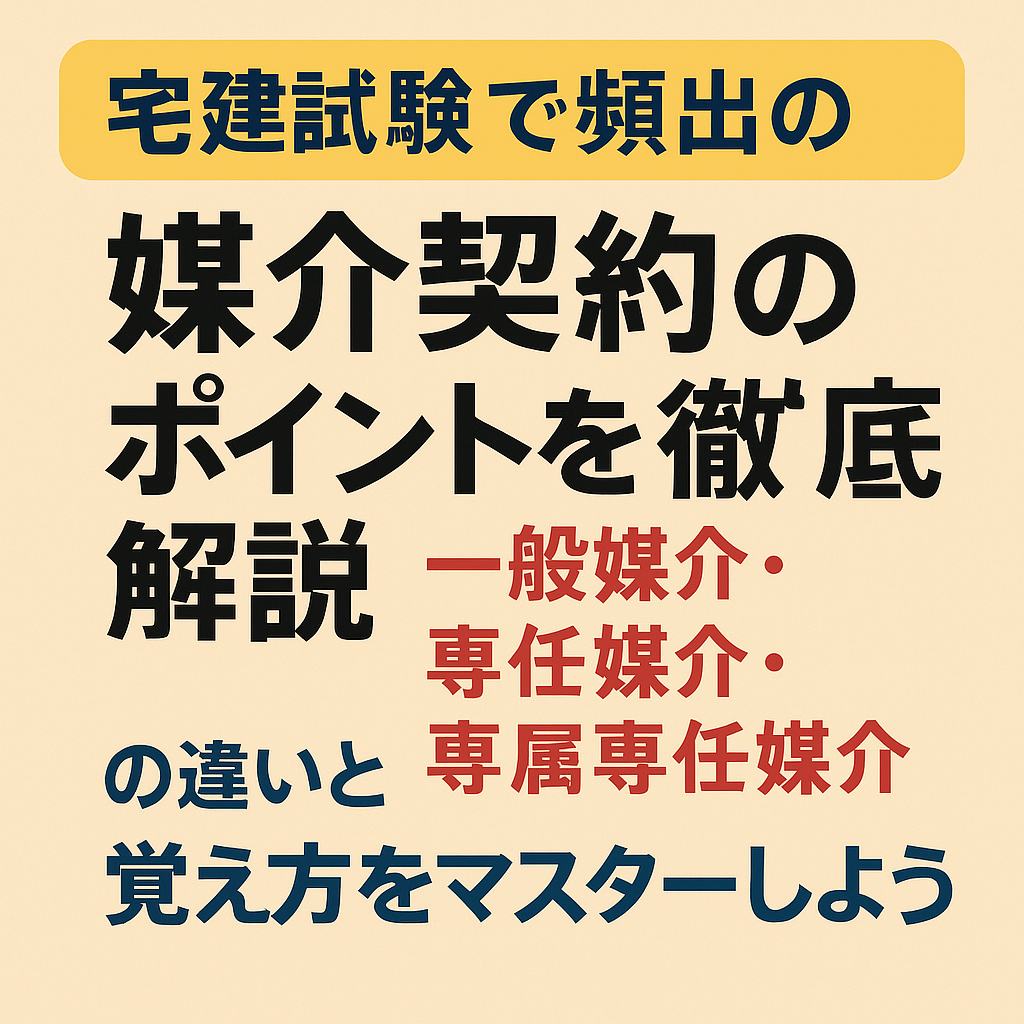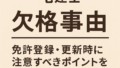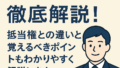宅建試験における媒介契約の重要性
宅建試験では「媒介契約」に関する知識が毎年のように出題されており、合否を左右する重要なポイントとなります。不動産取引において、媒介契約は宅地建物取引業者と依頼者との間のルールを定める重要な契約です。ここでは媒介契約の種類ごとの違いや特徴、試験に出やすいポイントを整理して解説します。
媒介契約とは何か?基本から押さえよう
媒介契約とは、宅地建物取引業者が売主や買主などの依頼を受けて、不動産の売買や賃貸の相手方を探す業務を行うための契約です。媒介契約を結ぶことで、業者は正式に依頼を受け、報酬を請求できるようになります。媒介契約は以下の3種類に分かれます。
一般媒介契約の特徴と注意点
一般媒介契約は、依頼者が複数の宅建業者に同時に依頼できる契約です。また、依頼者自身が相手方を見つけて直接契約を結ぶことも認められています。自由度が高く、縛りが少ないのが特徴です。
ただし、宅建業者は業務処理の状況を書面で報告する義務がありません。また、レインズ(指定流通機構)への登録義務もないため、情報の共有がやや遅れる可能性があります。
専任媒介契約のポイントを理解しよう
専任媒介契約では、依頼者は1社の宅建業者にのみ依頼できます。しかし、自ら相手方を見つけて契約することは可能です。つまり、業者独占ではあるものの、依頼者の自由は一部残されています。
この契約では以下の義務が業者に課されます。
- 7日に1回以上の業務処理状況の報告義務
- 契約締結から7日以内のレインズ登録義務
依頼者との信頼関係が重視される契約です。
専属専任媒介契約の制約とメリット
専属専任媒介契約は、依頼者が1社の宅建業者にのみ依頼する点では専任媒介と同じですが、自ら契約相手を見つけて直接取引することも禁止されています。つまり、最も制約の強い媒介契約です。
業者には以下の義務があります。
- 5日に1回以上の業務処理状況の報告義務
- 契約締結から5日以内のレインズ登録義務
専属専任は情報の広がりやすさと販売活動の積極性が期待される反面、依頼者の自由度は低くなります。
3つの媒介契約の違いを表で確認しよう
| 契約種別 | 他業者への重複依頼 | 自ら契約相手を見つける | レインズ登録 | 業務報告義務 |
| 一般媒介 | 可 | 可 | 任意 | 無し |
| 専任媒介 | 不可 | 可 | 7日以内 | 7日に1回以上 |
| 専属専任 | 不可 | 不可 | 5日以内 | 5日に1回以上 |
この表は試験対策にも非常に有効なので、しっかり覚えておきましょう。
媒介契約に関するその他の試験ポイント
媒介契約は書面で締結することが宅建業法で義務付けられています。契約書には、物件の概要、媒介の種類、報酬額、契約期間などを明記する必要があります。契約期間は3ヶ月以内が原則で、更新する場合も3ヶ月以内で更新しなければなりません。
また、契約の解除についても試験に出題されることがありますので、媒介契約の終了事由や違約に関する知識も一緒に押さえておきましょう。
覚え方のコツと試験対策
専任媒介と専属専任媒介は「専任」が共通しており、依頼者が1社にのみ依頼する点がポイントです。その中でも「専属」はさらに強い制約があると覚えてください。語感の強さから連想すると記憶しやすいです。
また、「5日」「7日」という報告義務やレインズ登録の期限は混同しやすいため、語呂合わせや表で整理して反復学習することが効果的です。
まとめ
媒介契約は宅建試験の定番分野でありながら、細かい違いが多く混乱しやすい部分です。特に、3種類の媒介契約の違いと、それぞれの義務・制約を正確に把握することが得点アップの鍵となります。繰り返し学習を重ね、確実に自分のものにしていきましょう。