宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
不動産市場の今を象徴する、衝撃的なニュースが発表されました。価格の下落のニュースも過去にありましたが、ふたを開けてみれば2025年上半期(1~6月)の東京23区における新築マンションの平均価格が、ついに1億3064万円となり、過去最高を更新したのです。上半期の平均価格が1億円を超えるのはこれで3年連続となり、もはや「億ション」が当たり前の時代に突入しています。なぜ、これほどまでに価格が高騰し続けているのか。その背景にある構造的な要因を理解することは、未来の不動産のプロである皆さんにとって不可欠です。
過去最高を更新 価格高騰は首都圏全体へ
今回の価格高騰は、東京23区だけの話ではありません。首都圏全体(1都3県)の平均価格も8958万円と過去最高を記録。さらに、東京都下(多摩地域)、神奈川県、埼玉県も軒並み前年から2ケタの伸び率を示すなど、価格上昇の波が首都圏全体に広がっていることがわかります。専門家は「驚くような超高額物件が牽引したわけではなく、全体の価格水準が底上げされている」と分析しており、この傾向は当面続くと見ています。
なぜ価格は上がり続けるのか 3つの複合要因
この止まらない価格高騰の背景には、主に3つの要因が複雑に絡み合っています。
- 慢性的な建設コストの上昇資材価格の高止まりに加え、建設業界の「2024年問題」に象徴される労働規制の強化や深刻な人手不足が、人件費を押し上げています。家を建てるためのコストそのものが構造的に上がっており、これが物件価格に直接転嫁されています。
- 国内外の旺盛な購入需要一般的な所得層が購入をためらう「買い控え」が見られる一方で、国内外の富裕層による購入意欲は非常に旺盛です。特に海外の投資家からは、香港やシンガポールといったアジアの主要都市と比べて、東京の不動産にはまだ「割安感」があると見られており、強い買いが入っています。
- 開発業者の「供給絞り込み」戦略建設コストが上昇する中、デベロッパーは採算を確保するため、誰にでも買える価格帯の物件を大量に供給するのではなく、高くても売れる都心の一等地などに開発を集中させています。結果として、付加価値の高いハイグレードな物件が増える一方で、市場全体の供給戸数は4年連続で減少し、希少価値が価格をさらに押し上げています。
「需要」と「供給」から見る市場の現状
まさに、宅建試験で学ぶ経済学の基本である「需要と供給の法則」が、現在の市場を分かりやすく示しています。
【供給サイド】は、建設コスト増やデベロッパーの戦略によって「減少」しています。
【需要サイド】は、一般層の需要は「減少」しているものの、富裕層や海外投資家といった特定の層からの強い需要がそれを上回り、市場全体を牽引しているのです。この需要の二極化が、平均価格を押し上げる大きな要因となっています。
中古市場と外国人投資家が与える影響
新築マンションの価格を語る上で、中古市場の動向、特に海外投資家の動きは無視できません。活発な中古物件の取引が市場価格を押し上げ、それが新築物件の価格設定にも影響を与えるという連動性が生まれています。「中古も高いから、新築もこの価格で」という状況が起きているのです。
宅建士としてこの市場をどう読み解くか
このニュースから私たちが学ぶべきは、現在の価格高騰が、かつてのバブル期のような実態の伴わない熱狂とは異なり、「供給減」「コスト増」「特定の強い需要」という構造的な要因に支えられているという事実です。そのため、専門家も「当面、下がることは考えにくい」と分析しています。
宅建士には、こうした複雑な市場メカニズムを正確に理解し、顧客に説明する責任があります。一般の購入希望者には、なぜ価格が高いのか、今後の見通しはどうなのかを。そして、富裕層や投資家には、なぜ東京の不動産が魅力的なのかを。それぞれの顧客の立場に立って、的確な情報と見識を提供すること。それこそが、これからの不動産のプロに求められる真の価値なのです。

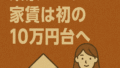
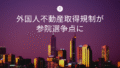
コメント