以下は、国土交通省が策定した 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月8日公表)を、試験・実務の観点から分かりやすく整理したものです。
賃貸・売買のいずれも扱う不動産業務において押さえておきたいポイントとなります。
リンク
1.策定の背景・位置づけ
- 不動産取引(特に居住用住宅)において、過去に「人の死」があった物件について、売主・貸主・媒介業者がどこまで調査し、どこまで入居者・購入者に告知すべきかという判断基準が明確でなかったことが、取引の円滑化や安心な流通を阻害する一因となっていました。 (国土交通省)
- 本ガイドラインは、業者(宅地建物取引業者)が法令(宅地建物取引業法)上負う義務の解釈を、現時点の裁判例や実務に照らして整理したもので、「義務そのものを強化」するものではなく、あくまで 判断・対応の目安を示したものです。 (国土交通省)
- 実務上、業者がこのガイドラインを参照して適正に対応していれば、トラブル防止・説明責任を果たす上で優位に働くと考えられています。 (国土交通省)
2.対象となる案件・物件の範囲
- 対象となる「人の死に関する事案」は、取引対象となる不動産(居住用不動産)で過去に生じた死亡事案を想定しています。 (国土交通省)
- 対象となる不動産の範囲は、主に「居住用不動産」であり、事務所・オフィス用途などの住宅以外の用途は原則対象外とされています。 (国土交通省)
- 分譲マンション等の集合住宅の「専有部分」はもちろん、「日常生活で通常使用する必要がある共用部分(例:玄関ホール、エレベーター、廊下など)」も告知対象の範囲に含まれうる旨が示されています。 (全宅協会)
3.業者(宅建業者)が取るべき「調査義務」
- 媒介を行う宅建業者は、売主・貸主(または管理業者)に対して、告知書(例:物件状況等報告書)等に過去に人の死に関する事案があるか記載を求めることにより、通常の情報収集義務を果たしたとみなされます。 (国土交通省)
- 一方、周辺住民への聞き込みやインターネット調査など、自発的・積極的な調査までを義務として要求するものではないとされています。 (全宅協会)
- 調査時には、売主・貸主に対し「告知しなかった場合の民事責任の可能性」などを助言しておくことが望ましいという留意事項も含まれています。 (全宅協会)
4.告知(通知)義務の考え方・基準
(1)原則として「告知しなくてよい」ケース
以下のような事案では、原則として買主・借主に対する告知義務はないとされています。 (全宅協会)
- 住宅で発生した「自然死」(例:老衰、病死)や、日常生活中の不慮の死(例:転倒による死亡、誤嚥による死亡など)で、かつ特殊清掃・大規模改修が行われていない場合。 (オーナーズ・スタイル・ネット)
- 集合住宅における「隣接住戸」や「日常的に通常使用しない共用部分(例:建物裏手・管理者専用階段など)」で発生した自然死・日常事故死。 (全宅協会)
- 賃貸借取引において、他殺・自殺・特殊清掃を要する死等の重大事案が発生した場合であっても、事案発生(または発覚)から概ね3年が経過していれば、原則として告知しなくてよいとする定めがあります。 (全宅協会)
(2)告知が必要となるケース
以下の場合には、告知義務が生じます。 (国土交通省)
- 他殺・自殺などの死亡、または死亡原因が不明で自然死とは区別できない事案。 (オーナーズ・スタイル・ネット)
- 死亡後、長期間放置され「特殊清掃」や大規模修繕・改修が行われた場合。 (公益社団法人 全日本不動産協会 –)
- 買主・借主から「当該物件に人の死があったかどうか」を問われた場合。 (全宅協会)
- 社会的影響が大きい、またはその物件・事案が「買主・借主が把握すべき特段の事情」であると業者が判断した場合。 (全宅協会)
(3)告知内容・手法の留意点
- 告知する場合には、発生時期(または発覚時期)・場所・死因・特殊清掃が行われたか等を簡潔に伝えることが求められています。 (全宅協会)
- ただし、亡くなった方やその遺族の氏名・年齢・住所・家族構成・具体的な死の状況等を記載・告知する必要はなく、名誉・プライバシーへの配慮が求められます。 (全宅協会)
5.特に注意すべきポイント(実務対応)
- 「自然死だから告知不要」と思っていても、特殊清掃・事件性・発覚遅延などがあれば告知義務が生じる可能性があります。例:「長期間発見されず特殊清掃した」→告知すべき。 (公益社団法人 全日本不動産協会 –)
- たとえ時効のように「3年が経過すれば告知不要」とされる場合でも、買主・借主から事案を問われた場合には説明義務が生じます。 (オーナーズ・スタイル・ネット)
- 調査段階で「売主・貸主から何も言っていない」「管理会社も不明」といった場合でも、業者として「売主・貸主に告知書記載を求める」「説明を助言する」といった対応が望まれています。無対応はリスクとなります。 (全宅協会)
- 告知義務を逃れるために「死者がいた建物を解体し土地にした」「死亡した人が搬送先で亡くなった」などのグレーゾーンがあり、今後も事例の蓄積・ガイドラインの更新が予定されています。 (全宅協会)
6.まとめ
「人の死」が発生した不動産取引では、買主・借主の心理的な抵抗・トラブル発生のリスクが高く、業者は適切に対応する必要があります。
本ガイドラインはそのための 実践的な目安を示したもので、特に次の点を押さえておきましょう。
- 調査:売主・貸主等に告知書記載を求めることで通常の情報収集義務を果たす。
- 告知が不要とされるケース・告知必須のケースを整理して理解。
- 告知の必要性は「死因・発生場所・発覚状況・社会的影響」等によって判断される。
- 名誉・プライバシーへの配慮を欠いた告知は避ける。
賃貸不動産経営管理士・宅建試験の観点からも、「心理的瑕疵」「事故物件」「告知義務」のキーワードと本ガイドラインの基準を押さえておくことが大いに役立ちます。
リンク
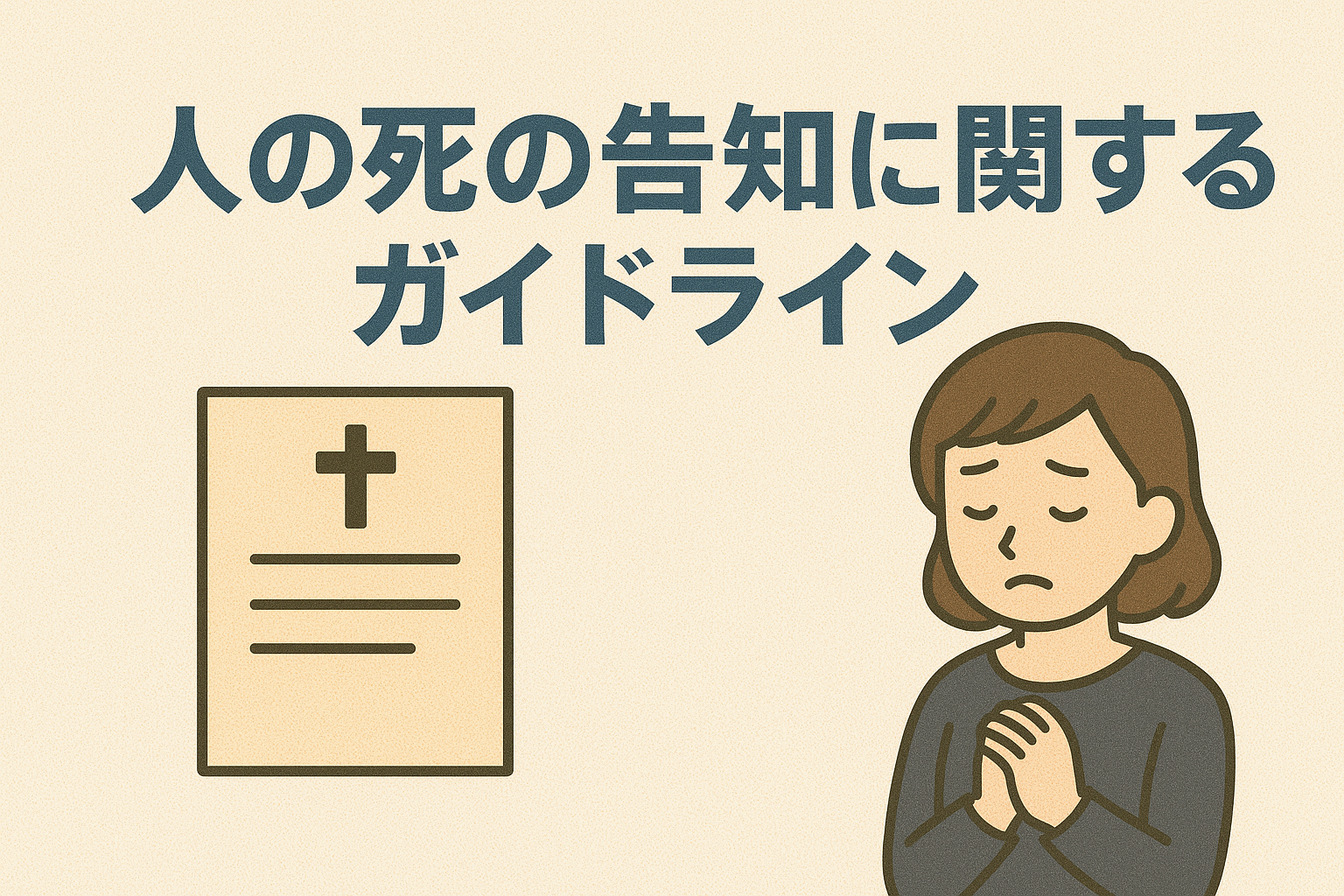
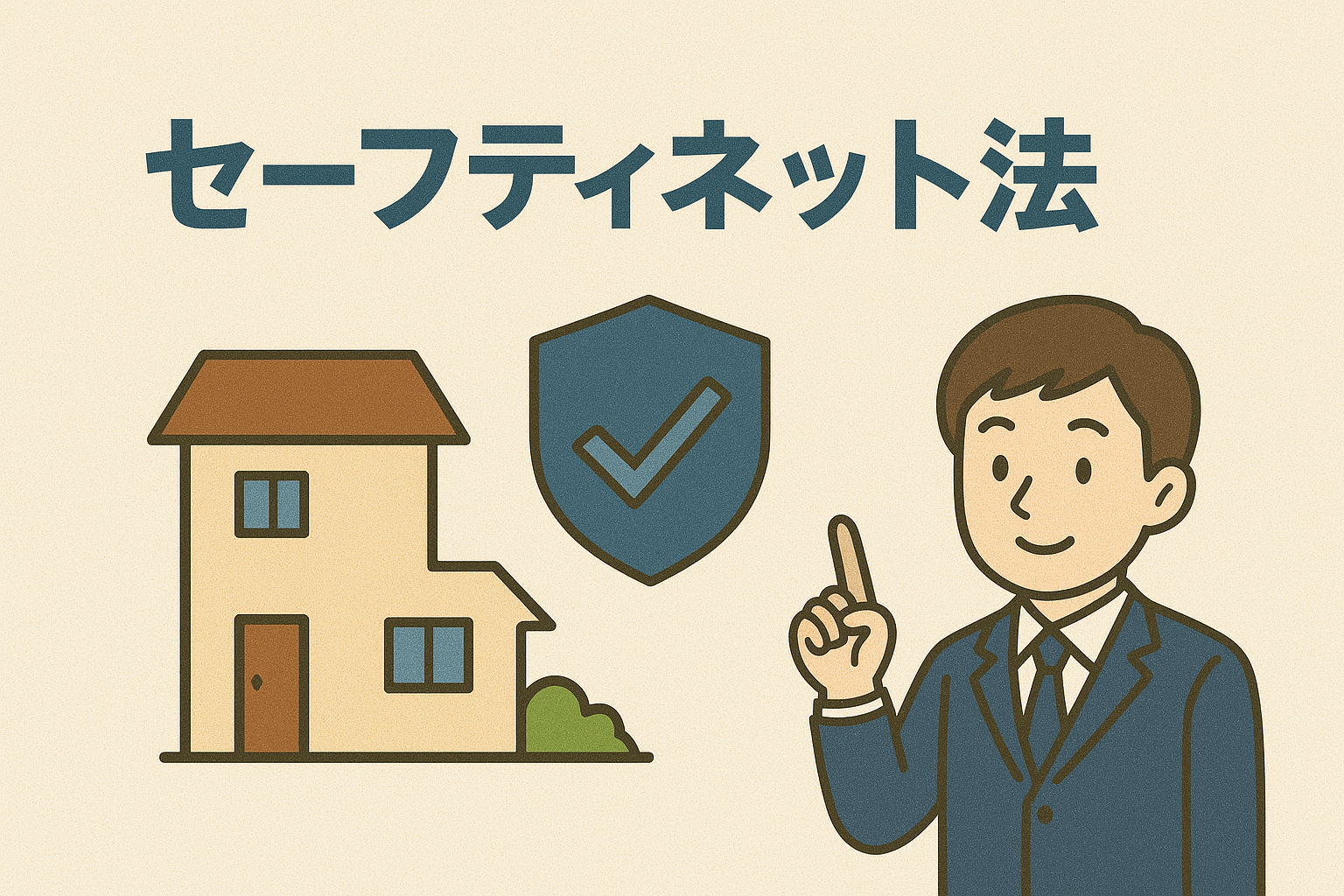
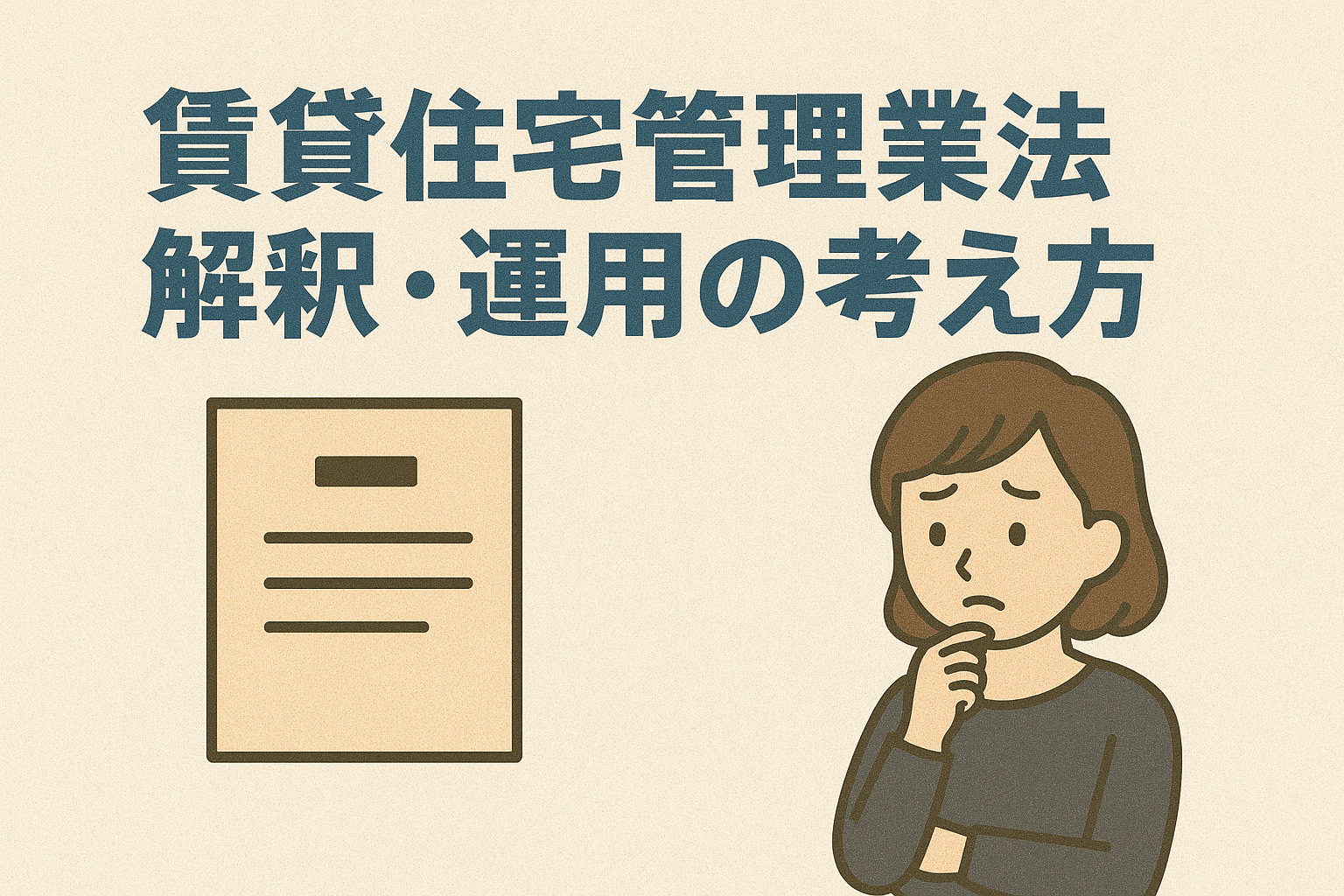
コメント