今回は、賃貸管理の根幹ともいえる「保証」と「敷金」の取扱いについて、学んだことをまとめてみたいと思います。同じく賃貸不動産経営管理士試験の受験を目指す方や、賃貸経営に携わる方の参考になれば幸いです。
まずは基本から 保証契約と連帯保証の違い
賃貸借契約では、賃借人の債務を担保するために保証人を立てることが一般的です。この保証人が負う債務を「保証債務」といいます 。
保証契約は、口約束では成立せず、必ず書面または電磁的記録で行わなければ効力が生じません 。これは「要式契約」といい、保証人になるという意思を慎重に判断させるための重要なルールです。通常は、賃貸借契約書の中に保証に関する条項と保証人の署名押印欄を設けることで、この要件を満たします 。
通常の保証人には、債権者(貸主)からいきなり支払いを請求された際に、まず主たる債務者(借主)に請求するように主張できる「催告の抗弁権」と、借主に資力があることを証明して、先に借主の財産から強制執行するよう主張できる「検索の抗弁権」が認められています 。
しかし、実務で圧倒的に多い「連帯保証人」には、これらの権利がありません。つまり、連帯保証人は借主とほぼ同じ立場で責任を負うことになり、貸主は借主に請求することなく、いきなり連帯保証人に家賃の支払いを請求できます。この責任の重さの違いは、必ず押さえておきたいポイントです。
近年の法改正で重要度アップ 個人根保証契約とは?
賃貸借契約における保証は、一度きりの取引ではなく、契約期間中に発生する家賃や更新料、損害賠償など、将来発生しうる不特定の債務をまとめて保証する形になります。
このように、一定の範囲に属する不特定の債務を個人が保証する契約を「個人根保証契約」といいます。
2020年の民法改正で、この個人根保証契約には非常に重要なルールが設けられました。それは、保証人が責任を負う上限額である「極度額」を書面等で定めなければ、その保証契約は無効になるという点です。
極度額を定めずに保証契約を締結してしまうと、万が一家賃滞納などが発生しても保証人に請求できないという事態に陥るため、管理実務において最も注意すべき点の一つです。
また、以下のようなケースでは、保証人が責任を負う元本が確定し、それ以降に発生した債務については保証の対象外となります。
- 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
- 主たる債務者(借主)または保証人が死亡したとき
敷金の法的な意味と充当のルール
敷金は、賃貸借契約において最も馴染み深い一時金の一つです。民法では「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されています。
つまり、名称が「保証金」などであっても、この目的で預かるお金は法的に敷金として扱われます。敷金によって担保される債務には、以下のようなものが含まれます。
- 未払賃料
- 借主の過失による物件の損傷等に対する損害賠償債務
- 賃貸借終了後、明渡しが遅れた場合の賃料相当損害金
ここで重要なのは、敷金の充当に関するルールです。
貸主は、借主に家賃滞納などがあった場合、敷金をその支払いに充てることができます。しかし、借主の方から「今月分の家賃を敷金から充ててください」と請求することはできません。これは貸主の権利であり、借主の権利ではないという点をしっかり理解しておく必要があります。
実務で必須の知識 敷金の返還と承継
敷金が借主に返還されるのは、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」と定められています。つまり、契約が終了しただけではダメで、物件の明渡しが完了して初めて、貸主は預かった敷金から滞納家賃などを差し引いた残額を返還する義務を負います。
よく誤解されがちですが、物件の明渡しと敷金の返還は「同時履行」の関係にはありません。判例でも、物件の明渡しが先とされています。借主が「敷金を返してくれないなら、部屋を明け渡さない」と主張することはできないのです。
また、オーナーチェンジなどで貸主が変わった場合、敷金の返還義務は、当然に新しい貸主に引き継がれます。これは、新貸主が旧貸主から敷金の交付を受けていなくても同様です。
一方で、借主が変わり、適法に賃借権が譲渡された場合は、特段の事情がない限り、敷金に関する権利義務関係は新しい借主には承継されないので注意が必要です。
礼金や更新料って法的にどうなの?
最後に、敷金以外の一時金である礼金や更新料についても触れておきます。
これらのお金は、敷金と違って民法に直接的な規定がありません。そのため、その有効性が争われることがありますが、判例では以下のように判断されています。
- 礼金賃料の前払いや、自然損耗分の投下資本の回収などの意味合いがあるとされ、消費者契約法に反して一方的に借主の利益を害するものでない限り、返還しない旨の特約は有効とされています。
- 更新料賃料の補充や契約を継続するための対価といった複合的な性質を持つものとされています。更新料の額が、賃料の額や更新される期間に照らして高額すぎるといった特段の事情がない限り、更新料特約は有効と判断されています。
まとめ
今回は、賃貸借契約における「保証」と「敷金」という、非常に重要で実務的なテーマについてまとめてみました。
特に、個人根保証契約の極度額設定や、敷金の充当・承継に関するルールは、トラブルを未然に防ぐために貸主・管理会社が正確に理解しておくべき知識だと改めて感じました。
賃貸不動産経営管理士の試験は、こうした実務に直結する知識が問われるため、とても勉強になります。試験合格を目指して、これからも学習を続けていきたいと思います。
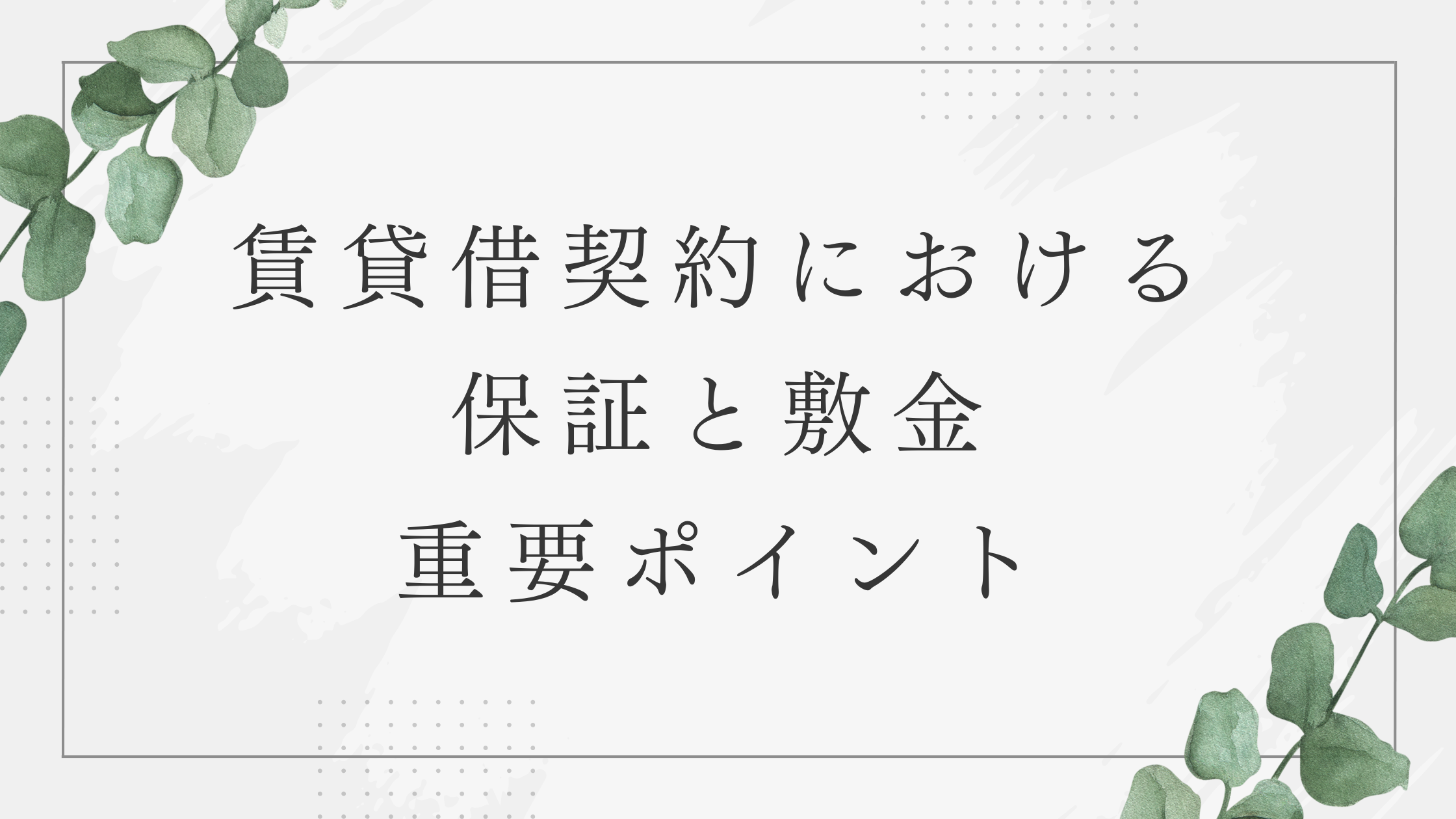
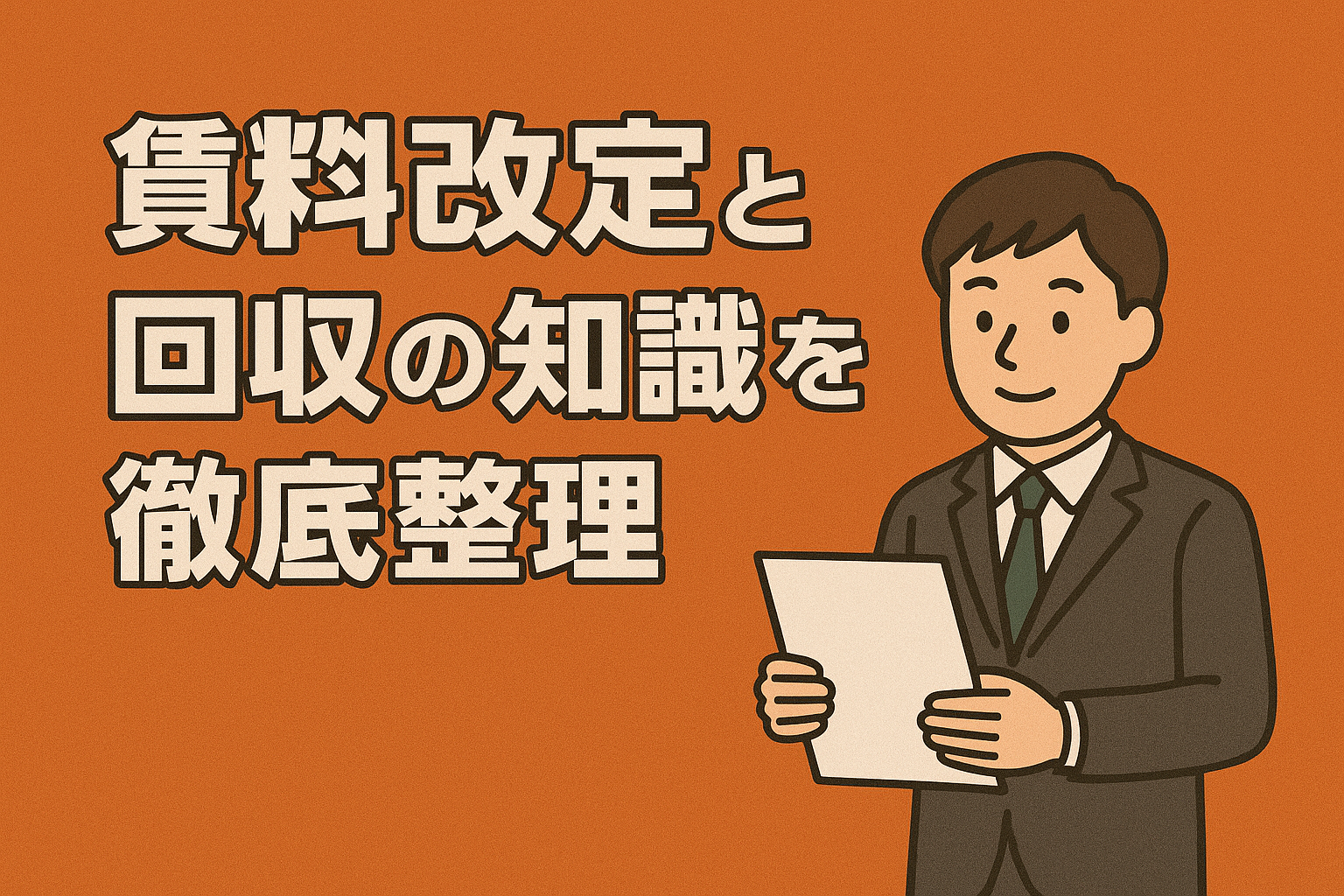
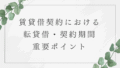
コメント