相続分野は民法の重要テーマであり、賃貸不動産経営管理士試験でも出題されやすい分野です。その中でも特に「遺言」「遺留分」「配偶者居住権」は近年の改正も多く、混乱しやすい部分でもあります。本記事では、それぞれの仕組みや特徴を整理し、試験対策として押さえるべきポイントを解説します。
1. 遺言とは
遺言とは、本人が生前に自らの死後の法律関係を定める行為をいいます(民法960条)。
遺言が効力を生じるのは遺言者の死亡時からであり(985条)、方式に従っていなければ無効です。
遺言の方式
- 普通方式:自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
- 特別方式:死亡危急者、伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者
各方式の特徴
- 自筆証書遺言:本人が全文を自書(日付・氏名・押印必須)。目録部分は自書不要だが署名押印必要(968条)。夫婦での共同遺言は禁止(975条)。
- 公正証書遺言:公証人と証人立会いで作成(969条)。最も確実で紛争防止に有効。
- 秘密証書遺言:存在は明らかにするが内容は秘密にできる(970条)。方式不備でも自筆証書遺言の要件を満たせば有効(971条)。
特別方式の遺言
死亡危急者や船舶遭難者など、緊急時に認められる方式(976条〜979条)。ただし普通方式が可能になってから6か月生存した場合は無効(983条)。
2. 遺贈とその効力
遺贈とは、遺言によって財産を与えること(985条)。
- 特定遺贈:特定の財産のみ(例:甲土地をAに遺贈)。
- 包括遺贈:全財産または一定割合(例:財産の2分の1をAに遺贈)。積極財産だけでなく負債も承継(990条)。
遺贈は受遺者の承諾がなくても効力が生じますが、受遺者は放棄可能です。
- 特定遺贈の放棄:いつでも可能(986条)。
- 包括遺贈の放棄:効力を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述(915条、990条)。
3. 遺留分
遺留分とは、被相続人が贈与や遺贈によっても奪えない、一定割合の相続分です。近親者の生活保障のために設けられています。
遺留分権利者(1042条)
- 配偶者
- 子
- 直系尊属
※兄弟姉妹には遺留分なし。
遺留分の割合(1042条1項)
- 直系尊属のみ → 1/3
- 上記以外 → 1/2
遺留分侵害額請求(1046条)
侵害された場合、金銭による支払いを請求できる。
- 請求期限:知った時から1年以内、または相続開始から10年以内(1048条)。
4. 配偶者居住権
2020年の改正で新設された制度で、試験でも頻出です。
意味(1028条)
被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物について、終身または一定期間、無償で使用・収益できる権利。
取得方法
- 遺産分割で配偶者居住権を設定する場合
- 遺贈により配偶者居住権を取得する場合
登記(1031条、不登法60条)
配偶者居住権は登記が必要。所有者と配偶者が共同申請。
権利の制限
- 譲渡不可(1032条2項)。
- 改築・増築や第三者利用には所有者の承諾が必要(1032条3項)。
- 通常の修繕費は配偶者が負担(1034条)。
配偶者短期居住権(1037条)
遺産分割や遺贈によらず、相続開始時から6か月は当然に認められる権利。生活の安定を図る制度。
【例題1】遺言方式
Q:夫婦が同じ遺言書に署名押印して「共同遺言」を作成しました。この遺言は有効でしょうか?
解答:無効。
→民法975条により、共同遺言は禁止されています。
【例題2】遺留分
Q:相続人が配偶者Bと子C・Dの3人。被相続人が財産3,000万円を第三者Eに全て遺贈した場合、各相続人の遺留分はいくらになるでしょうか。
解答:
- 総体的遺留分:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 法定相続分:B 1/2、C 1/4、D 1/4
- 個別遺留分:
B:1,500万円 × 1/2 = 750万円
C:1,500万円 × 1/4 = 375万円
D:1,500万円 × 1/4 = 375万円
【例題3】配偶者居住権
Q:相続開始時、配偶者が被相続人所有の建物に住んでいました。この配偶者はどのようにして居住権を取得できますか?
解答:
- 遺産分割による設定
- 遺贈による取得
→いずれかにより、配偶者居住権を取得できます(1028条)。
まとめ
- 遺言方式は「自筆・公正・秘密」の3種類+特別方式を整理。
- 遺留分は兄弟姉妹に認められない点に注意。計算問題は出題頻度高。
- 配偶者居住権は改正ポイントで試験頻出。取得方法と登記義務、短期居住権との違いを押さえる。
👉これらは条文知識とともに具体例を使った理解が重要です。本記事の例題を繰り返し解き、確実に得点源にしましょう。
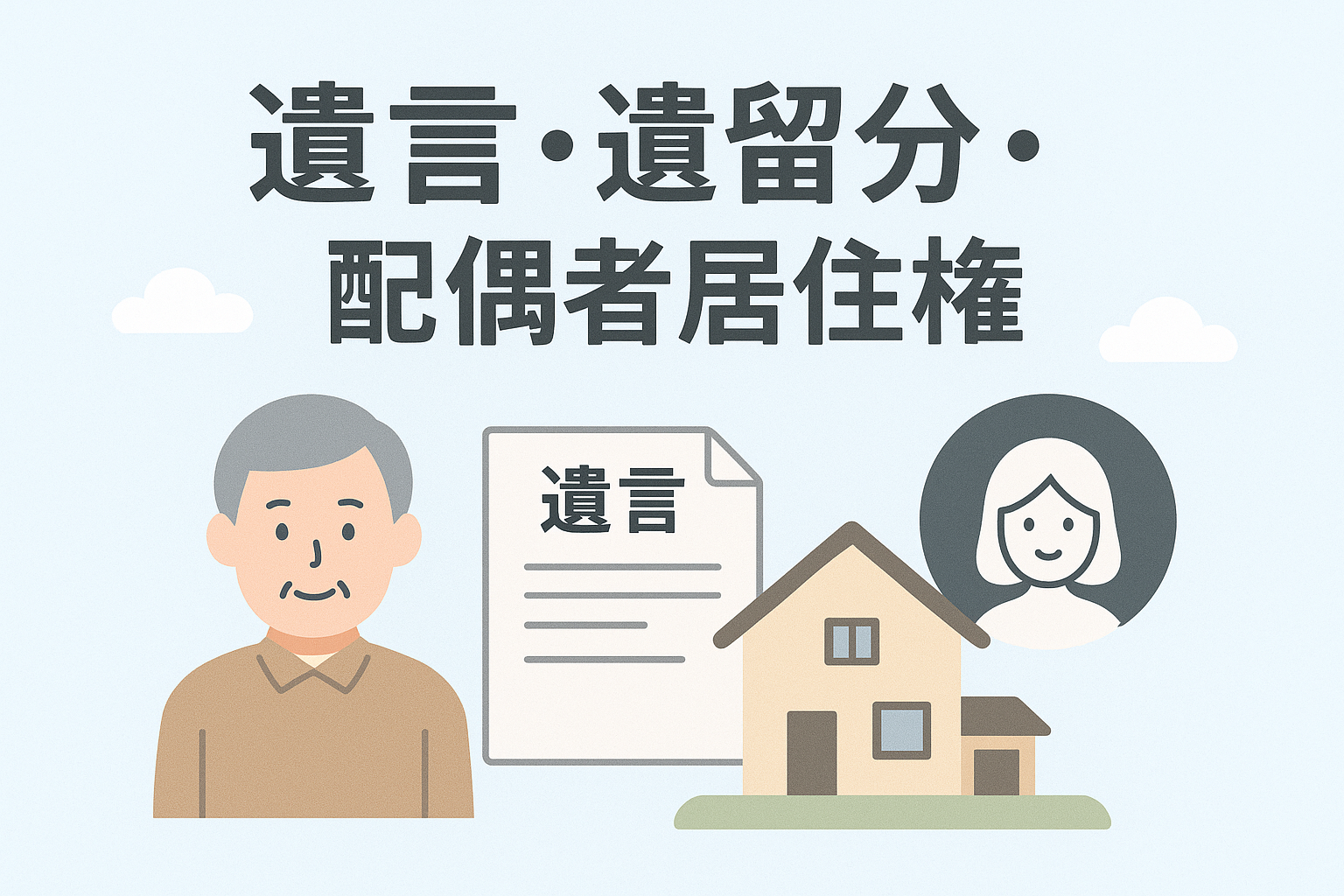

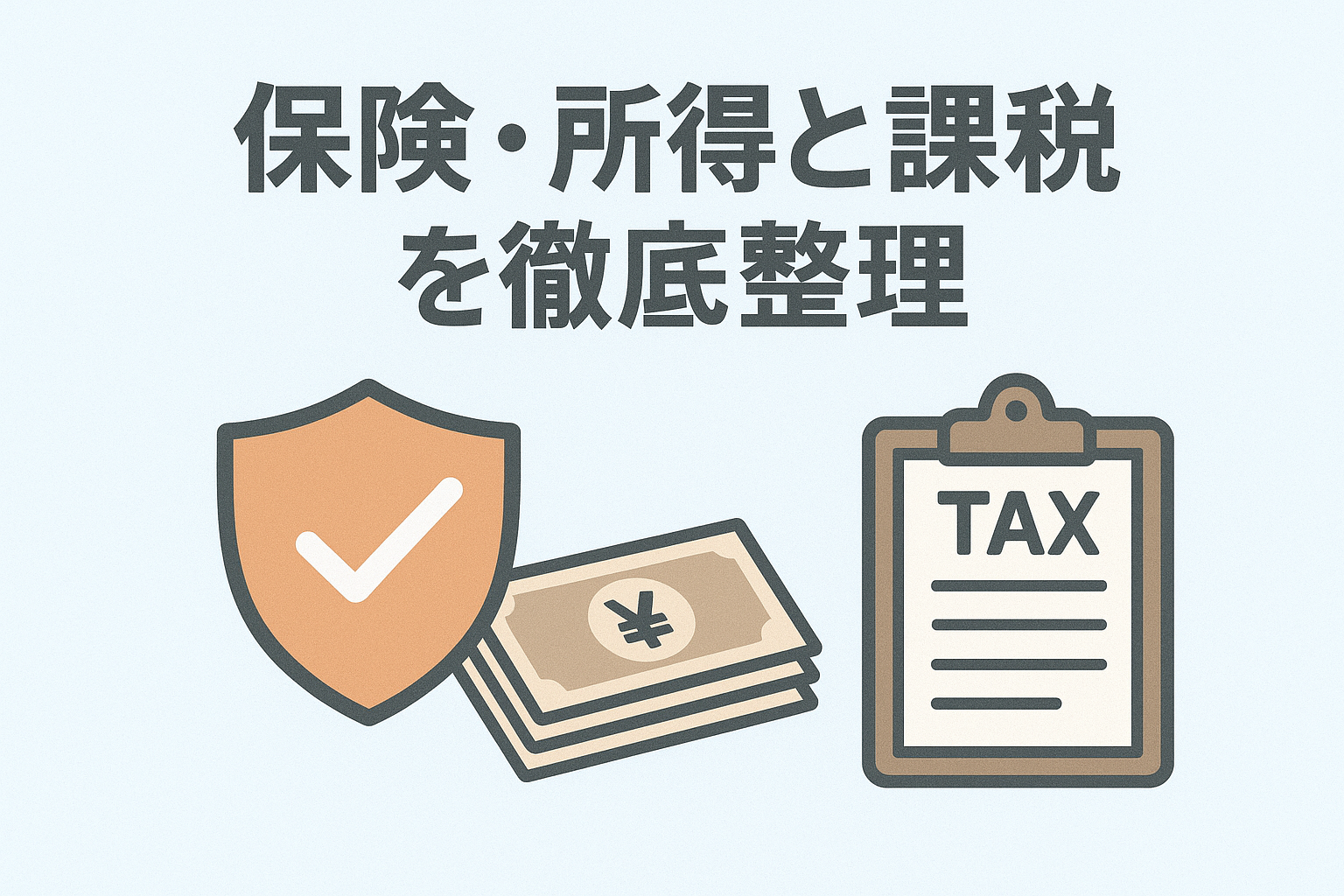
コメント