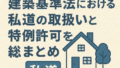建築基準法は、都市の健全な発展と安全な建築物の確保を目的とした重要な法律です。前回に引き続き、「集団規定」について解説します。「集団規定」は、建築物が集まって立ち並ぶ区域でのルールを定めており、宅建試験でも頻出のテーマです。
今回は「「道路と敷地」に関するルールを中心に、しっかりと解説していきます。特に、「接道義務」や「敷地の規制」などは、覚えておくべきポイントが多く、出題されやすい分野です。この記事では、例題も交えて詳しく説明していきます。
⸻
道路と敷地の基本ルール
建築物を建てるには、原則としてその敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。これは「接道義務」と呼ばれるもので、火災や災害時の避難や緊急車両の通行を確保するために定められた重要なルールです。
建築基準法第43条では、「建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。
⸻
建築基準法上の「道路」とは?
建築基準法で「道路」とされるのは、以下のようなものです。
1. 法定道路(42条1項各号)
- 1号道路(道路法による道路):国道や県道、市道など、一般に開放されている道路。
- 2号道路(都市計画法等による開発道路)
- 3号道路(既存の道路で、建築基準法施行時に存在していたもの)
- 4号道路(特定行政庁が指定した道路)
- 5号道路(位置指定道路):民間が造成した道路で、建築基準法上の道路として指定されたもの。
2. みなし道路(42条2項)
幅員4m未満であっても、建築基準法施行時から建築物が立ち並んでいた場合、特定条件を満たせば「道路」としてみなされます。
⸻
セットバックの考え方
みなし道路に面して建築を行う場合、道路の中心線から2m後退(セットバック)したラインまでを道路とみなします。このセットバック部分は建築に使用できず、道路と一体として扱われることになります。
たとえば、道路幅が3mしかない場合、建築物の敷地は道路の中心から2m以上の距離を取る必要があり、結果として建築可能な敷地面積が減ることになります。
⸻
接道義務の例外
原則として接道義務がありますが、以下のようなケースでは例外が認められる場合があります。
特定行政庁の許可による例外(43条但し書き)
- 周囲の状況から見て支障がないと認められる場合
- 特定の構造を備えた通路により接道義務を満たしている場合
このような例外が認められるのは、建築物の利用や安全に問題がないと判断される場合に限られます。
⸻
敷地に関する制限
敷地についても、いくつか重要なルールがあります。
敷地の一体利用
複数の敷地にまたがって建築物を建てる場合、敷地を一体のものとして利用するための許可が必要です。この許可は特定行政庁が与えるもので、利用形態に応じて一定の条件が課されます。
私道上の建築制限
位置指定道路のような私道に接する敷地に建築する場合、その私道の継続的利用が確保されていることが前提となります。たとえば、通行地役権が設定されていたり、使用契約があるなどの法的根拠が必要です。
⸻
よく出るポイント整理
- 道路に2m以上接していなければ原則建築不可(接道義務)
- 幅員4m未満の道路ではセットバックが必要
- 道路の種類には法定道路とみなし道路がある
- 私道の継続的利用に関する確認も重要
- 敷地をまたいで建築するには一体利用許可が必要
⸻
例題で確認!
問題:
次のうち、建築基準法上、建築物の敷地として適切でないものはどれか。
ア.幅員4mの私道に2.5m接する敷地
イ.幅員3mの道路に2m接する敷地(中心線から1m後退済)
ウ.位置指定道路に2m接する敷地で、通行地役権が設定されている
エ.幅員5mの市道に1.5m接する敷地
正解:エ
→ 市道(1号道路)でも、接道義務である2mに満たないため建築できません。
⸻
まとめ
建築基準法における「道路と敷地」の制限は、安全な都市形成に不可欠なルールです。宅建試験でも出題頻度が高く、接道義務や道路の種類、セットバック、私道の制限といったポイントは確実に押さえておきたいところです。
「なんとなく覚える」のではなく、具体的な例や数字をイメージしながら学習を進めましょう。今回の内容は、宅建試験における得点源となる分野ですので、繰り返し復習し、知識を確かなものにしてください。
この記事の内容をもとに、問題演習や過去問を通じて理解を深めていきましょう。