賃貸住宅管理業法では、登録を受けた管理業者が公正かつ適切に業務を行うために、さまざまな「業務上の規制」が設けられています。
また、違反した場合の「監督処分」についても明確に定められています。
本記事では、試験で頻出の条文(第10条~第26条)を中心に、業務上の原則から帳簿の保存、分別管理、秘密保持義務、さらには業務改善命令や登録取消処分までを体系的に整理します。
最後に例題も付けていますので、知識の定着に役立ててください。
信義誠実の原則(10条)
賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし誠実にその業務を行わなければなりません。
これは、いわゆる「信義誠実の原則」と呼ばれ、すべての業務処理の基本です。
管理業者は、専門家としての知識と経験を生かし、オーナーや入居者の立場を尊重しながら、誠実に業務を遂行する責務を負います。
この原則を怠ると、苦情対応や契約トラブルなどにつながるため、常に「公正・中立」の姿勢が求められます。
名義貸しの禁止(11条)
賃貸住宅管理業者は、自分の名義をもって他人に管理業を行わせること(名義貸し)を禁止されています。
これは、無資格業者が登録業者の名前を借りて違法に業務を行うのを防ぐための規定です。
名義貸しは登録取消処分の対象となる重大な違反ですので、試験でもよく出題されます。
事務所に備え置くもの(18条・19条・17条)
賃貸住宅管理業者は、営業所や事務所ごとに以下の3つを備え置く必要があります。
■ 備え置くもの
① 帳簿
② 標識
③ 業務管理者
(1)帳簿の備え付け・保存義務(18条)
業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに契約年月日・対象物件・報酬額などを記載し、5年間保存しなければなりません。
帳簿は電子データでも構いませんが、必要に応じて紙面で確認できるようにしておく必要があります。
記載事項(規則38条)
- 委託者の氏名・名称
- 契約年月日
- 契約対象の賃貸住宅(所在地・部屋番号・設備等)
- 受託した管理業務の内容
- 報酬の額(光熱費など一時立替分を含む)
- 特約や参考となる事項
📘 保存期間:各事業年度末から5年間保存が義務(規則38条3項)。
(2)標識の掲示義務(19条)
すべての営業所・事務所には、国土交通省令で定められた様式の標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
標識には以下の事項を記載します。
- 登録番号
- 登録年月日
- 登録の有効期間
- 商号・名称・氏名
- 主たる事務所の所在地・電話番号
分別管理の義務(16条)
賃貸住宅管理業者は、家賃・敷金・共益費などの預り金を自己の財産と区別して管理しなければなりません。
この「分別管理」は、オーナーの財産を保護するための非常に重要な制度です。
国交省令で定める方法(規則36条)
- 別口座管理:自己の固有財産の口座と分ける(契約ごとに分ける必要はない)
- 帳簿管理:どの契約に関する金銭かを帳簿やデータで即時判別できる状態にしておく
💡 家賃口座にいったん全額を入金し、その後管理報酬分を自社口座に移すことは認められていますが、速やかに処理する必要があります。
秘密保持義務(21条)
賃貸住宅管理業者やその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
この義務は、業務を辞めた後も継続します。
「従業者」には、再委託を受けた外部業者も含まれる点が重要です(解釈21条関係)。
裁判での証言など、正当な理由がある場合は例外です。
従業者証明書の携帯義務(17条)
賃貸住宅管理業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはなりません。
また、請求があった場合には必ず提示する義務があります。
内部事務のみを担当する者には携帯義務はありませんが、現場でオーナーや入居者と接する者は必須です。
証明書の有効期間は、従事期間に限って発行可能です。
委託者への定期報告(20条)
賃貸住宅管理業者は、1年を超えない期間ごとに、また契約期間満了後に管理状況を報告しなければなりません。
報告書は「管理業務報告書」と呼ばれ、書面または電磁的方法(メール・Web等)で交付できます。
記載事項(規則40条)
- 報告の対象期間
- 管理業務の実施状況
- 入居者からの苦情発生状況と対応状況
苦情の内容や対応履歴は記録し、報告に含める必要があります。
単なる問い合わせは対象外ですが、トラブルに発展したものは必ず報告対象です。
国土交通大臣による監督処分(22~26条)
賃貸住宅管理業者が法令違反や不誠実な業務を行った場合、国土交通大臣はさまざまな監督処分を行うことができます。
(1)業務改善命令(22条)
業務の適正な運営を確保するため、業務の方法変更や改善命令を出すことが可能です。
軽微な違反でも改善命令が出される場合があります。
(2)登録の取消し・業務停止(23条)
次のいずれかに該当した場合、登録の取消しまたは1年以内の業務停止が命じられます。
- 登録拒否事由(6条1項)のいずれかに該当した場合
- 不正の手段で登録を受けた場合
- 法令や命令に違反した場合
また、登録後1年以内に業務を開始しない、または1年以上業務を停止している場合も取消し対象です。
(3)登録の抹消(24条)
登録の更新をしなかった場合や廃業届出を行った場合、または取消処分が下された場合、国土交通大臣は登録を抹消します。
(4)公告(25条)
登録取消しなどの監督処分を行った場合、国土交通大臣はその旨を公告しなければなりません。
つまり、違反業者の情報は公にされます。
(5)報告徴収・立入検査(26条)
国土交通大臣は、必要があると認めるとき、
- 業務に関する報告を求める
- 職員を現地に派遣して立入検査・帳簿確認を行う
ことができます。
この場合、職員は身分証を携帯し提示する義務があります。
💬例題で理解を確認!
例題1(基本)
次のうち、賃貸住宅管理業法上「名義貸し」に該当するものはどれか。
(1)自社の従業員に自社名義で管理業を行わせる
(2)登録を受けていない他人に自社名義で管理業をさせる
(3)他社から委託を受けて一部業務を再委託する
(4)契約書作成を弁護士に依頼する
👉 正解:(2)
登録業者の名義を貸して無登録業者に業をさせる行為は、11条の「名義貸し」に該当します。
例題2(応用)
賃貸住宅管理業者が管理業務で受領した家賃と自社の資金を同一口座で管理している。
この場合の取扱いとして正しいものはどれか。
(1)特に問題はない
(2)家賃等を明確に区別できる帳簿管理をしていればよい
(3)必ず契約者ごとに別口座を開設しなければならない
(4)固有財産の一部を家賃口座に入金することは禁止されている
👉 正解:(2)
契約者ごとの口座は不要。帳簿で区別できればよい(規則36条)。
例題3(発展)
次のうち、国土交通大臣が業務改善命令を出すことができる場合として正しいものはどれか。
(1)業務を開始していない
(2)報告書を提出していない
(3)業務の適正な運営を確保するため必要があるとき
(4)業務を一時停止しているとき
👉 正解:(3)
業務改善命令は「業務の適正な運営確保のため必要があるとき」に発令されます(22条)。
まとめ:誠実な業務と適正な管理がすべての基礎!
- 信義誠実の原則はすべての行動の基本
- 名義貸し・分別管理違反・秘密漏えいは重い処分対象
- 帳簿は5年間保存、報告は1年ごとに実施
- 違反があれば国交大臣による監督処分(22~26条)
これらの項目は毎年必ず1~2問出題される超頻出分野です。
特に「分別管理」「帳簿の記載事項」「業務改善命令の要件」は間違いやすいので、条文番号とともに整理して覚えておきましょう。
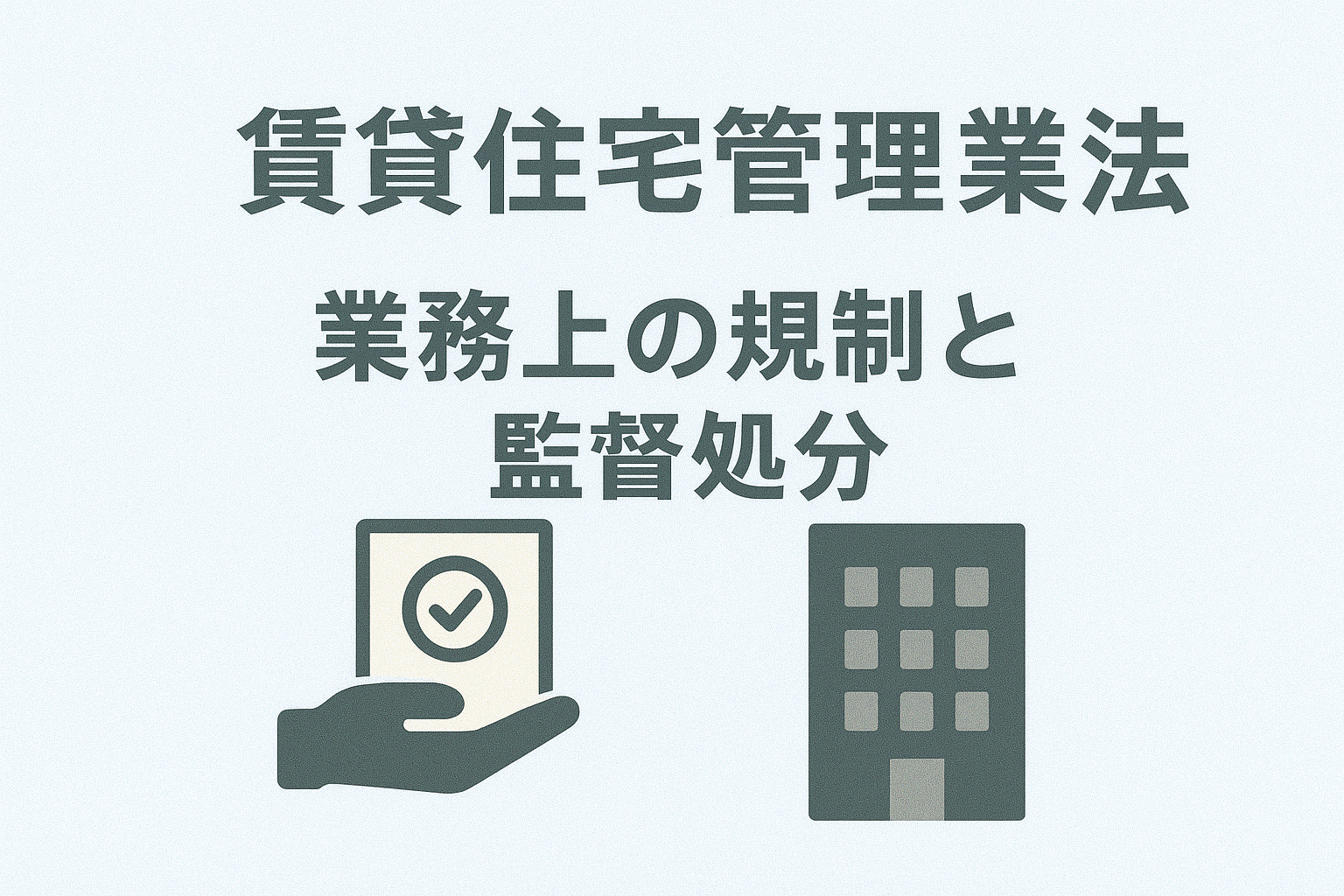
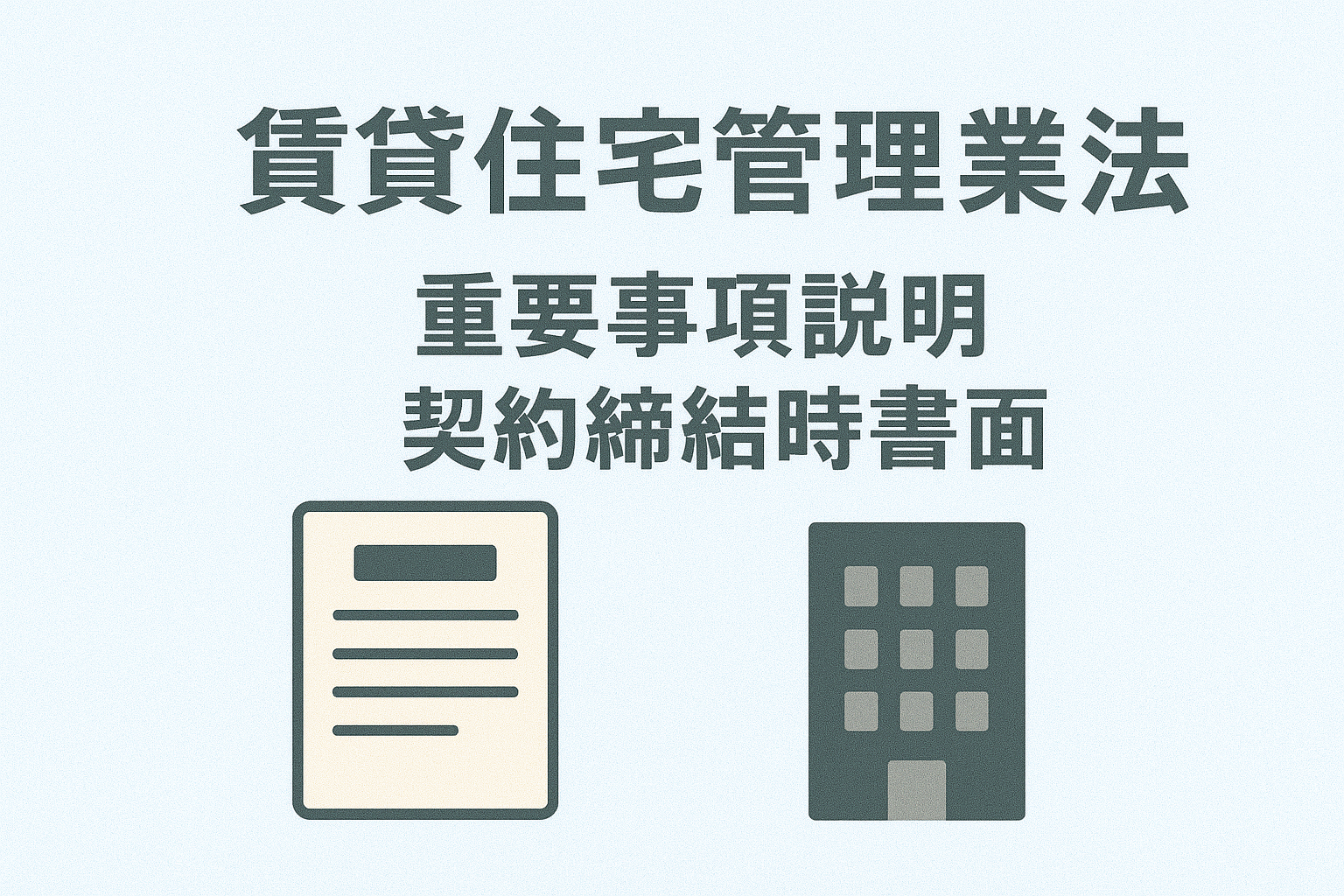

コメント