宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
本日も、首都圏の不動産市場の「今」を映し出す、非常に重要なデータについて解説します。不動産調査会社の東京カンテイが発表した7月の新築戸建て住宅の価格動向によると、東京23区の平均価格が8,137万円と、調査開始以来の最高値を更新しました。その一方で、千葉市やさいたま市といった郊外の主要都市では価格が軒並み下落しており、市場の「二極化」がますます鮮明になっています。この背景にある要因を理解することは、プロとして市場を読み解く上で不可欠です。
なぜ23区だけが過去最高値を更新したのか?3つの要因
まず、なぜ東京23区の価格だけがこれほど力強く上昇しているのでしょうか。その背景には、主に3つの要因が挙げられます。
- 高騰し続ける建設コスト建築資材や人件費、そして何より都心の用地取得費が高騰を続けています。家を建てるための根本的なコストが上がっているため、販売価格に転嫁せざるを得ない状況です。
- 法改正によるコスト増宅建受験者の皆さんには特に関わりの深いポイントです。2025年4月に施行された改正建築基準法により、省エネルギー基準への適合や構造の安全性に関する建築確認の審査が厳格化されました。これにより、建築期間が長期化したり、設計・申請に関わる人的な負担が増えたりと、さらなるコスト増につながっています。
- 希少価値を高める供給減需要に対して、供給が全く追い付いていません。7月の東京23区における新規供給戸数は、前年同月比で34%も減少しました。10年前と比較すると、供給戸数は半分以下です。この「モノが少ない」状況が、物件の希少価値を高め、価格を押し上げているのです。
郊外主要都市では下落が鮮明に
23区が過去最高値を記録する一方で、首都圏の他の主要都市では対照的な動きが見られます。千葉市では前月比13.4%安、さいたま市では9.2%安、川崎市や相模原市でも下落するなど、明らかに調整局面に入っています。
これは、物件価格が一般的な所得層の購入できる範囲(アフォーダビリティ)の限界に達し、高値警戒感から買い手がつかなくなっていることを示唆しています。
「青天井ではない」専門家が見る価格の限界
では、23区の価格はどこまでも上がり続けるのでしょうか。専門家は「青天井とはみていない」と指摘しています。その理由は、戸建て住宅の購入層が、投資家よりも実際に居住する「実需層」中心であるためです。実需層の購買力は、当然ながら年収やローン返済能力に上限があります。そのため、マンション市場ほど投機的な価格上昇はしにくく、どこかで価格の限界点に達する、という見方です。
法改正が価格に与える影響を学ぶ
今回のニュースは、皆さんが試験で学ぶ「建築基準法」のような法律の改正が、いかに現実の不動産価格に大きな影響を与えるかを示す、格好の事例です。「省エネ基準の適合義務化」といった条文が、建築コストを押し上げ、最終的に消費者が支払う住宅価格にまで直接的に繋がっています。法律知識が、実社会の経済を動かすダイナミズムを理解することは非常に重要です。
宅建士に求められる「二極化」市場の読解力
この一連のデータから、私たちが学ぶべき最も重要なこと。それは、もはや「首都圏」と一括りにして不動産市場を語ることはできない、ということです。東京23区のような「資産性が高く、供給が絞られたエリア」と、郊外の「実需層の所得と価格のバランスが問われるエリア」とでは、全く異なる論理で市場が動いています。
これからの宅建士には、この「二極化」した市場を正確に読み解き、顧客に対して「なぜこのエリアは高いのか」「なぜこのエリアは値下がりしているのか」を、背景にある要因まで含めて説明できる能力が不可欠です。平均値に惑わされず、エリアごとの特性を見抜く専門的な視点を養っていきましょう。
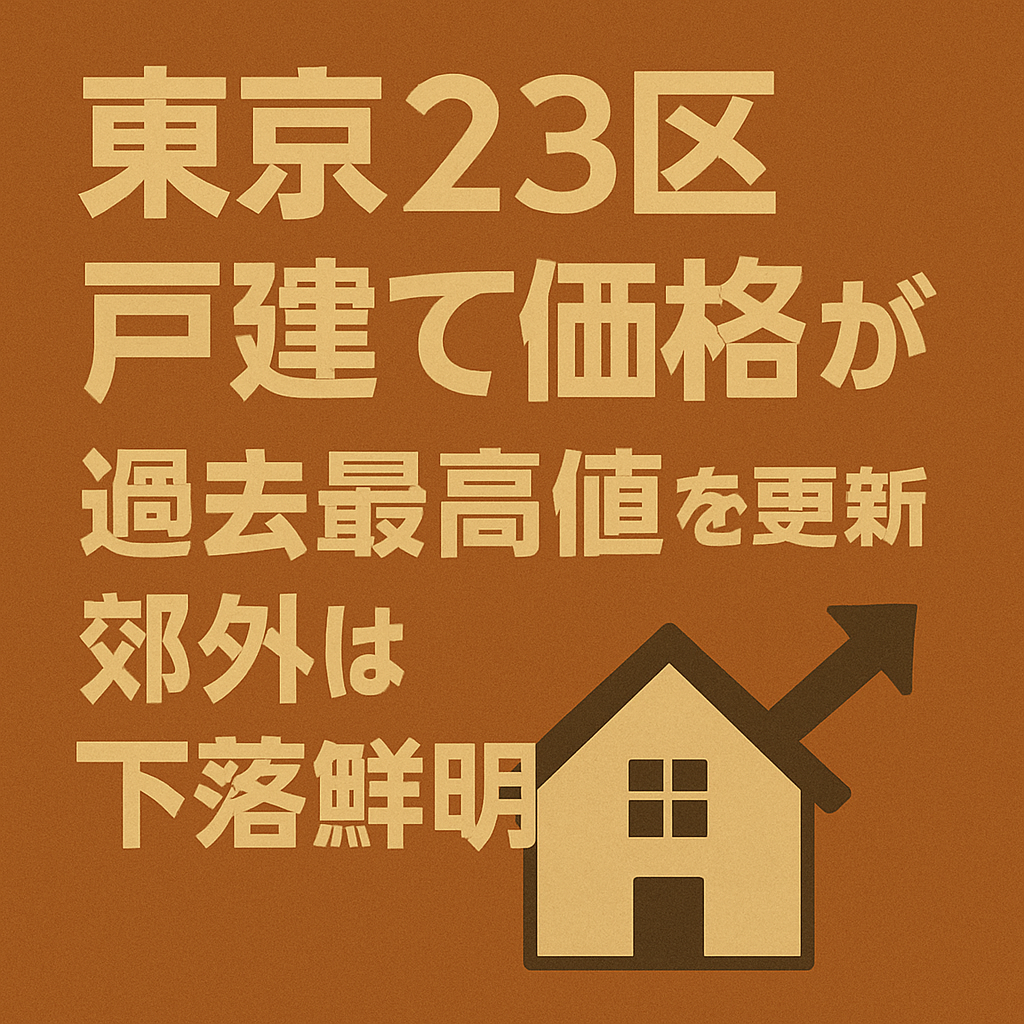
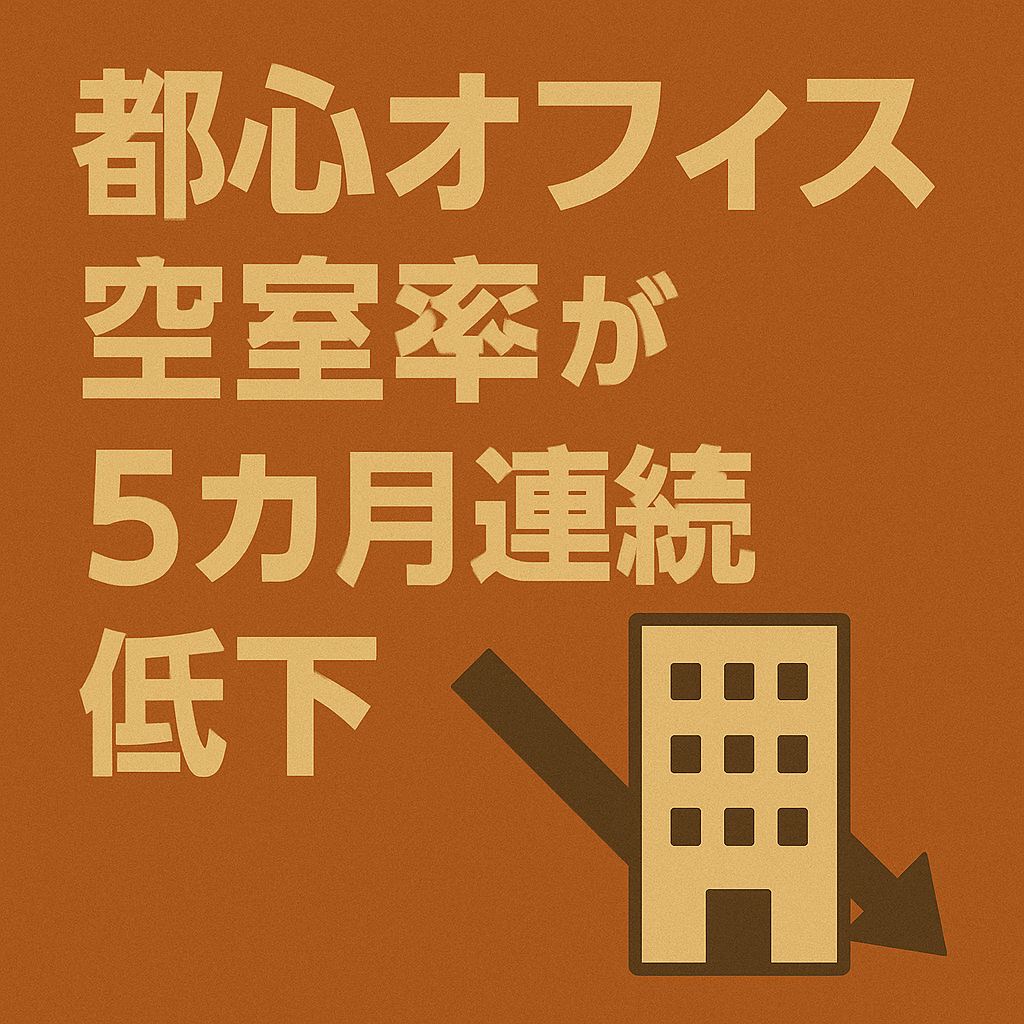
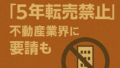
コメント