賃貸不動産経営管理士試験や宅建試験の学習では、「個人情報保護法」と「消費者契約法」が必ず登場します。これらは近年、社会的関心も高い分野であり、試験でも細かい条文や定義が問われやすいため、しっかり整理しておくことが重要です。今回は、両法の要点を体系的にまとめ、例題を交えて理解を深めていきましょう。
個人情報保護法の基本
個人情報の定義
個人情報とは、生存する個人に関する情報であり、氏名や生年月日、顔写真、免許証番号などによって特定の個人を識別できるものをいいます(2条1項)。
👉 死者や法人自体に関する情報は対象外ですが、役員や従業員に関する情報は個人情報に該当します。
キーワード
- 個人識別符号:指紋、顔認証データ、マイナンバー、免許証番号など。
- 要配慮個人情報:人種、信条、病歴、犯罪歴など。原則として本人の同意なく取得不可。
個人情報・個人データ・保有個人データの関係
この3つは入れ子構造で整理すると理解しやすいです。
- 個人情報:最も広い概念
- 個人データ:データベース化された個人情報
- 保有個人データ:事業者が開示・訂正・利用停止に応じられる個人データ
👉 試験では「個人情報>個人データ>保有個人データ」という関係を問われることが多いです。
個人情報取扱事業者の義務
個人情報を扱う事業者には、以下の義務が課されます。
- 利用目的の特定(17条)
- 利用目的の範囲内での利用(18条)
- 不適正な利用の禁止(19条)
- 適正な取得(20条)
- 取得時の利用目的の通知・公表(21条)
さらに個人データや保有個人データについては、次のような追加義務があります。
- 個人データの正確性確保(22条)
- 安全管理措置(23条)
- 従業者・委託先の監督(24・25条)
- 漏えい発生時の報告(26条)
- 本人の開示請求や訂正請求への対応(33〜35条)
監督・罰則
- 個人情報保護委員会が監督権限を持つ
- 違反した場合は「勧告・命令」→ 不履行なら刑事罰(1年以下の懲役や罰金)
- 個人情報データベースを不正に提供・盗用すると「個人情報データベース等不正提供罪」として処罰対象
👉 法人に対しても両罰規定が適用されます。
消費者契約法の基本
目的
消費者と事業者の「情報・交渉力の格差」を是正し、消費者を保護すること(1条)。
消費者と事業者の定義
- 消費者:個人(ただし事業として契約する場合は除く)
- 事業者:法人・団体・事業を目的とする個人
👉 個人でも事業用に契約する場合は「事業者」として扱われる点に注意。
取消権(4条)
消費者は、以下のような場合に契約を取り消すことができます。
- 重要事項の虚偽告知による誤認
- 将来の変動について断定的判断を提供され誤認
- 不利益事実を故意に告げなかったことによる誤認
- 居座りや退去妨害などによる困惑
👉 媒介業者や代理人の行為でも取消可能です(5条)。
無効となる条項
- 過大な違約金や損害賠償額の予定(9条)
→ 平均的損害を超える部分は無効。 - 消費者の不作為を承諾とみなす条項や、信義則違反で一方的に消費者に不利益を課す条項(10条)
→ 当然に無効。
試験によく出る比較ポイント
- 個人情報は「生存する個人」に限定。
- 要配慮個人情報は「原則本人同意が必要」「オプトアウト不可」。
- 個人情報>個人データ>保有個人データの関係。
- 消費者契約法では「取消」と「無効」の区別を押さえる。
- 不作為を承諾とみなす条項は無効(試験頻出!)。
例題演習
例題1(個人情報保護法)
次のうち、個人情報に該当しないものはどれか。
- 法人の役員の住所録
- 退職した従業員の在職中の給与情報
- マイナンバー
- 亡くなった人物の趣味に関する記録
解答:4(死者のみの情報は対象外。ただし遺族に関わる場合は個人情報となり得る)。
例題2(個人データ)
顧客名簿を紙でファイルに整理し、氏名で検索できるようにした場合、これは「個人データ」に当たる。〇か×か。
解答:〇。検索可能な体系を持つため個人情報データベースに該当。
例題3(消費者契約法・取消権)
事業者が「この物件は必ず値上がりします!」と断定的に告げ、消費者が信じて契約した。この場合、消費者は契約を取り消すことができる。〇か×か。
解答:〇。将来の不確実な事項について断定的判断を提供したため取消可能。
例題4(消費者契約法・無効条項)
賃貸契約書に「契約を解除する場合、必ず賃料6か月分を違約金として支払う」とある。この条項は有効か。
解答:×。平均的損害を超える部分は無効(9条)。
まとめ
個人情報保護法と消費者契約法は、定義や取消事由、無効条項など条文ごとに出題されやすいポイントが決まっています。
特に 「どこまでが個人情報か」、「消費者契約で取り消せる行為・無効となる条項」 は試験で繰り返し狙われるため、例題演習を通して整理しておくことが得点アップにつながります。

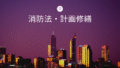

コメント