賃貸不動産経営管理士試験では、税金や会計の知識も出題範囲に含まれています。特に、固定資産税・都市計画税、相続税・贈与税、会計・簿記の基礎は実務と直結しやすく、理解が不十分だと得点を落としやすい分野です。
この記事では、重要ポイントを整理し、例題を交えながら試験対策の観点から徹底解説します。
リンク
固定資産税と都市計画税
固定資産税の基本
- 課税主体:市町村(資産が所在する場所)
- 課税客体:土地・家屋・償却資産
- 賦課期日:毎年1月1日現在の所有者
- 標準税率:1.4%(制限なし)
- 納付方法:普通徴収(年4回の分納可)
新築住宅の特例
- 一般住宅:3年間、120㎡以下部分の税額が1/2
- 3階建以上の耐火・準耐火構造:5年間に延長
- 長期優良住宅:さらに+2年(最大7年間)
住宅用地の特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準を1/6
- 一般住宅用地(200㎡超):課税標準を1/3
都市計画税の基本
- 課税主体:市町村(市街化区域内にある土地・家屋が対象)
- 制限税率:最大0.3%(固定資産税と異なり上限あり)
- 賦課期日:毎年1月1日現在の所有者
住宅用地の特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準を1/3
- 一般住宅用地(200㎡超):課税標準を2/3
👉 固定資産税の特例(1/6・1/3)の「2倍」が都市計画税(1/3・2/3)になる点が試験の狙われやすいポイントです。
相続税・贈与税
相続税の基本
- 国税であることに注意(固定資産税・都市計画税は地方税)
- 超過累進課税(10%~55%)
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の計算の流れ
- 課税価格の合計額を算出
- 基礎控除を差し引き、課税遺産総額を求める
- 相続税の総額を計算(速算表を利用)
- 各人に配分し、税額控除を差し引いて納付額を決定
評価方法のポイント
- 土地:路線価方式、公示価格の8割水準
- 建物:固定資産税評価額
- 貸家建付地:自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
- 小規模宅地等の特例:居住用330㎡まで80%減額など
贈与税の基本
- 暦年課税:110万円まで非課税、超過分に10~55%課税
- 相続時精算課税:特別控除2,500万円+基礎控除110万円、税率20%
住宅取得等資金の非課税特例
- 良質な住宅(省エネ・耐震):1,000万円まで非課税
- 一般住宅:500万円まで非課税
👉 相続時精算課税制度は「相続税の前払い」であり、一度選択すると暦年課税に戻せない点が試験の落とし穴です。
会計・簿記の基礎
企業会計原則
- 一般原則(真実性・継続性・保守主義など7つ)
- 損益計算書原則:発生主義・実現主義・費用収益対応
- 貸借対照表原則:資産=負債+純資産
簿記の種類
- 単式簿記:現金の出入りのみ
- 複式簿記:借方・貸方に分けて二面的に記録(企業会計で用いられる)
発生主義と現金主義
- 発生主義:事実の発生時点で計上
- 現金主義:現金の入出金時点で計上
👉 試験では「どの会計年度に属するか」を問う出題が多いです。
例題で理解を深める
例題1:固定資産税
Q:固定資産税の賦課期日はいつでしょうか。
- 1月1日
- 3月31日
- 4月1日
- 12月31日
解答:1. 1月1日
例題2:都市計画税の特例
Q:住宅用地200㎡以下部分の都市計画税の課税標準はどう軽減されますか。
- 1/6
- 1/3
- 2/3
- 全額免除
解答:2. 1/3
例題3:相続税の基礎控除
Q:法定相続人が4人の場合、基礎控除額はいくらでしょうか。
- 4,200万円
- 5,400万円
- 6,000万円
- 6,400万円
解答:2. 5,400万円
(3,000万円+600万円×4=5,400万円)
例題4:会計処理
Q:発生主義に基づく場合、令和6年12月に翌年1月分の家賃が前払いされたとき、収益計上の年度はどちらか。
解答:翌年度(令和7年)。
→ 前受収益として処理し、収益は翌期に計上。
まとめ
- 固定資産税と都市計画税は数値の比較(1/6と1/3、1/3と2/3)が狙われやすい。
- 相続税は計算プロセスと小規模宅地等の特例を押さえる。
- 贈与税は暦年課税と相続時精算課税の違いに注意。
- 会計は「発生主義・複式簿記・企業会計原則」が頻出。
👉 税と会計は数字が多く混乱しやすいですが、表や計算式を押さえながら整理することで得点源にできます。
リンク

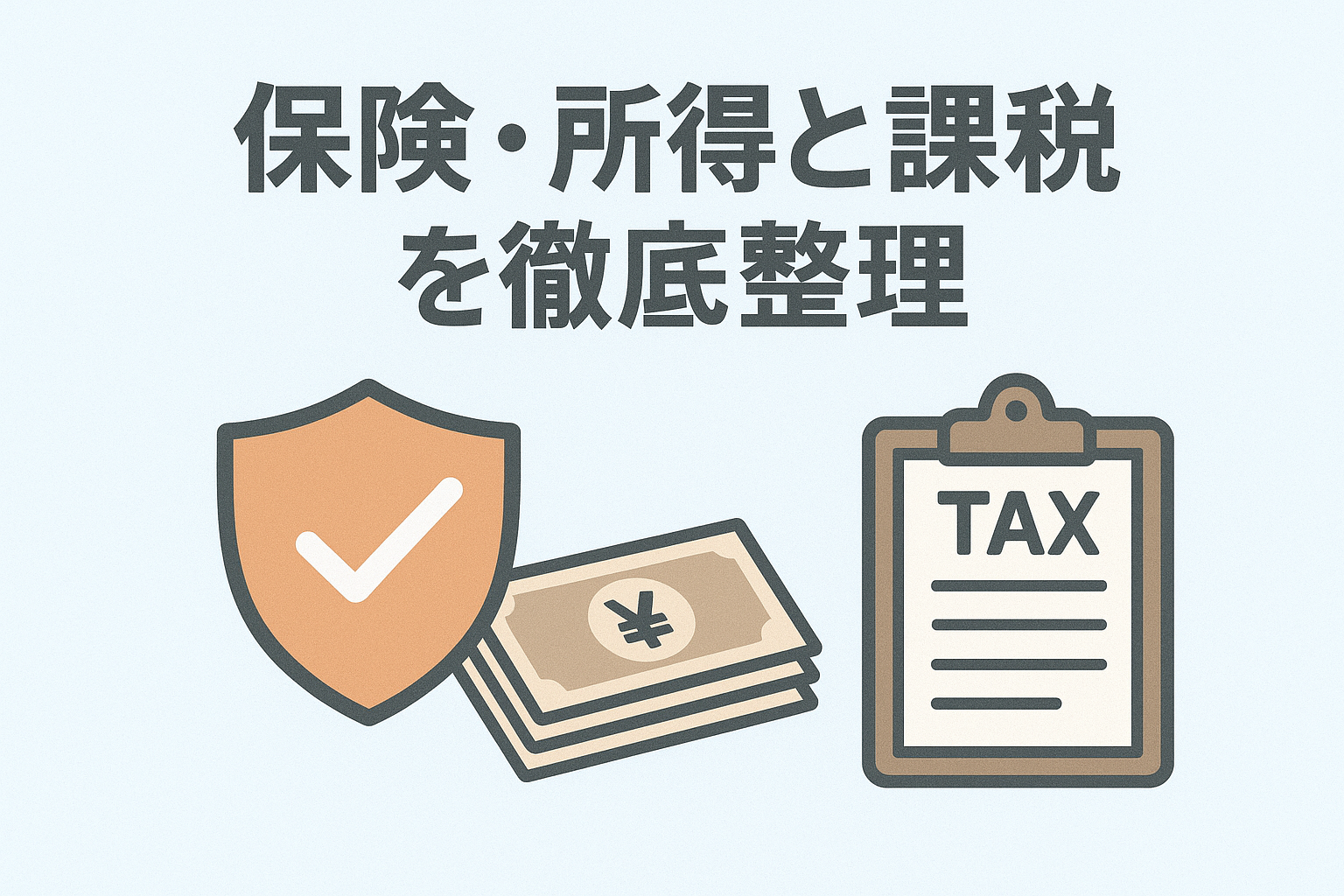

コメント