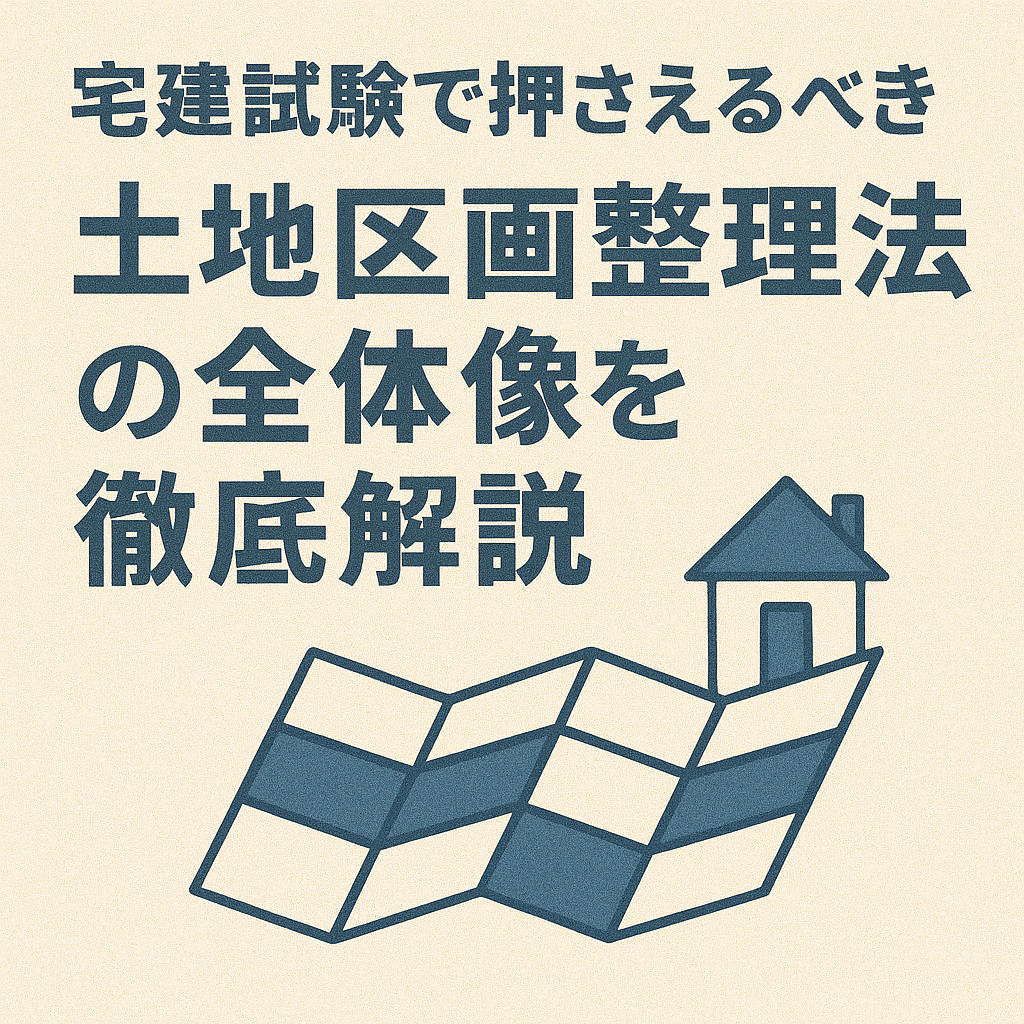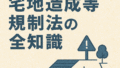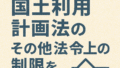宅建試験では「法令上の制限」の中でも、「土地区画整理法」が頻出項目の一つです。特に、土地の整理手法として登場する「減歩」や「換地」、「仮換地」などは、制度の理解が曖昧だと混乱しやすく、正答率が下がる傾向にあります。
この記事では、宅建受験生の皆さんが確実に得点できるよう、土地区画整理法の重要な仕組みや手続き、登記の扱いまでを丁寧に解説します。
⸻
土地区画整理法の目的と基本概念
土地区画整理法は、市街地を健全に整備するために制定された法律です。目的は、区画整理によって住みやすい街をつくり、公共の福祉の増進を図ることです。
この法律に基づく「土地区画整理事業」は、雑然とした街並みを再編成し、道路や公園の整備、土地の区画の整理を進めていくものです。
事業は都市計画区域内でのみ実施され、都市計画に基づく「施行区域」と、実際に施工が行われる「施行地区」に区分されます。
⸻
減歩と換地のしくみ
土地区画整理事業の核となるのが「減歩(げんぶ)」と「換地(かんち)」という2つの手法です。
- 減歩とは、各土地所有者が保有する土地の一部を無償提供することです。これは主に2つに分かれます。
- 公共減歩:道路・公園等の公共施設整備のための減歩
- 保留地減歩:事業費確保のための土地売却を目的とした減歩
- 換地とは、整理前の土地(従前地)を、整理後に別の土地(換地)として割り当てることです。
原則として、強制収用などは行わず、これらの手法を使って土地の形状を変更します。
⸻
公的施行と民間施行の違い
土地区画整理事業には2つのタイプの施行者があります。
公的施行
都道府県・市町村・住宅供給公社などが行います。これは都市計画事業として扱われ、市街化区域または非線引き区域内でしか実施できません。
民間施行
個人・組合・会社が施行者となるパターンで、都市計画事業でないため、市街化調整区域でも可能です。組合施行の場合、所有者や借地権者が7人以上で組合を設立します。
施行者に応じて、許可・届出の対象や手続きも異なるため、試験では引っかけに注意が必要です。
⸻
仮換地と換地処分の違いを理解しよう
施行中の土地は、そのままでは工事が進められないため、「仮換地」が指定されます。これは、従前地の所有者が一時的に移動して使用できる代替地です。
- 仮換地指定の効力発生日から、使⽤収益権は仮換地に移り、従前地には処分権のみが残ります。
- 仮換地には抵当権を設定できません(設定できるのは従前地のみ)
工事が完了すると、「換地処分」が行われます。これにより、正式に換地が成立し、権利関係も再構成されます。
- 換地処分の公告日が終了した時点で従前地の権利は消滅
- 公告の翌日から、換地の所有権が正式に発生
⸻
清算金・保留地とは?
換地によって不均衡が生じた場合は、「清算金」で調整します。従前地と換地の価格差を金銭で精算する仕組みです。
また、事業費を捻出するために換地を定めずに保留しておく土地を「保留地」と言います。
- 民間施行:自由に保留地を設定可能
- 公的施行:事業費確保目的のみ。しかも「施行後の土地価額」が「施行前の土地価額」を上回る範囲内でのみ設定可
⸻
建築行為の制限に注意
組合設立認可の公告日から、換地処分の公告日までの間は、施行地区内での次の行為には都道府県知事等の許可が必要です。
1. 土地の形質変更
2. 建築物の新築・増改築
3. 移動が困難な5t超の物件の設置
無許可で行うと、違法行為とされるため注意が必要です。
⸻
登記と管理の扱いも押さえる
換地処分後、施行者は速やかに登記所へ通知し、土地建物の登記を行います。換地処分が完了するまでは、原則として他の登記はできません。
また、公共施設が設置された場合、その管理は市町村や都道府県に移行します。
⸻
宅建試験によく出る例題で確認!
問題:
仮換地の指定があった場合に関する記述として、正しいものはどれか?
ア.仮換地に対しては抵当権を設定できる
イ.従前地の使用収益権は施行者に帰属する
ウ.仮換地の所有者は処分権を失う
エ.従前地の所有者は仮換地を使用収益できる
正解:エ
→ 仮換地指定により、従前地の使用収益権は仮換地に移転し、所有者は使用できます。抵当権の設定は従前地にしかできません。
⸻
まとめ
土地区画整理法は、内容が多く複雑に見えますが、構造を理解すればスムーズに得点できます。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 減歩と換地は事業の核
- 公的施行と民間施行の違い
- 仮換地指定と換地処分の効力の違い
- 使用収益権・処分権の分離と復元
- 建築制限のタイミングと範囲
- 清算金と保留地の扱い
- 登記と公共施設管理の移転
繰り返し例題に触れながら、確実に知識を定着させてください。