相続は民法の大きなテーマの一つであり、賃貸不動産経営管理士試験でも出題される分野です。相続は「財産を引き継ぐ」というイメージが強いですが、借金などの負債も承継される点、代襲相続や法定相続分、特別受益や寄与分など複雑なルールがある点に注意が必要です。今回は、試験対策に役立つ相続の基本から重要論点まで整理していきます。
相続とは何か
相続とは、被相続人の財産に属する一切の権利義務を相続人が承継することを意味します(民法896条本文)。
- 預金や不動産といった「積極財産」だけでなく、借金など「消極財産」も引き継ぐ。
- ただし「一身専属権」(扶養を受ける権利、身元保証債務など個人に強く結びつく権利義務)は承継されない(896条ただし書)。
- 相続は、被相続人の住所で開始する(883条)。
相続人の範囲と順位
相続人になれるのは以下のとおりです。
- 常に相続人となる配偶者
- 第1順位:子(嫡出子・非嫡出子を含む/胎児も相続権あり:886条)
- 第2順位:直系尊属(父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
→先順位の相続人がいる場合、後順位は相続できません(890条以下)。
代襲相続
被相続人の子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格・廃除となった場合、その子が代襲して相続人となります。
- 子の代襲相続(孫 → ひ孫まで再代襲可能:887条2項・3項)
- 兄弟姉妹の代襲相続(おい・めいまで/再代襲なし:889条2項)
補足:同時死亡の推定がある場合も代襲相続が発生します(民法32条の2)。
相続人の欠格・廃除
相続人でも、一定の場合には相続権を失います。
- 欠格事由(891条):被相続人を故意に殺害、遺言を偽造・隠匿するなど。
- 廃除(892条):虐待・侮辱・著しい非行がある推定相続人について、被相続人が家庭裁判所に請求して相続権を剥奪できる。
相続分と共同相続
複数の相続人がいる場合(共同相続)、**法定相続分(900条)**に従って分けます。
- 配偶者と子 → 配偶者1/2、子1/2(人数で等分)
- 配偶者と直系尊属 → 配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(半血の兄弟姉妹は1/2相続分)
特別受益と寄与分
特別受益(903条)
生前贈与や遺贈を受けている相続人がいる場合、その分を考慮して相続分が修正されます。
→婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産贈与は特別受益とみなされない(903条4項)。
寄与分(904条の2)
事業への労務提供や療養看護などで特別の寄与をした相続人は、その寄与分を加算して相続します。
遺産分割
遺産分割協議によって、相続人ごとに具体的な財産の帰属を決定します(906条)。
- 協議がまとまらない場合は家庭裁判所に請求可能(907条2項)。
- 遺産分割は相続開始時に遡って効力を生じるが、第三者の権利は害せない(909条)。
相続の承認と放棄
単純承認(920条)
財産・負債すべてを無制限に承継する。特別の方式は不要。
限定承認(922条)
財産の範囲内でのみ負債を承継する。相続人全員で家庭裁判所に申述する必要あり。
相続放棄(939条)
負債を含め一切を承継しない。相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述。
【例題1】相続人の順位
被相続人Aに配偶者B、子C、父母D・E、兄Fがいます。この場合の相続人は誰でしょうか。
- BとCとD
- BとC
- BとDとF
解答:2
→第1順位の子Cが存命なので、父母や兄は相続人になれません。
【例題2】代襲相続
被相続人Aの子Cが相続開始前に死亡していました。Cの子Dがいる場合、Dは相続人となれるか。
解答:はい。
→887条に基づき、Cの子Dが代襲相続人となります。
【例題3】特別受益
被相続人Aの子B・Cが相続人で、相続財産は1,000万円。Bが生前に200万円の贈与を受けていた場合、各相続分はいくらになるか。
解答
- みなし相続財産:1,200万円
- 各相続分:600万円
- Bの具体的相続分:600万円-200万円=400万円
- Cの具体的相続分:600万円
まとめ
- 相続はプラス財産もマイナス財産も承継する。
- 相続人の範囲と順位は必ず整理して暗記。
- 代襲相続は「子系は再代襲あり」「兄弟姉妹系は再代襲なし」。
- 特別受益・寄与分は具体例と計算パターンを押さえること。
- 相続放棄・限定承認の期限(3か月以内)は試験で頻出。
👉 相続は条文番号が問われやすい分野です。条文の根拠とセットで理解しておくと試験で差がつきます。


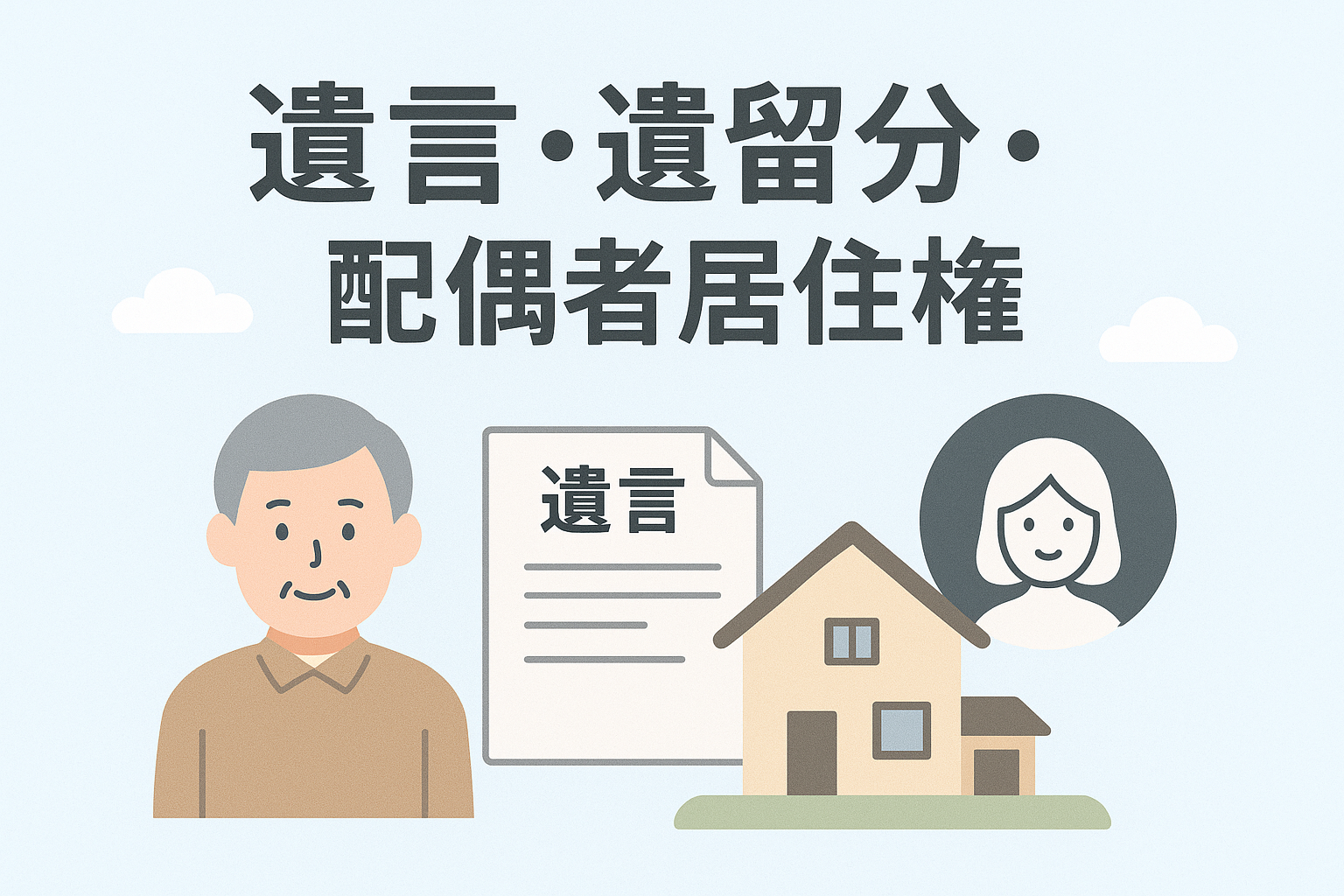
コメント