宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
不動産市場の過熱を象徴する、非常に重要なニュースが飛び込んできました。本日7月28日、東京・千代田区が、高騰を続けるマンション価格を抑制するため、不動産の業界団体に対して投機的な取引を防ぐための異例の「要請」を行ったのです。この動きは、一個人の取引を越え、自治体が市場に直接的なメッセージを送るという、特筆すべき事態です。未来の不動産のプロとして、この背景と意味を深く理解しておきましょう。
要請の核心「5年間の転売禁止」と「複数戸購入の禁止」
まず、今回の千代田区の要請の具体的な内容を見ていきましょう。ポイントは2つです。
- 市街地の再開発事業で供給されるマンションについて、原則として5年間は転売を禁止すること。
- 同じ建物において、同一名義で複数の住戸を購入することを禁止すること。
これらは、短期的な利益を狙った転売、いわゆる「マンション転がし」や、投資目的での買い占めを直接的に抑制することを狙ったものです。特に、公共性の高い「市街地再開発事業」の物件を対象としている点が特徴です。
なぜ今、千代田区が動いたのか その背景
この異例の要請の背景には、もはや看過できないレベルに達したマンション価格の高騰があります。今年上半期の東京23区の新築マンション平均価格は1億3000万円を超え、その要因の一つとして海外からの投機マネーの流入も指摘されています。「このままでは、本当に住むための家を求める人が買えなくなる」という強い危機感が、自治体を動かしたのです。樋口区長が「どこかで高騰する価格を落ち着かせなければならない」と語ったように、行政として強いメッセージを発する必要があったのです。
「要請」の限界と実効性への疑問の声
ここで宅建受験者として理解すべき重要な点は、今回の措置が法律や条例のような「強制力」を持たない「要請」であるという事実です。あくまで業界団体に対する協力のお願いであり、デベロッパーがこれに従うかは、各社の自主的な判断に委ねられます。
区民からも「行政が動くのはありがたいが、強制力がないと実効性に乏しいのでは」「5年経てば自由に売れるなら、投機抑制の効果は限定的ではないか」といった、その効果を疑問視する声も上がっています。
「買戻し特約」の活用は可能か?宅建業法上の考察
では、もしデベロッパーがこの要請に応じる場合、契約上はどのように実現するのでしょうか。ここで皆さんが試験で学ぶ知識が活きてきます。考えられる有効な手段が、民法上の「買戻しの特約」です。
これは、売買契約と同時に「売主が代金などを返還して、売買契約を解除できる」権利を留保する特約です。この特約を付け、「5年以内に第三者に転売しようとした場合、売主(デベロッパー)が元々の売買代金で買い戻せる」と定めることで、短期転売を事実上防ぐことができます。民法上、買戻しの期間は最長10年と定められているため、5年間という期間設定は法的に可能です。
宅建士として知るべき市場介入の動きと未来
今回の千代田区の動きは、一つの自治体の取り組みに留まらない可能性があります。これは、不動産の価格高騰が、もはや単なる経済の問題ではなく、社会全体で向き合うべき課題であるという認識が広がっていることの表れです。
今後、他の自治体が追随したり、国レベルでの法的な規制(例えば、選挙の争点にもなった「空室税」や「外国人所有規制」など)の議論が本格化したりするかもしれません。
これからの宅建士には、こうした行政や政治の動向を常に注視し、それが不動産取引にどのような影響を与えるかを正確に理解する能力が不可欠です。契約書に盛り込まれる特約の一つ一つが、こうした社会的な背景から生まれていることを知ること。それが、顧客からの信頼を得るための第一歩となるでしょう。
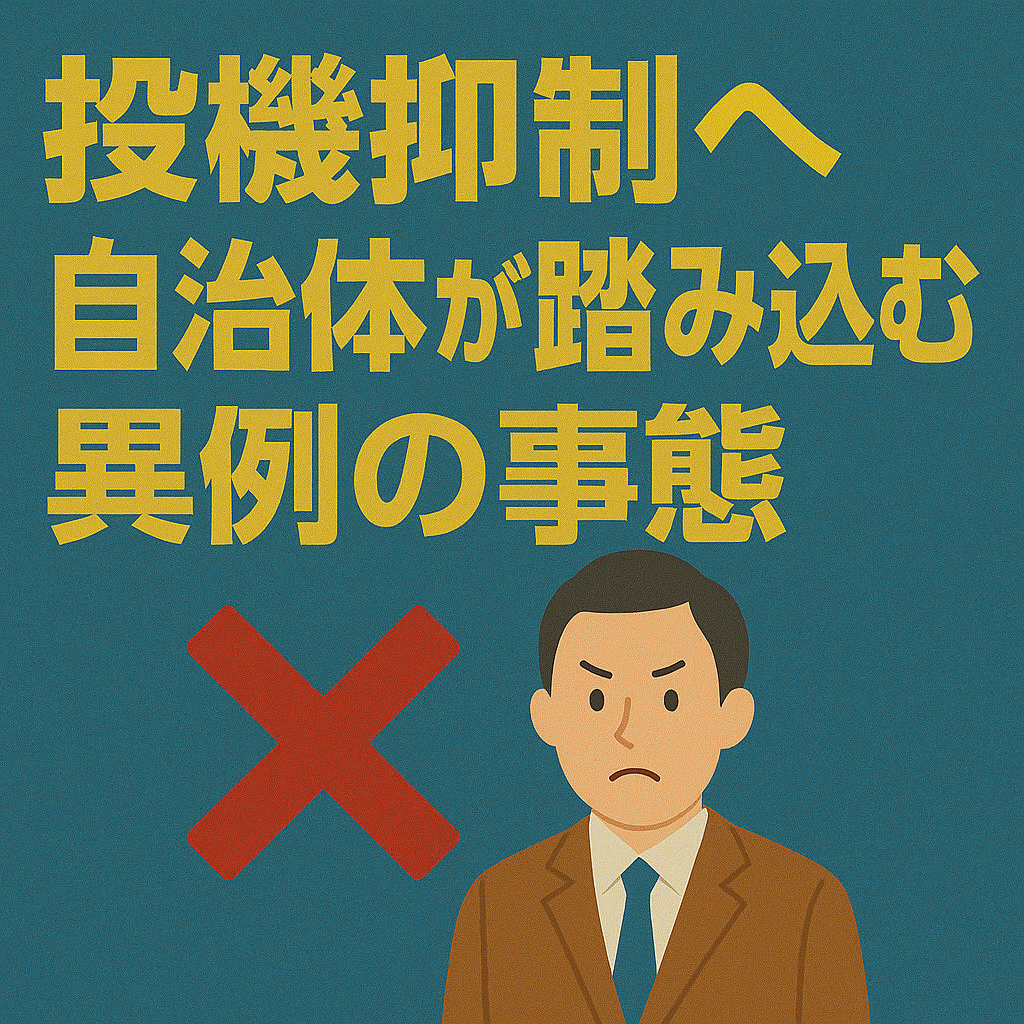

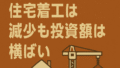
コメント