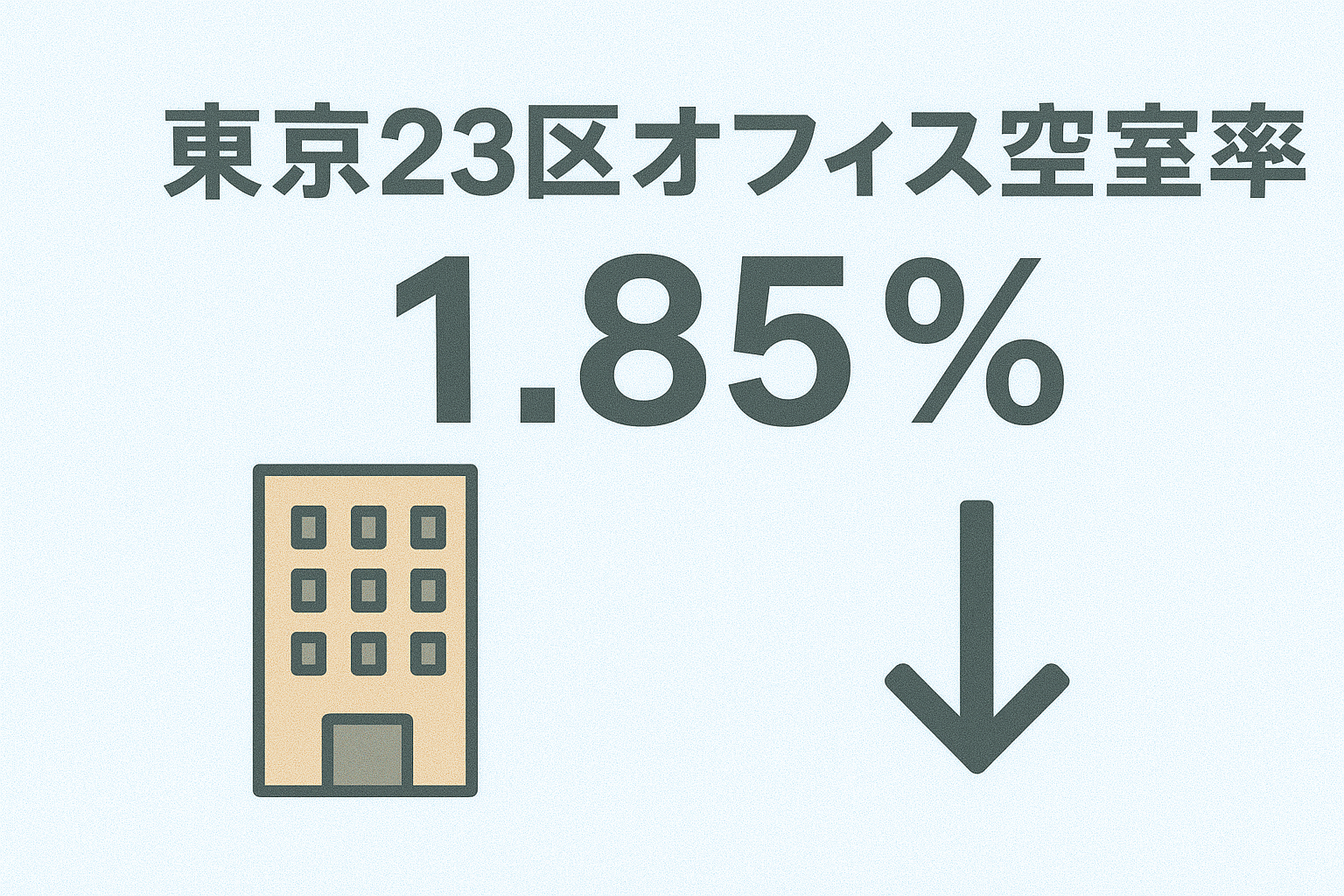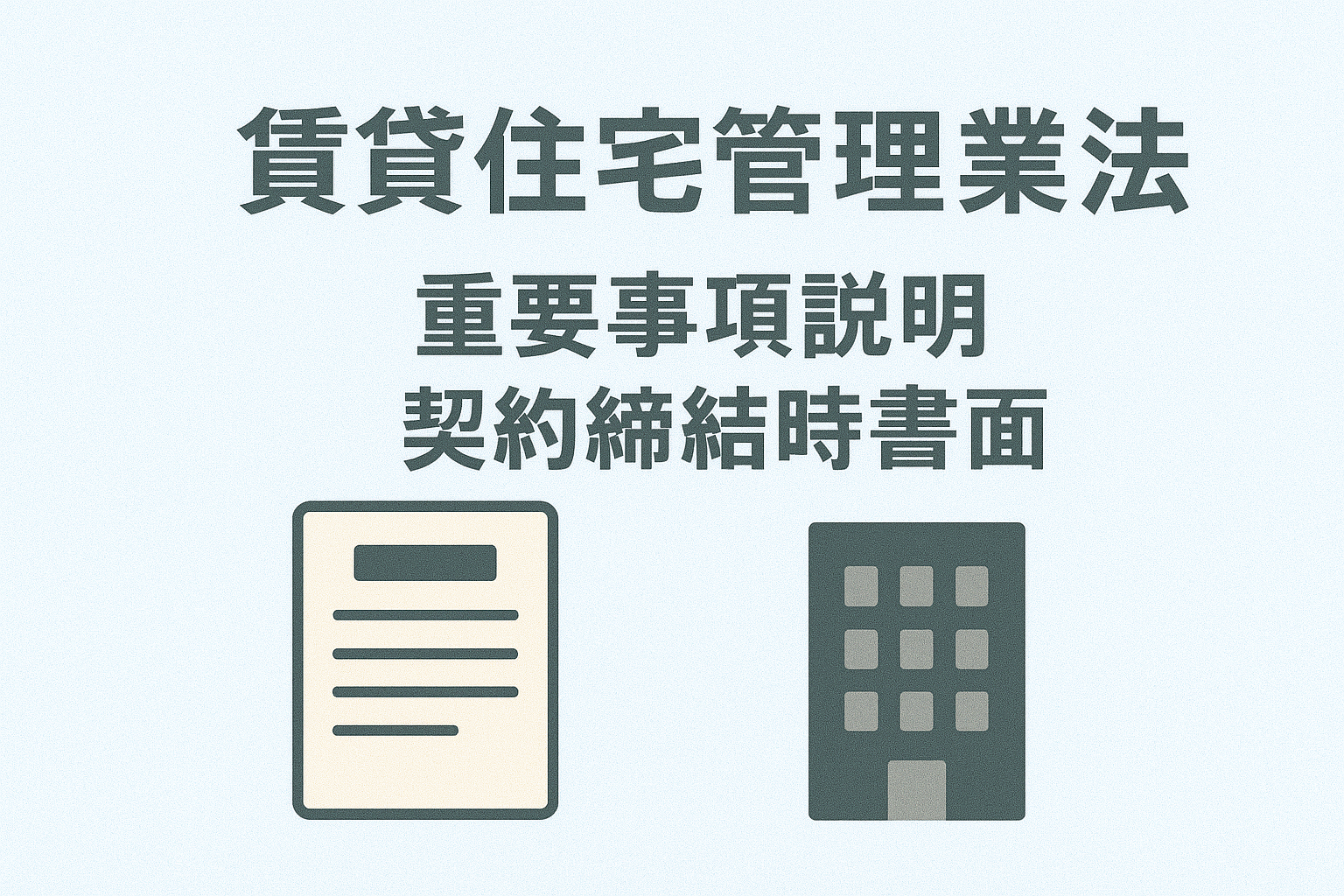賃貸不動産経営管理士試験の勉強、順調に進んでいますか?
インプット学習がある程度進んだら、次に重要になるのがアウトプット、つまり実際に問題を解くことです。問題を解くことで、知識が定着しているかを確認し、自分の苦手分野を明確にすることができます。
そこで今回は、試験の重要論点を盛り込んだ練習問題10問をご用意しました。
実際の試験のつもりで、ぜひチャレンジしてみてください。
まずは問題を一気に10問解いてから、下の解答・解説で答え合わせをしてみましょう!
賃貸不動産経営管理士試験 練習問題
第1問
賃貸借契約における連帯保証人に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか?
- 連帯保証人は、主たる債務者が賃料を支払わない場合、直ちに支払う義務を負う。
- 賃貸人は、賃借人と連帯保証人のどちらに先に請求してもよい。
- 連帯保証人が死亡した場合、その保証債務は相続人に相続されない。
- 個人が事業用の賃貸借契約の連帯保証人になる場合、保証の限度額(極度額)を定めなければ保証契約は無効となる。
第2問
建物の維持管理に関する記述として、最も適切なものはどれか?
- 消防用設備等の点検は、防火対象物の関係者が自ら行うことはできず、必ず消防設備士等に委託しなければならない。
- 建築基準法で定められた特殊建築物等の定期調査報告は、3年に1度実施する必要がある。
- エレベーターの定期検査報告は、設置者が任意で行うものである。
- 給水設備の清掃は、水道法によりすべての建物で年1回以上義務付けられている。
第3問
原状回復に関する特約について、消費者契約法に基づき無効となる可能性が最も高いものはどれか?
- 畳の表替え費用を、損耗の程度にかかわらず、退去時に賃借人が負担する旨の特約。
- 賃借人の故意による壁の穴の補修費用を、賃借人が負担する旨の特約。
- ハウスクリーニング費用を、退去時に賃借人が負担する旨の特約で、金額が社会通念上妥当な範囲であるもの。
- 鍵の交換費用を、紛失した場合に賃借人が負担する旨の特約。
第4問
賃貸住宅管理業法に関する記述のうち、正しいものはどれか?
- 管理戸数が100戸以上の賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、業務管理者を営業所又は事務所ごとに1名以上置かなければならない。
- 管理受託契約を締結する際、賃貸人への重要事項説明は書面を交付すればよく、口頭での説明は不要である。
- 賃貸住宅管理業者は、管理する物件の家賃、敷金等を自己の固有財産と分別せずに管理することができる。
第5問
サブリース方式の賃貸借(特定賃貸借契約)に関する記述として、最も適切なものはどれか?
- サブリース業者は、オーナーに対して、契約期間中はいかなる理由があっても借賃の減額を請求できない。
- 特定賃貸借契約の勧誘者は、契約によるリスクについてオーナーに説明する義務はない。
- サブリース業者が入居者(転借人)と締結する賃貸借契約は、普通借家契約でなければならない。
- オーナーがサブリース業者とのマスターリース契約を解約しようとする場合、正当事由が必要である。
第6問
賃借人の募集(広告)に関する記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)上、問題となる可能性が最も高いものはどれか?
- 「駅徒歩5分」と表示したが、実際には信号待ちの時間を含めると7分かかった
- 「最上階角部屋!」と表示したが、同じフロアに他に3戸の住戸があった。
- 契約済みの物件を、人気物件であるかのように見せるため、広告に掲載し続けた。
- 「日当たり良好」と表示したが、冬至の時期は隣の建物の影で日照時間が短かった。
第7問
賃貸建物の修繕義務に関する記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか?
- 賃貸人は、賃借人が快適に生活できるよう、常に建物を最新の状態に保つ義務を負う。
- 賃貸物の修繕が必要な場合、賃借人は遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。
- 賃貸人が必要な修繕をしない場合、賃借人は自ら修繕することができる。
- 賃借人の責任で修繕が必要となった場合、その費用は賃借人が負担する。
第8問
賃貸借契約の終了に関する記述として、最も不適切なものはどれか?
- 賃借人が破産手続開始の決定を受けた場合、賃貸人は直ちに契約を解除することができる。
- 期間の定めのある賃貸借契約で、解約権が留保されている場合、当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。
- 賃借人が賃料を滞納し、当事者間の信頼関係が破壊されたと認められる場合、賃貸人は契約を解除できる。
- 定期借家契約では、期間満了により契約は更新されることなく確定的に終了する。
第9問
個人情報保護法に関する賃貸管理業者の対応として、最も適切なものはどれか?
- 入居申込者から得た個人情報は、本人の同意なく、関連会社のダイレクトメール送付のために利用した。
- 賃料滞納があったため、連帯保証人に連絡する際に、本人の同意を得てから滞納の事実を伝えた。
- 従業員が退職後、顧客情報を漏洩しないよう、就業規則に秘密保持義務を定め、誓約書を取得した。
- 警察から捜査関係事項照会書による入居者の情報提供依頼があったが、本人の同意がないため一律に断った。
第10問
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する記述のうち、正しいものはどれか?
- 集会において、管理規約の変更に関する決議を行うには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による必要がある。
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者の頭数の過半数で決することができる。
- 管理者は、必ず区分所有者の中から選任しなければならない。
- 各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の管理費用を支払う必要はない。
解答と解説
お疲れ様でした!それでは、答え合わせをしていきましょう。
正解できたかだけでなく、「なぜその選択肢が正解で、他の選択肢が間違いなのか」をしっかり理解することが大切です。
第1問:正解 3
解説:
保証債務は金銭債務であり、相続の対象となります。したがって、連帯保証人が死亡した場合、その地位は相続人に引き継がれます。選択肢3は「相続されない」としているため不適切です。他の選択肢はすべて正しい記述です。特に選択肢4の極度額に関する規定は、民法改正の重要ポイントなので必ず押さえましょう。
第2問:正解 2
解説:
建築基準法第12条に基づく特殊建築物等の定期調査報告の周期は、特定行政庁が定めますが、多くの場合は1年から3年です。選択肢2はこれを述べており、適切です。
- 小規模な防火対象物では関係者による点検も可能です。
- エレベーターの定期検査は法的な義務です。
- 水道法による清掃義務は受水槽の有効容量が10㎥を超える施設が対象です。
第3問:正解 1
解説:
畳の交換や表替えのうち、経年劣化や通常損耗によるものは、本来賃料に含まれるべきと考えられています。これを損耗の程度にかかわらず一方的に賃借人負担とする特約は、消費者契約法により無効となる可能性が非常に高いです。他の選択肢は、賃借人の故意・過失や、社会通念上妥当な範囲での特約であり、有効と判断される可能性が高いものです。
第4問:正解 2
解説:
賃貸住宅管理業法では、登録事業者は営業所・事務所ごとに1名以上の業務管理者を設置することが義務付けられています。
- 登録義務の対象は管理戸数200戸以上です。
- 重要事項説明は、書面の交付と口頭での説明の両方が必要です。
- 受領した家賃等は、自己の固有財産と分別して管理しなければなりません。
第5問:正解 4
解説:
サブリースにおけるオーナーとサブリース業者の契約(マスターリース契約)には、借地借家法が適用されます。そのため、貸主であるオーナーからの解約申入れには、サブリース業者の承諾または正当事由が必要です。
- 借地借家法に基づき、サブリース業者も賃料の減額請求権を持ちます。
- 勧誘時には、家賃減額リスク等の説明義務があります。
- 入居者との契約は、定期借家契約も可能です。
第6問:正解 3
解説:
実際には契約できない物件を広告に掲載し続ける行為は、顧客を呼び寄せるための「おとり広告」とみなされ、景品表示法で禁止されている不当表示に該当します。
- 徒歩所要時間は80m=1分で計算し、信号待ちは含めません。
- 事実であれば問題ありません。
- 「日当たり良好」は主観的な表現であり、直ちに不当表示とはなりません。
第7問:正解 1
解説:
民法が定める賃貸人の修繕義務は、賃借人が目的物を使用収益するのに必要な状態を保つ義務です。「常に最新の状態」に保つ義務まで負うわけではありません。よって、この記述は誤りです。他の選択肢はすべて民法の規定に沿った正しい記述です。
第8問:正解 1
解説:
2020年4月の民法改正により、賃借人が破産手続開始の決定を受けても、それだけを理由として賃貸人が契約を解除できるという規定は削除されました。賃料滞納など、具体的な債務不履行がなければ解除できません。したがって、この選択肢は不適切です。
第9問:正解 3
解説:
個人情報保護法では、事業者は従業員が個人情報を取り扱うにあたり、適切な監督を行う義務があります。就業規則での秘密保持義務の規定や、誓約書の取得は、その適切な監督の一環として有効です。
- 目的外利用には本人の同意が必要です。
- 保証債務の履行請求のための情報提供に、都度の同意は不要です。
- 法令(捜査関係事項照会)に基づく場合は、同意なく提供できます。
第10問:正解 1
解説:
区分所有法において、規約の設定、変更、廃止は「特別多数決議」事項とされており、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。
- 共用部分の重大な変更も、原則として各4分の3以上の特別多数決議が必要です。
- 管理者は区分所有者である必要はありません。
- 各共有者は、持分に応じて管理費用を負担する義務があります。
まとめ
さて、何問正解できたでしょうか?
全問正解だった方は素晴らしいです!自信を持って本番に臨んでください。
もし間違えてしまった問題があった方も、全く落ち込む必要はありません。むしろ、本番前に苦手分野を発見できたと前向きに捉えましょう。
大切なのは、間違えた問題の解説をじっくり読み、「なぜ間違えたのか」を理解することです。その論点をテキストで復習し、知識を確実なものにしていきましょう。
試験日まであと少し。体調管理に気を付けながら、ラストスパート頑張ってください!応援しています!