サブリース契約をめぐるトラブルが増加するなか、国土交通省は「特定賃貸借標準契約書」を示し、透明で公正な契約の促進を図っています。
この記事では、この契約書の仕組みと内容を、賃貸不動産経営管理士試験に出題されやすい部分を中心にわかりやすく解説します。
特定賃貸借契約とは?
まず、「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者(サブリース業者)が転貸を目的として締結する賃貸借契約のことをいいます。
つまり、建物の所有者(貸主)が、サブリース業者(借主)に一括して建物を貸し出し、借主が第三者(入居者)に再度貸す「一括借上げ」の仕組みです。
- 貸主(甲)=建物所有者
- 借主(乙)=特定転貸事業者(サブリース業者)
- 転借人=実際の入居者
この三者の関係を整理するのが「特定賃貸借標準契約書」です。
契約の目的と適用範囲
この契約書の目的は、サブリース事業の適正化と貸主・借主双方の権利保護です。
主に、1棟の居住用建物を対象とし、貸主(オーナー)と特定転貸事業者の間で締結されます。
また、この契約書は借地借家法の適用対象であり、第32条(借賃増減請求権)などの規定がそのまま有効です。
経済情勢の変化などに応じて賃料の見直しができる点も押さえておきましょう。
主な条項と内容のポイント
■ 契約期間・目的(第1条〜第3条)
- 契約期間・引渡日・使用目的を明確に定めます。
- 借主は「居住の用」に限定して転貸できます。
- 民泊などの別用途に使う場合は、貸主の承諾が必要です。
👉 試験ポイント:居住目的以外への利用は禁止が原則!
■ 家賃・敷金の定め(第5条・第7条)
- 家賃の支払時期・改定方法を定めます。
- 借地借家法第32条に基づき、家賃増減請求権が行使可能です。
- 敷金は債務の担保であり、契約終了時には残額を返還します。
- 借主(サブリース業者)は、転借人からの敷金を分別管理する義務があります。
👉 試験ポイント:「分別管理義務」は頻出テーマ!
■ 維持保全と再委託(第10条〜第13条)
- 借主は、建物の清掃・点検・修繕など維持保全を行います。
- 修繕費用の負担区分(貸主/借主)を明確にします。
- 一部の業務は再委託可能ですが、全部の一括再委託は禁止されています。
👉 試験ポイント:「業務の全部を一括して再委託してはならない」!
■ 反社会的勢力の排除(第8条)
- 貸主・借主ともに、反社会的勢力との関係を持たないことを契約上明記します。
- これに違反した場合、即時に契約解除できる条項が設けられています。
👉 試験ポイント:「反社排除条項」は全ての標準契約書に共通して明記!
■ 契約解除・終了(第18条・第21条)
- 家賃の滞納や反社条項違反などがある場合、貸主は契約を解除できます。
- 契約が終了すると、貸主が転貸人(サブリース業者)の地位を承継します。
- そのため、入居者との契約関係は貸主に引き継がれます。
👉 試験ポイント:「契約終了時の地位承継(第21条)」は重要!
契約書の特徴と意義
特定賃貸借標準契約書の特徴は、サブリース契約を透明化し、オーナー・管理業者双方のリスクを軽減する点にあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 建物一棟(居住用) |
| 借主 | 特定転貸事業者(登録制) |
| 法律 | 賃貸住宅管理業法・借地借家法 |
| 義務 | 分別管理・維持保全・反社排除 |
| 終了時 | 転貸人地位の承継(貸主へ移行) |
実務での注意点
- 貸主は、契約内容・賃料・修繕費負担などを十分理解して契約すること。
- 借主(サブリース業者)は、入居者との転貸契約内容を明確にし、家賃の分別管理を徹底すること。
- 契約終了後は、敷金返還・書類引渡し・管理引継ぎを確実に行う必要があります。
試験対策まとめ
| 出題テーマ | チェックポイント |
|---|---|
| 契約の性質 | 転貸を目的とする契約であり、借地借家法が適用される |
| 再委託 | 一部のみ可能、全部の一括再委託は禁止 |
| 分別管理義務 | 敷金・家賃は管理業者の固有財産と区別する |
| 契約解除 | 家賃滞納・反社関係などで解除可能 |
| 契約終了 | 貸主が転貸人の地位を承継する |
まとめ
「特定賃貸借標準契約書」は、サブリース契約を公正・安全に進めるための基本文書です。
賃貸不動産経営管理士試験では、
- 分別管理
- 再委託制限
- 契約終了時の地位承継
の3つが特に狙われやすいポイントです。
実務においても、オーナーやサブリース業者が正しい理解を持って契約を締結することが、トラブル防止の第一歩になります。
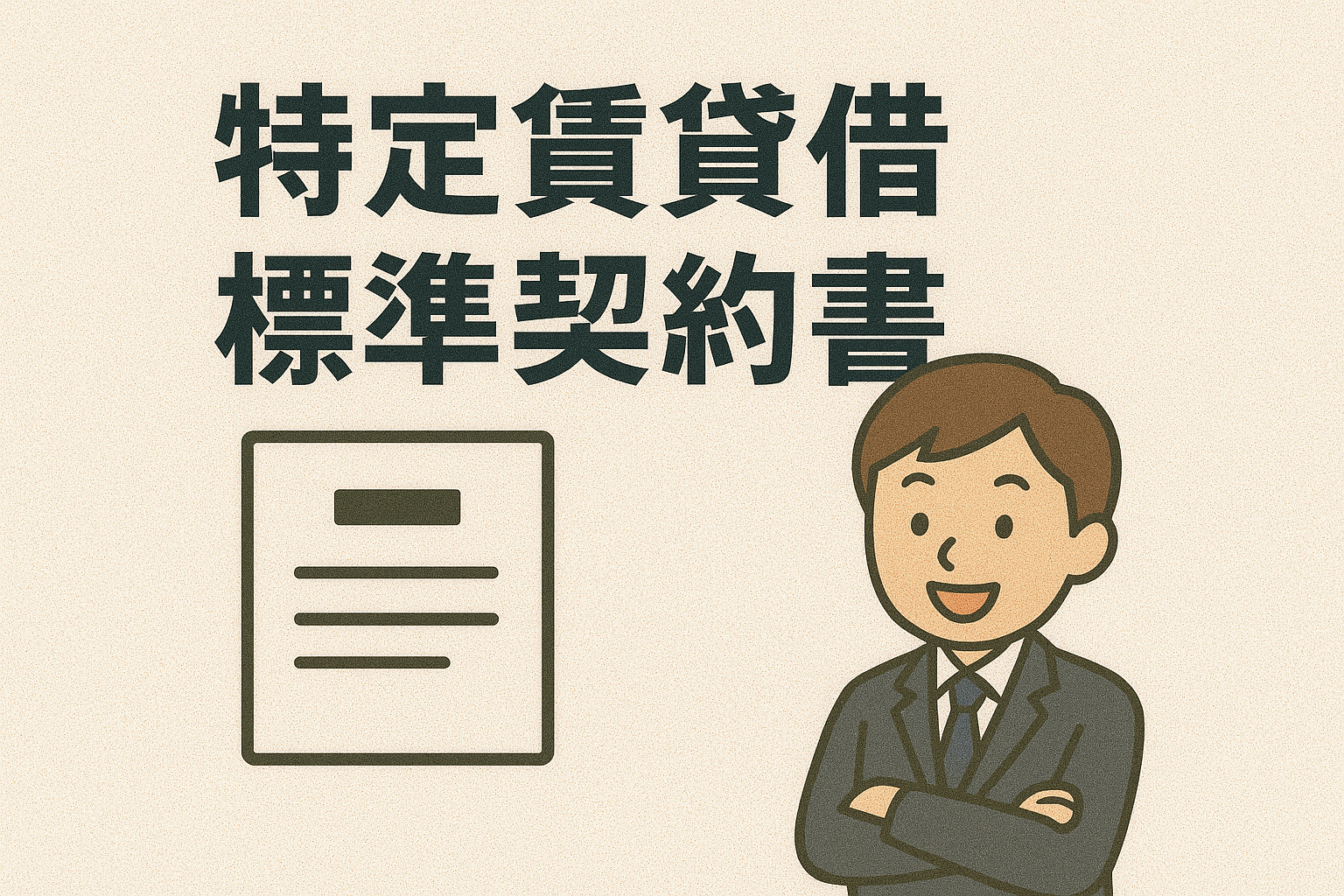


コメント