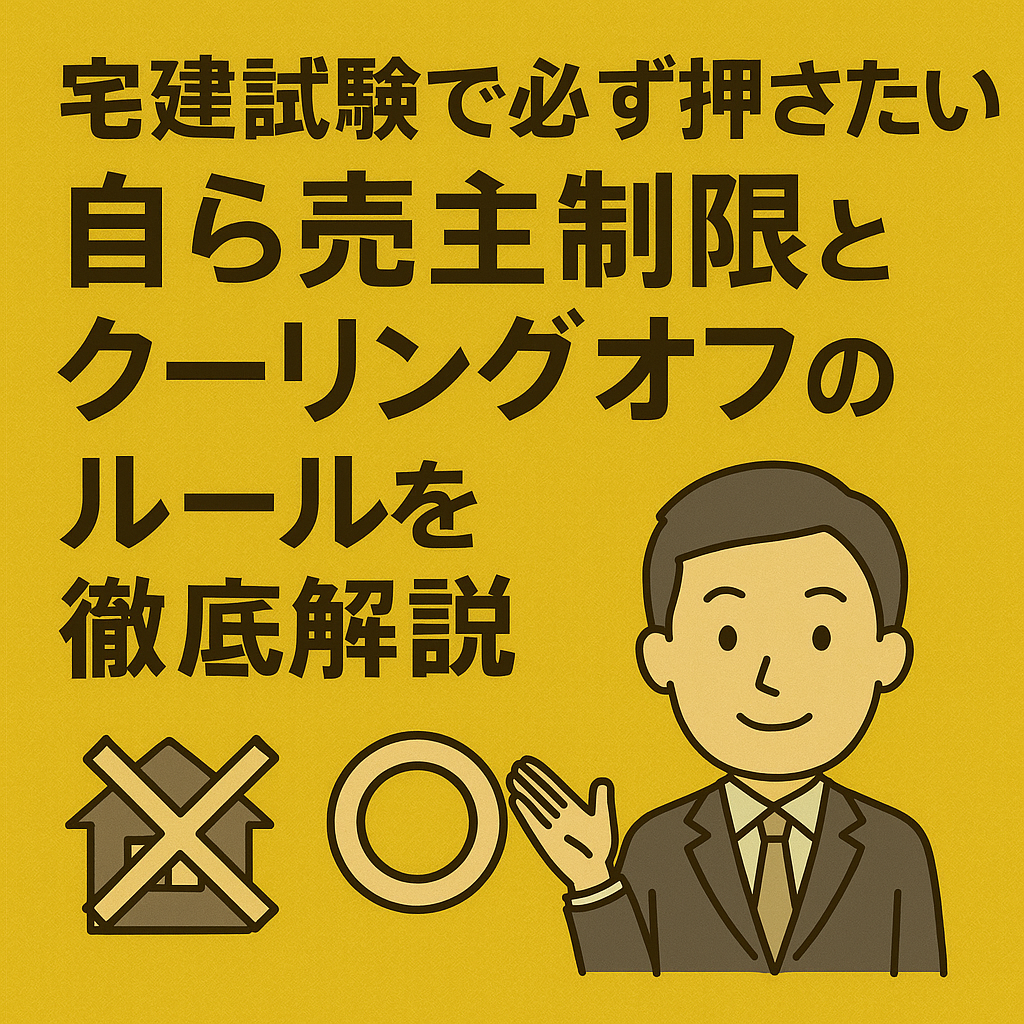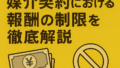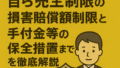宅建試験受験者の皆さん、こんにちは。
今回は宅建業法に定められた自ら売主制限について詳しく解説します。
宅建業者が自ら所有する宅地や建物を一般消費者に売却する場合には、通常の民法のルールよりも厳しい規制が適用されます。
この記事では、その適用条件と、特に試験で頻出するクーリング・オフ制度について、例題も交えながらわかりやすくまとめました。確実に得点できるようにしましょう!
⸻
自ら売主制限とは何か
通常の民法では「契約自由の原則」があり、当事者同士で自由に契約内容を決めることができます。
しかし、宅建業者が自ら売主となって一般消費者と売買契約をすると、知識や経験の差により消費者が不利になるおそれがあります。
そこで、宅建業法では、宅建業者が自ら売主となり、かつ相手方が宅建業者以外である場合には、以下のような制限を設けています。これを総称して「自ら売主制限」と呼びます。
⸻
自ら売主制限が適用される場合
- 売主が宅建業者であること
- 買主が宅建業者でないこと(一般消費者)
なお、売主の宅建業者を媒介・代理する他の宅建業者は、自ら売主制限の適用を受けません。あくまで売主となる宅建業者のみが対象です。
⸻
自ら売主制限の種類(全8種類)
自ら売主制限には、次の8つの制限があります。
1. クーリング・オフ
2. 損害賠償額の予定等の制限
3. 手付の額等の制限
4. 手付金等の保全措置
5. 自己所有でない物件の売買制限
6. 担保責任の特約制限
7. 割賦販売契約の解除制限
8. 所有権留保の禁止
今回はこの中でも特に重要な「クーリング・オフ」について詳しく見ていきます。
⸻
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、一定期間内であれば消費者が申込みの撤回や契約の解除を自由に行える制度です。
これは、冷静な判断ができるようにするための保護措置です。
⸻
クーリング・オフができる条件
クーリング・オフが認められるのは、次の2つの条件を満たす場合です。
- 売主が宅建業者で、買主が宅建業者以外
- 申込みや契約を「事務所等」以外の場所で行った場合
【事務所等とは】
- 宅建業者の事務所
- 専任取引士設置義務のある案内所や展示場
- 他の宅建業者が設置する事務所等
- 買主の申し出により行った買主の自宅・勤務先
これらの場所で申込みや契約を行った場合には、クーリング・オフできません。
※土地に定着していないテント張りの現地案内所は事務所等に該当せず、クーリング・オフ可能。
例題1
テント張りの現地案内所で売買契約をした場合、クーリング・オフできるか?
A. できる
B. できない
正解 → A
⸻
クーリング・オフができる期間
クーリング・オフには期限があります。
1. 宅建業者から「クーリング・オフできる旨と方法」を書面で告知された日から8日以内
2. 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払った場合はできない
- 8日間は、告知日を含めて数えます。
- 口頭での告知ではカウント開始しません。
- 申込み場所と契約場所が異なる場合、申込み場所で判断します。
⸻
クーリング・オフの方法と効果
クーリング・オフは必ず書面で行う必要があります。
また、書面を「発した時」(発信主義)に効力が発生します。
宅建業者に届いたかどうかではないので、注意しましょう。
【補足】
- クーリング・オフをした場合、宅建業者は損害賠償や違約金を請求できません。
- すでに受領していた手付金等は全額速やかに返還しなければなりません。
- 買主に不利な特約(クーリング・オフをできなくする特約など)はすべて無効です。
例題2
クーリング・オフの効力発生はいつか?
A. 書面が宅建業者に届いたとき
B. 書面を発したとき
C. 申込みをしたとき
D. 申込みから8日後
正解 → B
⸻
クーリング・オフ適用案内所の標識
クーリング・オフ制度の適用がある現地案内所などでは、適用があることを明示する標識を掲げなければなりません。
一方で、専任取引士の設置義務がある案内所ではクーリング・オフ制度は適用されないので標識も不要です。
⸻
試験対策まとめとポイント
この分野で必ず押さえたいポイントは以下の通りです。
- 自ら売主制限は売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の場合に適用
- クーリング・オフできるのは事務所等以外で申込み・契約した場合
- 書面での告知日から8日以内に限り可能
- 書面の発信時点で効力が発生(発信主義)
- クーリング・オフによる不利な特約はすべて無効
過去問では、適用条件や発生時期、方法など細かな点がよく問われますので、例題を繰り返して確実に覚えておきましょう!
⸻